ジセダイ総研
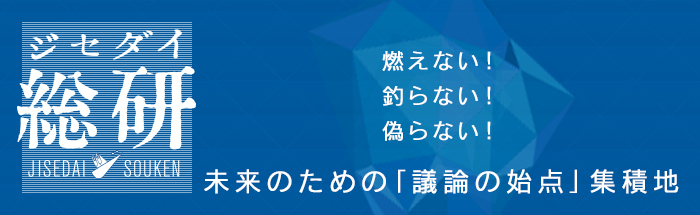
文学者たちのあっけない「転向」
1964年10月の東京オリンピックは、「筆のオリンピック」とも呼ばれた。小説家や評論家など物書きの多くが、まるで競うようにオリンピックのことで筆を執ったからである。
当時はまだテレビタレントがいなかった時代。文学者は文化人の代表格であり、その観戦記は、今日のテレビ番組のレポートやコメントのように広く消費された。こうした文学者たちの文章は、同年12月刊行の『東京オリンピック 文学者の見た世紀の祭典』(講談社、2014年同学芸文庫で復刊)にまとめられている。
今日改めてこの本を読むと、われわれは失笑を禁じえないだろう。というのも、名だたる文学者たちが、あまりにもあっけなく次々に「転向」してしまうからである。
文学者たちは、もともとオリンピック開催に対して批判的ないしは無関心だった。その辛辣な言葉の数々を少し引いてみよう。
「私もかなり批判的だった。たかがスポーツではないか。何の為にそんな大騒ぎをするのか」(石川達三)、「自分とは全く無関係なスポーツの行事が、東京でおこなわれ、私はそのあいだ、多少きゅうくつな思いをあじあわされることになるだろう」(菊村到)、「国家社会という批判すべき組織を考える立場から、今度のオリンピック開催に対して、しばしば疑問を提出して来た」(有馬頼義)、「オリンピックに、特に関心があったわけではなかった」(小林秀雄)、「やかましく、イライラした四年間だった」(遠藤周作)......。
ところが、いざオリンピックが目の前で開催されると、彼らの多くは競技に強い関心を示し、あるいは盛大な開会式に感動し、あるいは選手の敢闘に涙し、あるいは原稿をほっぽり出してテレビにかじりついてしまう。すっかりオリンピックの熱狂に魅せられてしまったのだ。そしてついに、彼らはほとんど口をそろえて「やってよかった」と結論づけるにいたるのである。
ひねくれ者で一癖も二癖もある文学者たちが、あまりにも簡単に「転向」していく。このような姿を読まされて失笑せずにいられようか。
本来スポーツに対して冷淡な文学者でさえこうなのだから、一般の民衆はなおのこと。前回の記事にも書いたとおり、当時の国民は東京オリンピックに対して概して無関心だった。ところが、その開催後には「やってよかった」という感想が広まり、無関心だった過去をすっかり洗い流してしまったのである。
32歳の石原慎太郎と東京オリンピック
旧東京都庁に到着した聖火リレーの様子。
東京都『第18回オリンピック競技大会 東京都報告書』(1965年)より。
このような「転向」した文化人のなかには変わり種もいた。当時32歳の新進作家だった石原慎太郎がそれである。
石原といえば、2020年の東京大会の招致実現に尽力した元東京都知事であり、自他ともに認めるナショナリストだ。東京大会の目的についても、テレビで「国威発揚のため」だと断言したこともあるという。
では石原は、1964年のときも東京オリンピックを「国威発揚」の祭典として歓迎したのだろうか。いや、そうではなかった。同年10月11日、すなわち開会式の翌日、石原は「読売新聞」にこう書いている。
「私は以前、日本人に稀薄な民族意識、祖国意識をとり戻すのにオリンピックは良き機会であるというようなことを書いたが、誤りであったと自戒している。
民族意識も結構ではあるが、その以前に、もっと大切なもの、すなわち、真の感動、人間的感動というものをオリンピックを通じて人々が知り直すことが希ましい」
これは本当に石原の発言なのだろうか。そう疑いたくなるくらい、当時の石原は、オリンピックに対して開明的な考え方を披露していたのだ。
これだけではない。石原は、オリンピックは「国家や民族や政治、思想のドラマではなく、ただ、人間の劇」といい、その「競技をながめる時、我々はその中に決して、民族の名誉、国家の名誉、思想の名誉などを掲げることはしまい」と述べる。
そして、「外国からやって来た選手も我々と同じ一人の人間である」といったうえで、「民族とか国家とか、狭い関心で目をふさがれ、この祭典でなければ見ることの出来ぬ、外国人対外国人の白眉の一戦を見のがしてしまうことも最も愚かしいことと思う」とまでいってのけるのである。
石原慎太郎、民族意識にめざめる
ところが、石原はすぐに変化を起こす。思っていたより日本人選手が活躍しない。他国の国旗ばかり見せられ、他国の国歌ばかり聴かされる。それに石原は苛立ちはじめるのだ。
同月16日の「読売新聞」に石原はこう書く。「どたん場にくれば平素の実力以上のものを出してしまう外国選手と、実力までも出し切れずに敗れ去る日本選手。われわれに欠けているものはなになのか」
これに対し、石原はややためらいがちにこう答えを出す。
「解説者は、彼らが胸の内にしまい、その背に無形に背負っているものの違い、国家民族への意識だと説いていたが、あるいはそうなのかもしれない」
つまり石原は、日本の選手が弱いのは、国家や民族に対する意識が弱いからだというのである。そしてそこから石原の筆は、現代の政治問題に及ぶ。
「この[戦後]復興にそって、日本という国家に対し、国民に戦前戦中とは違ってさらに新しい共同体への意識をいだかしめる、新しい国家の理念を自家発酵さすべく努力すべきだったのは政治である。政治、政治家はこの責めを怠った」
「妙な連想だが、いまもし地球が他の天体から野蛮に一方的に攻撃されたとき、地上の民族の中で、一番先に銃を投げ降伏するのは日本人ではないかというような気さえする」
スポーツと国民意識。ここまで来ると、われわれのよく知るナショナリスト石原慎太郎まであと少しだ。実際石原は、4年後の1968年、参議院議員に当選して政治家の道を歩みはじめるのである。
もちろん、石原は東京オリンピックの体験だけでナショナリズムに目覚めたわけではない。石原本人は、戦時中の体験(日本の戦闘機によって米軍機の機銃掃射から救われた)や敗戦後の光景(多くの日本人女性が米兵の情婦になった)にその原因があると回想している。
とはいえ、東京オリンピックの影響も決して無ではなかったのではないか。同大会で日本の選手が大いに勝利すれば、開会式の直後に見せたような国際主義的な認識を維持していたかもしれないからだ。東京オリンピックの開催は、世界的に有名なナショナリストの思想の一部を形作った可能性があるのである。
文学者たちの「転向」は他人ごとではない
こう考えると、文学者たちの「転向」は他人ごとではない。2020年には東京で再びオリンピックが開かれる。目の前で「感動的」なできごとが起こるとき、われわれは果たして冷静でいられるだろうか。
つい先日閉幕したリオ五輪にしてもそうだ。リオ五輪ははじめこそ盛り上がりに欠いた。ただ、日本人が次々にメダルを獲得することで空気は変化していった。そして閉幕式で公開された2020年東京大会の「ショー」で、その好意的なムードは頂点に達した。
「ショー」には、スポーツ選手だけではなく、キャプテン翼、パックマン、ドラえもん、ハローキティといった日本の人気キャラクターまで登場し、安倍晋三首相がスーパーマリオに扮するシーンまである。
「マンガ・アニメ・ゲームに政治を持ち込んだ」といえなくもない事例だが、現在のところ、それほどの批判はでていないようである。むしろスポーツに冷淡なひとびとにも評価され、成果は上々だったとさえいえる。人気キャラクターの動員は、みごとに成功したのだ。
たしかに、2020年の東京大会にはまだまだ批判も多い。ただ、今後あの手この手で効果的なプロモーションが行われるはずだ。1964年と異なり、現在の文化人は必ずしもオリンピックに対して批判的でも無関心でもない。スポーツが苦手な、インドアなひとも喜ぶような演出が繰り出されるだろう。
プロモーションがうまく噛み合えば、2020年の東京大会は、1964年のそれよりも遥かに盛り上がる可能性さえある。1964年大会の直後「やってよかった」と結論づけた小説家の菊村到は、それでいてもなお「ただし二度やるのはバカだ」と付け加える冷静さを保っていた。しかし、2020年の日本の文化人は「4年後もまたやりたい」などとうそぶくかもしれない。
2020年へ向けて、われわれはキャラクターの動員や「感動」を目の前にしてなお冷静でいられるだろうか。何かに突如として目覚めたりはしないだろうか。少なくとも私は、「たかがスポーツではないか。何の為にそんな大騒ぎをするのか」(石川達三)という覚めた態度を忘れずに持っておきたいと思っている。
辻田真佐憲氏によるこちらの記事も合わせてどうぞ。
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介
-
2017年01月26日 更新
オリンピックは内紛の歴史である 1940年の「幻の東京オリンピック」の場合
-
2016年12月01日 更新
東京の道路に名前を与えたオリンピック そして2020年の対策は?
-
2016年08月23日 更新
オリンピックの熱狂と「転向」する文学者たち 2020年われわれは冷静でいられるか
-
2016年07月21日 更新
多くの国民が無関心だった? 1964年のオリンピックはこんなにもダメだった
ジセダイ総研
ジセダイ総研 研究員
-
 高口康太
高口康太客員研究員
-
 北条かや
北条かや客員研究員
-
 さやわか
さやわか客員研究員
-
 土屋健
土屋健客員研究員
-
 牧村朝子
牧村朝子客員研究員
-
 安田峰俊
安田峰俊客員研究員
-
 戸部田誠(てれびのスキマ)
戸部田誠(てれびのスキマ)客員研究員
-
 タイナカジュンペイ
タイナカジュンペイ客員研究員
-
 田中秀喜
田中秀喜客員研究員
-
 ジセダイ編集部
ジセダイ編集部客員研究員
-
 石動竜仁
石動竜仁客員研究員
-
 三木義弘
三木義弘客員研究員
-
 崎山直樹
崎山直樹客員研究員
-
 宇野維正
宇野維正客員研究員
-
 辻田真佐憲
辻田真佐憲客員研究員
-
 丸島和洋
丸島和洋客員研究員
-
 大熊将八
大熊将八客員研究員
-
 広中一成
広中一成客員研究員
-
 野村泰紀
野村泰紀客員研究員
-
 五百蔵容
五百蔵容サッカー
キーワード
- まとめ
- アジア情勢
- アメリカ
- インタビュー
- オリンピック
- サッカー
- シリア難民
- テロ
- ドイツ
- ネット犯罪
- バングラデシュ
- 中国
- 台湾
- 外交
- 宗教
- 政治
- 歴史
- 男女
- 社会
- 社会カテゴリを追加
- 科学
- 結婚
- 編集部より
- 自然
- 軍事
- 音楽
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






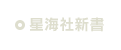


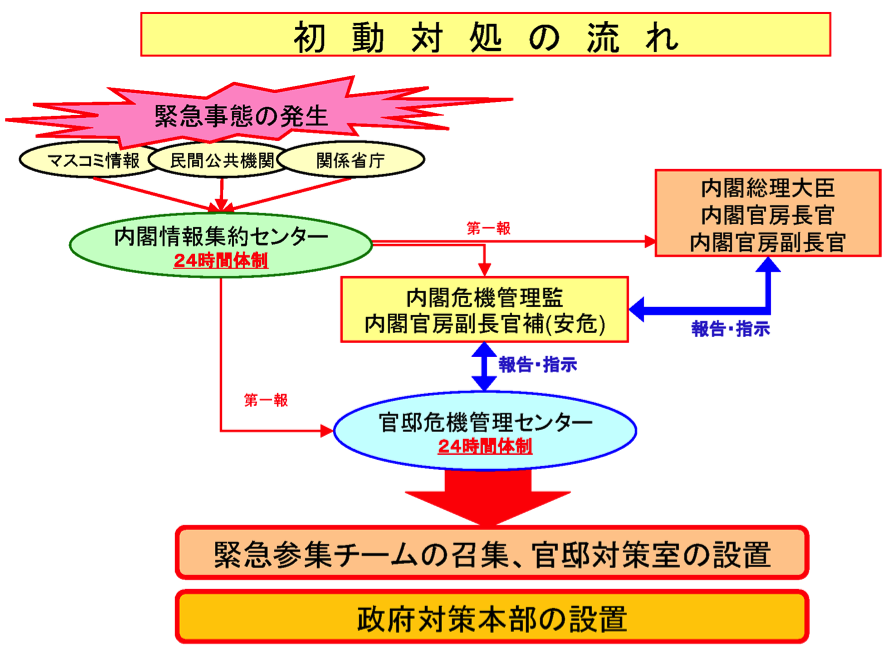




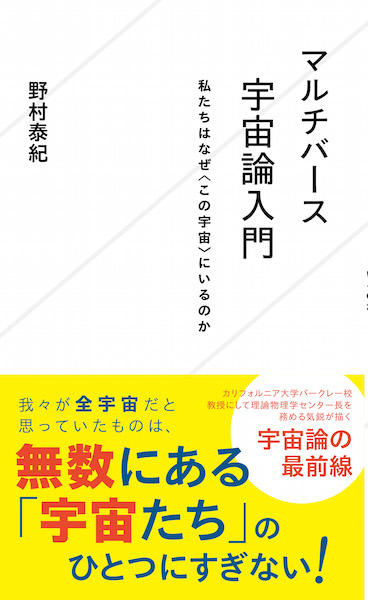


コメント