平成30年論
第2回:まるで『一九八四年』のようだと月並に思い、そして、吐き気さえしてきた2月
大塚英志
【1】「工作員」はAIにとって代わられる職業リストにあるか
2月に起きた、あるいは、この原稿を書いている3月7日の時点で、進行中の出来事を思い出してみる。
2月11日には、三浦瑠麗がTVのワイドショーで以下のような「テロリスト分子」発言を行ったという。
「実際に戦争が始まったら、テロリストが仮に金正恩さんが殺されても、スリーパーセルと言われて、もう指導者が死んだっていうのがわかったら、もう一切外部との連絡を断って都市で動き始める、スリーパーセルっていうのが活動すると言われているんですよ」「テロリスト分子がいるわけですよ。それがソウルでも、東京でも、もちろん大阪でも。今ちょっと大阪ヤバいって言われていて」
(大山 くまお「"工作員妄想"と批判された三浦瑠麗氏『大阪やばい』発言の情報源」 http://bunshun.jp/articles/-/6259)
「スリーパーセル」というのは、ラノベや『相棒』あたりに出てきそうだが、それが実在するという根拠は日本でいえばどうやら東スポのようなイギリスの新聞記事だと各所で指摘された。暗に関西の在日コリアンを示唆している、いない、という論争ともなったが、古谷経衡がこれを「工作員妄想」と名付けたのは興味深い。古谷は拉致事件をきっかけに「高度に訓練された北朝鮮の工作員が、現在でも日本の大都市部に潜伏している」というイメージの「醸成」がこの「妄想」の「遠因」にあると指摘する(「広がる『工作員妄想』~三浦瑠麗氏発言の背景~」https://news.yahoo.co.jp/byline/furuyatsunehira/20180213-00081557/)。ここで、古谷が「工作員妄想」のエッセイで何気なく使った「醸成」は戦時下のプロパガンダ用語で、「醸成」するよう誰かが工作する、という文脈で用いる。その意味で「工作員妄想」を誰が「醸成」したのかは考えておいた方がいい。
「工作」は、飯島勲や佐藤優あたりによって今ではインテリジェンス、と妙にスマートに言い替えられているけれど、政治的な工作やそれに伴う情報収集をどの国の政府も行っているのは言うまでもない。物書きが「工作」や、逆に「監視」の対象になっている、ということもいつの時代にもある話だ。大昔、保守論壇にいた頃、『諸君!』に書いた他愛もないエッセイに対して、宮内庁から「御説明をしたい」旨の連絡があり(無視したけれど)、「これで大塚さんも監視対象ですね」というくだらぬジョークを若い編集から聞かされもしたのを思い出す。
そういう質の悪い話が保守論壇の周辺の人たちは好きだから、「工作員妄想」は、三浦のように論壇に入り立ての若いアカデミズムの人間には感染し易いのだろう。
同情はしないが。
「工作員」なる語は今や半ば一般名詞化し、2ちゃんあたりに始まる、web上での世論誘導を日々推進する人々というニュアンスが当然ある。webでは、「反日」(ぼくもそうなのだろう)な人々は全員、「工作員」ということになるようだ。だがweb上の「工作員」活動に関していえば、「保守」の側の方が熱心だった印象がある。自民党が下野したあたりから「チーム世耕」や「自民党ネットサポーターズクラブ」を組織して世論の「醸成」に力を入れてきたのは、今更ぼくが説明するまでもない。
そういう「保守」の側の「工作員」活動の一つが、2月27日にwebメディアの「BUZZAP!」が報じた「宇予くん」問題だろう。日本青年会議所がTwitterアカウント「宇予くん」を用いて「正真正銘本物のネット工作」(「BUZZAP!」)を行っていたと流出した内部資料とともに報じた(http://buzzap.jp/news/20180227-jaycee-net-kaiken/)。
流出したとされる「保守キャラクターツイッター」企画書によれば、「宇予くん」は、「対左翼を意識し、炎上による拡散も狙う」ために企画され、多分、その名称は「右翼くん」の駄洒落であるとするとかなりつらいが、日の丸を背にした『コロコロコミック』にでもありそうなマスコットキャラといい、直後に左翼の陰謀説だという強引な説が流されたが、成る程、確かに今の若い子のことばでいうとむしろ保守を「ディスっている」としか思えない出来の悪さではある。
「BUZZAP!」も指摘しているが「ボーカロイド」や「ニコ動」を使うというアイデアや「YouTubeでバズるためには?」という議論自体が、ぼくぐらいにwebに詳しくないというか、無知の人間が企画していることがうかがえる。宇予くんのフォロワーはアカウントが消える前の時点で60人ぐらいだったようだから、「工作」には成功しなかったと思われるが、流出した資料からはこの「工作」を提案した広告代理店の存在がうかがえるが、そもそも広告代理店を使った時点で失敗していたのではないか。
というのは、どうやら今や「工作」はbotがTwitterで行うものが普通であるようだからだ。
その実態をドイツの「日本学」の研究者、シェーファー・ファビアンらは、2014年の日本の衆議院選挙前後のツイート542584個を分析し、そこで「ソーシャルbot」がいかに機能したかを分析する論文を公表している。(Schäfer Fabian, Evert Stefan, Heinrich Philipp「Japan's 2014 General Election: Political Bots, Right-Wing Internet Activism, and Prime Minister Shinzō Abe's Hidden Nationalist Agenda」『Big Data』Vol.5,No.4)https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/big.2017.0049
ファビアンらは、例えば類似した内容のある安倍支持のツイート12389個が、実は36個のツイートの文言の一部を修正したリツイートである、といくつかの具体的な事例を挙げて分析している。それらは「政治bot」の自動生成だが、興味深いのは、botのリツイートと人間のリツイートの間に差異が見つけ難いという指摘だ。それはAI工作員が、人間がリツイートする際の癖を学習して、より人間らしくツイートしているからだが、同時に人間工作員によるリツイートは思いのほか、botのように自動化されている、つまり考えなしで行われている、ということになる。何とも身も蓋もない結論なのである。
「宇予くん」もステレオタイプのヘイトを乱発したが、一昨年あたり、マイクロソフトのAI・Tayが反ユダヤ・反フェミニズムのヘイトスピーチ、中国でもAIが習近平と共産党批判をツイートし始めたことを思い出すと、そもそも「宇予くん」をプレゼンした代理店や「保守」工作員はAIにその座を明け渡す日が既に来ている、ということになる。「工作員」は、AIにとって代わられる職業リスト入りのようである。
情報操作を行う「工作員」が日々蠢いているという「妄想」としか思えないことばがweb上を今日も跋扈している。その日常にやや私たちは鈍麻している。しかし官僚組織が、実際に情報を書き換えていることが発覚したのは3月に入ってすぐだ。
3月2日の朝日新聞の報道に始まる、森友学園国有地取引に関する財務省の文書が、事件発覚後、国会答弁と矛盾する部分を改竄されたのではないか、という疑惑である(*この原稿を星海社に渡した3月8日から校正の戻って来た3月15日の間に改竄問題は大きく進展したが、事態の推移に応じた加筆訂正は一切、以下にはしない)。今のところ、これを朝日のフェイクニュースだという定番の反論(一定のweb工作員の活動はあるようだが)は大きな声にはなっていない。これに先立って、裁量労働制導入の根拠とされた統計が本来、対比できない数字を対比して裁量労働制の方が、勤務時間が短くなると都合良くつくられていたことも明らかになっていて、さすがに、官邸主導のあからさまな「工作」の度が過ぎて、今回に限っては「工作員妄想」ではなく現実だ、とは大抵の人は常識として思いはじめている。
そして朝日の森友関連文書改竄報道に対して「羽生結弦国民栄誉賞授与の方針決定」のニュースをぶつけてきたのもひどくわかり易い「工作」であった。「政府関係者」のリークだと記事(読売の報道による)に書いてあるのが、脇が甘い(裁量労働制問題のダメージ回復のために「読売」にリークしたら、朝日の「改竄」に被ったという説もあるが、どちらにせよリークのようだ)。
その、オリンピックの熱狂の中で憲法改定についての議論が自民党憲法改正推進本部で進んでいることも2月の出来事だ。webを検索すればいくつか記事には行き当たるものの、ネットニュースの見出しを見ている限りは気がつかない。自民党は2018年の運動方針として憲法の「改正案」を年度内に示す、としており、多分、ある日突然「改正案」がふって湧いたように報道されて、充分な説明と議論は尽くしたことになっているはずである。憲法についてはいずれ書くが、2週間、テレビのニュースがオリンピック一色に染まったことのツケは、いくらテレビというメディアの報道が信頼に値しないとはいえ、そのことで私たちが失ったものは少なくない。
そう気がつく時がくればいいが。
【2】夏目漱石と近代の病としての「工作員妄想」
このように2月から3月にかけて私たちは「工作員」という語の日常化や情報は操作し得るという感覚を自明のように生きていることを改めて確認する出来事が続いた。そしてそのことは実は私たちが思いのほか古い世界像を生きている、ということを改めて思い起こさせてくれた。というのは「工作員妄想」の歴史は思うにもっと古く、恐らくは「近代」の始まりに生じた病のような気がするからだ。
その話をしよう。
古谷の「工作員妄想」というよくできた造語からぼくがまず連想したのは、拉致問題ではない。夏目漱石の監視妄想・探偵妄想である。漱石の妻・鏡子が夫の「探偵妄想」についてこう回想しているのはよく知られるところだ。
全集にのこっている日記の一節にも、その書生さんが夏目の噂をしている夢のような話が書いてありますが、ちょうどその書生さんの二階の部屋から書斎が見下ろされるぐあいになっていて、毎晩部屋の窓に明かりがついて、そこで書生さんが相当高い声で音読するのです。(中略)それがいちいち夏目の異常な耳には、穏やかならぬ自分の噂や陰口に響くらしいのです。そうして高いところから終始こちらの方をのぞいて監視している。(中略)あれは姿こそ学生だが、しかし実際は自分をつけている探偵に違いない。こう一人できめているのです。学生さんこそいい面の皮です。
そこで朝起きて顔を洗って、いざこれから御飯という時になると、まずその前に書斎の窓の敷居の上に乗って、下宿の書生さんの部屋の方を向いて、大きな声で聞こえよがしに怒鳴るのです。
「おい、探偵くん。今日は何時に学校へ行くかね」とか、
「探偵くん、今日のお出かけは何時だよ」
とか、自分では揶揄(からか)ってるつもりか、先方でそんなにこそこそついてこなくたって、こちらで堂々と教えてやるよといったぐあいに、いっぱし上手に出たつもりらしいのです。
(述・夏目鏡子/筆録・松岡譲『漱石の思い出』1994年、文藝春秋)
漱石のこのような「探偵妄想」は漱石論の初歩の初歩なので、今更論じるのもいささか面はゆいが、『吾輩は猫である』や『明暗』といった代表的な作品を読んでいれば、しばしば探偵が登場することは大抵の人が気づいているだろう。
例えば『明暗』では「インヴァネスを着た小作りな男」が登場する。
インヴァネスを着た小作りな男が、半纏の角刈と入れ違に這入って来て、二人から少し隔った所に席を取った。廂を深くおろした鳥打を被ったまま、彼は一応ぐるりと四方を見廻した後で、懐へ手を入れた。(中略)先刻から気をつけるともなしにこの様子に気をつけていた二人は、自分達の視線が彼の視線に行き合った時、ぴたりと真向になって互に顔を見合せた。小林は心持前へ乗り出した。
「何だか知ってるか」
津田は元の通りの姿勢を崩さなかった。ほとんど返事に価しないという口調で答えた。
「何だか知るもんか」
小林はなお声を低くした。
「あいつは探偵だぜ」
(夏目漱石『明暗』)
この人物が、実際に探偵か否かは問題ではない。
「探偵に監視されている」という世界像が漱石の中にある。そういう世界に、漱石の作中人物は生きている。それが、漱石が彼の文学に書き留めた近代の感触である。
だから当然、漱石の作中人物はただ探偵妄想に憑かれているだけでなく、「探偵」が象徴するものが近代に根差す病の類いである、という程度の自覚はあるのだ。
「探偵といえば二十世紀の人間はたいてい探偵のようになる傾向があるが、どういう訳だろう」と、独仙君は独仙君だけに時局問題には関係のない超然たる質問を呈出した。(中略)
今度は主人の番である。主人はもったいぶった口調で、こんな議論を始めた。
「それは僕がだいぶ考えた事だ。僕の解釈によると、当世人の探偵的傾向は、まったく個人の自覚心の強過ぎるのが原因になっている。僕の自覚心と名づけるのは独仙君の方で言う、見性成仏とか、自己は天地と同一体だとかいう悟道の類ではない。(中略)今の人の自覚心と云うのは自己と他人の間に截然たる利害の鴻溝があると云う事を知り過ぎていると云う事だ。(中略)ヘンレーと云う人がスチーヴンソンを評して彼は鏡のかかった部屋に入って、鏡の前を通る毎に自己の影を写して見なければ気が済まぬほど瞬時も自己を忘るる事の出来ない人だと評したのは、よく今日の趨勢を言いあらわしている。寝てもおれ、覚めてもおれ、このおれが至るところにつけまつわっているから、(中略)この点において今代の人は探偵的である。
(夏目漱石『吾輩は猫である』)
「今代」とは「きんだい」とルビがふられている。漱石がこの時点で「近代」をどの程度、批評的にとらえていたかは漱石論の素人のぼくにはわからないが、探偵とは「自覚心」の象徴だと作中人物が論じていることは興味深い。この場合は自意識や自我と呼んだ方がいいだろう。この自我、「私」をめぐる知恵熱の如き煩悶の大衆化こそが、この国の近代の大きな特徴だからだ。
いきなり西欧からもたらされた「私」なるもの、そしてそれを可能にする言文一致体の一人称の普及は今で言う「セカイ系」の始まりだ。「私」のコントロールの術を知らぬから「私」の版図はひたすら肥大する。しかし、セカイにはまた別の「私」がいる。すると、自分の版図、つまり、「私」が虎視眈々と狙われている気がして来る。このように肥大した「自覚心」が危機にさらされる、誰かによって損なわれていないかと疑心暗鬼となる。これが漱石の分析する探偵妄想である。
この、探偵妄想、つまり他者に自分の領域を侵される、ということへの脅えがもっぱら金銭的な問題に接近するのが漱石の病の特徴だが、案外と近代の自我などというものは金銭に表象されるのかもしれないという点では、そう嗤ってもいられない。監視されるという感覚が自分の利害の損得だという漱石の論はややわかり難いかもしれないが、この国の現在、私たちの肥大化した自我としての「国」の損得、つまり、「国益」と「工作員妄想」が隣接していることを考えれば相応に説得力はある。私たちは東アジア諸国の「工作員」が日夜、領土や国益という「損得」を脅かさんと活動していると過度に信じたがる。「過度の」の領域が増えれば増えるほど「妄想」に近づくのは言うまでもない。
金銭はともかく、探偵妄想はこの国の近代にかろうじて成立したばかりの脆弱な自我が他者に脅え、「私」の領域が侵されるかもしれないという感情の上に成り立っていることは、漱石から最低限、読みとっておくべきだろう。
ちなみに、その漱石が結果として帝大講師の座を奪うことになる小泉八雲もまた、晩年は監視妄想に苛まれていた。
これよりさき、英国の女子教育家ミス・ヒューズ女史(ウエールスの人)が来て日本の教育を視察したが、ヘルンの名声を慕うて安井哲子女史を案内とし文科大学に赴きその講義をきいた。ワーズワースの講義最中であった。但し、ヘルンには無断であって、ヘルンが講義を終って教場を出る時に突然黒衣の婦人に握手を求められて驚いた。(中略)ただそれだけであったが、その事が偶然解職の前であったので、ヘルンは思い合せてこのヒューズ女史こそ探偵(スパイ)となって自分の講義をきき、日本政府に自分を讒(ざん)したのであると信じるようになった。当時留任運動の委員、安藤、石川、落合の三人にも、ヘルンは、ある婦人のために讒せられてかくなったという意味の述懐をした。
(田部隆次『小泉八雲(ラフカディオ・ヘルン)(第4版)』1980年、北星堂書店)
日本人、外国人を問わず、というよりも「近代」の「日本」を生きた人はこの「探偵」の視線を感じとることから始まった、というちょっとした証拠ではある。
しかし「探偵」とは得体の知れない何ものか、つまりいい換えれば、他者の視線である。他者の視線を感じとり監視妄想に苛まれるだけでなく、漱石は同時に他者の視線をあわせ持っていた。それが漱石を正気にとどめ作家にもした。だから探偵される漱石は同時に探偵する漱石でなければならなかった。『吾輩は猫である』では、金田家の回し者である「探偵」も登場するが、「猫」も実は「探偵」なのはそれゆえだ。
何探偵?----もってのほかの事である。およそ世の中に何が賤しい家業だと云って探偵と高利貸ほど下等な職はないと思っている。なるほど寒月君のために猫にあるまじきほどの義侠心を起して、一度は金田家の動静を余所ながら窺った事はあるが、それはただの一遍で、その後は決して猫の良心に恥ずるような陋劣な振舞を致した事はない。
(夏目漱石『吾輩は猫である』)
この「猫」こそが、大袈裟に言えば近代作家の眼差しである。以前、『「捨て子」たちの民俗学』に書いたことだが、多分、誰も読んでいないだろうからかいつまんで書くが、この「探偵」とは、近代文学の「方法」であった。
この国の近代において明治20年代、近代文学の成立に際して探偵小説の翻訳出版や新聞連載が多数なされたことはよく知られる。坪内逍遥なども探偵小説を翻訳した一人であって、その逍遥にとって「探偵」とはそのまま小説の方法論と意識されていた。
自叙体の主人公は猶注意深き探偵吏の如く常に毎に現在し其目を以て観其耳を以て聴き其触覚を以て感じ其口を以て客観的の観察と共に主観的の情実を語るべし
(坪内逍遥「英国小説之変遷」)
つまり、一人称によって成立した「私」は世界を観察し得る「探偵」、即ち「他者」なのである。
この探偵的方法は自然主義と近い意味を持つ。柳田國男が自身の自然主義を偶然、旅館で隣室に居合わせた見知らぬ他人の襖越しに聞こえる会話を、立ち聞きする様に比したのも、これと重なる考えかたである。この時の柳田は、この国の自然主義作者の特徴ともいえる「私」の肥大に極めて批判的であった。肥大する自意識が「探偵」を嫌うのは、「私」の領域に觝触するからでなく、冷静な観察者であるからだ。逍遥なり柳田が自身の文学を「探偵」と形容するのはひどく冷たい印象かもしれないが、それは対象の肥大した内面に取り込まれないために、つまり個であるために必要な文章技術であるからで、それは言い方を変えると世界に対して他者であることを引き受けることでもある。
などと話がやや脱線してきたが、「工作員妄想」が跋扈する世界像に於いて人々は未だ「探偵」に脅え続けている、ということになる。その意味で未だ近代の始まりの病にあり、それを対象化できないということは、未だ、「近代文学」以前を生きていると言う理屈になる。だからこそ「工作員妄想」を拉致事件以降の新しい言説と考えずに、むしろweb上に露呈した「未成熟な近代」の問題として考えていく余地がある。
すると、これほどにwebなりITが世界を変容させ、思想めいた議論もそのことを抜きに成立しないかのように見えながら、しかし、webを含む私たちの現在なり現実が思いがけないほどの「古い」ことを改めて思う。先ほど「古い」と記したのは「現在」が未だ「古い」創造力、いい換えれば「近代」の「想像力」の範疇内にある、ということを意味している。
その「古さ」を確認するために、冒頭に記した一群のニュースが描き出す平成30年2月の「現実」を今一度、おさらいしてみる。
社会の中に敵国工作員が潜み、社会の転覆を目論んでいる、とプロパガンダされ、情報は政治権力の都合のいいように「工作」され、そして官僚たちは政治家たちの政策を正当化するため統計資料を捏造し、公文書から不都合な事実を消す。
サヨク、というより、この国の外で襖越しに立ち聞きした探偵の耳にはそういう社会がここにあるように思える。
そして、そう記しながら、このような世界像の「古さ」にこそぼくは困惑する。この「古さ」は何より記述したぼくの思考なり言語の「古さ」に原因があるのだろう。しかし、このステレオタイプでしかないディストピアぶりは、ぼくにはジョージ・オーウェルの『一九八四年』の現実化に思えてならない、と、これもひどく意外性のないことを言わざるを得ないのだ。そう書くことは余りに凡庸だが、しかし、オーウェルの寓意の圏内に私たちの現在がある。少し前、webで「ディストピアあるある」なる文章を見た記憶があるが、この国の現在はまさにステレオタイプな「ディストピアあるある」的な範疇にある。
これは、いかなる停滞なのか。
去年あたりから『一九八四年』が売れている、という話を出版関係者からちらりと聞くようになった。今更、村上春樹の『1Q84』との混同でもないだろうし、アメドラではディックの『高い城の男』がアマゾンで映像化されたり、ここ数年、ディストピアという語そのものがなじみ深い語になったように、ディストピアそのものの流行は確かにある。
だが、それは流行というよりは、北米でも日本でもEUでも私たちの現実が『一九八四年』に近づいてしまっているからではないがと、これも月並みなことを敢えて書く。
ぼくはこの問題に限らず、このような「月並み」な批評や議論に立ち戻るべきではないか、と考える。それ故、ここから先は『一九八四年』論と現代社会という月並みなことを今更、書くことにする。
【3】『一九八四年』と文書改竄という職業
『一九八四年』について最低限確認しておけば、1948年に執筆され、既に原著はパブリックドメインとなった古典的ディストピア小説である。そして今回、問題としたいのは、その1948年の創造力の中に21世紀に入って十数年も過ぎ、ポストモダンということばさえ死語となった現在が、未だにある、ということについてだ。それはつまり私たちが社会なり現実を設計するための創造力が未だ1948年、70年前かそれ以前の水準にある、ということを意味する。
それは、当然だが、「探偵妄想」という近代初頭の病に未だ囚われていることの「古さ」とやはり重なり合う。
それではキンドルで『一九八四年』を買って(パブリックドメインなので無料バージョンの翻訳もwebにはあるはずだ)、読み進めてみよう。一応、全体のプロットは読んではいなくても何となく知っている、という前提で話を進める。
小説の冒頭、主人公のウィンストンは「探偵妄想」に似た視線を女から感じる。
しかしとくにこの娘はたいていの女性よりずっと危険だ、と以前、廊下ですれ違った時、彼女は横目でこちらの内奥まで貫き通すような一瞥をくれ、心がしばし、不吉な恐怖感で溢れた。〈思考警察〉の手先かもしれないという考えさえ脳裏をよぎった。そんなことはまずありそうもなかったが 安感はついぞ消えることがなく、彼女が近くに来ると、不安に恐怖と敵意までもが入り混じるのだ。
(ジョージ・オーウェル著・高橋和久訳『一九八四年』2009年、早川書房)
興味深いのはこの「他者への脅え」が「女性」への脅え、そしてそれを通り越して女性への「敵意」としてさえウィンストンの中にあることだ。
『一九八四年』は実はミソジニーやバックラッシュといった文脈で読みとれることは実は興味深いのだが、今回はふれない。だが、その感情は一方では主人公を最終的には陥れるオブライエンという男へのホモソーシャルな導入部での印象と、あるいはビッグ・ブラザーとの統合そのものがホモソーシャル的であることとあわせて読みとっておくべき問題だろう。
そういう文脈はさておき、こういった「探偵妄想」が決してウィンストンの妄想ではないのは、この世界では人々は居室一つ一つに設置された「テレスクリーン」で監視されているからである。このテレスクリーンは同時に端末でもあり、あらゆる情報はそこからもたらされる。
このテレスクリーンをスマホなり、対話型スピーカー端末なりと比べること自体、自分の想像力の陳腐さの証しとなるが、しかし、アマゾンの書評の一つには、ネットのある時代に作中の事柄は古くさすぎてつまらない、というニュアンスのものがあったので、一応「テレスクリーン」という比喩で「現在」を読み解くというわかり易い説明を一度だけしておく。
そもそも、「テレスクリーン」が予見したものはデバイスということばがなかった時点で、デバイスによって私たちの日常全てが監視可能になる、という未来である。
私たちはスマホの画面で留守中のペットや子供、遠方に住む年老いた親を「監視」できるのであり、「テレスクリーン」の日常化に気づいていないだけの話だ。それだけでなく、私たちの現在はスマホというモニター付きのデバイスをわざわざ持ち歩き、写真で自らを頻繁に撮影し、位置情報や検索・購入履歴も、その日の心拍数や歩いた歩数、その軌跡までiPhoneは勝手に記録し、そしてビッグデータとして吸い上げていく。スマホは携帯型テレスクリーンである。つまり、テレスクリーンのコンセプトが今や私たちの日常に違和なく組み込まれているのだ。テレスクリーンではライザップのインストラクターのように、毎朝の体操をサボタージュすると叱責が飛ぶが、ランニングなりその日の歩数について誉めてくれたり叱ってさえくれるアプリも確かあるはずだ。
今のところ個人情報の一元管理はされていないことになっているが、中国ではweb上で蓄積された個人の通販や決済データ、SNSの人間関係のデータ、そして公安などのデータに基づく信用情報が紐付けされ、点数化される「芝麻信用」が運用されている。点数は、クレジットの審査やあらゆるサービスに直結する。その便利さに類似したサービスが日本に導入される日はそう遠くないはずだ。
一方で何か犯罪が起きれば、まるでアメドラのように被疑者なり被害者なりの足取りが監視カメラの映像として次々と報道される。「監視社会」という言い方がもはや左翼の戯言にしか聞こえない程度には、私たちは監視されることになれている。
このように「テレスクリーン」一例だけでも私たちの社会は『一九八四年』が描いた想像力のなかにいる。
それは、私たちの現在が意に反して「監視社会」になったのではなく、望んでそうなったと理解すべきだ。
何故なら私たちの多くはこの「監視社会」をディストピアと思っていないからだ。その証拠に、『一九八四年』ではディストピアとして描かれた「監視社会」を生きながら、それを不快と難じない、あるいは快適さえと感じるメンタリティがいつの頃からか成立しているではないか。
いや、おまえは今しがた、私たちは近代の病としての監視妄想に苛まれていると言ったばかりではないか、と反論があるだろう。だが、スマホという「テレスクリーン」は同時に私たちの自我をテクノロジーで肥大させてくれる装置である。TwitterでもインスタでもLINEでもいいが、それは、物理的な距離を超えて私たちの内面を快適に拡張している。だからこそ、「工作員妄想」もまた肥大する。私たちは一方では、webのテクノロジーに快適に監視され、しかし、「工作員」に疑心暗鬼になっている。「工作員妄想」に苛まれながら国家の監視に安堵している。そういう矛盾を矛盾ともはや思えなくなっている。
そう考えると『一九八四年』をディストピア小説として読むことが可能なのか、いささか不安になる。
ぼくが「月並みな批評」がもう一度、必要だと考えるのはそれ故だ。
『一九八四年』の予見がいかに快適な現在としてあるかについては、「二分間憎悪」についてもいえるだろう。テレスクリーンに「敵」の映像が映ると人々はモニターの前で声をからして憎悪を叫ぶ。「憎悪」と漢字で書くよりは「ヘイト」と綴った方が恐らくは今の時代を連想しやすいだろう。「反日」なり「左翼」なり、差し出された「敵」にヘイトのことばを投げつける脊髄反射を身につける訓練を私たちは日々、ヤフーニュースのコメント欄あたりから受けている。林真理子が、定年退職して小遣の減った彼女の夫が、新聞や雑誌といった有償の情報源でなく「ヤフーニュース」のような無料のニュースに接していくうちに、言動が「ネトウヨ」化したと嘆くエッセイを前に読んだ記憶がある。
だが「二分間憎悪」に最も近いのは今では、「オワコン」扱いのニコ動だったのではないか。ニコ生あたりで繰り返された憎悪のことばで画面が埋まる光景は、ヘイトを「娯楽化」したといえる。あれがコメントする側にとって愉悦以外の何ものだというのか。
実は、「二分間憎悪」はオーウェルのフィクションではない。メディアが大衆の中の「他者」への憎悪を掻き立てることは今に始まったことではないが、第二次世界大戦下のBBCは「憎悪」と題する番組を放送していた。枢軸国をいかにヘイトするかという娯楽番組だ。そればかりか、チャーチルは、どういうものかまではわからないが、「憎悪訓練所」の設定を企てた、とされる。これらはいずれも、BBCで戦時下プロパガンダに関わったオーウェルの周辺で起きたことである。つまり権力者への礼賛でなく敵への憎悪の作法を「訓練」するという考え方が絵空事でなくあった。
しかし、オーウェルの関わったラジオ放送は当然、それを「娯楽」の装いで放送しなくてはならない。対して、実際にオーウェルが描いた「二分間憎悪」はオペラント条件付けが洗脳に近く、その点が描写そして古いといえば古い。「二分間憎悪」を不快なものとして描いたのは、ヘイトの娯楽化をフィクションとはいえ描くべきではないという倫理故なのか、あるいは、実際にそれを行うことの困難さを知ってなのかは判断がつかない。いずれにせよ、プロパガンダに関わった経験が作用しているはずだ。
ちなみに、ニコ動がヘイトを娯楽化できたのはそういう「ためらい」がなかったからだ。ただwebという工学がそれを可能にしたから行った。技術が可能にすることを実際に行うことに倫理的な躊躇がないというのが情報系・工学知の特徴で、そこにはかつての理系の人々が常に問題としていた、倫理という人文知との軋轢がない。
話を戻す。
ニコ生のコメントがAIで自動生成可能なことは数年前にニコ動自身が公表していたはずだ。つまり、ニコ生のことばは初歩的AIで再現できる程度に自動化している、ということになる。政治botと同じである。そして、このように、人々の思考が単純化され身体化されることが、『一九八四年』の世界が目論むことなのである。
そのために作中の世界で行われる最重要政策がことばの単純化である。
『一九八四年』の作中で主人公のウィンストンのような公務員が公務で用いるのはニュースピークという人工英語だ。これは英語から徹底して無駄を排除したものだ。『一九八四年』の巻末にはこのニュースピークについての架空の解説記事がわざわざ収録されているほどにオーウェルが腐心したアイデアである。
ニュースピークに於いては、同義語は一つに限定し他は抹消する。その作業を「ニュースピーク」作成に携わる男の話から確かめてみよう。
いや、かえってこの方がましだ。〈悪い〉がいささか曖昧なのに比べて、まさしく正反対の意味になるのだからね。或いはまた〈良い〉の意味を強めたい場合を考えてみても、〈素晴らしい〉とか〈申し分のない〉といった語をはじめとして山ほどある曖昧で役立たずの単語など存在するだけ無駄だろう。そうした意味は〈超良い〉で表現できるし、もっと強調したいなら〈倍超良い〉を使えばいいわけだからね。もちろんわれわれはすでにこうした新方式の用語を使っているが、ニュースピークの最終版では、これ以外の語はなくなるだろう。最後には良し悪しの全概念は六つの語――実のところ、一つの語――で表現されることになる。
(同)
「良い」を意味する多様な表現は「good」の一言に単純化される。後は「good」のかけることの何倍かで表現すればいい。それはgood(いいね)の個数しかない世界である。つまりはSNSであり、そこではもはや、言語としての「いいね」さえ用いられず、ハートマークや親指の示す方向によって表現される。アマゾンや食べログのレビューも同様である。LINEのスタンプもニュースピークの一種だろう。
そういうニュースピークを私たちは、喜んで用いている。
ラノベから「描写」が消えたり、形容詞が単純化したことについては以前どこかで書いた気がするが、これも自発的なことばの「ニュースピーク化」である。Twitterの140字は極端にしても、web上では「短く」「わかり易く」との抑圧はかなり強い。たまにwebの原稿依頼をうけてもこの部分で喧嘩になり掲載されない。星海社のサイトに放り投げてあるのは大抵そういう類いの原稿やインタビューだ。
ぼくの場合は知ったことではないから、嫌がらせのようにこの原稿も長く書くが、最初からwebがあった世代であればあるほど、ことばの「ニュースピーク化」には、自然に順応していくことになる。ぼくは別にここで美しい日本語の喪失を嘆いているのではない。だが、伝統主義者であるはずの「右派」のことばの貧しさ、単純さは安倍からネトウヨ、「宇予くん」まで共通なのはいうまでもない。それは首相のブレーンの文人が今や安岡正篤でなく百田尚樹であることにも如実に現れている。思想以前に学力やボキャブラリーがそもそも比べてはいけないが、違いすぎる。
新しい元号、よもや百田に相談、ということになっていないといいが。
こういったことばの単純化のもたらすものは明らかで、それは思考の単純化である。ニュースピークは思考の単純化を目論む政策なのである。国民がバカなのはいつの時代も為政者がのぞむことだ(ただ、今は国民も安倍・トランプを下回るバカでなければいけないのが厄介だ)。
「分るだろう、ニュースピークの目的は挙げて思考の範囲を狭めることにあるんだ。最終的には〈思考犯罪〉が文字通り不可能になるはずだ。何しろ思考を表現することばがなくなるわけだから。」
(同)
ここで言う「思考犯罪」とは、反国家的思想を密かに持つことだ。言語の複雑さや曖昧さや多義性こそが思考を複雑化させ、それが「思想」の温床となる。つまり、危険思想の持ち主になる。だから左翼のほうが、大抵頭がいい。ならば、「思想」を語り得ないほどにことばそのものを単純化させればよい。つまり、考えるためのことばを消去するのである。
それはつまりは、ぼくが「感情化」と呼んだ事態とも重なり合ってくるのは言うまでもない。
「二分間憎悪」同様、「ニュースピーク」にもモデルがある。それは1930年にイギリスで考案された850の単語と基本ルールからなる「ベーシックイングリッシュ」だ。第二次世界大戦下のイギリスの植民地であったインドでの統治に用いられた言語でもある。戦時下、チャーチルが連合国の共通言語としてのベーシックイングリッシュを推進せよと言い出し、BBCでオーウェルはこの案件に関わっていたようだ。実際に植民地向けのニュース原稿のベーシックイングリッシュへの書き換えも行われていた。これをエスペラント語の如き人工の国際語といえば聞こえはいいが、植民地に向けた、思考を単純化するための言語であったという側面は見ておくべき歴史だろう。
そしてこういった言語の単純化がもたらす思考の単純化は、『一九八四年』の世界では「犯罪中止」と呼ばれる。それは、危険思想、つまり社会体制を懐疑することを自ら踏みとどまる能力を可能にするもので、以下の如く、人々に「本能」のように植えつけられる、という。
あたかも本能によって、その一歩手前で踏みとどまれる能力のことを言う。そこには類推しない能力、論理上の間違いを見抜かない能力、イングソックにとって有害な議論であれば、どれほど単純な議論であっても誤解する能力、そして異端へと導くような一連の思考に対しては退屈したり不快感を覚えたりする能力が含まれる。犯罪中止とは要するに、「自己防衛的愚鈍」である。
(同)
「自己防衛的愚鈍」とはよくいったものだ。少し前、反知性主義という語が流行ったが、それとこの「自己防衛的愚鈍」はかなり近いように思われる。
このように世界を懐疑させないために『一九八四年』の世界ではことばを単純化させ、思考を単純化させるのである。
この思考の単純化と対となるもう一つの重要な政策が「歴史の書き換え」である。
『一九八四年』というと監視社会もの、という印象が流布しているが、実際に読んでいって実は生々しいのはウィンストンの職場での仕事のあり方だ。
彼の仕事は不都合な歴史の書き換えなのである。
ウィンストンはテレスクリーンに〝バックナンバー〟をダイヤルし、《タイムズ》の該当号を請求した。するとそれは数分のうちに気送管から流れ出てくる。彼の受けたメッセージは新聞の論説か記事に関わるもので、それが何らかの理由で改変、いや公式の言い方では修正、する必要があると看做されたのだった。例えば、三月十七日の《タイムズ》によると、〈ビッグ・ブラザー〉は前日の演説において、南インド戦線は当面異状なしだが、ユーラシアが近々北アフリカで軍事攻勢をかけてくるだろうと予言している。ところが実際には、ユーラシア軍最高司令部は南インドに軍事攻勢をかけ、北アフリカでは何の動きも見せなかった。そのために〈ビッグ・ブラザー〉の演説の一節を、現実に起こった通りに予言したという形に書き直す必要が生じたのだ。
(同)
政府の方針や政策と達成された事実、起きてしまった事実を合わせて過去の政府の発言を報じた記事や公文書を「修正」するのである。そうやって「修正」された結果、過去の政府発言と記事や公文書は常に一致を見るのである。
それでは、本来の事実、つまり、達成されなかった政府方針や不都合な事実の証拠となる文書や「修正」を指示した記録はどうなるのか。
ウィンストンはこの三つのメッセージ案件を処理すると、この口述筆機による訂正をすぐに《タイムズ》の該当号にクリップで留め、気送管に押し込んだ。それからできるかぎり無心に近い動作で、送られてきたメッセージや自分の書いたメモを丸めると、燃えさかる炎の待ち受ける〈記憶穴〉へと落とした。
(同)
「記憶穴」という含蓄に充ちた名の装置によって証拠そのものがなかったことになるのだ。
ここでわざわざぼくが指摘せずとも、この一年ほどのうちに起き、そして今も進行中の出来事を彷彿とさせるだろう。私たちが平成29年から30年にかけて、ウィンストンや「記憶穴」の存在を目の当たりにしたはずだ。
しかし、である。
平成30年2月の時点でこのオーウェルの小説の一節から思い起こされるこの出来事は、しかし、元号が変わって一、二年もすれば多くの人が忘却するはずだ。平成30年3月7日のプラットフォームでは、「公文書の改竄」のニュースが確認できても、瞬く間にタイムラインとともに消えていく。webそのものがあらゆるものをデータベース化し検索可能にしながら、しかし、「記憶穴」の役割を果たしているのである。
私たちがいかに忘れ易いかについての一例を挙げよう。Googleに「アメリカ 北朝鮮 攻撃」と入れると「11月」「12月」「1月」と予想が表示される。去年の10月22日の衆議院選挙の頃、私たちは朝鮮半島有事が目前だというニュースに胸躍らせていた(無論、皮肉で記すが、しかし実際に多くの人々は胸を躍らせていただろう)はずではなかったか。民進党の自滅があったとはいえ、その感情が政権選択を左右しなかったとは言わせない。
従って「記憶穴」の役割を真に果たす機能は、人々の心の内で行われるものとしてある。それをオーウェルは「二重思考」と名付けている。それは言い方を変えると「なかったことにする」思考である。
あらゆる記録文書が、その時々の正説と一致しているかどうかを確認するのは、単なる機械的な作業に過ぎない。しかし出来事は希望したように起こったということを覚えておく必要がある。そしてもし記憶を再整理したり、記録文書を改変したりする必要がある際には、それを行ったことを忘れる必要がある。その要領は、他の精神的技術と同様に習得可能である。現に党のメンバーの大半が、そしてもちろん、正統かつ知的である者の全てが、これを身につけているのである。オールドスピークでは、これはかなりあからさまに、「現実コントロール」と呼ばれている。ニュースピークでは、それは二重思考と呼ばれているが、ただし二重思考は、これ以外の機能も多く含んでいる。
(同)
普通、不都合な真実が修正されたことを気がつかないはずはない。それは『一九八四年』の社会でも同様である。しかし、気づいたこと自体をなかったことにする「精神的技術」によって歴史の修正は達成される。「二重思考」とは「自分が現実を誤魔化している」ことをわかっていながら、しかし自分の現実は少しも損なわれていないと信じる力である、ということになる。
その結果、最終的に何が起きるのか。
それは「歴史」の消滅である。
例えば、『一九八四年』の世界では社会体制の安定のため、三つの超大国が順列組み合わせで、産業としての戦争をしているという設定だ。しかし作中ではそのような戦争の歴史そのものが曖昧化しているのだ。
しかしその戦争の期間全体の歴史を辿ろうとしても、またある時点で戦っていたのは誰と誰なのかを明らかにしようとしても、それはまったく不可能だろう。書かれた記録にしろ口伝えの噂にしろ、現に今成立している敵味方関係以外のものについては、一言も触れていないからである。
(同)
いわゆる「歴史修正主義」は歴史の「書き換え」ではなく「忘却」を促すものだということを思い出そう(ヽヽヽヽヽ)。出来事を都合良く「修正」するのではなく、「なかった」ことにするのが「歴史修正主義」だ。だから「歴史修正主義」のもたらすものは「歴史」感覚の鈍麻である。それが一番、恐ろしい。『一九八四年』の世界が達成したのは「歴史の修正」ではなく「歴史の消滅」なのである。その意味でポストモダンの達成だといえさえする。
それでは、「歴史」が消滅するとどうなるのか。
歴史は止まってしまったんだ。果てしなく続く現在の他には何も存在しない。そしてその現在のなかでは党が常に正しいんだ。
(同)
もはや「歴史」はなく、「現在」しかない。「今」という微分化された現在がタイムラインとして流れていくがそれは歴史として蓄積されない。ただ、「現在」は常に為政者にとって「正しい」ものであり続ける。
『一九八四年』は、小説的物語としてはウィンストンの非合法組織との接触が発覚、そして、拷問によって恋人を売る、という結末で終わる。ラストでは恋人もウィンストンを売ったことが明らかになる。再会した彼女は言う。
「ときどきかれらは脅しをかけてくるのよ。耐えられないようなこと、考えるだけでも我慢できないようなことで脅してくるの。そしたらこう言ってしまうのよ。『わたしにそんなことをしないで。誰か他の人にして。誰々さんにやって』ってね。(中略)自分が助かるにはこれしかないと思って、その手で助かろうっていう気にすっかりなっているのよ。誰か他の人に対してやってほしいと心底願っているの。その人がどれほど苦しもうがちっとも構わない。自分のことしか考えてないのよ」
「自分のことしか考えてない」彼は鸚鵡返しに言った。
(同)
つまり「自分のこと」「自分の利益」しか考えられない人間となる。これもまたよく言われる「他者への想像力の欠如」と結びつけて論じることは易い。だからこそここでも凡庸な言い方を敢えてするが、人は「利他的」な行動を併せ持つことで「社会」はかろうじて可能となる。
それでは、利己的な欲求の果てに可能なものは何か。
彼は巨大な顔をじっと見上げた。その黒い口髭の下にどのような微笑が隠されているのかを知るのに、四十年という年月がかかった。ああ、なんと悲惨で、不必要な誤解をしていたことか! ああ、頑固な身勝手さのせいで、あの情愛あふれる胸からなんと遠く離れてしまっていたことか! ジンの香りのする涙が二粒、彼の鼻の両脇を伝って流れ落ちた。でももう大丈夫だ。万事これでいいのだ。闘いは終わった。彼は自分に対して勝利を収めたのだ。彼は今、〈ビッグ・ブラザー〉を愛していた。
(同)
オーウェルの小説と現在を照らし合わせ、あるあると思い当たるのとは別に、まるで北朝鮮や中国のようだ、とは感じられても、この国のようだとは考えられない人々も少なからずいるだろう。そういう人々に向けて、あなたは「二重思考」を無自覚に使い、そして安倍なり日本という〈ビッグ・ブラザー〉に帰依している、と言っても無駄であろう。
『一九八四年』をこのように「今」に照らし合わせて読みほどくと、さすがに吐き気がして来た。さて、あなたは吐き気を感じることができるだろうか。
【4】やり損ねた近代の「やり損ねのやり直し」をまたするのか
しかし、最後にもう一度、繰り返すが、それらも含めオーウェルの小説が描いたディストピア的創造力の中に私たちの現在が未だある、ということの意味だ。
今も、オーウェルがリアルだということは、かつてオーウェルがリアルであった「歴史」を忘却しているからに他ならない。
オーウェルの『一九八四年』は第二次世界大戦下、BBCでプロパガンダに関わり、「ニュースピーク」や「二分間憎悪」といった作中の描写が「現実」であった渦中を生きてしまったこと、そして、かつて社会主義にシンパシーを感じながらファシズム化した社会主義に裏切られた憤りという二重の屈託の中でつくられたものだ。つまり「戦時下」の経験を経た終戦直後の小説であり、つまりその時点での過去、そして、その時点での「現在」が孕む未来を想像したに過ぎない。多くのSF小説が描いた「未来」が陳腐になるように、ディストピア小説の描く未来もまた現在と照らし合わせて「陳腐」となるべきなのに、なっていない。
それは結局のところ「歴史」の忘れ易さに原因がある。忘れる、というよりはオーウェルの指摘したように「消滅」といった方がいい。ぼくがかつてポストモダニズム思想を少しも信用できなかったのは、とどのつまりは、それは「近代」を否定することで、「近代」は終わったものとして内省の材料から消去し、結局は「歴史」を忘却することを促すからである。現に、私たちは「近代」を忘れ、「戦時下」、そして「戦時下」と地続きの「戦後」を忘却しようとしている。
実は今回は、当初は前回に繋ぐ形で、「協働」「世界観」「ニコニコ」「投稿」といったwebやクールジャパン周りで用いられる用語が「近衛新体制」下のプロパガンダ用語だ、ということを書くつもりでいた。「協働」は、クールジャパンイベントによく引っ張り出されていた北米のアニメ研究者イアン・コンドリーが、コミケに於ける二次創作を版権元と同人作家の「協働」と表現(正確には翻訳者がこの語を選別した)したものがよく知られる。同時にこの語はニコ動の内部文書や、何より2000年以降の官僚文書に大量に登場する。近衛新体制は実は参加型ファシズムで、二次創作や「投稿」によって国民が自発的に参加することを促したが、その動員スキームこそ「協働」なのである。また「世界観」とは「近衛新体制」や「八紘一宇」の意味で使われる新語であり、「ニコニコ」は日本統治下の台湾で「ニコニコ共栄圏」なる語として用いられた。同時にこの語では元々は大正期に銀行が貯金と精神主義を結びつけた、つまり拝金主義を道徳で上塗りするために用いたキーワードで、戦時下に戦争の実態を隠蔽するプロパガンダ用語に転じたものである。
無論、今現在「使う側」はそういうつもりはない、と言うだろうが、少なくとも官僚レベルでは相応の自覚があるはずだ。ぼくは、この種のクールジャパン用語も一種のニュースピークに思える。
ことばというものが世界観や現実をデザインするのはオーウェルが描いたところである。だからこそ、こういう戦時下用語がクールジャパン周りに誕生することは気になるし、それ故、その歴史は辿っておくべきだと考える。そうしないと私たちの「現在」がいかなる「歴史」の範疇にあるかが見え難くなる。
webが進化し、思想もまたweb以降のテクノロジーに即して書き換えられている。しかし、「現在」がオーウェルの1948年の時点での第二次世界大戦の直後の想像力の範囲の中にある。そしてwebはむしろオーウェルのディストピアを快適な形で可能にさえした。そこではおよそ人文知の欠如した工学知・情報知の人々が悪気もなく無邪気に参画してニコニコディストピアに向けて日々邁進している。それが私たちの「今」の光景だ。文書を手作業で改竄する官僚も「工作員」同様にやがて、彼らによってAI化されるだろう。『一九八四年』のディストピアとはwebのもたらすポストモダンのユートピアとしていまやある、というのがぼくの感想だ。所詮、ポストモダニズムなど近代の掌のうちに最初からあった、ということだ。
ポストモダン思想はかつて、近代の無効を宣告し、たった今、安倍は戦後を消去しようとしている。それは、むしろ、「近代」や「戦後」という、大袈裟に言えば人類史に於ける「内省」の時代の消去のようにさえ思える。だとすれば、その結果、現れてくるのは「近代」なり「戦後」の問題を乗り越えた、あたらしい社会や歴史ではない。
「内省」を消去するなら、結局は、再び、やり損ねた近代の「やり損ねのやり直し」になる、とぼくは同じことを言うしかない。東浩紀が言っているらしい「観光客」なる概念が、柳田國男が明治の頃から唱えていた「世間師」という、分断された社会を繋ぐ知のありかたでしかないように(そのことは『社会をつくれなかったこの国がそれでもソーシャルであるための柳田國男入門』で書いた気がする)、「現在」に対する答えは「近代」の構想に腐心し頓挫した人々の思想のなかにしかない。
しかし、今や「近代の失敗のない無自覚なやり直し」は、この国だけでなく、ほんの少し前、西欧とは異なる近代を実現したといわれた中国(そういうことを言う人々が海外の思想業界にはいたものだ)や、あるいは「近代」のお手本であったはずのアメリカやフランスで繰り返されようとしている。それは歴史の進行、つまり成熟を拒み「近代」の幼年期に留まる所為にも見えて、なるほど、庵野秀明の『エヴァ』の「やり直し」が、シンジくんたちが14歳のままの世界にあるのはよくできたディストピアで、「絆」「つながること」の気色悪さを90年代にさっさと描いたことと併せて、やはり庵野は大事なところだけは間違えていないのだなあ、と思うのは余談。
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介

大塚英志
1958年東京都生まれ。まんが原作者としての近作に『クウデタア<完全版>』『恋する民俗学者』(http://comic-walker.com/)、海外のまんがアニメ研究者の日本語による投稿論文に門戸を開く研究誌『トビオクリティクス』を主宰。批評家としての近著に『感情化する社会』、『まんがでわかるまんがの歴史』、『動員のメディアミックス』(編著)など。
平成30年論
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






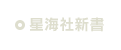



コメント