平成30年論
第3回:アメ・ドラと終わらない「ごっこ」の時代
大塚英志
柄谷行人があまり物を書かなくなった時期、韓流ドラマばかり観ているといっていたことに倣ったわけでもないが、僕も論壇誌や文芸誌で物を書かなくなって以降、義務的にそれらの雑誌を読む代わりに空いた時間でアメ・ドラばかり見るようになった。最初は律儀にDVDのBOXを買っていたりしたが、最近ではアマゾンプライムで、筆が進まぬ時などうっかり一日がかりでワンシーズン見てしまう、ということもしばしばある。
つい今し方見終わったのが「The Newsroom」というケーブルTVニュース局を舞台とするドラマだ。
かつてはそれなりにジャーナリストとして信念もあったが、いまは「ダメ」になっているニュース番組のアンカーマンの「カムバックもの」というハリウッド定番のストーリー仕立てである。しかし、この主人公が「ダメ」になっている理由が、酒浸りとか過去のトラウマといったお約束ではなく、視聴率を気にするあまり自分の意見を言えなくなってしまっている、というところが少し新しい。
冒頭、主人公はリベラル派大学教授の主催するジャーナリストの討論会に出席して、お茶を濁す発言に終始している。質問コーナーに移ると、白人で、金髪で、美人の女子学生が「もちろんみなさんわかっていると思いますが」的な前置きをして「アメリカが世界一偉大な国なのはなぜ?」という質問をする。まるで「日本のどこがすごいか」と誰彼かまわず訊きたがるような風景が、なるほどアメリカにもあるのかと思う。
他のジャーナリストはこれに対して「多様性」「機会」「自由」があるからと期待通り、答える。対して、主人公はアメフトのニューヨークジェッツがあるからとジョークでごまかすがウケない。そしてふと見ると、会場に「答えるまで帰さない」「(アメリカは)一番じゃない」と番組スタッフが出すようなスケッチブックに手書きのフリップを掲げる女性がいるのが目に入り(彼女が元恋人に似ていてそれで動揺した、ということが後でわかるのだが)、堰を切ったように、「本当のこと」を話し出す。
「アメリカは世界一の国じゃありません。カナダや日本にも自由がそれなりにある」「自由は200の主権国家の180ヶ国にある」と、一度、話し始めたら止まらなくなる。
質問した女子学生に「パーティーガール」と呼びかけ(まあ、はっきり「バカ娘」と言っているわけです)、「君が投票所に迷い込んだ時のために言うが、この国が世界一だと示す根拠は何もないんだ」「読み書きが世界7位、数学27位、科学22位」「平均寿命49位」「乳児死亡率178位」「平均世帯所得3位」「労働人口と転出4位」と数字を次々と掲げ、「世界一」なのは「人口に対する囚人の割合」「天使を信じる大人の数」「国防費」の3つだけだと、アメリカ礼賛がそのまま自尊心であるかのような、彼女の思い込みを容赦なく粉々にする。そして彼女に「20歳の学生にその責任はないが、君は最悪の世代の一人だ」と宣告さえする。しかし、彼の言葉は愚かな「パーティーガール」への説教でなく、ジャーナリストとしての自己批判に向かっていく。
彼の言葉は何より自身への怒りだったのだ。
彼は語り続ける。かつてのアメリカは「法律の制定もモラルに基づいて行った」「貧しい人々とでなく貧困と戦った」「知性を求めるのが恥ずかしくなかった」と語り、そしてそれが可能だったのは「尊敬される者たちによって情報を与えられていたからできたことだ」、つまり、ジャーナリズムが正しく機能していたからだと自身を諌めるように語る。しかし、それはリベラルふうの司会の教授でさえ期待しなかったまともすぎる、あるいは空気を一切読まない答えで、会場全体が思い切り引く。
挙句、女子学生からはハラスメントだと抗議される始末だ。
そうやって、主人公のフライングから物語は始まる。
フリップを持っていた女性が、物語構造上は、「冒険への召還」役の「使者」なのだが、その「冒険」とはジャーナリズムの復権である。そして主人公は元恋人のプロデューサーたちとともに、ジャーナリストとしての彼自身と、ワイドショー化したニュース番組の「立て直し」をしようとする。ハリウッド・ドラマとしての定型はしっかり踏まえ、いくつもの恋愛が交錯し、毎回、趣向を凝らしたプロットで「ドラマ」として充分に楽しめるから、以下に書くテーマめいた内容はネタばらしにはならないだろう(なっても別に構わないが)。
プロデューサーはジャーナリズム復権のミッションのため、主人公とスタッフにニュース編集の方針を示す。それは、
①選挙で投票する時に必要な情報か?
②議論の形としてこれが最良だろうか?
③背景(と字幕にはあるが「historical context」とセリフでは言っている)を紹介しているか?
④本当に2つの立場があるか?
の4つである。
冒頭での主人公のセリフ(「君が投票所に迷い込んだ時のために言うが」)や、この方針で示されているのは、「ジャーナリズムとは選挙という民主主義の根幹を機能させるための正確な情報と議論のあり方を提供するものだ」、という「定義」であることは明らかだ。つまり、民主主義のツールとしてのジャーナリズムを彼らは復権させようとするわけだ。冒頭の「パーティーガール」が象徴するのは、「正しい情報」を欠いた主権者の姿である。しかし、彼女が有権者として「バカ」であるその責の一端はジャーナリズムにある、というのが主人公たちの矜持だ。
彼らは、民主主義を嗤うのではなく、民主主義を機能させようとする。ドラマの中とは言え、公共メディアとして、とても正しい選択である。
中でも、「公共」のメディアのあり方として、注意しておくべきは4つめの「本当に2つの立場があるか?」という指針だろう。それは「公正さに偏るな」という意味だとも説明される。なぜなら、「立場」は「2つ」に限らないからだ。例えばそれはこういうことだ。「共和党が〝地球が平ら〟という試案を出したら〝地球の形で民主党と対立〟」という「2つ」の立場が見せかけ上あるように思えるが、「地球は平ら」という立場はそもそも成立しない。それなのに両論を扱うことが「公正さに偏る」という意味だ、と説明される。
どうやら、アメリカでも、政治的「公正」や「両論併記」というロジックで、「公正さに偏る」報道や議論がなされているのだな、とわかる。
さて、ここまで読んだ時、多くの人は、これはアメリカのトランプ政権下で作られた、リベラル派のジャーナリストが主人公のドラマだと思うだろう。しかし「The Newsroom」は、2012年のオバマ政権下の時代に作られたものだ。制作者側のアイロニーなのか、主人公は共和党員という設定になっている。
しかも、興味深いのは、ドラマの作中では、既に、アメリカは「分断」され、フェイクニュースや誤った情報にあふれている世界として描かれている点だ。まるで、トランプ政権誕生以降の状況への風刺のようだが、このような事態はもっと早く進行していたのだとわかる。
思想系の人々がトランプ以降の問題とする、「分断」「ポスト・トゥルース」、あるいは「共和党の地球が平ら法案」の喩えのように、存在しない「オルタナティヴファクト」を主張することがまかり通る、仮構の「公平さ」の主張などが、2012年の時点(TVドラマのデベロップメントの期間を考えるとその1、2年前)に少なくともTVドラマのテーマとなる程度には確実に認識されていたことがわかる。
主人公が共和党員である以上に興味深いのが以下の設定だ。
「ドラマ」である以上、主人公側が「戦う」「敵」がいる。それは視聴率第一主義の経営陣の親子として設定されているが、経営陣が主人公らを潰そうとするのは、彼が「ティーパーティー」を批判したからである。冒頭での主人公の暴走は、「天使を信じる大人の数」が世界一、あるいは、かつては「知性を求めるのが恥ずかしくなかった」、つまり、今は知性が蔑視されている、という発言からわかるように、「ティーパーティー」やそれを選挙基盤とする政治家への対決姿勢の表明と受け止められたのだ。
日本に例えれば、政権に忖度しまくりで、芸能ニュースあたりを無難に報じていたキャスターが、突然「日本会議」に喧嘩を売るようなものだ。
だが、主人公の本当の〝敵〟は、「ティーパーティー」そのものというより、それが象徴する「反知性主義」だ。「パーティーガール」の「わかっていると思いますが」という彼女の質問の仕方からわかるように、彼女は「求める答え」しか聞かず、かつ、その求める答えとは、自尊心と一体化した愛国心を満たすものだ。そういう答えを鸚鵡返すリベラル系コメンテーターをまず描くことで、それはリベラルの側でも同じだよね、というジャブを出した後で、物語は共和党支持者のキャスターが、「リベラル叩き」をするのではなく、「ティーパーティー」と対峙し、ジャーナリズムの復権と同時に「保守の再生」を図るという展開になる。しかも、その「保守の再生」とは、バカに向けた愛国心の垂れ流しではなく、バカな有権者を減らすことにある。
民主主義が機能しないのは国民がバカだからだ。確かに、ジャーナリズムに啓蒙などされると、イラッとくるかもしれないが、しかし、君たちはバカでいい、と囁く人々こそが民主主義の敵なのだ。
そういうドラマである。
ドラマではビンラディン殺害の描き方など、アメリカの独善に辟易する描写がないわけではない。
しかし、「ティーパーティー」が象徴するものによって、アメリカの分断が進む中で、ジャーナリズムと、今は野党にある「保守」(つまり、共和党)はどうあるべきか、というひどくまじめな問いかけが、ケーブルTV局のドラマでなされている。そもそも、日本でいわゆる「反知性主義」批判が議論として熱心に語られるのは2015年頃からである。しかし、アメ・ドラはこの数年、トランプの登場を予見したような「ハウス・オブ・カード」や歴史修正主義をモチーフとした「高い城の男」など、ポリティカルな先見性とエンターテインメントであることがきちんと両立する作品を登場させていて、比べても仕方ないが、ぼくにはそういう力量はない。
もう少しこのドラマの話をする。
ドラマのファースト・シーズンのラストでは、主人公は「ティーパーティー」が代表する「反知性主義」への対立姿勢を鮮明にする。いわば「宣戦布告」をする(まあ、そのことでセカンド・シーズンでは主人公たちは窮地に立たされるのだが)。
主人公は、彼のニュース番組で、33の州で選挙の際、免許証などの身分証の提示を求められるように法改正された問題を扱う。その結果、11%のアメリカ国民が選挙権を実質、失ったこと、それが「不正投票の阻止」と名目を掲げているが、実際にはブッシュ政権下での総投票数1億9600万票の内、不正投票は86票であったという「事実」を示し、法律は、共和党に投票しない人の数を減らすことが目的で、共和党員である自分はそれを恥じるとさえ主人公は言う。そして、自分は「強大な軍事力と良識ある政府」「法と秩序、資本主義を信じる」と「保守」としての立場を鮮明にした上で、「ティーパーティー」的な言説を次々と批判していく。いわば「ティーパーティーあるある」、である。
ティーパーティー、つまりキリスト教原理主義は、「科学を否定」「事実や情報を無視」「進歩を敵対し教育を悪者扱い」「女性の体への支配」「重度の外国人嫌悪、西欧ひいき」「反対意見への不寛容」「政府に対する憎悪」からなる、と「あるある」を列挙していく。引用はドラマの字幕からなので、正確な翻訳ではないが、ニュアンスはわかるだろう。
そして、とうとうキリスト教原理主義は「アメリカのタリバン」なのだ、と言い切る。結果、次のシーズンで「炎上」(あくまでドラマ内)するのだが。
「タリバン」という言い方は、なるほど、共和党、あるいはアメリカらしいと思わないわけではない。
しかし、ここで長々と引用した、ティーパーティー的思考の特徴は、2012年のアメリカのドラマの中でのセリフでありながら、2018年の日本の言論や政治のあり方に正確に呼応している。キリスト教原理主義にたいし、この国の「保守」言論が「日本原理主義」化しているのはいうまでもない。今や「日本」それ自体が「宗教」と化している。聖書の替わりに教育勅語あたりが持ち出され、その点で「日本原理主義」なのだと言える。ティーパーティーは「リベラル派の目的は国の破壊」だと罵倒し、「貧しいのは怠け者かバカだから」という自己責任論を振りかざす、というセリフも少し後のシークエンスにあるが、これも今現在の日本でよく聞くセリフだ。
ドラマは、このようにして数年前の時点で、反知性主義の時代に抵抗して、「あり得べきアメリカ」「あり得べきジャーナリズム」の姿を描いた。しかし、現実のアメリカはディストピア的選択をした。トランプを大統領として選び、フェイクニュースの担い手が、ジャーナリズムをフェイクニュースと罵倒することが喝采を浴びる事態となった。
そして、2012年に作られた彼の国の作品が今になって、アマゾンプライムで、日本で見られるようになったのは、単にアマゾンとこのドラマの制作をしたHBOとのビジネスの問題なのだろうが、しかし、よくできた偶然である。
いつもいう、偶然の批評、である。
さて、この国に当てはめて、もう少し考えてみる。このドラマが北米のケーブルTVで放送された直後、野党にあった自民党は、アメリカの共和党より早く政権に返り咲いている。野党時代の自民党がSNSを使った世論作りの準備をしていたことは前回触れたが、その後の自民党が支持基盤とし、さらに積極的に育成・組織化したのはまさにこのようなティーパーティー的有権者である。ティーパーティー的有権者を「日本会議」や「ネトウヨ」に置き換えれば、あまりにぴたりと当てはまる。そして、このドラマに示された「ティーパーティー」のあり方そのものを世論化してきたのが、与党復帰後の自民党である。
ドラマの「ティーパーティーあるある」と唯一違うのは、現在の自民党支持者が「政権を憎む」どころか、自己愛的に「政権を愛する」ことだ。しかし、これはドラマの中ではその時の与党はオバマ民主党政権だからだ。つまり「政権を憎む」とは、「リベラル政権を憎む」という意味だ。だから、与党復帰後の自民党はリベラル民主党政権時代に憎悪を向けることに熱心で、例えば、自民党(及びそれと一体だった官僚や東電)の長期に渡る原発政策の不作為の結果としてもたらされた原発事故は、たかだか、菅直人個人の不手際に狭小化された。
このような先進資本主義に於ける原理主義・反知性主義的政権選択をアメリカのトランプ政権、イギリスのEU離脱に先立ち、実は、日本が最初に達成してしまった。愛国心というと聴こえがいいが、韓国やフィリピンも含め自国原理主義の「感情」が、理性や知性を嗤う、という構図が世界中で政治や社会や言論を動かしている。
それらは、近代や民主主義の「終わり」というより「放棄」に思える。しかし、知性や理性といった社会を運用する基礎や近代的なシステムを放り出したとき、では、「近代」の対案としてあるのは、なんなのか。「原理主義」が国家を作れないことはイスラム国が証明したではないか。
だから、このドラマは「近代のやり直し」を訴えているように僕には見えた。
さて、この国の原稿を書いている4月半ば(星海社への入稿は4月12日である)、公文書改竄問題で安倍政権は末期のように見える。
しかし一方で、各世論調査の統計的偏りをあくまで統計学的に修正して、世論調査全体の動向を分析しているツイッター「はる/みらい選挙プロジェクト」によれば、内閣支持率は佐川氏証人喚問前後に微減した可能性があるが、30%台で横ばい状態である(4月9日、はる/みらい選挙プロジェクト情勢分析ノート)。自民党の支持率とともに思いのほか、強固である。この「内閣支持率30%台」の揺るぎなさとは何なのか?
「分断」がまさしく、この国にある証拠だという言い方もできるが、この30%が「バカ」だとは言わない。
この、自民党の「揺らがない」支持者は、僕のような旧世代でなく20代、女性より男性、地域でいうと西より東、ということは世論調査などからもうかがえる。だが、その「顔」が見えにくい。
この層が仮に「保守」だとした時、では、彼らが守ろうとしているのは何なのだろう。例えば、彼らは「日本」などというものは左翼である僕以上に信じていないのではないか、と思うときがある。彼らにどう語れば言葉は届くのか。そのことは、いずれ、考えてみる。
このドラマを見終えて、江藤淳のエッセイ『「ごっこ」の世界が終ったとき』を思い出した。'70年、安保再延長の初めに(正確には雑誌の登場は69年12月だったはずだ)発表されたエッセイだ。
このエッセイは大抵が誤読されてきた。左派の戦後民主主義的な言説の空虚さを批判した、あるいは、左派だけでなく右派を含む知識人の言論も「ごっこ」に過ぎないという言及のされ方をしてきた。しかしそれでは「言論」を嗤う、「反知性主義」的な知識人ヘイトのロジックになりかねない。
そうではない。
江藤が言いたかったのは、全く違う。
江藤があのエッセイで書いたのは、「われにかえる」という問題だ。私たちは「われにかえる」ことに脅えている。しかし、「われ」に返ることで初めて私たちの公的なものも、同時にそれに対する「反逆」も可能になる。さて、私たちはそれができるのか、という問いがエッセイの主題である(「The Newsroom」の冒頭で、暴走した主人公は、まさに、突発的に「われにかえってしまった」のである)。
そのことを、江藤のエッセイに沿って確認してみる。
まず、江藤のいう「ごっこ」のイメージの確認である。
「ごっこ」の世界では、どんな経験も決して真の経験の密度に到達することができない。もし途中でこの世界にほころび(ヽヽヽヽ)ができ、その結果ひとりが泣き出したり、誰かのひざ小僧から血が出たりすれば、とたんに「ごっこ」は成立しなくなる。その瞬間に現実が侵入して来て、みんなをわれにかえらせる(ヽヽヽヽヽヽヽヽ)からである。ふたたび禁忌と拘束にみちた現実の重みがのしかかり、子供たちは口々に「あーらよ、あらよ、だーれかさんはあらよ。いーってやろ、いってやろ、せーんせにいってやろ」とさけびながら、夕闇のなかに散って行く。(江藤淳「「ごっこ」の世界が終ったとき」)
このように江藤は「ごっこ」を単純に虚妄の比喩として使っていない。むしろ、「われにかえる」ことへの脅えの比喩としてこそ使っていることがわかるはずだ。ここを見落としてはいけない。
つまり、江藤のこのエッセイは、誰にでもわかる虚妄を虚妄と名指しするものではなく、私たちは「われにかえる」ことに耐えられるのか、という問いかけとしてこそあることがわかる。
だから、江藤はこの国が「ごっこ」の中から誰かが「われにかえらないよう」に互いに協調していることを何より批判する。
私がこんなことをいいだしたのは、現代日本の社会がこの「ごっこ」の世界によく似ているように感じられてならないからである。実際この社会は、真の経験というものが味わいにくい社会である。どこかに現実から一目盛ずらされているという感覚がひそんでいて、そのもどかしさと、そのための自由さ、身軽さが混在している。たしかに禁忌は緩和されているが、その半面ある黙契があって、なにかに対する共犯関係を強請されているという気分がびまんしている。みんながわれにかえらないために協力しあっているかのようでもあるが、ひとりひとりをとってみると、麻酔の覚めかけに味う吐き気のようなものを感じはじめていて、いったいこれはどういうことだろうかと思っている。(江藤淳「「ごっこ」の世界が終ったとき」)
「空気を読む」「同調圧力」といった言い方で、この国の言語空間を批判する際、抜け落ちているのはこの点である。つまり、一つの意見に誤っていると思っていても従うのは、互いに「われにかえる」ことを牽制しあっているからだ、と江藤は考える。「The Newsroom」の主人公も「ごっこ」を生きようとしたが出来なかった。恐らく主人公は「吐き気」にずっと耐えかねていたはずだ。あるいは、成る程、それは僕が、前回、感じた「吐き気」の正体かもしれない。
たった今、私たちは「公文書」をめぐって「ごっこ」をひたすら続ける政権と官僚の姿を目の当たりにしているが、彼らが「ごっこ」から降りられないのは「われ」に返ることに耐えられないからである。あの官僚たちが「吐き気」を感じていないはずはない。しかし、「われにかえって」しまえば、自らの嘘も、拠ってきたものもあまりに虚しいことが露わになり、そのことにこそ堪え難いから「ごっこ」を続けている。
では、「われにかえる」とはどういうことか。
江藤はアメリカ留学から戻り、「日本」で「われ」に返る。それは恐らく、江藤が「われにかえる」ことを最初に意識し、彼の批評の方法とした瞬間だったかもしれない。それは、「日本」で「われにかえ」ったのでなく、「日本」というものに対し、「われにかえ」ったのである。それはかつての「保守」にありがちなニヒリズムで「日本」を論じるのとは本質的に違う。
それは、東京オリンピックの開会式をテレビで見た時のことだった。
東京オリンピックの開会式の印象を江藤はこう描く。
いま日本は世界だ。世界は日本をとりかこむ敵意にみちた「他人」ではなくて、いま日本のなかに(ヽヽヽヽヽヽ)存在し、その中心に敬礼している。渋谷のアパートにふりつもるほこり(ヽヽヽ)も、宿屋にわいたノミも、東京中を掘りかえした建設という名の破壊も、みんなこの瞬間のためだったのだろうか。
「平和の祭典」という表向きの看板のかげで、なにか日本人にとってだけ意味のある秘密の儀式が進行している。私はその儀式のなかに吸いこまれ、昂奮のためにほとんど性的な充足を感じている。この充足感は、以前髪の毛をいじられたときのものに似ているが、本当はそれとは正反対のものかも知れない。そこには努力と犠牲が、なにものかにうけいれられ、意味づけられて行くような手ごたえがあるからだ。(江藤淳「日本と私」)
江藤はオリンピックの開会式に性的とさえ言える高揚を感じたと正直に告白する。この時、「日本人」である自分に江藤が感じた充足感を、恐らくは今の人々は、この国の再びの東京オリンピックにも期待するのだろう。
しかし、江藤はそこから「われにかえる」。否応無く、かえってしまう、のである。それは江藤が批評家だったから、としか言いようがない。
しかし、開会式が終ってテレビを消したとたんに、この「国家」は水にもぐった鯨のように姿を隠して、そのままどこかに行ってしまったようだ。それからわずか五日後に、中国が原爆の実験をおこなって夢をこわしてしまったからかも知れない。だがそれにしても、あのとき私を吸いこんで行ったものはなんだったのだろうか。それは行進というもののあたえる感動だけではない。なにかなをきっかけで姿をあらわした日本人の願望の集合のようなものだ。世界を自分のなかに含み、「他人」に絶対に出逢うまいとする願望。(前掲書)
江藤が開会式に感じたのは「日本人の願望の集合」である。それこそが、「ごっこ」のもたらしたものである。「他者」を拒み、ただ「われわれ」としてのみ、在ろうとする、いわば、「補完計画」状態だ。「ごっこ」の世界とは「他人」(まだ「他者」という現代思想用語が流行する前だ)を拒む願望であり、だから、世界を自分のなかに含」もうとする。つまりは、セカイ系である。オリンピックの高揚とはこのような「ごっこ」の表出であって、TV中継が終わった瞬間、江藤は「われにかえった」のだ。
しかし、ひとりで「われにかえった」人間は、憎悪される。誰もがわかりきった「ごっこ」を「ごっこ」だということは悪だというのが「ごっこ」の世界の唯一の規範だ。
ここでは「思想」はいくら唱えてもよい。あるいは「西洋」や「近代」の模型を頭のなかにこしらえて、その「人形の家」で生きているような錯覚をおこしてもよい。してはいけないのは、そういう幸福な「みんな」に、それは「西洋」でも「近代」でもないただのインテリ用のおもちゃだ、なぜなら君たちはチャンと幸福に生きているではないか、本当にこの日本で「西洋」や「近代」を生きようとすれば、そんな無傷のツルリとした顔はしていられないぞ、ということだ。つまりここでしていけないのは自分の思想を生きることだ(ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ)。いいかえれば「みんな」に対して「他人」になることである。あるいは自分の延長ではない「他人」が目の前にあらわれたとき、その存在のあたえる痛みと重みに耐えることだ。(前掲書)
先のドラマの主人公がしたのは「自分の思想を生きること」である。ドラマでは「痛みと重み」は主人公へのバッシングとして描かれるが、江藤のいうのは「孤立」ということだ。
江藤はあらゆるものから「われにかえる」。それは、あらゆる人たちに対して「他者」であることを意味する。そういう人だった。
およそ江藤淳という人は「われにかえる」ことを常に批評の根拠としてきた。
江藤には、「アメリカと私」「日本と私」「文学と私・戦後と私」、あるいは「山川方夫と私」と、「○○と私」と題されたエッセイが極めて多い。江藤はどこにいても、いかなる状況でも、それこそ、唯一の盟友としての山川の死に際しても「われにかえ」ろうとした人だった。その江藤が晩年、妻の死によって「われにかえれ」なくなっている様に、考えてみれば、ぼくは残酷な言い方だが、「吐き気」を覚え、彼を拒否したのだ、とも今になればわかる。
だから、こういう言い方をしていいのかわからないが、江藤が一人で自死し、対して、三島や西部邁が誰かの助力をもって自死したこととの違いは、残酷だがこういうことではないのか。三島や西部は最後に「ごっこ」の相手を必要とし、江藤は犬を知人に譲って、最後は、一人で死んだ。一人で、死ぬことで最後は「われにかえろう」としたのだ。
では、そうまでして「われにかえる」ことで、それでは何が可能になるのか。
それはいうまでもなく現実の回復であり、われわれの自己同一化(アイデンティフィケーション)の達成である。そのときわれわれは、自分たちの運命をわが手に握りしめ、滅びるのも栄えるのも、これからすべて自分の意志で引き受けるのだとつぶやいてみせる。それは生甲斐のある世界であり、公的な仮構を僭称していたわたくしごと(ヽヽヽヽヽヽ)の数々が崩れ落ちて、真に共同体に由来する価値が復権し、それに対する反逆もまた可能であるような世界である。われわれはそのときはじめてわれにかえる(ヽヽヽヽヽヽ)。そして回復された自分と現実とを見つめる。今やはじめて真の経験(ヽヽヽヽ)が可能になったのである。(江藤淳『「ごっこ」の世界が終わったとき』)
「われにかえる」ことで、初めて私たちは「私」となれる。仮構の「公」を江藤は「わたくしごと」だと言い切っている。江藤に言わせれば、今時の愛国心や「日本」など「わたくしごと」の極だろう。『エヴァ』のシンジくんのように脆弱な私が必要とする「公」はその限りに於いて、「社会」だろうが「日本」だろうが「わたくしごと」である。かつて「左翼小児病」という言い方があったが、今は「右翼小児病」が蔓延している。安倍や「ネトウヨ」に代表される人々のいう「国家」などというものは「わたくしごと」以外の何ものでもない。政権まわりの「私益」が「公益」と言い繕われていることの具体例は、掲げる必要もない。
江藤は、「私」になることで「共同体に由来する価値が復権し、それに対する反逆もまた可能であるような世界」、つまり、ナショナリズムもそこへの批判も初めて可能になる、と考える。ドラマの主人公は「報道」で、江藤は「批評」で、「ごっこ」という自己防衛の「わたくしごと」から、「われにかえろう」としているわけだ。
さて、このエッセイを書いている今、公文書問題などという、どうでもいいことより、東アジア情勢や憲法改定などもっと重要な問題があるはずだ、という議論がある。多くは、強固な、三十数パーセントの側に立つ人々の主張だ。しかし「公文書」改竄は、有権者に正確な政策評価の情報を与えることを拒んでいるという一点で、国民をバカに留めるという、近代、ないし、民主主義へのサボタージュであることが問題なのである。些細な問題ではない。改竄問題が露呈したということは、戦後の日本の言説や政治を支えていた官僚システムとそこに依存する政治・言論の相互依存関係、すなわち、「ごっこ」がもはや取り繕い難くなって来たことを意味する。
だとすれば、東アジア情勢の激変がこのタイミングで起きたのも偶然ではない。
そもそも、江藤の、「「ごっこ」の世界が終ったとき」における政治的主張とは、この国は、「日米安保による対米追従」と「自主防衛論」という、二つの「ごっこ」から「われにかえ」れ、というものだった。嘘だと思うなら、敢えて引用はしないから、原典に当たることだ。
江藤にとって、「占領」を引きずったままの戦後の言説そのものが「ごっこ」である。したがって、「対米追従」は、「占領」の延長でしかなく、「自主防衛」だ、核武装だといういまも続く勇ましい議論も、江藤に言わせれば、「日米安保」が永遠に続くと無邪気に信じた上で、いきまいているにすぎない。村上龍の小説で、ヤンキーゴーボーム、と叫ぶ青年に江藤が憤ったのは、「自主防衛論」と同じ、「われにかえらない」言説だからだ。
江藤のエッセイから50年近くを経て、左派の言葉はとうに終わっている。しかし、右派の言葉だけが、「ごっこ」を続けている。「保守」は、未だ、「日米安保による対米追従」、「自主防衛論」を都合良く、使い分けている。成田でなく、横田基地に降り立ち、帰りはハワイで、リメンバー・パールハーバーとツイートするトランプに、「国家」と自尊心が一体化した人々が怒らないのも頷ける。
それができないのは、怒った瞬間「ごっこ」が終わってしまうからだ。だから、今にも泣き出したいのに我慢して「ごっこ」をいる。
「改竄」問題が奇妙なのも、国民の7割が「われにかえ」りながら、3割が「ごっこ」を必死で維持しようとしている点だ。しかし、東アジア情勢に関していえば、日本以外の国は「ごっこ」をとうに終えていて、
日本だけが単独で「ごっこ」の維持に必死だというのは流石にわかる。今や、江藤が「ごっこ」と言い捨てた「保守」の言葉だけが延命して、東アジア外交での孤独の「ごっこ」を続けているのだ。
トランプは、内政ではフェイクニュースからなる新しい言語空間を作った。だから、東アジア情勢に関しても平然と新しいステージ作りに乗った。だから、今、東アジアは、日本以外は、違うステージにある。新しいバランスの中で「立ち位置」を取りなおしている。現に日本が動かなくとも東アジア情勢は動いている。
この国では、戦後日本を「平和ボケ」と嗤うことに熱心だった人が、この間、北朝鮮が攻めてきたらどうする、日米同盟強化だ、いや、核を持って自主防衛だ、という江藤の唾棄したレベルの「ごっこ」論を血気盛んに語ってきた。安保関連法案も成立し、九条は「変えること」が今や、議論の前提だ。しかし、それこそが右派の「安保ボケ」「戦後ボケ」ではないのか。
「話し合い」など無意味だと、散々嘲笑した「外交交渉」に拠って、しかも、あれほど見下してきた韓国政府の外交努力によって、事態は転換しようとしている。このままいけばトランプと金正恩がノーベル平和賞というブラックジョークが現実になりかねないが、日本の圧力の賜物などと言い繕っても、日本がこのゲームに参加を拒まれているのは、この国が「一人ごっこ」の継続を東アジア状勢の中で望み、その「ごっこ」を国民が政権を支える程度に支持しているからである。
だから現在の東アジア情勢を考えた時、この間の外交や安保法制、あるいは九条改憲論は果たして正しい選択だったのかと考える必要がある。この国は、少子高齢化による「縮小していく国」であり、好き嫌いでなく、東アジアは中国を中心に回る。アメリカの東アジアにおけるカウンターパートは、中国である。何より、朝鮮戦争が「休戦」から「終戦」となることは、東アジアにおける「ごっこ」の決定的な終わりを意味する。「朝鮮戦争」が終結し、北朝鮮が国際社会に復帰すれば、日本はもう一度、「戦後保証」を突きつけられる。そういった現実に「われにかえる」必要がある。
東アジアの小国としていかに生きていくべきか、軍事以外の安全保障の術はないか、東アジアの中での立ち位置をリセットしておくべきタイミングなのに、たった今も、それを逸している。国際社会における「ごっこ」の時代が東アジアの中で確実に終わろうとしているのに、「一人ごっこ」の継続を目論んでいるのが現在の「日本」ということになる。
そう考えると、いわゆる公文書問題の中でも、自衛隊日報隠蔽問題は、第一次安倍政権で綻び始めていた「ごっこ」を取り繕おうとする醜態だったことがわかってくる。
最後にその話をする。
南スーダンでのPKOは日報内の「戦闘」の2文字の記述を表に出させないために〈記憶穴〉に消えていた。それは、あくまで自衛隊の海外派兵が、非戦闘地域に対してなされている、という「ごっこ」からこの国が「われにかえらない」ためである。
しかし、そもそも2003年から2009年に至る自衛隊のイラク派遣(当時から「派兵」と書くと新聞などでは「派遣」と赤字が入った)を、しかしぼくが今も「派兵」と書くのは、自衛隊が「戦闘地域」で戦闘に参加していた事実があるからである。
その「事実認定」は、2008年4月の名古屋高裁の判決としてなされた。つまり、三権の一つ、司法の下した判断である。それは、ぼくも関わった「自衛隊イラク派兵差止等請求控訴事件」の裁判で、判決は、民事上はぼくたち原告の敗訴だが、一方、イラク派兵は「憲法違反」であると同時に、「イラク特措法」違反でもあるという司法の判断が事実として、出ている。当時、田母神俊雄元幕僚長が判決に「そんなの関係ねえ」と言い放ったことを覚えている人がいるかどうかはわからないが、仮にも司法の判断を、辞めたあととはいえ自衛隊の幹部が「関係ない」ということはシビリアンコントロールの根拠に関わってくる。そういう「法」の軽視が少なくとも当時から自衛隊の一部にでもあったことが今につながる。
詳しくは星海社新書『今改めて、「イラク自衛隊派兵訴訟」判決文を読む』に当たるなり、webで判決文全文を探すなりしていただければいい。重要なのは、イラクに於いて自衛隊はただ、「給水」を行っていたのではないということだ。それはあくまでも、陸自のPKO活動である。
もう一つの自衛隊の活動は、空自による多国籍軍の兵士の輸送である。そのことは国会での当時の答弁や公文書で裏付けられ、それは、誰でも手に入るし(この原稿の校閲資料としても校正者が入手してゲラに添付されていた)裁判でも証拠採用された。バグダットが当時、「戦闘地域」であったことは、例えば、参議院外交防衛委員会で「バグダット空港に降りる、あるいはバグダット空港から飛び立つとき、あるいはバクダッド空港におるときに」「ロケット砲が来る」「危険性と裏腹に」隊員はある、と久間防衛大臣の答弁として記録に残る。地対空ミサイルを回避するフレアがバクダットで自動発射されているという事実もある。これらの証拠の積み重ねで裁判所は、バクダッドは「戦闘地域」だったと認定した。そして、このような「戦闘地域」であるバグダットで、多国籍軍の武装要員の移送という「後方支援」を行ったことは「戦闘」の参加を意味し、イラク特措法と憲法に違反する、と司法によって判断されたのである。
自衛隊の活動を違憲などとは失礼だ的な議論もあるようだが、司法の判断は失礼かどうかではなく、法が正しく執行されているかである。特にこの判決は、憲法以前に「イラク特措法」違反であった点が大きい。自衛隊の海外派遣が法を侵し「派兵」となった事実は、安保法制をめぐる議論の中できちんと検証されるべきだった。
そもそも、このイラク特措法を改定し、サマワの陸自給水活動が終了後もバクダットでの空自による後方支援を継続したのが、当時の安倍内閣である。つまり、「違法状態」部分が、かつての安倍内閣で継続されたのである。このように、安倍には「違法状態」で自衛隊を戦地で活動させた前科がある。だから、安保法制をめぐっては、イラク特措法を守らなかった首相が推し進める法案が「守られる」のかを問うべきだった。違法状態の後方支援にイラク派兵違憲・違法判決が出たのは、安倍が持病で退陣した後の福田内閣の時だったが、同年の11月28日には空自の派遣輸送航空隊への帰還命令が出た。小さく新聞に出ただけだった。福田内閣は、違法状態は流石に継続できなかったということだ。
このイラク派兵の違法状態を、安保法制をめぐる議論において触れたのは例外的に、全く空気を読まない(褒めている)山本太郎だ。当時、航空自衛隊が輸送した6割が米軍だったと彼は国会で指摘したが、ほとんど注目されなかった。一方、ジャーナリストの布施祐仁が南スーダンについての情報公開を請求する中で「日報」という文書の存在に気づき、2016年9月30日に情報開示請求をしたところ「破棄」と回答され、「日報」問題が浮上した。
「日報」の隠蔽は、公文書改竄と同様に有権者に正しい情報を開示しないという点で、民主主義へのサボタージュである。しかし、「陸自」日報からは「空自」の活動の実態は見えて来にくいだろう。イラク「日報」をつかまされても、イラク派兵で、特措法や九条が破られた事実は見えてこない。
現在の憲法論議の愚かさはイラクで「憲法が破られた事実」を黙殺することである。イラク派兵で、自衛隊は戦闘に参加しない、という暗黙の了解が綻んだ。その「事実」(イラク戦争の実態や犠牲者、その正当性も含め)から「護憲」「改憲」は始めることをし損ねた。空自の後方支援問題を直視しないことは、「日報」隠しよりずっと根が深い。それは「一人ごっこ」への加担以外の何物でもない。
自衛隊の海外派兵にぼくは全く同意できない。
しかし、賛同する人々こそ、安保法制の議論の中で、イラクで何が起きていたのか、そして、イラク特措法や憲法は遵守されたのかを「公文書」で検証し、その是非を議論すべきであった。イラク戦争当時、久間防衛大臣は「実は結構危険で工夫して飛んでいる」とも呑気に述べているが、この国の中での安全保障をめぐる「ごっこ」を続けるために自衛隊の人々をリアルな戦闘地域に送っておいて、公文書を隠蔽する人々に、防衛を語り、憲法九条をいじる資格があるのか、とサヨクのぼくは思う。本来、違法状態の派兵を許してはならないと憤るのは「保守」の役割で、イラクの違法・違憲状態を検証してこそ、「改憲」は主張されるべきだ。左派もまた、そこから「護憲」論をたちあげるべきだろう。
ちなみに、江藤が、「「ごっこ」の世界が終ったとき」で述べたのは、外交交渉により、「米軍の海上兵力をグアムまで後退」させ、日米関係の対等な再構築をすることであった。まるで鳩山由紀夫のようなことを70年の時点で江藤は言っている。なるほど、鳩山は「保守」として「ごっこ」から「われにかえろう」とし、江藤のいうように孤立する羽目となったということだ。この国では「ごっこ」を終わらせようとする政治家は潰されるのである。それもこの国が「一人ごっこ」を続ける理由だろう。だが、多分、そういうステージそのものが変わりつつある。
だからこそ、この国の「保守」の安全保障論議が「一人ごっこ」になった、今、さすがに「われにかえる」べきなのに、この国に、東アジアに足場はもはや、ない。だから、友達が皆、帰った後の夕暮れで、泣きそうになりながら、一人、「ごっこ」を演じているのだ。
2018年4月、終わらない「ごっこ」の時代にこの国は単独で身を投げた。
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介

大塚英志
1958年東京都生まれ。まんが原作者としての近作に『クウデタア<完全版>』『恋する民俗学者』(http://comic-walker.com/)、海外のまんがアニメ研究者の日本語による投稿論文に門戸を開く研究誌『トビオクリティクス』を主宰。批評家としての近著に『感情化する社会』、『まんがでわかるまんがの歴史』、『動員のメディアミックス』(編著)など。
平成30年論
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






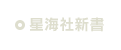



コメント