ジセダイ総研
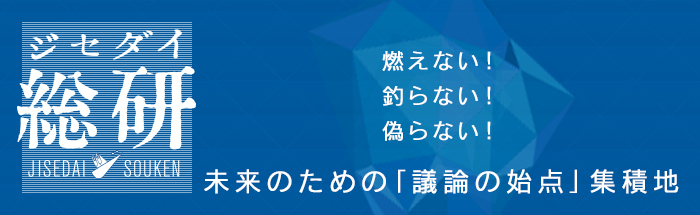
理想化された1964年の東京オリンピック
東京オリンピックは、3つ存在する。1940年の大会、1964年の大会、そして2020年の大会だ。このうち、1964年のそれは過剰に理想化されている。
日中戦争の影響で返上した1940年の大会は戦時下を象徴し、目下様々なトラブルを引き起こしつつある2020年の大会は「失われた20余年」を象徴する。この2つの東京オリンピックはいわば「暗黒時代」を背負っており、否定的なイメージを免れない。
これに対し、1964年の大会は高度成長期を象徴し、肯定的なイメージが強い。
当時の日本は、戦後復興を成し遂げ、新幹線や首都高を建設し、先進国の仲間入りを果たした。当時の日本人はみな夢や目標を持って、輝かしい明日に向かって努力していた。われわれはいま一度、2020年の東京オリンピックの実現を通じて、あの「黄金時代」を取り戻さなければならない。1964年の東京オリンピックは、このようなイデオロギーさえ今日まとっているのである。
思えば、高度成長期ほど肯定されやすい時代も珍しい。一昔前の「三丁目の夕日」ブームや、昨今の田中角栄ブームなどもその一例だろう。あるいは、リベラル派の「護憲平和主義」や、保守派の「専業主婦」賛美もまた、そうかもしれない。いずれも、高度成長期という特殊な時代に根を下ろした価値観だからだ。
とはいえ、1964年の東京オリンピックも、それが象徴する高度成長期も、そんなにすばらしいことばかりではなかった。その過剰な理想化は、戦時下の再評価などと同じく、われわれの目を曇らせ、社会を間違った方向に導くのではないだろうか。2020年の東京オリンピックを迎えるにあたって、神話化された1964年のイメージは解体されなければなるまい。
圧倒的な国民の無関心
そのためには、前回の東京オリンピックの実態を知ることが重要である。1964年の大会は、用意周到に準備され、国民にも歓迎され、大いに盛り上がって成功したと思われている。だが、実際はそんな単純ではなかった。
そのことを象徴するのが、前年の1963年1月6日読売新聞朝刊に掲載された記事「試練の年63年 オリンピック 盛り上がらぬ世論 "責任体制"どうつくる」である。ここでは、きたるオリンピックの問題が4点に整理されている。
①国民が、関係者まかせで無関心である
②組織委員会が、無責任で「半身不随」状態である
③関係者が、オリンピックに便乗して補助金や公共事業を乱発している
④関係者が、主役である選手を無視して独善的なプランを立てている
驚くべきことに、1964年のオリンピックも、今日と同じような批判に晒されていたのだ。これは読売新聞だけではなく、各紙で見られた論調だった。
以上の4点のうち、国民の無関心は特に深刻だった。1964年1月にNHKが行った世論調査にも、国民の無関心ぶりが強く出ている。以下では、東京都区部の数字にしぼって見てみよう(日本放送協会放送世論調査所『東京オリンピック』)。
まず、「あなたが近頃どんなことにいちばん関心をもっていらっしゃいますか」という設問。これに対して「オリンピックへの関心」と答えたのは、たった「2.2%」にすぎなかった。「いちばん」の関心とはいえ、これはあまりに低い数字だ。
それ以外にも、都民の無関心を示す調査結果が並ぶ。「オリンピックは結構だが、わたしには別になんの関係もない」に賛成は「47.1%」。「東京オリンピックは、それぞれの関係者がなんとかやってくれるだろう。わたしたちがとやかくいうことはない」に賛成は「64.0%」。「オリンピックを開くのにたくさんの費用をかけるくらいなら、今の日本でしなければならないことはたくさんあるはずだ」に賛成は「58.9%」。
さらに、オリンピック募金への寄付は「61.6%」が行わず、オリンピック記念切手は「76.8%」が買わず、オリンピック記念メダルは「94.4%」が買わず、オリンピック開・閉会式の入場券への申し込みは「81.1%」がしなかったという。
同じ調査は、オリンピック開会直前の10月にも行われたが、ほとんど同じような結果が出ている。「オリンピックは結構だが、わたしには別になんの関係もない」にいたっては、賛成が「56.8%」と10ポイント近く増加。また「あなたご自身として、そのほかに(引用者註、「募金のほかに」の意)、今度のオリンピックになにか協力したいという気持ちをおもちですか」には、「42.2%」が「もたない」と回答している。
NHKは金沢市でも同様の調査を行っているが、数字に大きな違いはない。国民の多くは、少なくとも開会直前まで、オリンピックに相当無関心だったわけである。
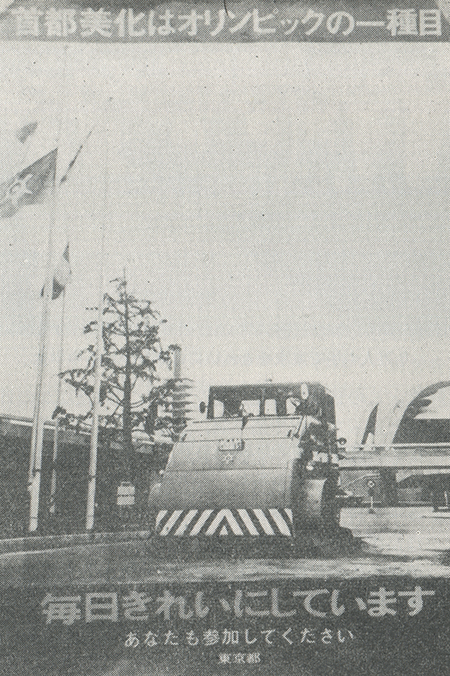
「首都美化はオリンピックの一種目」。東京都の美化運動ポスター。
『第18回オリンピック競技大会 東京都報告書』より。
無責任な組織委員会
こうした国民のしらけムードを作った原因のひとつが、組織委員会の無責任体質だった。
組織委は、オリンピック招致成功後に設置される、準備運営団体である。実務的な組織であるため、当初そのメンバーは官僚中心で少数になるはずだった。
ところが、そこに横槍が入った。自民党が政治家を委員に入れろと要求したのである。社会党や、委員から除外されていた自治庁や郵政省などもこれに加勢した。独自の財源を持たない組織委は政界に弱く、たちまち寄せ集めの組織となってしまった。
この結果、1959年9月の発足時、組織委は22名の体制となった。その内訳は、政府2(文部大臣、総理府総務長官)、国会議員5(自民3、社会2)、東京都2(都知事、副知事)、学識経験者3、財界2、報道関係2、日本体育協会5、その他1。なお会長には、大蔵官僚出身で衆議院議員の津島寿一、事務局長には、朝日新聞出身で水泳指導者の田畑政治が就任した。
このような寄せ集めの組織委は決断力に欠け、様々な意見に左右された。準備計画の変更も頻発し、国内では「無責任」と批判され、国外では「どの決定が本当か」と顰蹙を買った。
さらに1962年5月オリンピック担当相に就任した川島正次郎とも対立し、ついに同年10月会長と事務局長が辞任に追い込まれた。この背景には、田畑事務局長に対する、川島五輪相の個人的な恨みがあったともいわれる(波多野勝『東京オリンピックへの遥かな道』)。
その後、事務局長は与謝野秀(外務官僚。与謝野晶子の息子)に決まったが、会長がなかなか決まらず、翌年2月になってようやく安川第五郎(日本原子力発電初代社長)に落ち着く有り様だった。つまり、開会の約2年前に、組織委トップの不在が続いたのである。
今日でも、2020年大会の組織委員会(会長・森喜朗、事務局長・武藤敏郎)をめぐって、同じように無責任体質が問題になっている。新国立競技場の問題などをめぐって、オリンピック担当大臣やスポーツを所管する文科省との責任のなすりつけ合いも起こっている。
一般には、森喜朗の不穏当な言動に注目が集まりがちだが、彼を辞めさせたところでどうにもなるまい。これは組織的な欠陥だからだ。責任ある体制にするためには、権限を一箇所に集中しなければならない。ところが、オリンピック利権に群がる組織や人間があまりに多いため、それができないのだ。
2020年大会の組織委は、構造的な欠陥をいまだ解消できていない。このままでは、1964年大会のときのように、開会が近づいて再び問題が生じるのではないだろうか。
1964年の幻想にとらわれるな
以上、国民の無関心と、組織委の無責任体質について見てきた。1964年の東京オリンピックの実態もなかなか悲惨だったのである。
もっとも、絶望する必要はない。ダメならダメで、それを前提にすればよい。どうせ国民は無関心で、組織委員会は無責任だ。1964年でそうなのだから、価値観が多様化した2020年ではなおのこと。そのなかでできることをやればいいのである。
避けるべきは、幻想の1964年にとらわれて、現在を批判することだ。「昔はすばらしかった、みんな熱心に参加していた。だから、国民は挙って参加せよ。ボランティアや募金にも応じよ。どうしてこんなに国民は無関心なのか? 現在の日本人の道徳は荒んでいる!」こんな風潮は絶対に避けなければならない。
1964年の幻想にとらわれずに、適当にまあまあのところで済ませること。それが2020年の東京オリンピックの現実的なあり方ではないだろうか。
※なお、1964年と2020年の大会ではパラリンピックも開催された(る)が、本稿では紙幅の都合上割愛したことをお断りしておく。
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介
-
2017年01月26日 更新
オリンピックは内紛の歴史である 1940年の「幻の東京オリンピック」の場合
-
2016年12月01日 更新
東京の道路に名前を与えたオリンピック そして2020年の対策は?
-
2016年08月23日 更新
オリンピックの熱狂と「転向」する文学者たち 2020年われわれは冷静でいられるか
-
2016年07月21日 更新
多くの国民が無関心だった? 1964年のオリンピックはこんなにもダメだった
ジセダイ総研
ジセダイ総研 研究員
-
 高口康太
高口康太客員研究員
-
 北条かや
北条かや客員研究員
-
 さやわか
さやわか客員研究員
-
 土屋健
土屋健客員研究員
-
 牧村朝子
牧村朝子客員研究員
-
 安田峰俊
安田峰俊客員研究員
-
 戸部田誠(てれびのスキマ)
戸部田誠(てれびのスキマ)客員研究員
-
 タイナカジュンペイ
タイナカジュンペイ客員研究員
-
 田中秀喜
田中秀喜客員研究員
-
 ジセダイ編集部
ジセダイ編集部客員研究員
-
 石動竜仁
石動竜仁客員研究員
-
 三木義弘
三木義弘客員研究員
-
 崎山直樹
崎山直樹客員研究員
-
 宇野維正
宇野維正客員研究員
-
 辻田真佐憲
辻田真佐憲客員研究員
-
 丸島和洋
丸島和洋客員研究員
-
 大熊将八
大熊将八客員研究員
-
 広中一成
広中一成客員研究員
-
 野村泰紀
野村泰紀客員研究員
-
 五百蔵容
五百蔵容サッカー
キーワード
- まとめ
- アジア情勢
- アメリカ
- インタビュー
- オリンピック
- サッカー
- シリア難民
- テロ
- ドイツ
- ネット犯罪
- バングラデシュ
- 中国
- 台湾
- 外交
- 宗教
- 政治
- 歴史
- 男女
- 社会
- 社会カテゴリを追加
- 科学
- 結婚
- 編集部より
- 自然
- 軍事
- 音楽
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






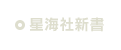


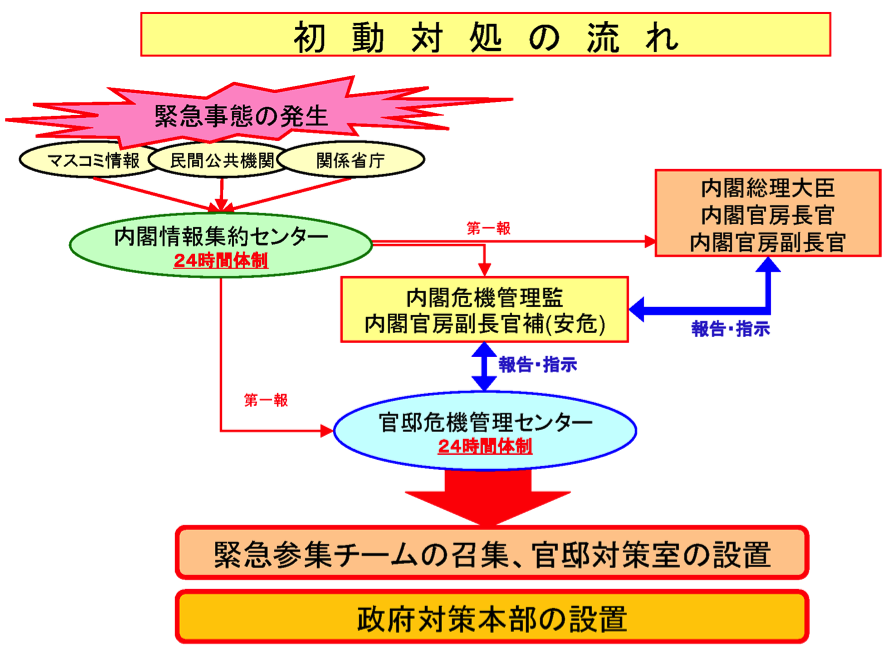



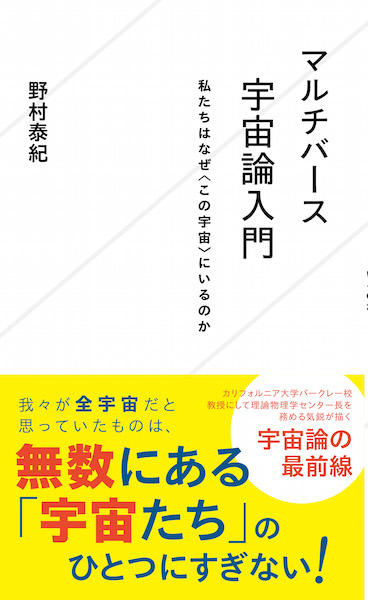


コメント