ザ・ジセダイ教官 知は最高学府にある
ジセダイ教官、初の理系の先生として、 東京大学大気海洋研究所「ウナギチーム」の青山潤先生が登場!【前編】

ザ・ジセダイ教官、はじめて理系の先生の登場です。
青山先生は、東京大学大気海洋研究所・塚本教授率いる“ウナギチーム”の一員として、マリアナ沖での産卵場特定やフィリピンでの新種発見など大活躍。
さらに、過酷な採集旅行を抱腹絶倒の文体で綴った『アフリカにょろり旅』で講談社エッセイ賞を受賞されるなど、その活躍は研究に止まりません。
その青山先生に、ウナギの面白いお話をたっぷりうかがいます!
取材・構成:平林緑萌(星海社) 撮影:山崎伸康
青年海外協力隊から帰ってきたら……バブルが終わっていた
青山先生はウナギの専門家でいらっしゃいますが、今日はウナギのみならず、色々なことをお聞きしたいなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
青山 こちらこそ、宜しくお願いします。
今回、かなり無理をして日程調整をお願いすることになり恐縮です。青山先生が現在お忙しい原因の一つでもある「ウナギ資源の減少」の問題についても、後程じっくりうかがえればと思っています。
青山 いや、こちらこそすみませんでした。ウナギの減少についてはまだ分からない部分も多いですが、事態はかなり深刻ですから、一般の人にも興味を持っていただけるといいですね。
というわけで、早速お話をうかがって行こうと思うのですが、先生は大学卒業後、青年海外協力隊に参加されていたんですよね。
青山 ええ、ボリビアに行っていました。
青年海外協力隊には、何故行くことになったんですか。
青山 いや、何も理由はないんです。私たちが大学を卒業する頃って、バブル絶頂期だったんですよ。確か、1989年でしたね。
昭和がそろそろ終わる頃……。
青山 そうですね。当時はもう、世の中をナメきっていたんですよ。「就職なんかサルでもできる」と(笑)。だから、「もうちょっと、おもしろいことやりたいなぁ……」ということしか考えていなかったんです。
学部のときも水産を専攻されていたんですか。
青山 そうです。協力隊で自分にできることはないかって探したら、養殖がありましたんで、行ってみようということになっただけです。
なるほど。で、ボリビアから帰国された時にはバブルは……。
青山 完全に終わってましたね(笑)。
一同 (笑)
青山 2年で帰ってきて、すぐ就職とかってことを考えればよかったんです。でも、ボリビアに行って、自分が何も知らないし、何もできないっていうことに衝撃を受けたんです。ですから、帰ってきたときにはもう、就職するっていう選択肢はあんまり考えてなかったんです。
もう一回自分を鍛えなおそう、というような。
青山 いや、そんなにかっこいいもんじゃないですけど、もう一回勉強しないとっていう。
そのときはまだ、研究テーマは決まっていなかったんですよね。
青山 何も決まってなかったです。
ウナギとの出会い以前は、どういうテーマで研究をされていたんですか。
青山 基本的にやってないですね。
えっ?
青山 想像がつくかもしれませんが、現在の日本の大学では、例えば学部の4年間水産を学んだとしても、現実的には魚なんか触りませんし。本当に広く浅くしか学ばない。現場で使えるような学問ではないですし、研究と言うほどのものでもないんです。
「魚を触らない」っていうのはどういうことなんですか。
青山 いや、もちろん触りますよ。実験なんかもありますからね。ただ、そういった課程で身に付く学問は、協力隊で求められているようなものではないんです。何に もないところへ行って、魚の養殖をやって、泥水の中からどれだけお金をつくりだすか──非常に商売チックな発想なんですけれども、そういった意味で考えた ときに、今の四年制の大学を出たからといって、それに対する実力は培われていないですし、そういった意味では「魚を触ったことがない」とも言える。
僕は文学部出身なので、理系の学部はだいたいみんな実学だろうなっていう、そういう偏見めいたイメージがあるんですが……。
青山 理系もやはり、いまは実学からかなり遠ざかっている分野も多いと思います。だから悪いというわけでもないとは思いますが、とにかく私はボリビアでは役に立たなかったんです。

学問が進みすぎてしまった
どうして水産が実学から離れてしまったんでしょうか。
青山 水産に限らずですが、学問が進みすぎているのが原因の一つだと思います。大学では、当然学問の先端の部分を教えなきゃいけない。もちろん、実学に近いよう なベースの部分も必要なんですけど、学問の最先端部分を教えないといけない以上、根幹の実学的で職人的な部分の密度が薄くなる。
青山先生自身は青年海外協力隊に行かれて、ご自分にその実践的な学問が足りないと感じられた。そして、実践的な学問を身につけようと東大に入りなおされたっていう感じですか。
青山 いや、そこまで考える余裕すらなかったです。自分の中で感じた衝撃があまりにも大きくて。協力隊の現場で自分が役に立つと思えなかったですし、自分が勉強 してもう一度ここへ来れば役立てるというような感触もなくてですね。逃げるように、「なんでもいいからもうちょっと勉強したい」と。明確な目的はないけれ ども勉強したい、っていうのが正直な感想ですよね。
その結果として、世界の各地のウナギを探しに行くことになったという……。
青山 そうですね(笑)。
カメラマン山崎 最初に水産に入ったきっかけっていうのはなんだったんですか? 元々、釣りがお好きだったとか……。
青山 はい、やっぱり子供の頃から魚や釣りは好きでしたね。小学校時代は川崎に住んでいましたので多摩川によく行っていました。中学校から横浜に戻ったんで、江ノ島あたりにも行きましたね。
多摩川ではウナギを釣ったことっていうのはありますか。
青山 ないですないです。
やっぱもう今はもうとれないんですか。
青山 わかりませんが、少なくとも僕らが小学生のときに行ってた多摩川っていうのは、堰の下のあたりが真っ白に泡立って……。
あ、まだまだ汚なかったんですね。
青山 はい。その泡の中に飛び込んでたっていう記憶はありますよ(笑)。風が吹くとその泡がもう、多摩川からわーってまきあがるっていう景色は覚えてますね。
確かに僕が小さい頃もまだ川は汚かったですね。「今年も大和川が全国ワースト1でした」みたいなことを、小学校のころ先生が言っていた記憶があります(笑)。話を戻しますと、ウナギを研究されることになって、特にウナギ好きっていうことはなかったんですよね。
青山 ええ、全くないですね。
先生は、何か思い入れのある魚ってありますか。
青山 思い入れという意味ではやっぱり、実際に協力隊時代にボリビアで使ってた、ニジマスとか、カワマスの仲間ですね。それこそ、人生ではじめて「なんとかしなきゃいけない」っていう愛情を持って見た魚ですから。
「こいつで食えるようにしなきゃいけない」っていうことですよね。
青山 はい、そうなんですよ。増やさなきゃいけない。
なるほど。ウナギとはまたその向き合う姿勢が違ったんですね。
青山 はい。一般に魚類とか、生物の研究者ってその生き物が元々好きで関わる方が非常に多いんですけど、私はそういう意味ではもう全然、ダメです(笑)。
海洋研の方々もやはり……。
青山 やはり多いですね、ある生き物に思い入れがあるという方が。
ウナギチームのボス・塚本勝巳教授はどうなんでしょう?
青山 塚本先生は、元々回遊現象そのものに興味を持ってますんで。今までの研究歴はサクラマスやアユ、要するに海と川を行ったりきたりするような生き物ですね。その中のひとつがウナギだったんです。
回遊する魚が大好きでいらっしゃる、と。『アフリカにょろり旅』での相棒・渡邊俊さんはどうでしょう
青山 そういえば、あんまり聞かないですね。俊もどっちかっていうと、マニア気質じゃないような気がします。

『アフリカにょろり旅』誕生のきっかけ
元来、研究者ってマニア気質な方が多いと思うんです。
青山 はい、それは言えると思いますね。
でも、今は自分の研究をするだけでなく、一般の人たちに「自分たちはこういうことをやってるんです」というのを紹介していかないといけない時代ではないかと思うんです。
青山 そうですね、そういう事が求められている面はあります。
そんなわけで、青山先生のウナギ採集旅行を描いたエッセイ『アフリカにょろり旅』についてお聞きしたいのですが、これはどういう経緯で書かれることになったんでしょうか?
青山 きっかけは、作家の阿井渉介さんが、ウナギの産卵場調査船に乗ってこられたことです。週刊誌の取材で、確か2001年のことでした。作業の合間なんかに、 阿井さんとバカ話をしていたんです。そのときに阿井さんがおっしゃってたのは、「あなたたちが何をやったかっていう結果は新聞や本を読めばわかるけれど も、それがどうやって得られたかっていう部分は全く見えない」ということなんです。
確かに、成果は報道されますけど、過程は分かりませんもんね。
青山 「だから外に出さなきゃいけない」ということを言われたんです。外に出さないから、一般の人は大学の教員とか研究者について、白衣を着て、眼鏡をかけて、しかめっ面で、壁の中で変なことやってる人たち──という印象しか持たれないんだと。
僕の理系の学問に対する偏見じゃないですけど、外から見えないから、想像するしかない部分はありますよね。
青山 そうなんですよ。阿井さんは調査船に乗って、「こんなバカなことをやってんのか!」と衝撃を受けたと仰るんです。それを聞いて、なるほどと思ったんですよ ね。新しい知見を得るというのは、研究という活動の一つの大きな魅力なんですけれども、振り返ると、それを得るまでの道筋っていうのも科学の魅力の一つ で、こういうのをより多くの人たちに知ってもらうというのは意義のあることなのかな、というふうに感じたんです。
なるほど。でも、そこから刊行までに結構時間がありますよね。
青山 当たり前の話ですが、エッセイを書いても研究者としては業績にもなりませんし、評価もされないんですよね。研究が忙しくて時間もないし、正直こんなの書く んだったら、論文を書いてたほうがよっぽど今のシステムの中では評価されるっていうことで、ずーっと無視してたんですよ(笑)。
すぐに取りかかったわけではなかったんですね。
青山 その後、2004年に南極へ行く船がありまして、私と俊でそれに乗ったんですよ。ウナギは熱帯の赤道周辺に産卵場が集中していますんで、日本を出て赤道を 越えるときは忙しいんですけど、南極へ入っていくと暇なんですよ。同じ部屋で俊が後ろにいるし、「じゃあ、阿井さんに怒られないように書いてみるか」と。
怒られないように、だったんですね(笑)。
青山 そう、そうなんですよ(笑)。その航海で原稿だけ書き上げたんですが、出版なんて正直、実現すると思ってなかったんですよね。でも、船を降りて阿井さんに原稿を渡したら、阿井さんの人脈で持ち込んでいただいて、それであっという間に講談社からの出版が決まったんです。
山崎 日記を付けていたのではなく、航海の中で記憶をたぐり寄せたんですね。
青山 はい、日記は全く付けてませんでした。だから、当時の記録は全くなかったんです。よかったのは、同じ二段ベッドに俊が寝ていたことですね。分からなくなったら、「どうだったっけ?」って聞いて、二人で当時を思い出しながら会話をして書いていきました。
なるほど、そういう経緯だったんですね。
青山 本が出たのも驚きましたが、色んな方が評価して下さったのも驚きましたね。
い や、本当におもしろかったですよ。我々のような一般人は、最先端の論文を読んでも理解できないですし、新書になることがあっても、下手したら10年くらい かかっちゃう。でも、日本のウナギ研究が世界に誇りうるもので、しかしながら、その最先端の研究者はバックパッカーのような貧乏旅行をしてウナギのサンプ ルを集めいているという(笑)。単なるエッセイとして読んでも、抱腹絶倒で文句なしに面白いですから。
青山 いや、ありがとうございます。正直な話、文芸の世界で評価していただけるなんて思っていなかったですから(笑)。

社会に出たあとの学びの形
最近では、多くの人が四年制大学を卒業しています。しかし、せっかくそこで学問を修めても、社会に出ちゃったら学問の世界とは切れちゃうことが大半だと思うんです。
青山 そうでしょうね、それが普通だと思います。
で も、そうすると、せっかく4年間で基礎を作って、まだまだ積み増していけるはずの学問と縁が切れてしまいますよね。それが、本当にもったいない事だと思っ ているんです。青山先生がボリビアで強烈な体験をされたように、社会に出てから学びの重要性に気づくことも多いと思うんですよね。普段、本作りをしなが ら、そういった学びの意欲を持った若い社会人のことを常に念頭に置いているんですが、社会に出てから学び続ける事について、青山先生はどのような方法があ るとお考えでしょうか。
青山 今おっしゃったことを、作り手側として強く感じてらっ しゃるっていうのはものすごく理解できますね。一般の方の学びという観点で言えば、最終的にはモチベーションの問題になるとは思います。今はインターネッ トなどもありますし、それぞれの大学も最先端のものを発信していますから、卒業しても学び続けるモチベーションさえあれば、とは思います。ただ、新たに何 かを勉強しようというのは難しい状況かも知れません。
というと?
青山 やはり、先ほども言ったように、学問が進みすぎてしまったんです。それぞれの分野が細分化、先鋭化してしまったせいで、一般の方が手に取れるような一般科学書──入門書に当たるようなものが非常に少なくなっています。
確かに、入門書なのに難しい本が多い印象はあります。
青山 書いている研究者としては崩しているつもりでも、なかなか一般の方は入りづらくなっていると思います。例えば私自身、関連のない分野のブルーバックスを読んで、理解できないことが往々にしてあるんです。
本当の意味での入門書になっていない、ということですね。
青山 そうです。よく、講演なんかで言うんですけれども、マッターホルンの写真を出して「今の科学っていうのはこうなってしまっている気がする」って。
マッターホルンですか?
青山 つまり、非常に鋭敏な峰になっていて、頂上は小さい。研究者は、その頂上の辺りで一生懸命上に登ろうとしいる。その下に大学院生がいて……っていう考え方 をすると、山自身が高くなりすぎていて、昔は論文があって専門書があって一般書があって、という構成でこの山全部をカバーできてたんだけれども、みんな上 にずれざるを得なくなって、裾野の部分の、実がたいへんおいしいところを登るための手助けする道具がないんじゃないかと。
登山口がなくなっちゃってるんですね。
青山 そうなんです。ですから私は、『アフリカにょろり旅』のようなバカなことを書くときに、科学的な部分はもう抜いてしまおうと思っているんです。阿井さんに 言われた、研究者っていうのは別に霞を食って生きてるやつじゃなくて、普通の人と同じ、本当にバカな人間なんだということをまず伝える。それを読んで、 「なんでこいつら、ウナギなんかに命かけてんだろう。バカじゃないの?」ってちょっとでも興味を持っていただければ、次のステップとしてブルーバックスな んかに繋がって、峰の上に登っていけるんじゃないか、と。
まず、興味を持ってもらう部分の裾野を広げるという事ですね。
青山 そうです。でも、『アフリカにょろり旅』だけじゃなくて、マッターホルンの一番麓の部分に、そういった「科学の面白さ」だけを伝えるシリーズがあってもいいんじゃないかなって気もしてるんですよね。
そういうのがあったら是非読んでみたいです──というか作ってみたいです! 書いてくれる方、いらっしゃいますかね……。

旅から帰ったら、研究室で地道な作業
抱腹絶倒の調査旅行についてはどんな事をされているのか分かったんですが、そこから帰られたあとの作業についてもお聞きしていいでしょうか。
青山 そこからがむしろ、私たちとしては本番ですね。ただ、そこはやっぱりみなさん想像される通り、白衣を着て、実験室へ入って、遺伝子を解析してっていう地味な作業になります(笑)。
持ち帰られたウナギの標本は、どうなるんでしょうか。バラバラにされちゃうんですか。
青山 いいえ、基本的には全てホルマリンで固定してあります。渡邊俊が形態をやりますし、私が遺伝子をやりますが、特にバラバラにはしないですよ。
遺伝子はサンプルの量が少ないだろうと分かるんですが、形態の研究って、骨格にしちゃう必要はないんですか。
青山 今はレントゲンでやるんですよ。骨格標本も当然作ってますが、ほとんどはレントゲン写真ですね、CTスキャンのような。
なるほど。いや、そういうのわからないんですよ!
青山 ああー、なるほど。
標本はホルマリン漬けの状態のまま、作業だけは淡々と進んでいくっていう感じなんですね。
青山 そうですね。俊は体の各部のプロポーションから外部形態を測りますし、内部形態はレントゲンを撮ってやります。一方、私は持ち帰ってきたサンプルから遺伝 子を抽出して、特定の遺伝子の塩基配列を解析して、家系図のようなもの──系統っていいますけど、系統解析にかけるというような作業をやっています。
それは、まず論文で発表されるんでしょうか。
青山 科学論文がまず最初ですけれども、専門的で学術的な『海洋と生物』とか『遺伝』なんていう雑誌に発表したりもします。
『史学雑誌』みたいなものですね。
青山 やっぱり、歴史の分野でもあるんですか(笑)。
はい、あります(笑)。
青山 それから、一般の市民の方への講演のときにも、説明するように心がけていますね。

遺伝子データをコンプリートして分かったこと
山崎 『アフリカにょろり旅』って、18種類の最後の1種を捕まえる旅じゃないですか。
青山 ええ、そうですね。
山崎 それは僕らにも伝わるトピックというか、ドラマ性があると思うんです。ただ、青山先生が一番おもしろい部分って、一般読者と少し違うんじゃないかと思うんです。先生が一番興奮する瞬間っていうのは、どのタイミングなんですか。
青山 本には一切書いてないんですけれども、18種集めてやりたかった事があるんです。今地球上には熱帯を中心に色々なウナギがいますが、おもしろいのは、基本的に各大陸の東側にしかいない。例えばアメリカ大陸もそうです。
ニューヨークの側にしかいないってことですね。
青山 そうですね。ヨーロッパは別ですけれども、オーストラリアやアフリカも西側にはいないんです。なんでそういうおかしなことが起きるんだろう、と。それは やっぱり進化が原因だと考えられます。昔地球上のどこかでウナギの祖先が生まれて、それがワーっと広まってったわけですから。
山崎 それは面白い謎ですね!
青山 その謎を解くためには、彼らの家系図を作らないといけない。誰が祖先でどう広まったか。それをやるためには、まず全種類集める必要があったんですね。実際 に家系図を作ってみますと、ウナギはおそらく、今の大陸移動よりちょっと前に生まれて、インドネシアあたりに出てきて、海流に乗って広まってった……って いうストーリーを描けたんですよ。そうすると、今の地理分布も説明できるんです。その時は興奮しましたね。
山崎 ピースが埋まった瞬間……。
青山 ええ、そうですね。ウナギがいまこうなっている理由がわかったのが一点ですし、それからもう一つ、ウナギの産卵場調査がニュースにもなってますけれども、 卵って人類で誰も見たことがなかったんです。卵を見分けるためには遺伝子をみるしかなかったんですよね。ウナギの子どもに関しても、形態的には種類が判断 できない。これがどの種類の子どもであり卵なのかっていうのを判断するためには18種類全部のデータがないと、言えないんですよね。数種類の遺伝子データ をもっていたとしても、種内変異というものもありますから、うまく位置づけられない個体が絶対にでてくる。
なるほど、完全でないといけないんですね。
青山 全部集めたことによってデータベースが完成して、分類学的な問題があって研究が進んでいなかった、熱帯のウナギに関する調査が一気に進展しました。地理分 布の謎が解けたこともそうです。それから、予想していたんですけれども、ある意味宝箱のような、ものすごく強力なツールを手に入れたわけですよね。これが あれば熱帯のウナギ全部、俺だけは種類の判断ができるっていうことになる。その二点が一番、科学的な意味では興奮といいますか、おもしろかったところです ね。

干物で発見、新種のウナギ
ウナギの全18種っていうのは、動かないんでしょうか。
青山 実は、3年前に新種を私たちがフィリピンで見つけたんです。これについても、連載していたんですが……。ですから、今は全19種類になっています。
それは、まだまだ増えるんでしょうか。
青山 何百種ってことはないにしても、まだまだいると思いますね。
楽しみですね。19種目はどういった経緯で発見されたんですか。
青山 私たちは18種を集め終わった段階で、「世界中のウナギの遺伝子を知ってます」っていう自信があったわけです。その後、産卵場調査に出たときに、ある航海で、遺伝子的に既存の18種と一致しないウナギのレプトセファルス(幼生)が採れたんです。
おお!
青山 海流のことを考えると、その品種はフィリピンのルソン島に遡上してるとしか思えない。ということは、ルソン島の川の中に、誰も知らないウナギがいるだろう……と。
それも18種類集めていたからこそ、わかったことですよね。
青山 そうなんですよ。もし集めてなかったら、「俺たちが遺伝子情報を持ってない種類なのかなあ」っていう程度で、それが新種であるという確証が持てないわけですよね。
山崎 一部の民族で食されてたとかそういうのはなかったんですか。
青山 それがね、食されてたんです! その新種のサンプルを集めるべく、バスに乗って、フリピンの太平洋側をずっとウナギを集めながら移動するという調査をやったんです。ただ、親の形を知らないんですよね、僕たちも。
幼生しか見ていないから。
青山 そう、色もわからなければ形もわからないっていう状態で、手当たり次第にウナギを集めて、遺伝子を調べたんです。1年目は全滅で、既知の種しか採れなかっ た。それで、2年目は範囲を広げて、ルソン島の一番北からバスで、レイテ、サマール、ミンダナオ島の北部のほうまで到達して、ウナギをかき集めました。そ したら、そのときに1匹だけ、ルソン島の北部で採れた個体がその遺伝子型だったんですよね。
うわぁ、それはスリリングですね!
青山 その個体は、ネグリートっていう先住民族──東南アジア一帯にいる先住民族で、身長がものすごく低くて、肌の色が真っ黒、アボリジニとかパプアニューギニ 人とかみたいなイメージ。彼らが未だにタイとかフィリピンとの山中で狩猟メインの生活をしているんですが、その個体はネグリートが村の中で捕ったものだっ たんです。しかも、彼らは基本的に街に出てこない人たちなんです。聞くところでは、フィリピン人が砂糖とか米とか持って、山の中へ二泊三日くらいで歩い てって、野豚とかウナギとかと物々交換をして街へ持ってくるそうです。そして、物々交換の結果として街に降りてきたのを、私たちがたまたま手に入れたんで すね、そのウナギの…………干物を。
あっ、干物だったんだ!
青山 そうなんですよ(笑)。「こんな干物じゃなくて、生きてるやつが必要なんだ」って言ったら、「それはネグリートじゃないと捕れないから、俺たちには無理だ」って言われて、「だったら、ネグリートの村に行く!」って言って(笑)。
早く読みたいんですけど、いつ単行本にまとまるのでしょうか(笑)。
青山 『小説現代』で連載していたんですけど、中断してしまって、ちょっとグズグズ状態になってるんです。近いうちにでもぜひ(笑)。
じゃあ、ぜひ再開していただいて、単行本にも是非(笑)。

(後編へ続く)
ジセダイ教官の紹介

青山潤
1967年横浜市生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了。東京大学大気海洋研究所特任准教授。
塚本勝巳教授率いる“ウナギチーム”の一員として、ウナギ研究の最前線で活躍中。
2007年、『アフリカにょろり旅』で講談社エッセイ賞を授賞。
|
氏名
|
青山潤
|
|---|---|
|
フリガナ
|
アオヤマジュン
|
|
所属
|
東京大学
|
|
職名
|
准教授
|
|
研究分野・キーワード
|
うなぎ
|
|
経歴・職歴
|
2004年 東京大学 / 海洋研究所 / 助手
2007年 東京大学 / 海洋研究所 / 助教 2008年 東京大学 / 海洋研究所 / 特任准教授 |
|
著書
|
ザ・ジセダイ教官 知は最高学府にある
あわせて読みたい
ジセダイジェネレーションズ U-25 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






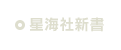





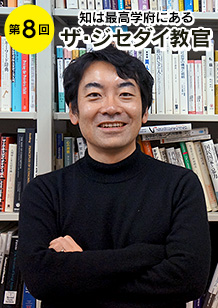

コメント