アジアIT闇鍋紀行
第8回:中国ライター、中国語を喋ったせいで見下される

外国に行くにあたって、その国の言語を操れるかどうかは非常に大きなポイントだ。観光にしてもそうだし、仕事となればなおさらだ。
しかし、中国においては下手に中国語で話さない方がいい場合がある……。
今回は、そんな話を皮切りに、中国企業をめぐる日本との取材に関する習慣の違いをご紹介しよう。
中国語を喋ったら、警備員に怪しまれる
またも私は、詰所で待機させられていた。
2人の中国人中年警備員は、「なんだおめぇ〜」と言わんばかりのバカにした目つきで私を見ている。
ここは、中国のとある日本企業の警備員室だ。
以前私が軟禁されたのは、商標を侵害したパクリケータイが売られた携帯電話市場で、写真をたくさん隠し撮りしたからだった。だが今回は違う。アポイントメントを取っての真っ当な取材だ。
だが、中国語で「取材に来た。○○さんと会う」と要件を話したら、『北斗の拳』で理不尽にモヒカンに脅されるような状況に陥っている。
私はただ、雲南省で鍛えた中国語を使って、アポがあることをダニエル・カールさんのようにフレンドリーに伝えただけなのに。
困った私は、アポイントのメールに書かれていた「日本語が話せる中国人スタッフ」に日本語で電話をかけた。
すると、ニタニタ笑っていた中国人警備員2人はやがて笑顔がなくなり、青ざめていく。
最後には「ごめんなさい」の一言もなく、「……行ってください」と(中国語で)言われた。
実は、この会社の警備員の対応は相当温厚な部類に入る。
広東省在住の知人のジャーナリストは、広東省のある工場で、工場の周りを歩いていただけで、警備員が鬼のような形相で追いかけてきたという経験をしている。
下手に中国語を喋ると見下される
種明かしをすれば、警備員の彼らは仕事を全うしていただけである。
ただ、私の中国語の発音を聞いて育ちを判断し、見下していただけなのだ。中国は多民族国家で、普通語(標準語)の下手な中国人も多い。そして、私は外見的に「中国語の下手な、怪しげな中国人」と判断されたのである。
これは、他のケースにも応用できるだろう。例えば、デモ(雨傘革命)が話題となった香港などでも、日本語を話した方が安全だろう。反中感情が強いため、中国語で話せば中国人と勘違いされて扱いが悪くなる可能性がある。
また、上海でも日本語を話した方がいい。上海っ子は上海の外から来た人間を見下す傾向があるからである。
香港や上海や北京などの先進地域に留まらず、雲南省昆明市にすら言葉による見下しはある。
昆明の西部に「馬街」という青空市場で有名な郊外の地域がある。昆明人から見て田舎臭い普通語(標準語)を、馬街で学んだ普通語、略して「馬普」と呼ぶ。昆明では「うわコイツ標準語が下手だなあ!」という時に「馬普」と表現して笑う。
私自身も昆明で自己紹介するときには、「まあ馬普ですけどね」と自虐ネタを話して場を温めようと努力している。
昆明郊外の馬街。昆明人いわく、私の中国語は馬街の人が話そうとする中国語のように下手だという
取材を嫌がる中国企業
警備員がマシなら、会社も応対してくれるだけマシだった。
この会社は日本人の知人を経由してアポを取ったので、末端が勝手に田舎者と判断しようが、大事にならず社内に入って取材ができた。
日本の会社に予め挨拶し、名刺交換した場合も容易にアポはとれる。
だが、純粋な中国企業の取材ともなると、今も昔も連絡すらちゃんととれないことがよくあるのだ。
その確率はかなりのもので、日本と無縁な中国企業へのアポ取りが成功しただけでガッツポーズをしてしまうほどだ。
にわかには信じがたいと思うので、実情を詳しく紹介しよう。
まず、日本の企業で取材するときは、「企業紹介のページ」の「取材申込フォーム」から問い合わせのメールを送れば、普通は広報担当者からメールが返ってくる。
取材申込のフォームがなくても、トップページのメールアドレスに問い合わせのメールを送れば、広報担当者から返事がくるし、大代表の電話番号にかければ担当の部署にまわしてくれる。
西欧はもとよりインドだって東南アジアだって、この常識は割と通じる。例えば私のようなフリーランサーが、インドの新基幹産業であるソフトウェア企業──そのなかでも大手の企業に取材を申し込み、副社長クラスから話を聞くことが可能だった。
だが、中国では外資系企業を除いてそうはいかない。
中国がテーマのドキュメンタリー番組やドキュメンタリー記事で、純粋な中国企業が取材に対応し、トップやトップに準じる人がインタビューに応えたコンテンツはほとんど見たことがない。
つまり、有名なテレビ局ですら、中国企業に真正面から取材をするのが極めて難しいのだ。
英会話学校の子供達に英語で取材される筆者。まだ彼女らはピュアでインタビューに対し前向きだ
中国の企業にサイトにあるアドレスにメールを送る。
メールアドレスは設定したが、誰も目を通さないのか、まず返信は来ない。そもそも、中国でのインターネットコミュニケーションはチャットが中心で、メールを使う習慣が他国と比べて非常に希薄だ。
では、公式サイトに書かれた大代表の電話番号や、会社を紹介するサイトに書かれた会社の電話番号にかけてみるとどうなるか。
まず前述の通り、私の訛った言葉により大きなハンディキャップを背負う。
中国の見知らぬ人に中国語で電話をかけた人なら経験があるだろうが、喋ったところで受話器から出てくる音声は、ジャイアンがのび太の胸ぐらをつかまんばかりの「あ?」「あ!?」という声ばかり。
そして、ちゃんとこちらがメディアの人間で、取材をしたいという趣旨が伝わったところで、今度は「だが断る」と回答される。
なぜ断るのかというと、「メディアと担当者を繋いだことで、繋いだ私に責任が降りかかるのが嫌だ」というのが理由だ。
私は、こんなやり取りを数えられないほど経験した。
言論に関する自由度が低いせいで、中国ではジャーナリズムがないような印象がある。
が、政治に関係しない民間企業の悪事についてはそうではない。むしろ、テレビのドキュメンタリー番組や有力雑誌などで頻繁にすっぱ抜かれており、メディア関係者は企業にとって公安のような存在で、正義のためとはいえ関わりたくないというのがよく聞く意見なのだ。
取材=金銭を払う、という感覚が普通
それでもまれに取材が通り、中小企業なら上層部と、大企業なら広報担当と話をする。
すると会社紹介や製品紹介で客観的な面はなく、美辞麗句ばかりの主観的アピールのみ聞かされる。
日本企業や他国の企業では「こんな意見もありますが、ここはまさに改善中の点ですが〜」などという改善中アピールもあるが、そういった話は純中国企業では出てこない。
中小企業としてはアピールする絶好の機会とはいえ、かなり広告色っぽくなってしまうため、広告色を抜いた記事づくりをより意識しなければならず、より手間がかかるというのが正直なところだ。
企業によっては、取材が終わったあと、担当者から「……ところで、いくら払うのですか?」と聞かれることもある。
これらは、中国において、自社製品を紹介するにあたって、掲載枠を買って記事広告を作る習慣が非常に馴染んでいることと関係がある。
故に、私のような国外メディアに非中国語で記事を書く人間に対しても「記事が掲載される=金銭を支払う必要がある」という思考が当然のように働いてしまうのである。
もちろんそこは「いや、日本と中国は習慣が違うので、必要ないです」と言って断るのだが、取材時の担当者のこれでもかという自社プッシュの発言にはこうした背景もある。
また、沿岸部の大都市にある企業の取材だと、取材が終われば「失礼します」で終わるのだが、内陸の中小企業の場合には「さぁて食事でもどうですかな」と声がかかる。
ホテルのレストラン程度のランクのレストランに入り、度数40度前後の「白酒」で飲めや食えやの宴会となり、こっちはすっかり酒に飲まれてタクシーでホテルに戻ることとなる。
地元のレストランでもてなされるときは、嬉しさ半分白酒攻撃に恐怖半分
企業の自画自賛に注意せよ
結局のところ、今も昔も、手間がかかる割に注目している純中国企業を真正面から取材しても意味のある情報はあまり入ってこない。
だから、内部のスタッフと知り合いになって内情を聞くのが、私にとってベストな取材手法である。
中国メディアの記事でも、「企業の内通者によれば、こういう情報が出ている」という記事の信頼度は中国人の間でも高く、日本よりもずっと拡散し信頼されうる情報となる。
インパクトのあるネガティブな記事であれば、企業はその話題の火消しに躍起になる。
とはいえ、特定の企業のスタッフとそう簡単に知り合いになる手段はなく、知り合いから知り合いを紹介してもらうという、非常に地道な作業を積み重ねていかなくてはならないし、確実にできる作業でもない。
「特定の企業のスタッフと知り合いになって内情を聞く」よりも、「知り合いができて、その業界の内情を聞いて関心をもって記事化する」ほうが楽なので、私は気楽に知人をつくっている。
また、広告記事が多いからこそ、実は中国の製品サービス紹介記事は自画自賛が多く、それを見抜く力が必要になってくる。
鵜呑みにして、翻訳して転載された記事を見れば、なんだか中国製品の未来はものすごく明るそうに見えてしまうのだが、実際なかなかそうはならない。
私自身、自腹で様々な中国製品を買ってきたので、その辺は体得したつもりだ。
そんなわけで次回は、体得の過程で経験した微妙な中国製品について書いてみたいと思う。
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介
アジアIT闇鍋紀行
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






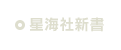








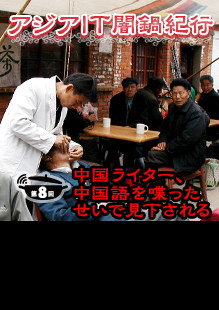
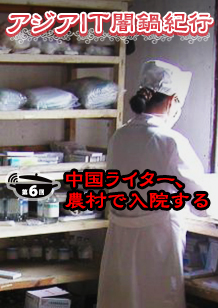

コメント