ティーンムービーを見くびるな
第1回『ちはやふる 上の句/下の句』----風と光があなたに恵むように
宇野維正
クオリティの低いものも少なくなく、見くびられがちな「ティーンムービー」。しかしその中にも、演者・作り手双方の新たな才能のきらめきに立ち合ったかのような、ハッとする作品が存在します。また、そんな作品が増えてきています。本連載では、「今、観るべきティーンムービー」を男女問わず、「映画館に年に数回以上行く」すべての観客層に向けてリコメンドしていきます。第1回の題材は、広瀬すず初主演で話題を呼んだ2016年のヒット映画『ちはやふる』です。書き手は、映画・音楽ジャーナリストで『1998年の宇多田ヒカル』、『くるりのこと』の著者、宇野維正さん。鋭い分析にうなり、映画を観たくなることうけあいです。
前口上
映画批評の連載を始めます。作品の対象は、現在の日本の「ティーンムービー」です。「ティーンムービー」とは何か? ここでは、主にコミックを原作とするティーン向けの恋愛映画のことを「ティーンムービー」と呼びたいと思います。中には小説が原作であったり、オリジナル作品であったりすることもあります。また、必ずしもテーマの中心が恋愛でないものもあります。しかし、そのムーブメント(とあえて呼ばせてもらいます)の中心にあるのは「コミック原作の恋愛映画」です。近年、このジャンルの映画は日本の実写映画界に大きな商業的成果を残してきました。地上波テレビ局の影響力低下によるテレビドラマ映画ブームの終焉と入れ替わって、その屋台骨を支えていると言ってもいいでしょう。
最初にはっきり言っておきます。現在の日本のティーンムービー、その作品の平均値はとても低いと言わざるをえません。「はたして映画館の大きなスクリーンで上映されることを想定しているのか?」と思わずにはいられない、テレビサイズの画面設計のまま映画に引き伸ばしたような作品(テレビドラマ映画の多くが抱えていた問題とも同じです)、観客の対象年齢を見限ってナメてかかっているかのような、雑な展開と構成の作品(ベテラン監督の作品に多かったりします)、監督の力量や脚本の質を云々する以前に、撮影、照明、美術、編集、劇伴といった映画の骨格を成す部分が破綻している作品......。
それでも、年に何回はハッとさせられる作品が増えているのです。また、ジャンルムービーとしての商業的成果の蓄積が、このジャンルに次々と新たな才能を呼び込むようにもなってきています。本連載では、そんな「今、観るべきティーン映画」を男女問わず、「映画館に年に数回以上行く」すべての観客層に向けてリコメンドしていきたいと思います。今後は公開前、公開中の作品を中心に取り上げていくつもりですが、第1回となる今回は連載の意図を明確にするために、現在のティーンムービーの盛況を象徴する作品であり、ちょうどBD/DVDがリリースされたばかりの『ちはやふる 上の句/下の句』を取り上げたいと思います。
この連載では、毎回、作品の批評を二つのパートに分けて論じていきたいと思います。一つは、その作品をより深く理解するための「解説」。その上で、作品をより深く楽しむための「見方」を提示していこうと思います。というのも、映画にまつわる言説において、現在の日本ではあまりにも「解説」に重きが置かれすぎていると思うのです。もちろん、映画の正しい「解説」は重要です。長いこと日本では「解説」にもなっていないただの「文章の半分以上があらすじの感想文」が映画にまつわる言説のメインストリームにのさばってました。それに比べれば、近年、ネットや書籍を中心に、様々なファクトや説得力のある仮説や映画史に基づく作品周辺の「解説」にアクセスできる機会が増えていることは喜ばしい状況です。ただ、そんな「解説」の充実ぶりとは相対的に、本来最も重要なはずの「スクリーンで何が起こっているか?」について書かれること、語られること、つまり映画の「見方」についての言説がやせ細ってきているように思えるのです。したがって、この連載ではあえて「ここまでが解説」「ここからが見方」と、自分が映画を批評する上で重要だと考える二つの要素を明示化していきます。
言うまでもなく、映画の「見方」は一つではありません。この連載で提示する「見方」を一つのヒントに、読者の方々が自分の目で映画を「見る」ことにより意識的に、鋭敏に、能動的になってもらえたら、映画の楽しみ方が広がるはず。この連載の動機にはそんな思いがあります。映画ファンを自認する人たちからは見くびられがちなこのジャンルの作品にも、多様な「見方」が詰まっている。それを、この連載で解き明かしていければと思っています。
『ちはやふる 上の句/下の句』の「解説」
原作は末次由紀による、競技かるたに打ち込む少女・綾瀬千早が主人公のコミック。『BE・LOVE』で2007年末から始まった連載は現在も継続中で、単行本も32巻まで出ている。アニメ化もされていて、2011年から2012年にかけて、そして2013年と、2期にわたって日本テレビ系の深夜アニメ枠で放送された。今回の実写映画化に該当するストーリーは『上の句』が4巻の途中あたりまで、『下の句』が5巻の途中あたりまでだから、実は『ちはやふる』サーガの中ではまだまだ序盤ということになる。
巻数の多いコミック、特にまだ連載が継続中のコミックを映画化する際には、脚本(原作のある映画の脚本は本来脚色と呼ぶべきだが)家の手腕が問われる。本作の脚本を手がけているのは、監督の小泉徳宏。これまで『ガチ☆ボーイ』(舞台原作)、『カノジョは嘘を愛しすぎてる』(コミック原作)と原作ものを映画化してきた小泉監督だが、脚本まで手がけるのはこれが初めて。しかも、よくありがちな専業の脚本家との連名クレジットではなく、単独クレジットである。『上の句』『下の句』、それぞれの見事な演出プランと構成は、監督自身による脚本執筆なしには実現できなかっただろう。
先ほど『下の句』は5巻の途中あたりまで」と書いたが、小泉監督は原作の脚色において、『上の句』『下の句』それぞれのテーマをより浮き立たせるために、見事な手さばきでそれ以降の巻のエピソードを随所に挿入していく。例えば、『下の句』では様々な局面において「仲間との繋がり」というテーマを描いているが、その上で重要な役割を果たす競技かるた部と吹奏楽部との交流は、原作ではずっと後の11巻で描かれていたエピソードだ。また、原作の各場面のセリフについても、脚本家としての権限と監督としての責任の合わせ技でもって、大胆に変えている。優れた監督が必ずしも優れた脚本家ではない、というか、そこは本来分業であることが当たり前なのだが、こと「コミック原作の映画化」を成功させる上では、脚本も兼任できる監督が撮るというのは重要なポイントなのかもしれない。もちろん、その監督に原作への深い理解と敬意があることが前提だが。
小泉監督がそのように原作から縦横無尽に「いいとこどり」をできたのは、基本的に今回の企画が「これっきり」のものであったからだ。しかし、ご存知の方も多いように、『下の句』の公開日には続編の製作が発表された。撮影は2017年の春とのことなので、早ければ2017年中に公開されるその続編は、本シリーズの「完結編」になると予告されている。広瀬すずという当代きっての人気若手女優のスケジュールをおさえる上で、おそらく水面下での調整はしていたはずだが、異例の『下の句』初日舞台挨拶の壇上での発表となったのは、その前に公開されていた『上の句』が期待以上のヒットを記録していたからだ。
『上の句』が約16億円、『下の句』が約12億円の累計興収を上げた『ちはやふる』だが、注目すべきは数字よりもそのヒットの仕方だった。2016年3月19日に公開された『上の句』は、動員ランキング初登場4位と、必ずしもスタートダッシュをきったわけではなかったが、一度7位まで落ちたあと、2週連続で4位を記録するという、このジャンルの映画ではあまり前例のない「口コミ」での粘り強いヒットとなった。
『ちはやふる 上の句/下の句』の「見方」
小泉監督の『上の句』と『下の句』における演出プランは明確だ。それぞれの作品を別のタイミング、別の環境で観ると気づきにくいかもしれないが、『上の句』と『下の句』では明らかに画面の中の光量、明度が違う。露出過多、逆光づかいというのは、このジャンルの第一人者である三木孝浩監督作品でも特徴的な手法であるが、小泉監督は『上の句』においてその手法を過剰なまでに多用している。
最も顕著なのは、夜の駅のホームや街灯の、ほとんどハレーションを起こしているんじゃないかというほどの異常な光源の明るさだろう。また、競技かるたの試合会場では、その背景は全面が窓になっていて、クライマックスにおける主人公・千早はその窓から射す光によってほとんどシルエットと化している。それは、あたかもカトリック教会において背景のステンドグラスから射す光でシルエットとなったキリストの十字架のようだ。
いや、大げさでもなんでもなく、『上の句』はその眩しすぎる光によって聖なる存在=千早の輪郭を照らしてみせた作品なのだ。最初、千早は競技かるたの伝道者としてそれぞれの登場人物たちの前に現れる。ティーンムービーである以上、もちろんそこでは恋愛感情も描かれるわけだが、太一(野村周平)が幼少期から秘めてきた千早への想いも、孤独という暗闇の中にいた机くん(森永悠希)が自分に手を差し伸べくれた千早に抱く想いも、無邪気な眼差しで「かるたより大事なものって何? 例えば?」と問いかける千早には届きようがない。また、千早が競技かるたの魅力を最初に教えてくれた新(真剣佑)に抱いている想いも、恋愛感情とは異なる、伝道者が神に対して帰依するような感情だ。千早は決して性的な存在になりえない、聖的な存在なのだ。
90年代からゼロ年代にかけての岩井俊二作品や行定勲作品において、日本映画に独特なあの(物理的な)「暗さ」を排除してみせた名撮影監督・篠田昇の光のテクニックは、2010年代ティーンムービーの(一部の意識的な)担い手たちによって、登場人物を演じる美少女やイケメンをよりフォトジェニックに映す手法として引き継がれてきた。しかし、小泉監督(と撮影監督の柳田裕男)は、『上の句』で改めてその手法に必然性と意味を見出してみせたのだ。
「光の映画」である『上の句』に対して、『下の句』は「風の映画」だ。春から初夏にかけて、つまり光の時間=昼が長くなっていく季節が舞台であった『上の句』から、『下の句』では光の時間=昼が短くなっていく夏から秋までの季節が舞台となっている。そこでは、さっきまであんなに輝いていた光は途端に力を失い、その代わりに、登場人物たちの髪を、木々の葉を、風鈴を、序盤のシーンからこれみよがしに風が揺らしている。これは、『上の句』にはほとんどなかった描写だ。
『下の句』における風の存在は、「吹かない風」を描くことによっても、さらに強調されていく。最も象徴的なのは、今回の映画において試合の応援以外ほとんど何もしていない顧問の先生(松田美由紀)の数少ない能動的なアクションでもあった、競技かるた部の部室に届けた壊れかけの扇風機だろう。また、本稿前半の「解説」でも触れた『下の句』に移植された原作11巻の吹奏部とのエピソードは、まさにその風の有無(部室の窓の開閉)を描く上でも必要であったことがわかる。
閉ざされた窓は、閉ざされた心を表している。新が心を閉ざしたことは、千早にとって神からの拒絶に等しかった(だからこそ、彼女は留守電で一方的に神=新に語りかけ続ける)。そして、『下の句』から登場する「修行者」詩暢(松岡茉優)の存在は、千早の「伝道者」としてのアイデンティティーを根底から揺るがしていく。
そうしてストーリーが停滞し、風が完全に止んだように思えたのちに、再び画面の中で風を吹かせるのは、今度は自分の足で、自転車で、スクリーンを左から右へと走り抜けていく登場人物たちだ。そんな登場人物たちの横断移動を、カメラは平行距離を保ちながら長回しでとらえていく。『下の句』は、人はどうやって自分から風を起こしていくのか、そして、その風はいかに他者へと伝播していくのかを描いた作品なのだ。
その映画が、作り手の鋭敏な意識と繊細な意図によって作られているかどうかを知りたければ、例えば、その作品に映っている空を見てみるといい。「光の映画」である『上の句』と、「風の映画」である『下の句』では、どちらもクライマックスに入る合図として空のカットが映し出される。『上の句』では、これまで作品全体を照らしていた「光」=太陽を覆っていく雲が、『下の句』では、書店でバイト中の新が見上げた空に「風」で流れる雲が、それぞれ強い意味性を持って描かれている。「光」と「風」を司る空は、『上の句』でも、『下の句』でも、それぞれ同じように作品世界に、そして登場人物たちの心に、激しい雨を降らせる。そして、その雨が止んだ瞬間、登場人物たちは再び大いなる「光」に包まれて、「風」を切って(=かるたを取って)いく。
近年の日本映画界において、主に製作サイドの予算の都合による前編・後編ものの量産は、安易な「商業的行為」だと度々批判にさらされてきた。しかし、小泉監督は自ら手がけた脚本による巧みなストーリーテリングだけでなく、このような演出プランの違いによって、前編と後編をそれぞれ独立した作品として見事に仕上げてみせた。また、ここで取り上げた「光」と「風」の描写は、コミックの原作ではどうしても表現しきれない、実写映画ならではの表現であることにも着目してほしい。すでに評価も定まった、たくさんのファンがいる人気コミック原作を実写映画化する「芸術的理由」について知りたければ、まずは『ちはやふる 上の句/下の句』を観てもらいたい。
作品情報
| サイト更新情報と編集部つぶやきをチェック! |
|---|
ライターの紹介

宇野維正
1970年、東京都生まれ。音楽/映画ジャーナリスト。洋楽誌、邦楽誌、映画誌、海外サッカー誌などの編集部を経てフリーに。現在は映画サイト「リアルサウンド映画部」で主筆を務める。『装苑』『GLOW』『MUSICA』『NAVI CARS』などで批評やコラムや対談を連載中。著書『1998年の宇多田ヒカル』、『くるりのこと』(新潮社)。
ティーンムービーを見くびるな
あわせて読みたい
苦しみの執筆論 千葉雅也×山内朋樹×読書猿×瀬下翔太:アウトライナー座談会 最新エントリー
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






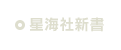






コメント