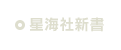エディターズダイアリー
『「百合映画」完全ガイド』序文を全文公開します
石川詩悠「百合映画」300本以上を紹介する前代未聞の一冊、『「百合映画」完全ガイド』(星海社新書)。
本日6月27日、いよいよ発売日を迎えました。
そこで今回は、『「百合映画」完全ガイド』の序文を全文公開します。執筆陣が本書に託した思いは、この序文に詰まっていると言っても過言ではありません。序文を読んで、なにか響くものがあったなら、どこか思うところがあったなら、ぜひこの本を手にとってみてほしいと願います。
『「百合映画」完全ガイド』序文
この本は女性同士の関係性を描いた映画作品を取り上げ、その魅力について語ろうとしている。取り上げる作品は、必ずしも明確にそれとわかる女性たちを描いているものばかりではない。女性たちの関係性はサブプロットというべきなのではないかという作品もあるかもしれない。しかしそうした作品についても、あたかも最初から女性たちの関係性がメインプロットであったかのように、彼女たちの存在を誇張して観ていく。
なぜそんなことをするのか。理由はふたつある。ひとつは、映画史における「女性同士」というモチーフの位置づけを検討してみたいという歴史的な興味があるから。もうひとつは、現在の日本における「百合」という言葉について、これから説明するように私たちがある歪みを抱えているから。
「百合」と見なせるような映画は古くからあった。日本では、1930年代にはすでに、夭折した及川道子を主演に撮られた清水宏『港の日本娘』(1933)、吉屋信子の原作による石田民三『花つみ日記』(1939)といったいわゆる「エス」ものと呼ばれる作品群があった。海外においても、「最古の女性映画」と称される、寄宿舎での同性の年上への淡い思いを描いたレオンティーネ・サガン『制服の処女』(ドイツ・フランス合作)が1931年に公開されている。とはいえ----本書の文脈でいえば『花とアリス殺人事件』(2015)と『リップヴァンウィンクルの花嫁』(2016)の----岩井俊二がたびたび影響を公言するクロード・ガニオン『Keiko』(1979)の公開時ですら、「百合映画」あるいは「女性映画」「レズビアン映画」という言葉はまだ馴染みのないものであっただろう。
那須博之『セーラー服 百合族』(1983)は、「百合」という言葉の普及に大きな影響を与えている。制服の少女たちが睦み合う姿や、男性の乱暴なセックスへの反発というようなテーマは、現在の「百合」のイメージにも部分的に受け継がれていると言えよう。古い映画について「百合」映画だと言えるとすれば、こうした比較的新しい作品によって生み出されたモチーフとしての「百合」を事後的に当てはめることによってのことであろう。だから厳密には、1930年代の作品までも取り扱おうとする本書において、「百合」は非歴史的なものだ。
とはいえ、これから述べるように私たちは「百合」が歴史を超越した静的なものとなってしまうことに抵抗しようとしており、「百合」が時間とともに絶えず変化していくことを望んでいる。概念の正当な範囲を超えて映画史を参照するのは、私たちが範囲外にすら「百合」を見出してしまうということを通じて、概念の変化可能性を担保しようとしているからである。「百合」の映画史的な検討とは、そういった意味で行われるときのみ可能なものだろう。
ではもうひとつの理由、「百合」という言葉について私たちが抱えている歪みとは、どのようなものか。
本書タイトルの中心を成すこの単語は、いまや頻繁に目にする言葉であるにもかかわらず、その意味を捉えることが難しい。そもそも「百合」とは何か。たとえば2016年から例年ヴィレッジ・ヴァンガードによって開催されている『百合展』のステートメントでは、開催年にもよるがおおむね「女性同士の何か特別な感情を伴う関係性のことを指す」と説明されている。これはあまりに曖昧で、「百合」とそうでないものとを識別するには、ほとんど役に立たないように思われる。そのことは展覧会側も承知しているようで、2019年に発表された脚本家・綾奈ゆにこによる「序文」では、何が「百合」なのかは最終的に観る側に委ねられる、とされている。
言い換えれば、「百合」とは作品に最初から帰属する属性であるというよりも、受容者側が作品に触発されることで、いわば個人的に見出すものであるとされている。こうした考え方に沿って言えば、私たちが共有している「百合」の観念とは、「百合」として最初から存在している作品のファンが共有するものというよりも、作品としては別々のものに各々の人間が「百合」という同じものを見出している、というようなかたちで存在していると言える。
こうした「百合」の観念上の自由さの一方で、では「百合」について私たちがイメージするものがどの程度多様なのかと自問してみると、どこか不安を覚える。
先述の『百合展』においては、制服を着た少女たちの写真やイラストがしばしばメインビジュアルに掲げられていることに象徴されるように、学校のイメージが目立っている。これは単に展覧会のコンセプトがそうであるというよりも、そもそも私たちが共有する「百合」が学校に関するイメージをその中心に位置付けているからではないかと思われる。このことはたとえば、「社会人百合」なるものが単に「百合」とは表現されず、わざわざ区別の符号として「社会人」を加えられていることからも察せられる。
「百合」の多様性についての不安が露呈するのは、明らかに「女同士の感情的結びつき」が見て取れるにもかかわらず、それを「百合」と呼ぶのをためらうようなイメージに出合ったときだ。そうしたイメージもまた人によって異なるのだろうが、独断を承知で挙げてみるなら、そこに描かれる人々が政治的に正しくなかったり、政治的な運動をいざなうものであったり、露骨な性的描写が含まれていたりするようなものなどだ。
つまり、何を「百合」とするかについて表向きには自由とされながらも、「百合」の中心と周縁を決定する暗黙のルールが存在していて、それがたとえば学校のイメージの頻繁な登場といったかたちで現れているのではないか。
より突っ込んで言うなら、「百合」の中心と周縁という構図は、イメージから安全な解釈を確保し、危険な部分については隔離するという、ある種の安全装置として機能しているのではないか。これはまず何よりもセクシュアリティの問題であるが、イメージと同じくらい多様な受け手のジェンダーは、イメージとの相互作用によって更にその複雑さを乗算的に増してしまうので、限られた紙幅で論じることは断念せざるを得ない。ただ、そうした多様性のうちに、様々な状況に応じて、たとえばセーラー服のイメージが「百合」のうちで特権的地位を占めるというような勾配が生じ、そうした勾配にセクシュアリティをめぐる何らかの葛藤が忍び込むというのは、ありそうな話である。中心的なイメージが存在すること自体を拒否する必要はさしあたりないだろうが、しかしそれがあくまで偶然の産物であり、自明視されるべきでないことは、折に触れて確認すべきだ。
こうした見地に立つとき、たとえば「百合」定義をより厳密化していったとしても、あまり意味はないだろう。それでは中心を再強化するか、せいぜいその位置をこっそりと植え替えるだけであって、多様であるはずの「百合」が制度化されているという点について切り込むことはできない。
『百合展』が言うように、「百合」が受容者によって見出されるものであるとするなら、私たちはすでに、そこに生きる二人と、二人のまなざしを見つけてしまっている。ならば私たちはむしろ、「女たちの関係性」というほとんど何にでも当てはまってしまいそうな「百合」の曖昧さを活かしていく道を採りたい。何を「百合」とするのかは各人に委ねられるということをあえて過剰なまでに真に受けて、女が二人映ってい(て関係しているように見え)る画面を見るたびに「百合だ」とつぶやく。なぜ? 『ベッカムに恋して』(2002)で一秒だけ繫がれる手を、『犬猫』(2004)での場所を超えて向かい合う視線を、『水の中のつぼみ』(2007)で吹く風を見過ごしてしまいたくないから。そして、それが一体何なのか知りたいから。自分が「百合だ」とつぶやいてしまったことに誠実でいたいから。
この方法は、結局あらゆる作品を「百合」へと単一化させていくだけではないかと思われるかもしれない。ある側面ではその意見は正しい。しかし、「百合」へと収束させていくことは、逆説的に各作品がもつ固有性へと拡散させることにもなるのだ。
本書はいわゆる王道的な「百合」作品を多数扱う一方で、「百合」の共通認識からは離れているように思われる作品をも「百合」であると主張することがある。その解釈は場合によってはほとんど妄想的に映るだろう。だがそうしたこじつけによってこそ、かえって見たことのない「百合」が見えてくるのだ。
スパイク・ジョーンズ『マルコヴィッチの穴』(2000)を「百合映画」として見た者はほとんどいないだろう。そのタイトルも相まって、多くの場合は男性を主軸にした映画として受容されてきた。だが、これをあえて二人の女性に焦点化して見直してみてほしい。するとただちに、これほどまでに複雑怪奇な「女と女」を描いた映画が存在していたのか、と驚かされる。
私たちにとって、「百合」は約束されたものではなくむしろ出発点だ。なんの変哲もなかった写真の中に霊を見つけてしまった途端に写真全体が「心霊写真」になってしまうときのような、それを見出してしまった瞬間を核として作品全体が再構築されていくような不気味な何かだ。それは同時に、制度化された「百合」を不断に再構成し続けるためのチャンスとしても機能するだろう。知っている「百合」とは別物であるにもかかわらず、それが「百合」であると思ってしまった瞬間、確かに捉えていたはずの「百合」が軋みながら変形する。中心と周縁が存在することが問題なのではなく、制度として硬直してしまうことが問題なのだ。つぶやくことを恐れてはならない。
最後に、本書の書かれ方について一点書き添えておこう。本書は映画を紹介するガイドブックであるが、同時に私たちは、この本を単なるバイヤーズガイドにもしたくなかった。つまり、簡単なあらすじと見どころを紹介した上で「こんな人にオススメ」で済ませてしまうようなものにしたくなかった。本書が取り上げる作品数は300本を超えるが、あらすじだけに集中すれば、そのすべては「ある日、女と女が出会い、結ばれる、あるいは別れる物語」になってしまうかもしれない。映画はあらすじではない。この本の紹介文はおおむね、すでにその作品を見た人が、同じくすでに見た人に向けて語るような態度で書かれている。いわゆるネタバレも随所に存在する。しかし私たちは、こうした態度こそが映画の面白さを伝えるのに最適であると信じている。
紹介の際には作品へのアクセス情報も可能な限り掲載した。一人の人間が作品を完全に見尽くすことはありえない。あとに残るのは、常に何かを見逃したという感触だけ。私たちが見たものもまたごく僅かな一部に過ぎない。だがそのことが、私たちをまた次の作品へと向かわせる。あなたがこれまでに見たことのないものを見る、本書がその助けとなることができたなら、それは望外の喜びである。
ふぢのやまい
鶴田裕貴
『「百合映画」完全ガイド』(星海社新書)
編著:ふぢのやまい
著:牛久俊介、児玉美月、将来の終わり、
関根麻里恵、髙橋佑弥、鶴田裕貴、中村香住
装画:志村貴子
発売日:2020年6月27日
定価:880円(税別)
ISBN:978-4-06-520179-4
エディターズダイアリー
投稿者
あわせて読みたい
ジセダイエディターズ
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.