新人賞投稿作品
炭水化物を見つめて~パンの世界
椿田 胡桃コピー
世界の…は途方もなくむりなんだけど、旅歩いたあっちこっちにおける、パン文化見聞録。各地のパンを食べ肥えながら、それを作り、食べる人たち――「彼らの世界」というものに目を凝らし、その息遣いの一端をここに描きつける。
カテゴリ
紀行・旅行
内容紹介
どのような食文化が育まれてきたのか。小麦・それも「パン」に今回焦点を当て、各地域に根付くそれぞれを旅の中から見つめる。
「パン」を凝視していると、ポツンとただひとり立っていたその位置から、じわりじわりと視界が開けてくる。そこに広がっているのは、それを作り、食べる人達が営んできた、生活習慣、嗜好、そして歴史…。「パン」に対する興味は、やがてそこで生きる「人々」へと繋がってゆく。そして「パン」とは、人々にとってのアイデンティティーでもあることに気付くのだ。
目次案・語りたい項目
はじめに
I植民地時代の名残
・ベトナム 「フランスパン」から「バインミー」へ (ソクチャン他)
・ラオス ベトナム人コミュニティー(サバナケット)
・カンボジア ノンパンの母子 (ストゥントゥレン)
・インド 「ワッサン」(ポンデチェリー)
II異文化の匂い
・ロシア 出稼ぎのウズベキ人たち(シベリア鉄道)
・ビルマ ペチペチ平焼き (ヤンゴン)
・タイ 欧米嗜好も侮れない(コンケン)
・マレーシア 耳か中身か(クアラルンプール)
III いつものそれを、一つ。
・ タイ 豆乳おばさんと揚げパン(バンコク)
・グルジア 奇怪型・菱形ビヨーン(トビリシ)
・イラン 砂利焼きサンギャクの至福(アルダービール)
・トルコ
・なぜここにフランジャラ(ドーバヤズット)
・巨大パンの威厳(トラブゾン)
・ウクライナ 黒パンの重みと菓子パンの軽さ
・ルーマニア トラディショナルパンケーキ(シビウ)
・ブルガリア 「バリニッツァ」で朝食を(シューメン)
IV強烈なアイデンティティー
・中国 歯が立たないほどのパン(ウィグル自治区)
・トルコ フルンと家庭の共存する世界「ハムル」(ディヤルバクル)
・ナゴルノ・カラバフ 「カラバフスキ」という、独自性
書き出しの第1章
「食べる」とは、生きとし生ける、ありとあらゆるものにとって、命を繋ぐ上で欠かせない行為。であるからして人間にとってもモチロン、それに関わる営みとは、生活の中でも重きを占めるものである。
が、それは土地環境や民族等、「まとまり」によって異なり、一様ではない。
もしあなたが「未知のまとまり」に遭遇したならば、そして、そこに生きる人々の暮らしについて知りたいと思うならば、その糸口として、古来より食卓に欠かせないとみなされている食べ物・主食の類に着目してみるのもいい。
たとえば、小麦から作られる「パン」がある。
西アジア原産の小麦は、製粉されて様々な形へと姿を変え、世界で広く食されてきたことは改めて言うまでもない。その「様々」のうちの一種である「パン」にスポットを当てる理由――とは、単に私の好みデス、と答えるしかないのだが、「パン」と一言で表せられるものはあちこちに存在するとはいえ、それもまた一筋の縄で括るには、あまりに多様性に満ちている。
それが、面白い。
各地の「パン」を吟味することは全く難しい事ではなく、パン屋に行けばいいじゃん、という話でしかない。…んだけれども、そりゃ自販機じゃないんだから、言葉の通じない場所でのやりとりには緊張が伴わないはずがない。でも、「コレください」「いくらですか」のセンテンスと、あと数字の言い方を覚えさえすればなんとかなる。パン屋にやって来た人間が欲しいものは、パンに決まっているのだ。大事なことは、礼儀正しく。かつ、焼き立ての温もりにタッチするよう、タイミングを狙うことであり、モジモジしている場合ではないのだ。
手にしたパンがアツアツならば、スグのスグ・道を歩きながらでもその喜びを享受したいし、モチロンどこか適当な場所に腰を掛けても、宿に戻って一息ついてからでもいい。玉ねぎ嫌いの子供が、目をピンセットにしてポテトサラダを凝視するように、一切れごとに丹念に丹念に観察し、咀嚼して得られる感覚・その味を言葉で表現しよう努力にひとり遊んでみるだけだ。
そうするうちに勢い付く好奇心は、「パン」そのものから、「誰が、どのように作っているのか」へと波及するだろう。
「現場」が見たい。でも一見さんに作業なんて見せてもらえるだろうか――不安・緊張を抱きつつパン屋へと歩を進めるが、「パン食い」の世界において、客と店との間に「関係者立ち入り禁止」的な壁を張られることもまた、殆どないのだ。
彼らと接触し、しつこく長居するなどしていれば、出入りする客ともやがて顔見知りになるだろう。
さらに知りたくなる。あなたたちはいつ、どのように、どれくらいパンを食べているのですか。いつから、「このようなパン」が食べられてきたのですか。なぜ、「このような」パンなのですか。
ここで「いつのもパン」が、「いつもの」となった、その由来・経緯とは何だろう。環境や土の性質によって、穀類の収穫量や種類は変わり、経済状況によって、その製粉の具合やパンへの生地配合は調整されよう。また傍で成り立っている「食」との組み合わせるのに「相応しく」と求められた果てのソレ、なのかもしれない。
小麦を栽培・収穫し、製粉する。水や塩などと配合させ、捏ねる。成形する。パンは、人が手を施す必要があるのに加え、生地を放置することで空気中の微生物の力を借り、「醗酵させる」という工程も経る。醗酵によって生地の形や風味は変化し、その度合いによって、最終的な出来上がりは大きくも微妙にも揺れ動く。
「醗酵」は、自然の力に思いを馳せる、パン作りの醍醐味ともいえる現象であるが、とはいえそれに因らない・つまり捏ねた生地を「無醗酵」で焼き上げるパンもある。生地にバターを折り込んで「層」を作ったり、ソーダ(膨張剤)を混ぜたり、薄く伸ばした生地を高温に晒して水分を蒸発させたり等で、気泡を生地内部に発生させれば、火通りよく、噛み心地も良いものが出来る。これもまた「ナルホドね」と、旨く食べられるよう凝らされた知恵に、感じ入るのだ。
「パン」を食べる。そのサイクルの中にある人々にとって、「いつものパン」の姿かたち、香り、味わいは、空気のように水のように、自身の体内に浸透しているものだろう。そしてまた、生まれた時から周囲に在った家族、隣人、友人らと共に食んできたものでもある。それを食べ続けることによって備わる感覚、慣習、そして育つ味覚がある。
パン食いの世界において、「パン」とは周囲との記憶と分かち難いもの。「愛郷心」――その表象ともいえるのだろうか、「パン」とは。
とはいえ、「貧困」「村落破壊」或いは、自由のない「束縛の世界」。故郷とは、暗い陰に彩られた、振り返りたくないものだと見なす人もいる。万人が故郷に対し、一様に「愛しさ」を持っているとは限らないが、両親があるからこそ自分が存在するように、そこで生まれ、生きてきたがゆえに備わったものは、無意識のうちにも個人の価値観に影響を与えることだろう。一つのパンを「いつもの」とみなすこともまた、それを食べ続けてきた積み重ねに因るのであり、ゆえにそれは、自身の歩んできた道を想起させる、一つのアイテムであるともいえる。
パンとは、自己を構成する骨格のひとつであり、アイデンティティー――個人の「原風景」でもあるといっていいのではないか。
たとえば、トルコにおいてのことだ。
華やかなりしイスタンブールからは東に約一一〇〇キロ。トルコ中部・アナトリア半島のど真ん中よりチョイ南東寄りに、「マラテヤ」という町がある。ここからは世界遺産「ネムルート山」に車で約三時間と近く、そこへ向かう為の拠点として、この町に立ち寄る旅人も少なくない――らしい。ただ私としては、ここにある馴染みのパン屋で体重を増やすということが、トルコに来たならば避けられない、必須の旅程なのである。
そういうわけでお約束の日々を堪能したのち、後ろ髪をひかれながらも、帰国の為にイスタンブールへと向かう夜行バスに乗り込んだ。
発車して二、三時間だったろうか。夕方、バスは幹線道路沿いの大きなドライブインに停まり、隣席のおばさんは、乗客の多くが向かっている食堂の方には背を向け、外の植え込みのヘリに行き、腰をかけた。屋内で食事をする気がなかった私も、「こっちこっち」と手をチョチョイ振られるがままに、その隣に。
大きく開けた空に、曖昧に染まった夕暮れを見上げた。あぁ、涼しいですねぇ。綺麗ですねぇ…等などの言葉を口走ろうとすると、おばさんはスカーフを巻き付けた頭を低くして、足元に置いた手提げかばんに手を突っ込み、ゴソゴソとなにやらまさぐっている。そうしておもむろに引き出し、見せてくれたのは、「パン」。
厚さ一センチほどの、扁平に焼かれた「平型パン」だ。わらじ二個分の大きさはある。まさか今パンが出てくるとは思わず、「ン?」という顔をしていると、それを掌より大きく千切り、「コレ、ね」と渡してくれた。ど、どうも…と受け取ると、再び頭を垂れて背中を丸め、次に引き出したるは、マスカットのような薄緑色のブトウの房。それも少々、こちらへ。
…パンと、果物?
「ありがとうございます」と両手で受けながらも、内心は「んんんん?」と、戸惑っていた。
おばさんは早速パンをひと口しては、続けてブドウをプチンプチンと千切り、モグモグとする。これは、「夕食」のつもりだろうか。予め準備していたのだろうから、このカップリングは「無理やり」というわけではないのだろうが、しかし果物は「オカズ」とみなすもんなのだろうか。…もしかすると、これはパンに「ジャム」のつもりなのかもしれない。それならば違和感がない。「ジャム」との違いは、果物を煮ているか・煮ていないか、であって…。
おばさんは、現在イスタンブールに住んでいるが、故郷はマラテヤ。里帰りをしてしばらく過ごし、今はまた家に帰る途中であるという。
アナトリアでは、多くの地域で「平型」が一般的であるが、その姿かたちは「マラテヤで」よく見るスタイルだ。この厚さ、この大きさ。そして表面の、この網の目模様…。
「イスタンブールでは、こういうパンを食べますか?」
一応問いかけてみると、首を振った。さらに意地悪く「どっちが好き?」などと訊くと、こっち、と笑って言いながら、またパンを千切ってくれる。
パンとブドウの組み合わせは、思ったほど悪くはないのだと気が付いた。お供にチャイ(トルコ紅茶)が欲しいところだが、爽やかな味と瑞々しい果汁をたっぷり抱えたブドウが、パンを含んだ口にはいい潤しとなって、食べていて心地よいのである。結局、違和感なく食べ進んでしまった。
「じゃあ、しばらく食べられませんね。このパン。」
その愛着とは、比べられるべくもないのかもしれないが――私も「そのパン」に囲まれた日々をかの地で過ごしていたから、おばさんには、あたかも同郷人のような親近感が湧いてくる。
イスタンブールに多いのは、フランスパンのような棒型の、フックラとしたパンだ。「平型」も無いこともないのだが、棒型に比べれば少数派。しかも、マラテヤなど「平型」がメジャーである地域の平型と比べると、味・触感ともに異なるのである。
ここでその違いについての詳細は避けるが、ともあれ「パン」自体は食事に欠かせないのだから、不本意ながらも「郷に入っては郷に従え」。あるものに甘んじるしかない。そのとき、自分の中に「パン」に対する固定したイメージが存在していたことを、つくづくと実感することだろう。パンとは、自分の過去、そして故郷への思いを呼び覚ますものでもあったのだ。
その大きなかばんの中に、まだ数枚入っているパンは、「マラテヤ」。――「故郷」そのものなのだろう。
身に覚えはある。紙袋に、母の作ったおでんや煮物、焼き菓子を詰めたタッパを入れ、「またね」と、実家から一人暮らしのアパートへと出て行った、学生時代――
望郷の念は、誰にでもある。
「クルド人」も「ラズ人」も「トルコ人」も、「日本人」という括りも関係ない。誰にとっても共通な「思い」だろう。
だからこそ、それぞれが譲れないものがある。それが、「パン」にも個性を与えているのだ。
やがて「彼ら」の大事なパンが、私自身にとっても「かけがえのないもの」のように思えた時――また食べに戻ってこようと心に誓った時、自分もその世界の一員になれた気がする。
あくまで「気がする」に過ぎないのだが、正直、それが快感でもある。
とはいえ。「パン」とは変幻自在に出来上がるものだけに、作り手のクセや主義もまたよく反映され、その特徴を細かく探っていけばキリがない。よって、ひとところのパンを「その国の代表」のように紹介することは、あまりに大雑把すぎることは心得てはいるつもりではある。「すましに丸餅」が日本の正月の典型的なお雑煮である、などと紹介されたなら、私だってちょっとムッとするだろう。が、「では」と、一見同類と思われる地域単位へ視界を狭めたつもりでも、その内でも区域によって存在する特徴に気付いてくる。それを無視して一括にすることは、やはり「ウチらの雑煮は…」と納得のいかない意見が飛び出す、「価値観の押し付け」に等しいこともあるだろう。地域における特徴づけ・線引きなんて、曖昧でしかないのかも…と弱気になる。さらに、世帯で「自家製」が当たり前の地域ならば、パンの特徴なんて「各家庭」で異なるといえるのであり、無限大に枝分かれてゆく個性を前に、結局「収拾がつかない」という結論に落ち着くしかない。
雲をつかむようなその「枝分かれ」・世帯一つ一つのありさまを見てゆく紙面は、欲しいんだけれども今はない。だから、「諦めの境地を持ちつつも」と前置きし、スポットを大きく、時には狭い範囲に当てながら、その中で垣間見られるその特徴を、あくまでも「傾向」として括ってゆくことを言い訳しておきたい。それって「逃げ」じゃん、と言われても仕方ないんだけれど、記したことが「全て」であるかのような断定ではない、ということだ。
個性はそれぞれ。のびのびとあってよい。まとめられなくともよい。…んだけれども、そうはいっても。その中でも「共通点とは何か」と探り探り、意味付けしたがる私がいるのだ。
応募者紹介
椿田 胡桃さん
学生時代よりイイ歳こいた今に至るまで、そしてこれからも、東南アジア、東アジア、南アジア、ロシア、旧ソ連圏、西アジア等々へと旅を続ける。人間は何を食べてきたのか・各地の食文化に興味を持ち、仕事もまたその見聞が奥深くなることを期待してパン製造業に従事した。現在は関節を悪くし、デスクワークに身を置く日々だが、パン作りはダメになっても旅には出る。発つ日に向けて、体力づくりは継続中。
ランキング
あわせて読みたい
ミリオンセラー新人賞
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






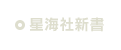


ジセダイユーザからのコメント