新人賞投稿作品
福島第一原発事故と日本の思想
戸谷洋志コピー
東日本大震災とともに日本を襲った、福島第一原発事故。その本質を捉えるために、日本の知識人たちは多彩な思想を展開した。あの事故は私たちにとって何を意味し、何を変え、何を暴露したのか。予測不能の事故後を生きるために必携の教養書。
カテゴリ
哲学・思想
内容紹介
本書は、福島第一原発事故に対する日本の諸思想を要約し、マッピングし、大きな哲学史のうちに位置づけようとするものです。本書では、まず科学技術をめぐる哲学史を簡潔に紹介した上で、社会学者の大澤真幸、社会学者の開沼博、哲学者の中沢新一、評論家の宇野常寛、哲学者の東浩紀の思想を紹介していきます。最後に、以上の諸思想をマッピングして、哲学史の文脈に位置づけ直します。本書は、一人の思想家を長大に考察するのではなく、「福島第一原発事故」を一つのキーワードとして、オムニバス形式でわかりやすく思想を紹介するスタイルを採ります。それによって、読者の関心に柔軟に対応しうる手軽な教養書であることを目指します。
目次案・語りたい項目
はじめに
第一章 哲学史のなかの原発
科学技術文明をめぐる哲学/〈原子力時代〉と人間性の関係――ハイデガー/人間の想像力の有限性――アンダース/未来世代への責任――ヨーナス/悪意なき悪としての原発事故――デュピュイ
第二章 未来の他者との連帯――大澤真幸の思想
〈破局〉としての福島第一原発事故/3.11の連想――9.11と九五年/詩的真実として語ること/未来への責任が抱える困難さ/〈予感による剽窃〉/未来の他者への呼びかけ
第三章 〈善意の分断〉へのまなざし――開沼博の思想
権力と服従の縮図――原子力ムラの歴史/〈再宗教化〉による分断/福島に残された〈空白〉/そこにある〈日常〉をみる/それでも連帯をするために
第四章 一神教からの大転換――中沢新一の思想
エネルギーの存在論の構築へ向けて/一神教的技術としての原子力/消し去られた〈贈与〉/一神教から仏教への大転換/思想としての再生可能エネルギー
第五章 拡張現実の時代へ――宇野常寛の思想
〈破局〉のイメージは正しいか/村上春樹と原発事故/〈世界の終わり〉でも〈終わりなき日常〉でもなく/新たなる想像力への展望――〈拡張現実の時代〉/AKB48にみる生の肯定性
第六章 観光地化が紡ぐ〈弱いつながり〉――東浩紀の思想
「ぼくたちはばらばらになってしまった」/記憶の風化への抵抗/〈フクシマ〉のイメージを書き換える/〈観光〉による連帯の可能性/言葉にならないものを、語る努力
おわりに――〈福島第一原発事故〉が問いかけること
書き出しの第1章
はじめに
2011年、東日本大震災の後、日本は独特の緊張感に包まれた。当時、筆者は千葉県に住んでいた。その時のことは今でも鮮明に覚えている。筆者が住んでいた地域は震度5弱で、震災がもたらした被害の全体を顧みれば、幸運にも被害は軽微だったといえる。しかし、筆者にとって印象深かったのは、その後だ。押し寄せた津波によって福島第一原発がメルトダウンを起こし、1986年のチェルノブイリ原発事故以来の大事故に発展したことは、周知の通りである。関東一帯では計画停電が実施され、筆者の住んでいる地域も例外ではなかった。市街地には灯りがなくなり、出歩く人の姿もなく、奇妙な静けさに包まれていた。まるでこの世界から誰もいなくなってしまったかのように。
福島第一原発事故の現場は、東京からわずか200キロメートルしか離れていない。事故は先進国の首都のすぐ隣で起きた。この事故をそれ以前の原発事故から区別する最大の特徴はそこにある。事故は、私たちの生活している世界から遠く離れた、僻地のような場所で起きたのではない。そこは、首都圏に住む人々が容易にアクセスすることができる場所なのだ。つまり、世界最大級の人口密集地域のすぐ隣で、原発事故は引き起こされたのである。
メルトダウンを起こした原発への対処を、私たちはメディアを通じて見守った。しかし、現場の対処に当たっている技術者のアプローチは常に後手に回り、解説をする専門家の主張にもそれぞれに食い違いが生じていて、曖昧だった。暴走する原発を制御することは誰にもできないし、はっきりした解決法をもつ専門家もいない。私たちはそう思い知った。依然として、事故の完全な収束への見通しは立っていない。喩えるなら、日本の首都のすぐ隣で、誰にも手を付けられない怪物が眠っている、そしてこの状況が少なくとも数十年に渡って続いていく。現在の日本社会が置かれているのはそうした事態である。
これに対して、事故直後から、多くの知識人が多彩な言説を世に送り出してきた。その中には、事故の処理を科学的・技術的な見地から論じるものもあれば、もっと踏み込んで、日本の社会のあり方、あるいは事故後の人間の生き方にまで言及するものもあった。首都圏の電力システムに直接的な打撃が与えられたことによって、そもそも原子力発電に支えられた社会のあり方そのものが疑問視された。また、原子力という暴走する科学技術の前で、まったく成す術のない人間の存在そのものが、改めて反省されもした。原発事故とは、科学技術の専門知に関わる問題だけでなく、私たちが生きる社会、あるいは私たち自身の生き方にまでも関わる問題なのである。
こうした、原発事故後の社会のあり方や、人間の生き方をめぐる言説を、本書では大雑把に「思想」と呼ぶこととする。
著名な知識人たちは、矢継ぎ早に、ともすれば過剰とも思える頻度と速度で書籍を出版した。もちろん、社会が混乱している中で言説を提示することは、知識人の使命の一部ではある。そうした思想を参照することで、今まで言葉にできなかったことに言葉を与え、見過ごしてきた論点に気づきを促すことができる。しかし、現在のような状況が読者にとって有益かといえば、必ずしもそうではない。大型の書店に行けば、原発をめぐる様々な思想書が乱立し、読者はどれを選べばよいか戸惑ってしまうことも多いだろう。また、インターネット上に溢れる言説の夥しさも、原発について考えることをかえって妨げている可能性がある。震災から数年が経ち、事故直後の思想が出尽くしたと思われる今、必要なのは、こうした雑多な思想群を整理し、論点を精査し、福島第一原発事故に対する知識人たちの応答を概観することではないだろうか。――これが、本書の出発点となる動機である。
こうした関心に基づいて、本書は、特に社会的に影響力が高い五人の知識人――大澤真幸、開沼博、中沢新一、宇野常寛、東浩紀――を取り上げ、それぞれの思想の要諦を明らかにし、マッピングすることを試みる。この五人はそれぞれに異なる出自をもっている。専門分野も異なるし、世代も大きく隔たっている。本書が試みるのは、そうしたまったく異なる思想を〈福島第一原発事故〉というキーワードによって繋げ、相互の関連性と相違点を意識しながら思想を読み解いていくことである。それによって、読者に対して、同事故をめぐる日本の思想への最良の入門書となることを目指す。
とはいえ、この五名の思想に少しでも触れたことがある読者は、本書の試みがあまりにも無謀であると思われるかも知れない。〈福島第一原発事故〉をキーワードとするのだとしても、果たしてそこに意味のある脈絡を見つけることはできるのだろうか。筆者自身、本書が極めて冒険的であることは自覚している。そこで、いわば日本の思想を位置づけるための地図を広げるために、これまでの哲学史の中で原発がどのように考えられてきたのかを、まず第一章で確認しておきたい。
〈原発〉と〈哲学〉の組み合わせを奇異に思う読者もいるかも知れないが、戦後、多くの哲学者が原発について議論してきた。それは、原発が極めて特殊な性格をもつ科学技術であるからだ。科学技術というものは、もともとは人類が自然を支配するために、そして人類を幸福にするために生み出された道具である。そうであるにも関わらず、科学技術の一つであるはずの原子力技術は、人類を絶滅させる力をもち、かつ、人類によってはコントロールすることのできないものである。戦後の哲学者たちの頭を悩ませたのは、人類が生み出したはずの科学技術が、そうした人類を絶滅させる力、いわば〈世界の終わり〉を引き起こす力、つまり人類自身を遥かに超えた力をもつ、という逆説であり、この逆説から浮かび上がる人間の存在そのもの歪な姿である。
しかし、私見に拠れば、〈福島第一原発事故〉はそうした哲学史の中の原発の理解に大きな修正を強いるものである。何故なら、繰り返しになるが、事故は日本の首都のすぐ隣で起きたものであり、そこはあまりにも多くの人々の生活圏と境を接しているからだ。確かに原発は〈世界の終わり〉を引き起こす圧倒的な力を秘めている。しかし私たちは、その暴走する力をすぐ間近に感じながら、新たに日常を始めなければならない。言い換えるなら、私たちが繰り返される日常を送るとき、〈終わりなき日常〉を生きようとするとき、その視界には否応なく暴走する原発の姿が入り込んでくるのである。
だが、そんな風に日常を生きることが、果たして人間にできるのだろうか。私たちは、繰り返されてゆく日常生活の内側に、〈世界の終わり〉という非日常の鼓動を感じ続けなければならない。そしてそれは、一過性の出来事ではなく、途方もない年月に渡って持続してゆくのである。そうした日常を生きることが、果たして私たちにできるのだろうか?
ごく素朴に返答にすれば、それは不可能だ。日常の中に非日常が含まれるという事態は、あるいは〈終わりなき日常〉の中に〈世界の終わり〉が含まれるという事態は、一見して分かる通り矛盾している。その場合、私たちが採りうる選択肢は次の二つでしかない。一つは、原発がもつ圧倒的な力を過小評価して、その非日常性を黙殺し、日常に浸透させることである。もう一つは、そもそも日常なるものを否定し、現在が常に非常事態であることを自覚し、〈フクシマ〉を破局の象徴として意識しながら生きることだ。――言うまでもなく、どちらもあまり魅力的な選択肢ではない。
では、それ以外の可能性を考えるには、どうすればよいのか。〈世界の終わり〉が内在する〈終わりなき日常〉を生きるためには、私たちの事故後の生をどのように考えればよいか。恐らくそのために必要なのは、原発がもつ超人間性の意味や、私たちの〈世界〉に対するイメージを再検討し、私たちが当たり前としてきた既存の概念の枠組みを新たに再編成することである。そうすることでしか、福島第一原発事故という前代未聞の事態を捉えることはできない。ただし、それは言うほど簡単なことではない。私たちは、自分たちの〈世界〉を、慣れ親しんだ言葉や概念によって形成している。それを一度バラバラにして、新しく構築し直すということは、今まで疑うこともなかった様々な〈当たり前〉を一度放棄するということであり、ある意味では大変な忍耐力を必要とする作業だ。
しかし――それを成し遂げることこそが、思想の力なのである。
福島第一原発事故という出来事、すなわち非日常性を内包する日常を生きなければならないという事態を、概念の再編成によって新たに解釈すること。本書が取り上げる五名の知識人の思想は、この課題を引き受けるという点で、軌を同じくしている。そして、〈福島第一原発事故〉をめぐる日本の思想は、この問題関心に基づいて整理され、マッピングすることができる。そうした地図を描くことで、この未曾有の事故に対して日本の知性が示した応答を可視化してゆくことができるはずだ。
本書は六章から構成されている。第一章において原発をめぐる哲学史を駆け足で概観し、第二章から、日本の知識人たちの思想を一つずつ紹介してゆく。最後に、本論で紹介してきた思想群を概観し、〈福島第一原発事故〉の思想史的意義を素描する。ただし、各章は独立して書かれているため、読者は自身の関心に従って途中から読み始めることもできる。
私たちは、これからも、暴走する原発が存在する〈世界〉に生き続けなければならない。非日常の呼吸をすぐ隣で聴きながら、日常を営まなければならない。事故後に芽吹いた多彩な思想群は、そうした〈世界〉を生きるための、考えるための、語るための手がかりになるはずである。本書が、そのためのよき案内役となることを願ってやまない。
応募者紹介
戸谷洋志さん
ランキング
あわせて読みたい
ミリオンセラー新人賞
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






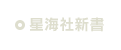


ジセダイユーザからのコメント