新人賞投稿作品
1+1=2が正しい「理由(わけ)」
石川友太郎コピー
なぜ「円い四角」は存在しないのか。数学と論理学から人生の意味を辿る旅。
カテゴリ
数学
内容紹介
円周率πは存在しないのか。数学は矛盾の塊りなのか。
人々が生きる理由を見失った19世紀末は、数学が正しい理由も見失われた時代だった。
世界が戦争の世紀に突入する中、一人の哲学者の思想が復活する。
彼の名はゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ。
その思想は今世紀のコンピュータ社会へと通じているのだ。
混沌とした現代文明の源流を探る一冊。
目次案・語りたい項目
はじめに 「1+1って、何で2になるの?」
第一章 戦争と懐疑の中で (17世紀)
◆ 三十年戦争 踏みにじられた希望
◆ ガッサンディ 全ては見かけに過ぎない
◆ ホッブズ 真理とは恣意である
◆ デカルト 数学は自然法則だ
◆ パスカル 真理を諦め「賭け」に生きる
第二章 無限の宇宙へ (紀元前~17世紀)
◆ ゼノンとアリストテレス パラドックスを封印する
◆ ルクレティウス 宇宙人は実在するのか
◆ クザーヌス 円は線であり、三角形である
◆ ガリレイ 無限小は実在する
第三章 ライプニッツ登場 (17世紀~18世紀)
◆ 三十年戦争後 荒廃から立ち直るために
◆ ルルス アダムの言語と大いなる術(アルス・マグナ)
◆ 普遍的記号法 人類史上未完の計画
◆ 微分積分学 無限小という虚構
◆ ニュートン 充足理由律をめぐる論争
◆ 二進数計算 中国学と「無からの創造」
第四章 理由の喪失 (18世紀~19世紀)
◆ 啓蒙主義 形而上学を追放する
◆ カント 数学は心に宿っている
◆ ロマン主義 ライプニッツはスピノザ主義者なのか
◆ 解析学 病的な関数の発見とその治療
◆ カントール 階層化する無限大
◆ 整数論 円周率πは存在しないのか
◆ ニヒリズム 神無き時代のモナドロジー
第五章 蘇るライプニッツ (19世紀~現代)
◆ ブールから論理主義へ 普遍的記号法は復活した
◆ ヒルベルトの形式主義 数学に限界はない
◆ 直観主義 汲み尽くせない無限
◆ 現象学と新カント派 ニヒリズムとの対決
◆ 様相論理 「ならば」の意味から可能世界へ
◆ ゲーデル 普遍計画は破綻したのか
◆ チャイティン ライプニッツ、新時代へ向かう
最終章 可能世界を越えて (20世紀~現代)
◆ バーワイズ 可能世界から状況へ
◆ プリースト 矛盾律への挑戦
◆ 仏教 「2=1」で、「1=2」になる?
書き出しの第1章
はじめに 「1+1って、何で2になるの?」
皆さんはそういう疑問をもった事はないでしょうか。
私がこの問いを父親にぶつけたのは、中学一年生のときでした。
何で、そんな疑問を思いついたのか。私もよく覚えていませんが、小学生から中学生になり、「算数」が「数学」という名前になって、急に世界が変わった様に見えたからでしょう。
皆さんも覚えている通り、中学になると、マイナスの数、すなわち負数が出てきます。
小学校では0以上の数、つまり自然数しか習っていませんから、1―2のような0より小さい数が必要となる計算は出来ないはずでした。ところが、「―(マイナス)」という記号を使った途端、どんな数同士でも引き算が出来るようになったのです。
整数という名の、自然数に負の数を合わせた新しい数の集まりを作り出すことで、新しい計算方法を産み出したのです。
負数だけでは、ありません。私たち人類は無理数、虚数、そして超越数に計算不能数といった新しい数を次々と頭の中からひねり出すことで、自然科学で多くの遺産を築き上げていったのです。
でも、私たちがそんな風に、勝手に数を発明していって、大丈夫なのでしょうか。
どんどん数を増やしていくうちに、どこかで、大きな失敗が起きるんじゃないでしょうか。
中学生時代の私には、そういう漠然とした不安があったのかもしれません。
そして、「1+1はどうして2なの?」という、私の問いかけに対する父の答えはこうでした。
お父さんはお前の疑問に対する答を知っている。
しかし、中学生のお前にそれを分かるように説明するのは難しい。お前がもう少し大きくなっていろいろ勉強したら、お父さんも教えられるように、なるだろう……。
何となく、はぐらかしたような感じの答えだな。実は知らないんじゃないのか?
そう、皆さんは思ったでしょうか。当時の私も少し、そう思いました。
ですが、今の私は、父が何らかの答えを準備していたのだ、と思っています。
私の父は高校の教師だったのですが、カントやヘーゲルといった哲学者の著作をドイツ語の原書で読んでいた人でした。
そういうわけで、おそらく父親の回答は、カントの超越論哲学に基づいた答えと、おそらく大差のないものだったはずでしょう。
超越論哲学とは、人間の思考の働きを自分自身で調べて、その限界を見極めようとする哲学です。
この試みによって、カントは数学がどうして成り立つのかを考えました。
その答えは、簡単に言うと、こうです。
人間には元々、心の中にあらかじめ必然的な思考の枠組みが備わっている。その枠組みを前提として、数学という学問は成立している。したがって、1+1が2になるのは、心の仕組みのせいで、それ以外に考えようがなくなっているからである……。
実のところ、数学を発展させたのは、この理屈が間違っていると考えた人たちでした。
それは、19世紀から20世紀にかけてのドイツの数学者たちです。
彼らはカントの思想をあまりにも狭苦しいものと感じたのです。
この人たちがそう思った理由は様々です。
無限とは何か?
感覚的な経験の奥には何が潜んでいるのか?
そして空間の仕組みはどうなっているのか?
これら全ての疑問に答えるには、心の枠組みなどというものは邪魔に見えました。
ですが、彼らは自分たちの疑問に答えていくうちに、思いもよらない奇妙なものを次々と発見していきました。
方程式の答えにならない数。
連続なのに微分できない関数。
内角の和が180度にならない三角形。
そして、全体と部分がピッタリ同じ数になる無限集合……。
それらは、数学的な真理の土台を脅かすものでした。
数学者たちは自分たちの足元が次第にぐらついていることに怯え始めたのです。
こうした不安を抱いたのは数学者だけではありませんでした。
彼らの時代には、自然科学全般や人間の生き方にも、疑いの眼差しが向けられていったのです。
自然科学が解明できることは、もはや限界に来ている。だから、こう唱えよう。「Ignoramus, Ignorabimus(我等は知らず、知らざるべし)」と。
神は存在しない。したがって、人間が生きることに意味や根拠などない。この世の一切は力への意志であり、存在は無である。
第一次世界大戦によって、科学兵器が多くの人命を奪ったのも、この時代でした。
人々は自然科学と生の意味への信頼を見失っていくことになります。
そんな時代に、一人の哲学者の思想が蘇ることになります。
その人物の名は、ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ。
このライプニッツの影響を受けて、数学者や哲学者は1+1=2が正しい理由を考えようとします。
この思索は数学基礎論という分野へと続きます。
数理論理学や計算理論などの計算機科学(コンピュータ・サイエンス)の土台が築かれたのは、この分野からです。
ライプニッツといえば、1と0の二つの数値だけを用いる二進数計算、即ち今日でいうビット列計算を開始した人物としても知られています。つまり、コンピュータの基礎となる計算様式です。
それに加えて、自分自身でも機械仕掛けの計算機を作っています。
これらの業績により、ライプニッツは計算機科学の産みの親として考えられています。
ライプニッツが影響を与えたのは計算機科学ばかりでは、ありません。
普通、ライプニッツというと微分積分学を思い出す人が多いですが、それ以外にも多彩な側面があるのです。
位相幾何学に、場の理論や相対性理論。
これらの20世紀以降になって大きな影響力を持った数学や物理学の分野は、ライプニッツを先駆者とすることができるという説も存在しているくらいです。
それだけでは、ありません。
哲学の分野でも、ライプニッツの思想が当時の流行だったニヒリズムとの対決に活用されます。
ナチスが台頭していく時代の中で、生きる意味や理性への信頼を取り戻そうとした人たちは彼の哲学に活路を見出します。
現象学や分析哲学といった現代思想の源流はここから生み出されていったのです。
こうしてライプニッツの思想は、現代社会に計り知れないほどの影響力を持っていくことになります。
本書の目的は、ライプニッツという分岐点を挟んだ様々な時代で、数学や論理の正しさについて考えることが、人生の意味や社会のあり方について考えることと、密接に関わってきたのを示すことです。
すでに見たように、19世紀末から20世紀前半の頃は、数学の基礎が問われると共に、人の生き方が大きく問われた時代でしたが、この二つのことは無関係ではないのです。
そもそもライプニッツが生きた17世紀もまた、ヨーロッパ史上で最も危機的といわれた世紀の一つでした。
国家と宗教の対立、そして戦争と病。
人々が政治や信仰に幻滅し、生きていくための理由を失った時代でした。
こうした時代にはあらゆる真理が疑われていきます。神様だろうが科学だろうが全てが不信の対象となります。
そして、あらゆる真理の中でも最も疑いにくい真理も疑いの対象となります。
それが、数学です。
もともと数学mathematicsの語源を表わすギリシャ語「マテーマタ(μαθηματα)」は「学ばれるべきもの」一般を指し示す言葉でした。
ギリシャ人は数学によって幾何学や天文学を発展させ、弁論術の習得のために役立て、善悪を見抜くための基準としたのでした。
つまり、あらゆる学問の根幹だったのです。
そのために、あらゆる真理を疑っていったときに、最終的に疑われたのは数学的な真理なのでした。
こうして、「1+1=2になるのは、なぜなのか?」という問いが生じるのです。
こうした問いが出て来る時代には、論理学によって問題を解決しようとする人々が現れます。
そして、数学の正しさは論理の正しさに基づいている、と考えます。
論理学logicも、もとの語源は「ロゴス(λογος)」すなわち言葉です。哲学者ヘラクレイトスにより、万物をつかさどる理法として提唱されたのが、その由来です。
論理学の起源はアリストテレスの名辞論理学とされていますが、これはあまり今日では見かけないものになっています。
しかし、それとは別に、ヘラクレイトスの影響を受けた人たちが発展させたものは、普通に今日の数理論理学の教科書でも使われています。
それは命題論理学と呼ばれるものであり、発展させたのはストア派の哲学者です。
ストア派という名前を聞いて、すぐにセネカやエピクテトスやマルクス・アウレリウスの名前が浮かぶ人は、多分、人生に悩んだ経験がある人だと思います。
ストア派といえば、自殺の肯定です。
これは奇妙なことです。今日、哲学や論理学に関心のある人で、命題論理が自殺に結びつくと考えている人は、まず見かけません。
しかし、ストア派の人たちが命題論理の提唱から宿命論を結論付け、自ら死を選ぶ生き方を肯定するのは自然なことだったのです。
何でそうなるのかは、後の章で説明することになりますが、初期ストア派の人々も、ライプニッツや20世紀初頭の人々のように、悲惨な時代に生きていました。
紀元前323年にアレクサンドロス大王が死去したことにより、マケドニア帝国は分裂します。これが、後継者争いを巡る戦争へと発展したのです。
そうした時代の中で、哲学者たちは生き方の理想を求めて、三つの学派に分かれて論争を行ないます。
エピクロス派、ストア派、そして懐疑論者です。
このうち、数学や論理学に疑いを向けていくことになるのは、ピュロンという人物の思想を受け継いだ懐疑論者でした。
この時代の数学者たちは、物体を「三次元の広がりを持つ抵抗を伴うもの」と考えました。
そして、ユークリッドの『原論』に見られるように、点は部分を持たないもの、線は幅を持たない長さ、平面は幅を持つ長さとみなし、それらが物体を構成すると主張しました。
しかし、懐疑論者に言わせれば、これは正しくありません。
こんなわけのわからないものが物体から独立した実体として存在しているわけがない。だから、点や線や平面などは始めから存在していないと認めるべきだ、というのです。
こうしてストア派は懐疑論者と論理の正しさを巡って、論戦を行なっていきます。
また、ストア派とエピクロス派は、宿命論と自由意志に関する論理学上の見解が違うことから、対立していきます。
この争いはストア派と懐疑論者の主張に違いが見えなくなる三世紀ごろまで続きました。
その後、ストア派はキリスト教文明に受け入れられますが、懐疑論者とエピクロス派の影響はしばらく歴史上から姿を消すことになります。
このように、社会が混乱した時代には、正しい思考やコミュニケーションのあり方として、数学や論理学が注目されることになります。
混乱が生じているのは、人々が意思疎通を図るための正しい基準がないからだ。
その基準は、形式的な言葉と規則を持った数学や論理学に見出されるだろう。
そして、数学的に人間社会を運営すれば、この混乱を円滑に処理できるようになるはずだ。
そういう主張が歴史上に何度も現れるのです。
現代がまさにそういう時代で、コンピュータという数学の産物によって、物資の生産と販売および輸送を管理し、インターネットの検索サービスやコミュニケーションツールを生み出し、そして金融工学を用いて高額の株取引を自動的に行なうことになります。
こうした時代に乗り遅れまいとして、多くの親が子供を塾に通わせて数学や英語を必死に勉強させ、グローバルな人材競争に勝ち抜こうとします。
ビジネスマンの間でも、ロジカルシンキングなどという言葉が流行りましたが、商談を行ない易くするために論理的に話したいという欲求が存在します。
哲学者たちも数学や論理学に頼ろうとします。ソーカルとブリクモンの『知の欺瞞』という本で批判を受けたフランス現代思想による濫用や、人々が自然に使う言葉の曖昧さを嫌った分析哲学による道具的な使用に至るまで、まるで思想家たちの居場所がもうここにしかないんだと言わんばかりの態度です。
ですが、歴史的に見ると、こうした状況は珍しくありません。
これまでの歴史を振り返ってみると、思想の混乱やコミュニケーションの阻害、そして人間の自由意志といった問題を打開するために、似たような解決策が浮かんでは消えていきました。
そして、後世の人々は全く解決されていない問題を無視することによって素通りしていき、問題が思い出されたときには同じことを繰り返すか、見当違いの解決策を提案することになります。
だからこそ、私たちは時折、過去を思い出さなければいけないのです。
現代でも、まだまだ解決されていない論理学の問題がいっぱいあるのですから、このことは尚更です。
本書の最後の方で、ライプニッツ以降から現代までの論理学で何が上手くいっていないのか、その方向性を紹介してみたいと思います。
しかし、その量は膨大です。私自身が一応、大学院で数理論理学を専攻していたわけですが、正直言ってその全てを把握するのはとても無理です。
ですから、本書で紹介するのは、私の関心のあった部分です。
私が研究していたのは、認識論理や非単調推論など、人間の日常的な推論を非古典論理の枠組みで把握する試みだったのですが、そこで可能世界意味論というものが使われます。
しかし、どうも可能世界というものは、この作業には不向きな側面があることが、言語学者や哲学者などに指摘されて、いろいろ改変が加えられたのです。
可能世界は、元々、ライプニッツが考え出したものでした。ところが、この堅苦しさの原因はそもそもの出発点であるライプニッツにあったような気がします。
これは重要なことだと思います。可能世界こそがライプニッツの思想を支える主柱なので、これを改変することは、私たちの思想のあり方を改変することにも関わります。
ここからどのような世界観が生じてくるのでしょうか。最後にその辺りについて、簡単にまとめたいと思います。
さて、それでは物語を始めましょう。
舞台は17世紀のヨーロッパ。戦争の時代の中、一冊の書物の翻訳によって、懐疑論が復活するところからです。
第一章 戦争と懐疑の中で (17世紀)
◆ 三十年戦争 踏みにじられた希望
現代のコンピュータ社会の出現は、15世紀のグーテンベルクによる活版印刷以来のメディア革命と呼べるものです。しかし、情報の氾濫は、多くの恩恵と同時に、混乱をもたらすものであることを、現代の私たちは知っています。
コミュニケーションの拡大と新時代への淡い期待。しかし、貴重な学問や商売のアイデアとともに、ネットに溢れているのは、意見の対立、真偽の不確かな主張、デマや流言や陰謀論、そして、政治と社会と貧困と戦争への危機意識……。
印刷術が出現した時代も、まさにそういう現象が起こり、やがて悲惨な出来事へと向かっていきました。
活版印刷が発明されたのは、ルネサンス期のことでした。
そのおかげで本の大量生産が可能となり、多くの知識が世の中に広まりました。
ヘレニズムの時代に発展した哲学や天文学や数学などの著作が翻訳され、オカルト思想と混ぜ合わさった姿で紹介されるようになったのです。
それらの中には、ディオファントスの『算術』も含まれていました。フェルマーも『算術』を読んで勉強し、ページの余白に様々な定理を書き残しました。それらは整数の性質について調べたものでした。
有名なフェルマーの最終定理もその中の一つです。
整数論と呼ばれる数学分野はこうして生まれました。
また、ルターがドイツ語で聖書を翻訳してくれたので、いちいち教会の神父様の所に行かなくても、直接、神様の言葉に触れることが出来るようになりました。
ヨーロッパの人々は、自分たちの知ることのできなかった大量の情報を前にして、新しい世界の到来を予感しました。
ですが、それらの新しい知識は、人々に争いの種をばら撒きました。
ルターやカルヴァンの新しい教えを信じるプロテスタントの信者と、古い教会の教えを信じるカトリックの信者は衝突を起こすようになります。
人々の間でも、薔薇十字団という秘密結社が新しい世界を築くための秘密を握っているらしいという、怪しげなビラも飛び交うようになりました。
彼らに世界の真理を教わろうと、懸命に探した人たちもいました。しかし、そんな陰謀めいた秘密結社がどこにあるのか、誰も知りませんでした。
印刷術がもたらした莫大な情報はむしろ、何が真実で何が嘘なのかを、判定する基準を見失わせたのです。
17世紀の初頭には、ついに戦争が起こります。
三十年戦争と呼ばれる悲惨な戦争です。
最初は、プロテスタント側とカトリック側の国同士の争いだったのですが、どういうわけか、途中から、カトリックの国であるはずのフランスがプロテスタント側の同盟者になり、何が戦争の原因なのか、全く分からなくなりました。
戦争は主にドイツ領内で起こりました。
元々、ドイツは一つの国ではなく、領邦と呼ばれる個別の小さな君主領の寄せ集めでした。
したがって、それぞれの土地ごとに信仰も産業も文化も異なる状態でした。主にエルベ川の流れる北から東の寒い地方では、ルター派の信者が多く住んで、農業を営んでいました。それに対してライン川の流れる西から南にかけての地方では、カトリック信仰が栄えて、商業的に発展していました。
このように、国家としての統一感が全くなかったせいで、他の君主国からの草刈場となったのです。
戦場と化したドイツでは、人々は文字通り、死肉を食らう事態にまで行き着きました。
1635年の冬に最悪の飢饉が起ったのです。
犯罪人の死体が絞首台から引き摺り下ろされて、食べられました。
墓から真新しい死体を掘り起こし、人肉を売りさばく者も現れました。自分の子供を食べたと告白する女も現れました。
こうした状況で、信仰は役に立たないどころか、かえって失望させました。
ルターの教義は、各地の諸侯が教皇の支配からの自由を主張するのに便利でした。
しかし、それは民衆が求める自由とは程遠いものだったのです。
かつて16世紀にドイツで農民戦争が起った時のことです。
ルターは君主よりも反乱を起こした民衆の方を非難し、これを弾圧しようとしました。
そして、1555年のアウクスブルクの宗教和議により、君主はカトリックかルター主義かの信仰を臣下に対して強制する権利を得ました。
それに同意できない人々は移住を迫られるしかありませんでした。
元々、ルターの信仰義認説は人間の自由意志をほとんど認めていませんでした。
ルターは、人間の本性は生まれつき悪なので、正しい行いに従って生きることは出来ない、と思っていました。
だから、人は自らの意志と行動によって救われることはなく、ただひたすら神を信じることにのみ自由と正しさは存在するのだ、と説きました。
当時の民衆は政治的に無力な状況に置かれていただけでなく、貧困や病、そして死と隣り合わせの生活を強いられていました。そのために、正しい行ないなどという綺麗ごとだけでは、とても生きていけないのは、当たり前のことでした。
したがって、ルターの思想は現実味を持っていたと言えます。
何かの犯罪を行なわざるを得なかったとしても、信仰によって許されるからです。説教臭いカトリックはこのような許しを決して与えようとはしませんでした。
しかし、この思想を信じることは、個人の自由や道徳への欲求を抑圧することになったのです。
こうして、人々が抱いていた、新世界への希望は踏みにじられました。
真理や正義といった価値観を、誰も信じられなくなっていきました。
◆ ガッサンディ 全ては見かけに過ぎない
このような状況下で、主にフランスを中心として、懐疑論が広まっていきます。
フランスでは、16世紀にナントの勅令によってユグノー戦争が終わるまで、カトリックとカルヴァン派の激しい内戦が行なわれていました。そのおかげで、三十年戦争が始まる頃には、すでに世界の行方に対して、悲観的な論調が漂っていました。
こうした状況の中、1562年にアンリ・エティエンヌがラテン語に翻訳した一冊の本が思想界に影響力をもたらします。
セクストス・エンペイリコスの『ピュロン主義の概要』という書物です。
そこで述べられている懐疑論のおかげで、ルターやカルヴァンが声高に唱えた真理に対し、疑念が生じるようになりました。
すると、随筆家モンテーニュなどによって、次のような主張が唱えられるようになりました。
世の中に絶対に正しいとも間違っているとも断言できるものなど、存在しない。したがって、証拠の無いものについては真偽を述べることなく、判断中止(エポケー)すべきである。
これによって、あらゆる真理は、感覚的経験が作り出す見かけに過ぎない、という思想が登場します。
ピエール・ガッサンディという哲学者がいます。
この人は中世のスコラ哲学の支柱だったアリストテレスの思想に疑問を抱いて、エピクロスの原子説に接近します。
アリストテレスの思想では、感覚的な質料(ヒュレー)には形相(エイドス)が宿っている、と考えられました。
つまり、人間の経験は事物の本質的な真理を告げる、と思われていたのです。
しかし、ガッサンディは、そのような本質などというものは事物には無く、物質は細かな目に見えない原子の集まりである以上、実験的に見かけによって判断されることしか知りようが無いのだ、と考えます。
しかし、それでは数学的な真理はどうなるのでしょうか。
数学は、一見すると、感覚的に確かめられるものではありません。1+1=2であると人は考えるとき、何かの見かけについて語っているとは思えません。
だからこそ、プラトンも、幾何学は感覚的に確かめられるのではなく、イデアという感覚を越えた実在の世界を直観することによって、客観的な真理を確かめられるのだ、と考えました。
ガッサンディの知り合いのメルセンヌも、数学の知識だけは疑うことはできないはずだ、と主張して、懐疑論を退けようとしました。
これに対して、ガッサンディは、にべも無く次のように言います。
「これ[数学]は、アリストテレス的意味における学問ではなく、われわれが保持すべきであると判断したものの一つである。それゆえ、私は数学の中で確実で明晰なのはすべて見かけに関係しており、決して絶対的原因だとか本性とかに関係しているわけではないと結論する」(佐々木力 訳 [6]上巻 p.164)
これは実に、衝撃的な考えでした。
すでに私たちは、古代のヘレニズム期において、懐疑論者たちが数学的な真理を批判したのを見てきました。
しかし、彼らの主張が復活するまで、1+1=2であるというのは、キリスト教文明では疑われたことがない真理でした。
ヨーロッパは17世紀の近代の時代に入り、物事を徹底的に疑っていくことによって、宗教や学問の権威を引き摺り下ろし、人間の主体的な自由を獲得しました。そして、物事の確からしさを実験によって確かめていくという、自然科学の基礎もまた、得ることが出来たのです。
しかし、それは人間が真理という名の確実性とその根拠を失うことを代償として、得られたものなのです。
世界から確実性が失われたとき、人は何を信じて生きていけばいいのか。
思想家たちの挑戦が始まります。
◆ ホッブズ 真理とは恣意である
ガッサンディの思想はジョン・ロックを通じて、英国の経験論哲学に影響を与えたといわれています。実際、彼は『リヴァイアサン』の著者として知られるホッブズと友人でした。
ホッブズもまた、人間が知識を得る手段として、感覚を重視します。
経験論者にとって、懐疑論の克服はとても重要なテーマになります。そもそも経験論を英語にするとempiricism、すなわちセクストス・エンペイリコスの名前と同じです。
元々、経験論は古代医学のエンペイリコイという経験学派を祖とします。医学では理論の構築よりも患者を治すことが優先されますから、理論を疑い経験を重視するのは当たり前です。セクストス・エンペイリコスもそうした人たちの一人でした。
このように、経験論のルーツ自体が理屈を否定する懐疑論なので、感覚を越えた眼に見えないものを可能な限り排除した上で、物事の正しさを考えなければなりませんでした。
また、ホッブズ自身にとっても、懐疑論との対決は、とても重要なことでした。
ホッブズは英国国教会の牧師の家系で、三十年戦争の直接的な被害を受けていないのですが、ピューリタン革命という内戦の余波を受けて亡命生活を強いられた人でした。
そういうわけで、正義を声高に叫ぶ人間に対して非常に懐疑的です。
しかし、彼の立場は王政支持でしたので、国王の主権を正当化する方法も考えなければなりませんでした。懐疑論者のように、自分も真理について全く何も言えないというのでは、王権を守ることはできません。
ホッブズはどのようにこの難題を克服したのでしょうか。
まず、彼は唯物論を唱えました。人間は単なる「自動機械」に過ぎず、善悪などの道徳も人が主観的に思いつくものであり、客観的な自然の中には存在しない、と考えます。
このような考えから、決定的な一歩を踏み出します。
ホッブズは、人間の思考は機械的な計算に他ならないのだ、と主張します。
西洋哲学では、「人間は理性的動物である」という、有名な人間の定義があります。
ここから、ホッブズは次のように考えます。「動物」という言葉の意味は、「人間」から「理性的」を引き算して得られるものだ、と考えるのです。
例えば、近くに人間が立っていたとします。
段々と遠ざかっていくにつれて、その姿がぼやけていきます。
すると、それが人間であることが次第に分からなくなっていき、その存在が理性的であるという証拠はなくなっていきます。
しかし、未だにその存在が生きている動物であることは、人間であることがわからなくなっても、理解できるわけです。
こうした物事の観察を、ホッブズは引き算と変わらない推論だと、みなすのです。
「したがって、我々は、(中略)数を数えるという他ならぬその機能によって、あたかも人間が他の被造物から区別されるように、計算すなわち推論を数においてのみ場所を占めるものと考えてはならない。というのも、「大きさ」「物体」「運動」「時間」「性質の程度」「行為」「概念」「平均」「言葉と名辞」(中略)は、足し算そして引き算が可能だからである」(伊藤宏之、渡部秀和 訳 [14] p.24)
つまり、人間が言葉を使って物事を考えることと、足し算や引き算で数を計算することには、何の違いもないというのです。
このような考えにより、ホッブズは人工知能の祖父と呼ばれています。
後の章で見るように、ライプニッツはこの考えに非常に大きな影響を受けることになるのですが、問題はここからです。
ホッブズの主張の通りだとすると、言葉を使って物事の定義さえ決めてしまえば、幾何学などの推論の結果は、計算によって、自動的に得られるものになります。
では、物事の定義とは、どのように決めるのでしょうか。
ホッブズは、人々が名辞(名前)を使って、恣意的に決めた、と考えます。
「ここからまた、次のことが演繹される。つまり、最初に真実は、事物に付加された全ての名辞から初めに、もしくは他の事物に付加された名辞から引き受けられた全ての名辞から独断的に作られる、ということである」(同前 p.58)
ホッブズによれば、「人間は動物である」と言えるのは、「人間」という名前と「動物」という名前が、同じものに付けられることを、人間が好んだからだ、というのです。
この理屈が正しければ、「1」や「2」といった数字も、何かの実体を固定的に名指しする記号ではない、ということになります。
「1+1=2」になるのも、人間が好き勝手に決めたルールによってそうなっているだけであり、客観的に正しいことでも何でもない、というわけです。
この考え方だと、どんな数学のルールでも人々の間でデタラメに決めて、勝手に正しいと言ってしまっても構わないことになります。
例えば、「2+2=5」と考えたところで、単なる記号の恣意なのだから、そうみなしても不都合はないことになります。
どこかの未開の民族で、子どもの頃から「2+2=5」であると教わったために、私たちと違う考えをしていることがありえる、と言えます。
このように、数学や言語などの一定のルールを備えた真理は、単なる特定の共同体の約束事に過ぎないという考えを、規約主義といいます。
こうした考えは現代の分析哲学でも議論の種になっています。
クリプキという哲学者がいます。
彼は弱冠18歳にして、様相論理の公理系S5の完全性を証明した天才です。
といっても、数理論理学に興味のない人には、何がどうすごいのか、伝わらないと思いますが……。
それはともかく、クリプキはウィトゲンシュタインという哲学者の考えを借りて、以下のような計算が成り立つ可能性を指摘しました。
私が、これまでの人生で、68+57という計算を実行したことがないとしましょう(もっと大きな数でも構いませんが、ここではとりあえず、そのように仮定します)。
そして、私は計算して、「68+57は125だ」と、当然にも発言したとします。
「ここで私は、突飛な懐疑論者に出会った、と仮定しよう。この懐疑論者は、私の答えに対する私の確実性に関し(中略)、疑問を投げかけるのである。彼の示唆するところによると、おそらく私が過去において「プラス」というタームを用いたとき、「68+57」に対して私が意図したであろう答えは、「5」であったにちがいない! のである」(黒崎宏 訳 [15] p.13)
つまり、私が「68+57は125だ」と言ったとき、それを言う前には、プラス算(足し算)ではなく、57以上の数同士を組み合わせると、すべて「5」になるクワス算を実行していた可能性がある、というのです。
ところが、LSDなどの麻薬によって頭がおかしくなってしまい、たまたま「125」という答えを導き出すことができた、のかもしれないのです。
だとするならば、過去だけでなく現時点においても、「68+57は125だ」と確実に言えなくなります。すると、計算規則は無意味な言葉の羅列ということになります。
では、どうしたら「68+57は125だ」と主張できるのか。
それは、そのような規則を表明したときに、受け入れてくれるような言語の共同体によって確かめられるのだ。
規約主義とは、そういう考え方のことです。
ホッブズは数学を規約主義的に考えることを全く躊躇しません。
「「2+3=5」という事が主張されたならば、人は数の秩序を思い出し、同じ言葉を話す者の共通の同意によって、それは人間社会に必然的な同意であるが、5は2と3を一緒にした名前の言葉であると決定するだろう。人がその時、2と3とを一緒にすれば5となることが真実であると同意すれば、その同意が学識と呼ばれる。そして、これが真実であると知ることは、我々自身によって作られたことを承認することに他ならない」(伊藤宏之、渡部秀和 訳 [14] p.1113)
数学ですら、この通りです。したがって、ホッブズにとっての懐疑論の解決策とは、規約主義以外の何者でもありませんでした。
ホッブズは哲学の主要三部門を幾何学、自然哲学、政治哲学に分けます。
このうち、幾何学と政治哲学は自然哲学とは違って、人間が作ったものを対象とする、と考えます。
自然の運動の原因について、私たちはよく知らない。しかし、幾何学と政治の法律については、私たち人間が作ったものだから、原因を知ることができる。
だから、幾何学と法律の推論の正しさについては、確実に知ることができる、というわけです。
この超唯名論と呼ばれる立場によって、ホッブズは社会契約説に基づく君主制を正当化します。
元々、自然には善悪の基準など存在しない。だからこそ、人間は個々人でバラバラに善悪の基準を決めることになってしまうし、他人への義務も守られない。
だが、そうすると世の中に争論が起こって、ついには戦争になってしまうので、真の善悪の基準を決める統治者を決めるべきだ、というわけです。
ホッブズはこのような論法によって、ものの見事に懐疑論を打ち破る王政擁護を行なってみせたのです。
しかし、こうした便宜的な解決策は、結局、相対主義的な無神論ではないか、という批判を巻き起こします。
批判者たちの中には、ケンブリッジ・プラトン主義という英国の人々もいましたが、この主張はニュートンに影響を与えていきます。
そして、英国と海峡を挟んだ大陸の方でも、恣意的でない数学的真理を見出そうとした哲学者がいました。
それは、デカルトです。
◆ デカルト 数学は自然法則だ
デカルトは三十年戦争の初期の頃に生きた人でした。
世界中にありとあらゆる情報が飛び交い、人々が何を信じていいのか、よくわからないまま、戦争に突入していった時代にいたのです。
彼はそうした時代にどう生きていったのか。
それを記した本が、有名な『方法序説』です。
彼は、幾何学、論理学、神学、弁論術、そして哲学だけでなく、錬金術や占いなどの怪しげな知識にも手を染めていきました。
学校から飛び出して、世俗に住む人々の生活も、見て回りました。
オラニエ公マウリッツの軍隊に入り、オランダの独立戦争にも参加しました。三十年戦争の初期で最も重要な戦いに位置づけられる「白山の戦い」にも従軍しました。
ですが、それらから得られた知識は、絶対に正しいとは、言えないものばかりでした。
他人から教わったものは、確からしく見えるだけで、間違っている可能性を排除できないものばかりでした。
デカルトはこの世の全てのものを疑いました。
世の中にはすでに懐疑論が横行していたので、真理を見つけるためには、懐疑論者以上に徹底的に物事を疑わなければなりませんでした。
そして最終的にデカルトは、自分の考えだけを、確実に存在するものだ、とみなします。
われ思う、ゆえにわれ在り。
不確実な時代の中で、唯一、明晰にして判明である、と理解できるものは、自分の存在だけだったのです。
と、このくだりはよく知られている話だと思いますが。
実は、注意深く『方法序説』を読むと、「明晰にして判明である」と理解できる事柄は無条件で正しい、とは結論付けていないのです。
この結論のために、デカルトは神の存在証明を行なおうとします。
自分という存在は不完全なのに、不完全な存在を越えた完全な何かについて、考えることが出来る。
その考えはどこから来るのか。不完全な自分からではない。完全なる本性を持ったもの、つまり神から、やって来るのだ。
デカルトはそういうおかしな理屈を主張したのです。
完全なるものについて、考えることが可能だからといって、どうしてそれが存在しなければならないのでしょうか。
そのせいで、デカルトの神の存在証明には、いろいろ批判が行なわれています。
ところが、困ったことに、デカルトに言わせれば、「われ思う、ゆえにわれ在り」という命題も、神の存在が証明されなければ正しくないものなのです。
「というのは、第一に、今しがた私が規則としたこと、つまり、われわれが極めて明晰かつ判明に理解することはすべて真である、ということでさえも、神があり存在すること、神が完全な存在者であること、われわれのうちなるすべては神に由来すること、のゆえにのみ確実であるからである」(山田弘明 訳 [16] p.64)
ということは、もしも神の存在証明が上手くいかなければ、他の真理もすべて駄目になり、デカルト哲学の全体系は崩壊してしまうはずなのです。
その体系の中でも重要な役割を果たすのが、実は数学なのです。
だからこそ、もう少しきちんとした説明であって欲しいのですが……。
とにかく、彼の数学についての考え方を見てみましょう。
すでに述べたように、デカルトは「われ思う、ゆえにわれ在り」を証明する過程で、この世のあらゆるものを疑うことに決めました。
それらのなかに、当然、幾何学(つまり、数学)も、入っています。人は単純な幾何学の推論でさえ誤ります。そうである以上、数学は疑われて然るべき、というのです。
この時点で、デカルトの主張はプラトンとは違います。数学を必然的な真理とはみなしてはいません。
つまり、「1+1=2」が成り立たない可能性があるわけです。
そればかりか、デカルトは矛盾律すら疑っていたことを、1644年5月2日付のメラン神父宛の書簡で告白しています。
矛盾律とは、Aを何らかの命題(つまり、真か偽かを問える文の内容のこと)としたとき、Aかつ非Aは成り立たない、というものです。
後の章で記しますが、ライプニッツは矛盾律の成り立たない世界の存在を認めません。しかし、デカルトの数学に対する懐疑はそこまで徹底したものだったのです。
それでは、数学的な法則の真理はどのようにして生み出されるのでしょうか。
デカルトは神の存在を証明した後で、次のように言います。
「神はそれらの法則を自然のなかにしっかりとうち立て、その概念をわれわれの精神のなかにしっかりと刻印しているので、われわれがそれを十分に反省したあとでは、世界に存在し生起するすべてのものにおいて、それらの法則が正確に守られていることを疑えないほどである」(同前 p.69)
デカルトによれば、数学や矛盾律などの法則が正しいのは、神が自然のなかにそれらの法則を創造するとともに、人間の心の中に生得的に法則を埋め込んでおくからなのです。
このようなデカルトの学説を、永遠真理創造説と呼びます。
これはかなり大胆な主張だといえます。
デカルトによれば、数学とは自然法則以外の何者でもないのです!
実は、デカルトは人類史上で「自然法則」という言葉を最初に用いた人間だったのです。
何故、そのように考えるのか。もう少し詳しく説明してみましょう。
デカルトの考えによれば、幾何学の対象である拡がりのある延長、すなわち空間とは、物質に他なりません。
つまり、後のニュートンやカントが考えたように、物質の無い空っぽな空間の存在を認めません。空間そのものが物質である、と考えます。
これを物質即延長テーゼと呼びます。これによって、空間のイメージを扱う幾何学そのものが自然科学と同じものになるのです。
一見すると、変な考えですが、現代物理学の観点からすれば正しい、と主張する人もいます。例えば、アインシュタインもその一人でした(小林道夫『デカルトの自然哲学』 [24] p.195など)。
現代物理学で考えられている場の理論では、真空は何もない空っぽの空間ではなく、それ自体が物理的な影響を伝える媒質である、と考えます。つまり、空間を物質と同様の実在物として考えるのです。
そういうわけで、それほど馬鹿馬鹿しい考えでもないのです。
幾何学についてはそれでいいとしても、それで数学全般が自然法則だと言えるのでしょうか。
幾何学は円やコンパスなどで描かれる図形の性質を調べる数学です。もともと幾何学geometryの語源が「測量術」にあるように、土地の面積を測るために必要な学問でした。
農耕が行なわれていたエジプト文明で、何度もナイル川が氾濫して、土地の面積を測りなおさなければならなかったので、幾何学が必要となりました。
したがって、幾何学はもともと物理的な空間を測るための数学だったのです。
ところで、私たちが数学の授業で習ったxやyなどの未知の数を解く方程式は、代数学という分野に属するものです。
代数学algebraとは、数の代わりに文字を使って計算する数学です。9世紀イスラムの数学者フワーリズミーによる『ジャブルとムカーブラの計算法についての簡約な書』の書名に出て来るジャブルal-jabr、つまり「復元すること」が語源とされています。
代数学はイスラムからイタリアへと渡り、ルネサンス期に商業が盛んになったために、商売を管理するための道具として発展していきました。
これらは単なる記号を使っただけの計算ですが、自然の中に存在する法則だといえるでしょうか。
実は、ここにこそ、デカルトの数学史上の功績があります。
デカルトは、数学の問題とは、何らかの比例関係(つまり、数同士の関係)を扱うことだと考えて、以下のように言います。
「私はこうも考えた。それら(比例関係のこと……著者注)を個別的によりよく考察するためには、それらを線において想定すべきであること。何故なら、線以上に単純で、私の想像や感覚に対して判明に表象されるものはないからである。だが、それらの比例を記憶にとどめ、多くを一度に理解するためには、それらを出来るだけ短いある記号で説明する必要があること。そして、こういう仕方で、幾何学的解析と代数とのあらゆる長所を借り、一方の短所をすべて他方によって正すだろう、と私は考えた」(同前 p.40)
つまり、線を引いて作図する行為は、記号を使った計算手続きと同一のものとして解釈できる、と言っているのです。
ここでデカルトが述べていることは、後世において、二変数xとyの組(x, y)で表わされる座標のことである、と解釈されました。
私たちは中学の時に、様々な方程式をグラフの上に線で表現することを勉強しました。
例えば、xの二乗に関わる方程式を放物線で描いたりしました。
つまり、a、b、cを実数とするとき、
y = a x^2 + b x + c
という二次方程式を使うと、xの部分に何らかの数値を代入したときにyの値が確定します。
(著者注……x^2は「xの2乗」を意味します。これ以降、^という記号が出てきたら、乗数を意味しているものと思ってください)
そうして出て来る(x, y)の組に対応する点をグラフ上にプロットしていくと、放物線のカーブを描きます。
そういう理由で、x軸とy軸が直角に交わっている座標(直交座標)のことをデカルト座標と呼ぶようになり、デカルトは解析幾何学の祖と呼ばれるようになったのです。
ところで、この直交座標を思いついたのはデカルトではありません。実は、ライプニッツが発案者です。
デカルト自身はそれまでの数学者と代わり映えのない斜交座標という斜めに交わった線を使っていたというのが、本当のところです。
その事を考えると、デカルト座標と名前をつけるのは変なのですが……。
後からやって来た数学者が、先人たちの考えを明確化し、それを先人の偉業ということにしてしまう。そういうことは、数学の歴史ではよくあることのようです。
ただし、既知の数a、b、c……と未知の数x、y……を使って方程式を記述する方法を開発したのは、文句なしでデカルトです。
これを使うと、未知数の計算を空間内部の線を引く作業とみなすことが容易にできます。
デカルトによれば、空間の法則は物理的な自然の法則に他ならないので、代数的な方程式もまた自然法則になるのです。
こういうことをデカルトが言い出すまでは、代数学は不遇の地位にありました。
それ以前の時代には、代数学は単なる発見法とされ、公準を基礎とした幾何学と比較して厳密さが低いものと考えられました。
また、アリストテレスの哲学が権威を振るっていた時代であり、数の計算と幾何学は全く取り扱っている対象が違うので、それらを結び付けて考えることは間違いだとされていました。
ところが、デカルトが方程式を一種の図形として考えたことで、それまでの幾何学では発見できなかったことを、次々と見つけ出せるようになったのです。
こうして、デカルトの自然学の構想は普遍数学の道へとつながっていきます。
さて、デカルトは自分の方法で、どういう数学的問題に取り組んだのか。
例えば、ギリシャの三大作図問題です。
ギリシャの三大作図問題とは、次の通りです。
(1)与えられた立方体のちょうど二倍の体積を持つ立方体を作れ(立方体の倍積問題)。
(2)与えられた円と同じ面積を持つ正方形を作れ(円積問題)。
(3)任意に与えられた角を三等分せよ(角の三等分)。
これらの問題を定規とコンパスを使って、解く問題です。
ただし、定規とコンパスしか認められません。
この問題に対して、デカルトは、定規とコンパスだけを使った作図には限界があると、考えました。
その限界は、代数方程式の解の作図法によって示されます。
代数方程式とは、任意の整数列a_0、a_1、……、a_(n-1)、a_nが与えられるとき、
a_n x^n + a_(n-1) x^(n-1) + …… + a_1 x + a_0 = 0
で表わされるn次の方程式のことです。
デカルトの頃には、三次方程式と四次方程式の解き方については、すでにカルダーノの公式とフェラーリの公式が知られていました。
しかし、五次以上の方程式についての解法は知られていませんでした。
これに対して、デカルトは、どんなn次の代数方程式の解であれ、その長さは作図可能だということを、示そうとしていたのです。
まず、一次方程式と二次方程式について、考察します。
デカルトの証明によれば、ある長さの線が与えられたときに、定規とコンパスで引ける線の長さは、足し算、引き算、掛け算、割り算、そして平方根の計算を繰り返すことによって、得られるものだけです。
一次方程式と二次方程式の解はこれらの計算を繰り返せば得られるものですから、定規とコンパスで作図可能ということになります。
デカルトはこの証明から、定規とコンパスだけでは、三次方程式や四次方程式の解は作図可能ではないだろう、と洞察しました。
このことが、三大作図問題に関係するのです。
なぜなら、三次方程式の解が作図可能になれば、三大作図問題のうち、二つまで解決できるからです。
立方体の倍積問題は、もとの立方体の一辺の長さに2の立方根を掛ければ、解くことができます。ところが、2の立方根は三次方程式の解なのです。
角の三等分も、ヴィエトの三倍角の公式などによって、三次方程式を解く問題に置き換えられます。
この二つの問題は三次方程式を解く問題になるので、一次方程式と二次方程式しか解けない定規とコンパスだけでは解答不能のはずである。
デカルトは、そう理解したのです。
ただし、理解しただけで、証明はしていません。この証明には、特殊な数学が必要で、19世紀以降になるまで、待たなければなりませんでした。
その代わりに、デカルトは円錐曲線を使った作図法を考えます。
円錐曲線というのは、楕円、放物線、そして双曲線の総称です。
いずれもxとyの二次方程式によってデカルト座標で表わせます。
円錐のどこかの部分をスパッと平面で切り取ると、その断面がこの三つの曲線のいずれかになるため、円錐曲線と呼ばれています。
この円錐曲線によって、デカルトは三次方程式や四次方程式の解の作図法を見出しました(この方法の説明は中村義作、阿邊恵一『代数を図形で解く』(参考文献 [23])にあります)。
こうして、デカルトは立方体の倍積問題と角の三等分を解決します。
ここまでは、よかったのですが。
デカルトは五次以上の方程式の作図法にもいくつかの複雑な例を示しました。
これによって、任意の代数方程式の解について、作図可能性に成功したと結論づけてしまいます。
これがもし本当だったら、デカルトはすごいことを達成したことになったでしょう。
もっとも、ライプニッツなどの後世の数学者たちはその間違いに気付くのですが……。
それはともかく、こうしてデカルトは、方程式と作図の同一視が有効であることを示しました。
これは確かに、定規とコンパスによる幾何学の進歩と呼べるものでした。
しかし、デカルトはまだ三大作図問題のうち、重要なものを一つ解いていませんでした。
それは円積問題、つまり与えられた円と同じ面積を持つ正方形を作る問題です。
では、デカルトは円積問題をどう処理したでしょうか。
定規とコンパスだけではこの問題もやはり難しいかもしれない。しかし、方程式を使って図を描く方法なら出来るんじゃないのだろうか。
実は、デカルトは、この問題に答えられなかったのです。
この問題を解くためには、円周率
π = 3.14159265359……
の長さを持つ直線を引く必要があります。
円積問題を解決するには、πの平方根を円の半径の長さに掛けた線分を引き、それを一辺とした正方形を描けばよいからです。
デカルトの時代には、アルキメデスの取り尽くし法やヴィエトの方法によって、円周率を計算する方法がありました。
しかし、デカルトの調べた方程式による作図法からは、円周率の長さの直線を引ける方法が見つからなかったのです。
円周率πは半径1に対する円周の半分の長さと同じなので、それを求めるには、曲線の長さを求める方法を必要とします。
ところが、デカルトは「直線と曲線との間の比は知られていないばかりでなく、私の信ずるところでは、人間には知りえないものであって、そこから精密で確実なものは何ひとつ結論しえないであろう」(原亨吉 訳 [26] p.31)と考えていたのです。
つまり、曲線の長さを求める方法は存在しないだろう、と主張しているのです。
こういうわけで、円周率を求める方法をデカルトは提起しなかったのです。
結果的に、デカルトはいくつかの曲線についての考察を放棄します。
円錐曲線などのxとyの二変数による有限次方程式を「幾何学的曲線」と名付け、螺旋や円積線などを「機械的曲線」と呼んで、区別します。
アルキメデスの螺旋や円積線は機械的な道具を用いれば、引くことができます。そして、円周率πの長さの線は、これらの曲線を使えば、簡単に引けます。
ところが、まさにこれらの曲線の数学的性質をデカルトは方程式で表わせなかったので、幾何学の枠組みには属さないと考えたのです。
デカルトは円積問題に答えられなかったのですが、これが意味するところは重要です。
このデカルトの推察に基づけば、円周率πは代数方程式の解にはなりません。
彼の憶測では代数方程式の解は幾何学的に作図可能ですが、πの長さはそうではないからです。
ところが、代数方程式の解となる数は無限に存在するはずなのです。
単純に、2の平方根、立方根、四乗根、五乗根、……はそれぞれ、
x^2 - 2 = 0
x^3 - 2 = 0
x^4 - 2 = 0
x^5 - 2 = 0
……
となるxの値ですから、任意のnについて、2のn乗根は代数方程式の解となります。
同様の考えで、3のn乗根、4のn乗根、5のn乗根、……も代数方程式の解ですから、任意の自然数m、nについて、mのn乗根もそうなります。
代数方程式の解となるすべての数の集まりは、mのn乗根を全て含みます。
すると、該当する数は無限に存在するはずなのに、その中に円周率πが含まれていないことになります。
つまり、デカルト流の代数的な記号と幾何的な想像力を結びつけるやり方だけでは、表現できない何かが数学には潜んでいるらしいのです。
無限という、想像力を超越した領域に、円周率の謎が隠されているからです。
眼に見えない無限の領域をどうすれば数学的に表現できるか。
この問題に答えられなかったところに、デカルトの限界があったのです。
◆ パスカル 真理を諦め「賭け」に生きる
結局のところ、デカルトの哲学は、さまざまな批判を浴びます。
アントワーヌ・アルノーはパスカルと共にジャンセニスムという宗教思想の擁護者であり、ライプニッツとも論争を交わした人です。
このアルノーは、デカルトが循環論法を犯している、と指摘します。
デカルトは、「明晰にして判明」という基準を出発点にして神の存在を証明しておきながら、この基準の正しさそのものを神の存在によって導き出すわけです。
この指摘は、「デカルトの循環」として有名です。
また、論敵であるガッサンディやホッブズに対しても、批判を受けます。
デカルトのように理性ではなく、経験を重視した彼らは、デカルトの心身二元論を批判して、唯物論を唱えます。
そして、デカルトの神の存在証明を、神についての考えと、その存在を区別できない不十分なものとみなします。
「無益で不確実なデカルト」(前田陽一、由木康 訳 [27] p.56)
パスカルもまた、このようにデカルトを断罪します。
パスカルはデカルトによる神の存在証明が数学=自然学的な真理を保証するためだけに行なわれたものだったことを看破します。
「私はデカルトを許せない。彼はその全哲学の中で、できることなら神なしですませたいものだと、きっと思っただろう。しかし、彼は、世界を動きださせるために、神に一つ爪弾きをさせないわけにはいかなかった。それから先は、もう神に用がないのだ」(同前 p.56)
パスカルもまた、ピュロン主義の影響を受けた人物でした。
パスカルは先述のとおり、ジャンセニスムというカトリックの宗教運動に関わっていました。
この運動は戦争の災禍の中、人間の罪深さについての反省から生まれたものでした。
ジャンセニスムの人々は、アウグスティヌスの思想に、自分たちの救いを求めました。
そして、人間は自らの意志によって罪から救われるのではなく、神の恩寵によって救われると考えました。
これはルターの自由意志批判と似ているように見えます。ルターもまたアウグスティヌスの影響を受けていました。
しかし、彼らは恩寵によって清らかな魂を得られれば、厳格な道徳による信仰生活が得られると信じていたので、人間は悪を克服できると思っていました。
よって、彼らは奇跡を信じました。パスカルもまた神秘体験を得て、信仰に確信を持つようになりました。
戦争で荒廃していく人々の心に、倫理的な生き方を取り戻そうとしたのです。
ところがルターを批判するために、自由意志を擁護したカトリックの主流派からすれば、彼らの主張は足元を揺るがせかねないでした。
そして、ジャンセニスムは教皇から異端宣告され、弾圧を受けます。
パスカルはアルノーと共に、主流派であるイエズス会に抵抗していくことになります。
パスカルの立場はとても厄介でした。
パスカルはプロテスタントの唱える真理に否定的だったので、懐疑論を積極的に受け入れました。
しかし、イエズス会に対しては自分たちの真理を主張しなければならなかったので、懐疑論を否定しなければならなかったのです。
ピュロン主義は元々、あらゆることに判断中止を貫くことで、何事にも心を煩わせない無動揺(アタラクシア)の境地に至ることを理想としていました。
しかし、パスカルに言わせれば、こんな判断中止による無動揺の境地など、この世のどこにも存在しないものでした。
こうしてパスカルは懐疑論そのものまで懐疑をし、ストア派にもピュロン主義にも依存しない信仰による生き方を選択します。
この真実と虚偽の間で絶えず戸惑いながら信仰へと向かう姿勢は、彼の数学観にも現れています。
『幾何学の精神について』という短い文章で、幾何学で使われる言葉の定義について、簡単な考察が行なわれています。
パスカルは、「定義は、命名する事柄を指示するためにだけ作られるのであって、その事柄の本性を示すために作られるのではない」(支倉崇晴 訳 [28] p.400)と述べて、アリストテレスの哲学を批判します。
というのも、aという言葉の定義を行なうためには、何らかの別の言葉bを使うより他なく、その言葉bの定義を行なうためには、また別の言葉cを使う以外になく……、という無限後退が起きるからです。
こんな定義づけの後退を延々と繰り返していくと、どうなるでしょうか。パスカルは以下のように、断言します。
「探求をますます推し進めることによって必然的に到達するのは、もはや定義不可能な根源的な言葉にであり、また、その証明に用いるこれ以上ないほど明白な原理にである。そこで分かる事は、どんな学問にせよ、絶対的に完璧な秩序において論じることなど、人間には元々どうあってもできないということである」(同前 p.398)
つまり、どこかでこの定義づけは終着点を迎えるしかなく、無限に遡っていくことなどできないのだ、ということです。
この終着点は、当然、正しさを保障できるかどうか、分かりません。
正しさを語れない以上、幾何学のルールは無意味な言葉の羅列である可能性があるのです。
この点で、パスカルの思想にはヒルベルトの形式主義の萌芽が見られる、と考える研究者もいます。形式主義については後の章で説明します。
こうして、パスカルは幾何学の正しさを、単に信仰することしかできません。
パスカルは『パンセ』において、「われわれが真理を知るのは、推理によるだけでなく、また心情によってである」(前田陽一、由木康 訳 [27] p.188)と主張します。
パスカルにとって、数学の正しさとは、「幾何学の精神」とともに、「繊細の精神」を要求するものだったのです。
ところで、パスカルが無限後退の問題にこだわったのは、デカルトと同様に、「無限」を考察しようとしていたからです。
デカルトの考えでは、神は無限なる存在でしたから、神の存在を証明するということは、無限の存在を証明することと同様でした。
しかし、パスカルはこの証明を無益で不確実だと言いました。パスカルにとって、神、即ち無限について論じることは不可能だったのです。
「もし神があるとすれば、神は無限に不可解である。なぜなら、神には部分も限界もないので、われわれと何の関係も持たないからである。したがって、われわれは、神が何であるかも、神が存在するかどうかも知ることができない」(同前 p.158)
従って、パスカルにとって、神が存在するかどうかというのは、一か八かの賭けになります。つまり、確率の問題です。
パスカルはフェルマーと共に、確率論の創始者と呼ばれていて、偶然起こった出来事にも何らかの規則が存在すると主張した最初の人でした。
パスカルはド・メレの依頼によって、掛け金の分配問題の数学的研究を行っているうちに、この考えに辿り着きました。
「聖アウグスティヌスは、人が海の上や、戦争などで、不確実なものために働くのを見た。しかし彼は、人がそうしなければならないのだということを証明する確率決定の規則を見なかった」(同前 p.165)
パスカルは、人間が賭け事などという不確実極まりないものに自らの気晴らしを見出す場合にも、確率的な規則が働いているのであり、人が航海や戦争などという確実性がないことをする場合にもそうなのだ、と考えました。
そして、パスカルは、神が存在するという確実な証拠はどこにもない、という無神論者の主張に対して、次のように言い返します。
そもそも人間は不確実な規則に基づいて行動しなければならない。神がいなければ君は何も失わないが、神がいたら君は無限に儲かるのだから、さあ賭けたまえ。
確実なものなど何もないと主張する懐疑論に対して、不確実なもののなかにも規則が存在すると説いたパスカルの思想は、懐疑論批判として優れた側面を持っていました。
しかし、パスカルは、真理と虚偽の間で絶えず宙吊りにされる思想から、まとまりのある体系を作り出すことができませんでした。
元々、『パンセ』は『キリスト教護教論』というジャンセニスム擁護の著作として企画されていたものでしたが、パスカル自身の重い病のせいもあって、結局、未完に終わります。
パスカルの思想は断片的なものに留まり、社会的な影響力を及ぼしていくには、取り留めのないものとなってしまいました。
ジャンセニスムの運動も18世紀には消滅することとなります。
ホッブズからデカルトを経て、パスカルに至るまで、戦争の混乱と懐疑論に挑戦した人々は、結局、時代の波に飲まれていきました。
しかし、彼らの思想の一部分は、やがてライプニッツに影響を与え、大きな計画へと変化します。
その計画について説明する前に、本節で無限についての話題が出てきたので、次の章では、無限論を振り返ります。
数学の正しさへの問いが17世紀に盛り上がったのは、懐疑論の影響と共に、無限に関する論争があったことに原因があります。
アルノーの循環論法の指摘やパスカルの無限後退も、元々はセクストス・エンペイリコスが紹介した論法です。相手の論理を無限の循環や無限後退に陥れてしまえば、どんな理屈も破綻に追い込めます。
しかし、セクストス・エンペイリコスだけが古代において無限を問題にしたのではありません。そもそも無限論は、古代ギリシャ時代からヘレニズム期にかけて、哲学者たちの間で盛り上がった問題でした。
ところが、この問題は15世紀になるまで、人々の間から忘れ去られてしまいます。
それを復活させたのは、何だったのか。
それは、とある修道院に眠っていたエピクロス派の一冊の書物でした。
参考文献
[1] スチュワート・シャピロ『数学を哲学する』金子洋之 訳 筑摩書房(2012)
[2] 内山勝利(編)『哲学の歴史 第2巻 帝国と賢者』中央公論新社(2007)
[3] セクストス・エンペイリコス『ピュロン主義哲学の概要』金山弥平、金山万里子 訳 京都大学学術出版会(1998)
[4] 森毅『魔術から数学へ』講談社学術文庫(1991)
[5] アミール・D・アクゼル『デカルトの暗号手稿』水谷淳 訳 早川書房(2006)
[6] 佐々木力『科学革命の歴史構造(上)(下)』講談社学術文庫(1995)
[7] ヘルムート・プレスナー『ドイツロマン主義とナチズム』松本道介 訳 講談社学術文庫(1995)
[8] 小田垣雅也『キリスト教の歴史』講談社学術文庫(1995)
[9] C.ヴェロニカ・ウェッジウッド『ドイツ三十年戦争』瀬原義生 訳 刀水書房(2003)
[10] リチャード・ポプキン『懐疑―近世哲学の源流』 野田又夫、岩坪紹夫 訳 紀伊国屋書店(1981)
[11] 小林道夫(編)『哲学の歴史 第5巻 デカルト革命』中央公論新社(2007)
[12] 佐々木力『近代学問理念の誕生』岩波書店(1992)
[13] J.W.N.ワトキンス『ホッブズ―その思想体系[新装版]』田中浩、高野清弘 訳 未来社(1999)
[14] トマス・ホッブズ『哲学原論―自然法および国家法の原理』伊藤宏之、渡部秀和 訳 柏書房(2012)
[15] ソール・A・クリプキ『ウィトゲンシュタインのパラドックス』黒崎宏 訳 産業図書(1983)
[16] ルネ・デカルト『方法序説』山田弘明 訳 ちくま学芸文庫(2010)
[17] 瀬山士郎『幾何物語』ちくま学芸文庫(2007)
[18] ヴィクター・J・カッツ『カッツ 数学の歴史』上野健爾、三浦伸夫 監訳 中根美知代、高橋秀裕、林知宏、大谷卓史、佐藤賢一、東慎一郎、中澤聡 訳 共立出版(2005)
[19] カール・B・ボイヤー『ボイヤー 数学の歴史 3(新装版)』 加賀美鐵雄・浦野由有 訳 朝倉書店(2008)
[20] 佐々木力『デカルトの数学思想』東京大学出版会(2003)
[21] 矢野健太郎『角の三等分』ちくま学芸文庫(2006)
[22] 瀬山士郎『はじめての現代数学』ハヤカワ文庫(2009)
[23] 中村義作、阿邊恵一『代数を図形で解く―直感でわかる数学の楽しみ』 講談社ブルーバックス(2000)
[24] 小林道夫『デカルトの自然哲学』岩波書店(1996)
[25] 野崎昭弘『πの話』岩波現代文庫(2011)
[26] 『増補版 デカルト著作集1』三宅徳嘉、小池健男、青木靖三、水野和久、赤木昭三、原亨吉 訳 白水社(2001)
[27] パスカル『パンセ』前田陽一、由木康 訳 中公文庫(1973)
[28] 赤木昭三、支倉崇晴、広田昌義、塩川徹也(編)『メナール版 パスカル全集 1』白水社(1993)
[29] スティーヴン・グリーンブラッド『一四一七年、その一冊が全てを変えた』河野純治 訳 柏書房(2012)
応募者紹介
石川友太郎さん
大学時代は物理学を学んでいたが、入学当初から哲学を学ぶべきだったと後悔する。
何となく哲学に近そうな分野として、人工知能と数理論理学を学ぶため、大学院に入学。
認識論理学や法的推論など、人の知識や常識を形式化する非古典論理を研究する。
以来、数学や論理学などの人間社会との関係について、考察するようになる。
ランキング
あわせて読みたい
ミリオンセラー新人賞
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






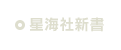


ジセダイユーザからのコメント