新人賞投稿作品
アポロンが触れる刻(とき)
なしコピー
はたして人類は、臨界を超えた破滅の炎を手に入れた刻(とき)、どのような選択に迫られるのか?
カテゴリ
歴史
内容紹介
二十世紀前半の歴史を、文明、戦争、科学、そして、核兵器開発などの要素を重ねながら俯瞰してみる。
目次案・語りたい項目
原発問題にいまだに揺れている日本に対して、原子爆弾と歴史というアプローチから提言してみたい。
書き出しの第1章
『ある若者の燃えつきた恋文』より抜粋。
拝啓
あなたのことを想うと、夜は眠れず。
あなたの姿に焦がれると、体は震える。
あなたこそが私の全てであり、私の生きる意味である。
あなたがあって、私の時間は存在する。
あなたなくして、私自身は存在しない。
あなたに会いたい。
あなたをこの腕に包み込みたい。
ああ、いち早くあなたのもとへと駆けつけたい……
* *
一九四五年・六月上旬。
アメリカ合衆国ワシントンD.C.ホワイト・ハウスのオーバル・オフィス(大統領執務室)。
在日本アメリカ合衆国大使および国務長官代理のジョセフ・クラーク・グルーは、アメリカ合衆国第三十三代大統領のハリー・S・トルーマンを目前にして困惑していた。
第二次世界大戦末期下。
前大統領のフランクリン・ルーズベルト以来、アメリカ・イギリス・ソ連(現在のロシア)・中華民国(現在の中華人民共和国)の大国が世界平和の維持を務めるという、「四人の警察官構想」に楔を打つべく、つい先頃の五月にソ連への軍事援助の凍結の発表をアメリカの代表としてグルーは行った。
はたして、国際平和を目的として、カント的なコスモポリタニズムを掲げる四人の警察官構想に、どうしてアメリカはそのような水を差す行動に出たのか。
資本主義を標榜するアメリカではあるが、前任の大統領であるルーズベルトは、共産主義にいささかの希望を見出しており、共産主義国家と大同盟する事で、多少の懸念はあるものの、理想的な国際社会が築き上げられるのではないか、と模索していた。だが、ルーズベルトが急死して、世情が変わるにつれ、トルーマン政権の頃には、共産主義は自由主義、資本主義に対する脅威と見られるようになっていた。
つまり、第二次大戦後の国際社会をアメリカがリードしていく上で、ソ連や中国などの共産主義国家とは協調は望めない。それは即ち、戦後の覇権争いが、資本主義と社会主義ないし共産主義との対立構造になると見越しての事だった。
そこでアメリカは直近の戦争の終結を予期して、ソ連への武器貸与援助を断った。この方策を推したグルーに対して、現大統領のトルーマンも賛同していた。だからこそグルーは思っていたのである。もうすぐ、この戦争は終わる、と。イタリア、ドイツの枢軸国が降伏した現在、残る日本に対して後は降伏勧告を通知すれば、悪夢のような世界規模の今次の戦争は終結するはずだ、と。トルーマンも同じ考えで、気持ちは汲んでいるはずだ、とも。
しかし、グルーは困惑しているのである。
グルーは東京空襲、大阪空襲、さらには沖縄本島での上陸作戦を経て、日本が気息奄々(きそくえんえん)たる状況である事を、トルーマンは理解していると考えていた。また、知日派でもあるグルーは、これ以上の日本への攻撃を望まない。だからこそトルーマンには王手(チェックメイト)を宣告して欲しかった。もはや日本が連合国に歯向かう力はないのだから。
それ以上に、むしろ日本に対して降伏勧告を躊躇していると、ソ連が対日参戦をしてきてしまう。そうなると戦後の国際間における、アメリカとソ連のパワーバランスに支障をきたす事になる。
グルーは危惧する。
ソ連が対日参戦してくれば間違いなく日本は自らの側から降伏を申し出るはず。そうなれば今次の戦争は終わる。だが、そのようなシナリオになれば、ソ連が戦争を終わらせた立役者になり、アメリカの沽券にも関わってくる。そうなってしまえば戦後、アメリカが世界のリーダーシップをとっていく上で、かなりのマイナスポイントとなる。
そのようなリスクがあるにも関わらず、グルーの日本への降伏勧告の提言を、アメリカ合衆国第三十三代大統領は棚上げにする。
今、この時も。
「しかし、大統領閣下(プレジデント)。このまま日本を放っておいた状況におくとソ連が……」
「まだ、な。まだ……なんだよ」
直立しているトルーマンはグルーには背を向けたまま、窓の景色を眺め、淡々と答えた。グルーにはその表情は窺えない。グルーは一つ咳払いすると語気を荒めて、
「ですが事態は一刻の猶予も……」
「まだ終わらすわけにはいかんのだよ」
グルーの強い口調を遮ったトルーマンの言葉は、あくまで短く静か。だが、低く重たい声音であった。微動だにしないその背後からは、相変わらず気色は窺えないものの、その姿から放つ異様な気迫に押され、グルーは閉口してしまった。
しかし、終わらすわけにはいかない、というトルーマンの一言からグルーは一つの疑念ともつかない考えが浮かんだ。
もしや、あの『爆弾』の完成を待っているのでないか?
不意によぎる思い。同時にそれを思い出すと奇妙な徒労感に襲われる。一方で自分と同じく中老も半ばにある目前の男の背からは、弱気な気配はもちろん、倦むべき衰えも、一片の老いすらも感じられない。
ハリー・S・トルーマン。前大統領の急死によって副大統領から自動的に昇格した大統領のポスト。実力、というよりは射幸的な意味合いが強かった大統領就任劇。その縁にありカリスマ性という部分でフォロワーする者は多くはなかった。だが、今、目の前にいる眼鏡をかけた優等生然たるこの男からは、はたして強い後光(ハロー)すら垣間見えた。
自らと等しい「老い」を、トルーマンは持っているとグルーは思っていた。年老いて精神も脆くなっているはずだ、と。しかし、この男には意気が感じられた。強さが溢れていた。壮(そう)が漲(みなぎ)っていた。だが、若さではない。清く澄んだ若さとはかけ離れている。それはもっと黒く歪んだある種の妄執。
そして、グルーは顧みる。
この男は自らの存在意義(レーゾンデートル)を、『原子爆弾(アトミック・ボム)』に仮託しているのではないか、と。
応募者紹介
なしさん
第一回立川文学賞佳作入賞
ランキング
あわせて読みたい
ミリオンセラー新人賞
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






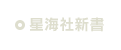


ジセダイユーザからのコメント