新人賞投稿作品
Good medicine tastes bitter.
ちゅるコピー
他人に手痛い仕打ちを受けた者だけが、そうでないものに対してだけ、やさしくできる。
ほんのちょっぴり他人より上手に。
カテゴリ
エッセー
内容紹介
「僕」は、華の都「東京」にきて、その実力のなさに絶望する。光ケーブルと体ごとつながりそうな暮らしの僕は、しかし、そのインターネットという空間にも、嫌気がさし、次なるアスピリンとして、アルコールを求めおぼれた。
「僕」は一件のお店で、とある女の子と出会い、恋をする。そして、手痛く振られる。失意のどん底、新しい恋を見つける。そして、振り回され、ボロボロになった僕は、幼い頃、貧しさにあえぐ家に生まれ、お母さんどこ?と叫んでいたことを思い出しながら、一粒の涙を流す。
涙目の、僕は天使のような美少女と出会う。今度こそはと、結婚をする直前、親の猛反対を受け、駆け落ちを決意する。血と地の縁に別れを告げる物語。
目次案・語りたい項目
・インターネットジャングルの引きこもり
(東京に来て、しばらくひきこもってネットをしていた場面)
・東京ジャングルに住みたい。二人きり
(夜の仕事の女の子にまんまと引っかかる話)
・下北沢ブルース
(サブカルでメンヘラな美少女に振り回される話)
・赤水と社宅と僕
(幼少期、極貧だった話)
・ドンペリニョン狂想曲
(女の子に振られて、借金をしながら、「お店」で貢ぐ話)
・やっぱり大好き東京ジャングル
(疑心暗鬼な「僕」がフツーにかわいい女の子と出会う話)
・駆け落ち喫茶
(親に結婚を反対されて、遠くに逃げる話)
書き出しの第1章
【女子力とサラダ問題】
上京当初、コンパによく誘われた。
合コンというやつである。
女の子の会費が男子の半分とかになっているアレ。
僕のことをあまり知らない友だちになったばかりの人たちは、最初のうち、それによく誘ってくれたのだが、次第に誘われなくなった。
「ああいう場所得意じゃないからさあ」と真面目ぶって答えたものだが、その言葉の意味を彼らはどうやら誤解していた。
確かに可愛い女の子は、あまりああいう場に来ない。
いかなくても、街角でさえ、声をかけられるからだ。幾人もの男達に。
だが、彼女らにも付き合いがある。
友だちの付き添いで、合コンに来ることもあるのだろう。
たとえ、1%以下でも、もしもそんなチャンスがつかめるのなら、本来なら、そんな場に顔を出すのが普通なのだろう。
多分、普通の男子よりも僕は美少女が大好き。きっと異常なほど、好き。
でも、僕がそこに顔を出さなかったのには、理由がある。
女子達は、当時流行っていた「女子力」をひけらかすために、もしくは男子らからの要請に応えるために「サラダを取り分けたり」するだろう。
僕は、これが嫌だったのだ。
そこに女子力を見出す彼女らと、彼らに。
それは、きっと家庭的な行動だ。優しさを持った行動だ。
だけれど、全方向の優しさを持った行動。もしかしたら、嫌われないための行動だ。
参加者全員に。
僕はこの問題を考えるとき、嫌気が差す。
狭量で性格の悪い自分自身に。
僕だって、サラダを取り分けてほしい。お菓子を作ってきてほしい。手料理を作ってほしい。
飲み会で、僕はサラダを取り分けたり、お菓子を作ったり、手料理を作ってきたりして、女子力アピールをする女子が、家庭的であることをアピールをする女子が所帯じみているように思えて、得意じゃないと言ってきた。
あれは嘘じゃない。
ただ、若さゆえの過ち、言葉が足りなかっただけなのだ。
僕は、嫌いなのだ。
サラダをとりわけ、手料理を作ったり、お菓子作りをしたりする、それを僕以外にもしたりする好意の方向性が広い女子が。
好意を示すレンジが広い女子が。
だから、僕は、例えば、飲み会でなら、僕以外に話しかけられて、困った顔をしながら、あたりさわりのない話題を返す女子が好きなのだ。
僕が彼女をパーティに連れて行く妄想を良くするのは。
パーティドレスが狂ったように好きなのは、前述のコンテクストに当てはまるシチュエーションと近しい距離にあるからなのだ。
ああ、嫌になるよ。心の狭さに。
僕の大学生活は、憧れの東京での生活は、コンクリートジャングル。
周り大きなものに囲まれて、狭いところに詰め込まれて、はじまった。
自分の心に閉じこもることからはじまった。
【2001年の邂逅】
僕がパソコンと出会ったのは、インターネットと出会ったのは、小学生の頃だったと思う。
学校では、ワードやパワーポイントを習った。(そこでは、往々にしてめちゃくちゃダサいものが、見本になっていた)
インターネットも少しした。
ここでも、やはりめちゃくちゃダサいものにアクセスした。
周りの友人らは、確か、面白フラッシュなんてものが格納されているサイトにアクセスして、声を押し殺しながら笑っていた。
僕は、割と根暗だったし、人と同じものを見るのが嫌だったから、当時流行のテキストサイトによくアクセスしていた。(あなたは何人目の訪問者です!というカウンターと、CGIでできたチャットスペースの設置されているあれだ。相互リンクは、大抵常に募集中だった)
そこには、僕が知らない世界、見たことのない世界が広がっていた。
信じられないほど、理知的で意地の悪い議論。その応酬。
何かに入れ込みすぎて、崩壊しそうな人々の日記。
ど田舎にいた僕は、ものすごい親近感を覚えた。
みんなで同じフラッシュを見て笑っていては、みんなと同じになってしまう。
僕は、笑う側に満足したくなかった。せめて、僕と嗜好のあう人を笑わせてみたかった。
ゼロ年代の始めくらいまでのインターネットは、まだ、アングラで社会的にマジョリティではない人々とその意見がマジョリティを占めている、という感があった。
僕は、ここで面白いことがしたいと思った。
普通に、生きているだけでは、学校に通うだけでは、出会えない人を笑わせてみたいと思った。
家には、親が仕事で使っているパソコンがあったから、HTMLを覚えることは難くなかった。ホームページビルダーはなかったけれど、僕のホームになりそうなものを創り上げることは、すぐできた。
【ポストモダンの先に】
翻って、今のインターネットにあの頃のワクワクはあるのだろうか。
確かに、今でもインターネットは面白い。
表現の幅も広がり、表現する人も増えた。
テキストや写真だけじゃない。動画だってみられる。
だけど、一抹のさみしさを覚えるのは僕だけなのだろうか。
インターネットって、もっと狭いものだった。
好きな子がやってる前略プロフを見にいったり、その子のページに書き込みをしてる男に憤慨したり。mixiができたときには、好きな子の友人の男すべてに違反申告
をしたりした。
そんな僕もきっと丸くなった。僕が大人になったからなのか。
だけれど、僕はやっぱり狭い世界が好きなのかもしれない。世界は、近くなった。
そして、多分少しだけ窮屈になった。
インターネットは、マスにリーチできる(する)手段になった。
言い換えれば、テレビ的に、つまり多くの人に受けるものをこれまで以上に発信する手段になった。それは、商業的に、正しい。すごく正しい。
だけど、僕が好きだったインターネットは、最近、勢いを弱めている。
あのアングラさは、もうない。
すぐに、正義の味方みたいな大多数にそれはおかしいとインターネットの世界から追いやられてしまうから。これは、例えば、テレビでもそうだから(どちらも特権的でなくなったので善し悪しあるけれど)時代の要請かもしれない。
だけれど、もしそうなのだとしたら、僕はインターネットをもう趣味として楽しめないかもしれない。
川本真琴氏も、半径3メートルの内側にある幸せを噛みしめようと歌っているのに。
チャットモンチーは歌う。ケータイを川に落としたら、何だそんなものでつながっていたのか。と。
近くにある幸せを噛みしめたい。
近くにいる人を笑わせたいよ。
近くにいる人以外、くすりともしない表現で。
【人生がときめく片付けの魔法】
10年代を生きる僕。
ひょんなことから、自宅のパソコンは悲鳴をあげた。
ブルースクリーン、強制シャットダウン。
僕と広い世界は切断さらた。
パソコンのない生活は不便だ。と思っていた。
しかし、意外にそうでもなかった。
僕は、パソコンで何を見ていたのだろう。
違う。何かを探していた。あの頃みたいなワクワク、ときめきを。
だけど、パソコンは、インターネットは今や、世界と繋がるための、世界の大勢の人と繋がる人の手段。
そうでない人が押し潰されている可能性は否定できない。できないんだ。
僕はパソコンにインターネットに張り付いていた。
どこにでもいける万能感の裏に焦燥感を感じていた。
空いた時間で、いつもはネットの海を泳ぐ時間で、僕は掃除をした。
レンジフード、グリルの油取り。
窓拭き。時間ってちゃんとあるんじゃないか。
そう思えた。
Tommy february6を聴いて、本を読んで。紅茶をいれて。
良さそうな鍋や包丁を探したりして。
なんだ、一つ減らしただけで、軽くなる。人生は軽快になる。
名著『人生がときめく片付けの魔法』にもあった。
自分の身の回りに、ときめくものだけを置いておくことで幸せになれる。そうでないものは、ありがとうと言ってバイバイする。
スピリチュアルだなあと思ったけれど。表現がそう思わせるだけで、実際、自分がときめかないものを身の回りに置くことは良くない。
確信した。
やっぱり僕は、狭い幸せな世界が好き!
電話して、LINEして。
たまにTwitterをして。
ゼロ年代は、小さな物語を生み出して、10年代は、その否定がなされようとしていたけれど。まったくそんなことはない。
小さな物語が結集して、大きな物語を踏み越えていくかもしれない。
好きなものに囲まれた世界の結集に、既存の世界は、もう抗えなくなっている。きっと。
次の瞬間、僕はパソコンを廃品回収に出した。
プロバイダを解約した。
ドアを開け放って、ようやく東京ジャングルに出向くこととなったのだ。
【歌舞伎町の女王】
「昼職につきたいんですよね。終電で帰りたい」
目の前で僕にビールを注いでくれる女性は言う。
僕はインターネットという麻薬を捨てて、アルコールにおぼれ始めていた。
僕は違和感を持った。
「昼職」というのは、いわゆる夜の仕事についている人がよく使うギョーカイ用語だからだ。
僕は、そういう夜のお店がないから、ショットバーに狂ったほどに通いつめては、バーテンと話し込んでいたのだが。
「すみません、昔、そういうお店で働いてました?」
彼女は一瞬、ギクリとした顔をして、僕に向き直り、笑顔をたたえた。作り物の笑顔を。
僕は、しまったなあ。と思った。
そういう、「ホント」っぽいしぐさに弱いのだ。
僕は。
僕が彼女にほれ込むのに、そう時間はかからなかった。
応募者紹介
ちゅるさん
ランキング
あわせて読みたい
ミリオンセラー新人賞
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.






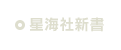


ジセダイユーザからのコメント