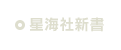星海社新書
甲斐武田氏の新たな通史(レビュアー:大石泰史)

「虚」を剥いで「実」を探る歴史の醍醐味
今年の大河ドラマ『真田丸』の視聴率は、かなりいいらしい。現在、物語は織田信長による甲州攻めから始まり、羽柴(豊臣)秀次が切腹するという段階まで進んだ。冒頭の甲州攻めでは、敗軍の将となった武田勝頼を演じた平岳大さんの演技が好評だったと聞く。これまでの勝頼は、著者も述べているように「後世の評価はあまり高くな」(158頁)かった。しかし、文書・記録類を駆使して勝頼の再検討を行った平山優『敗者の日本史⑨ 長篠合戦と武田勝頼』(吉川弘文館-2014)によると、従来の評価は余りにも低いという。そうした点で今回のドラマにおいて描かれた勝頼像は、ある意味史実に近づいた感がある。
大河ドラマは史実を採り入れる一方で、当然「ドラマ」としての虚構も含みながら物語が進んでいく。何しろ大名たちの日常生活は、なかなか史料に残らない。だからこその虚構なのだが、視聴者は「こんなことがあったかもしれない」というその〝虚実ない交ぜ〟のストーリーを楽しむ。ただ時折、研究者からすると困ったことが起きる。それは、虚構部分を史実と勘違いされてしまうことだ。
私は来年の大河ドラマ『おんな城主 直虎』の時代考証を、小和田哲男静岡大学名誉教授と一緒に担当する。5月に主人公の直虎を囲むキャストが公表され、さらに先日、その第2弾も発表された。今川氏が大河ドラマに登場するときは、だいたい義元が桶狭間において織田信長に討たれ、その後の氏真によって滅亡するという、「天下人」信長と家康のいわば〝引き立て役〟とされる。来年の大河ドラマにおいて、今回の勝頼のように、史実に近い今川氏像が浮かび上がってくれれば言うことないのだが......。
ところで勝頼の評価がこれまで低かった背景には、おそらく一面では、彼の父信玄を「偉大」に見せることが重要だったという点があろう。つまり、勝頼もじつは〝引き立て役〟の一人だったのだ。
これは、信玄の前代信虎にしても同様である。信虎への評価は、「強権的な面や粗暴な性格が強調されて」(79頁)おり、それはやはり前代の悪政を正した「偉大」なる信玄を語るうえで欠かすことのできない重要なストーリーだった。そうしたこれまでの評価を、史料を基に一枚ずつ剥いでいく。歴史研究のおもしろさはこういったところにもあると言える。
「国衆」研究など新成果を加えた「武田の新通史」
『真田丸』の第2話において、勝頼が真田昌幸の居城岩櫃城(群馬県東吾妻町)へ移らず、小山田氏の岩殿城(山梨県大月市)へ向かおうとしたものの、小山田氏の領域に入ることもできずに踵(きびす)を返すシーンがあった。これは、近年の「国衆」研究から想定される場面であった。
国衆とは、「周辺の強大な勢力(戦国大名)に従属しながら、一郡〜数郡程度の領域を支配した領主」(26頁)で、「戦国大名の下で支配領域の存立が維持できないと判断した時には、国衆が他の戦国大名に寝返ったり、複数の戦国大名の間で「両属」の関係になったりする」(同)存在であった。勝頼が小山田領へ入れなかった上記のシーンはまさにそれで、2007年の『山梨県史』通史編中世以外、これまでの自治体史ではこうした自立的な領主の存在に配慮することがなかったのである。
この「国衆」の研究成果を本書に取り入れているというのは、大きな特色だろう。武田が領国とした甲斐と信濃は、その国衆が多く存在していた。そのため、本書でもその研究成果を活かす必要があった。
特に甲斐国内の小山田氏については、「国衆」という切り口によるアプローチから様々な知見が得られている。著者が今回、基底に据えた『勝山記』という年代記は、その小山田氏の領域下において記されたものであるため、「国衆」小山田氏の動向を抑えることもできる。
さらに『勝山記』の特徴として挙げられるのは、甲斐国内の情勢に併せて、天候や災害について多くの記載があるという点であり、それを本書に盛り込んでいるのも特色の一つである(巻末に「『勝山記』に見る甲斐の情勢」年表がある)。天正13年(1585)11月に飛驒地方を襲った地震によって、同国の国衆・内島氏理(うちがしまうじまさ)は居城の崩落で没しているし(大石編『星海社新書 全国国衆ガイド』204頁)、三河の徳川家康も同じ地震によって、同年8月の上田合戦で真田昌幸によって打ち負かされたことに対する雪辱を果たそうという意向を、結局取り止めてもいる。
こうした自然災害は大名・国衆の動向だけでなく、民衆にも大きな影響を与えている。天文10年(1541)の信玄による信虎の追放は、前年の大風(台風)が農作物へ影響を与え、さらに同10年も100年に一度の大飢饉であったにもかかわらず、信虎は戦いを継続した。そのため領民あるいは大名の被官等に「徳政」意識が芽生え、信虎の追放劇が無血で行われたのだ(88頁)。
これまで武田氏といえば、「屈強な騎馬部隊」を有する戦国大名を想像する方が多かったであろう。最新の戦国史に関する研究成果は上記の「国衆」研究や「自然災害と大名との連関」を踏まえた研究のほか、「自立する百姓等と対話する大名」を研究する方向性となっている。
そのため、これまでの武田氏にまつわる〝屈強〟なイメージを抱いている方には、ぜひ本書を一度手にとっていただきたい。〝屈強〟〝精強〟なイメージは大名個人に付けられたものであり、戦国時代全体からすれば、あまりにも一面的に過ぎない。本書のタイトルにもある「内政」を理解し、最新の研究成果を踏まえれば、大名は領民と一体化したものだったということが理解できるだろう。
「武田氏3代」からの脱却
もう1点、付言しておきたいことがある。それは、本書第1章の始まりが明応元年(1492)からということである。本書『戦国大名武田氏の戦争と内政』のように、タイトルに「武田氏」となっていると、そのほとんどにおいて信虎から物語が始まる。つまり、第1章に信虎の生涯や事績、彼による甲斐の平定と、領国外における北条・今川氏等との戦いなどが記され、このうちの1節分として、明応頃の武田氏と甲斐国内の国衆等との対立を挿入しているに過ぎないのだ。
先述のように、本書が『勝山記』を基にしているため、明応期における信虎の祖父信昌とその次男油川信恵vs.信昌長男信縄との対立を、著者は丁寧に記述している。
加えて武田氏の滅亡後、その領国支配の方法は、特に近世においても真田氏に受け継がれていた。これは、元和8年(1622)における真田氏の松代転封以後における貫高使用からも明らか(194頁)であり、勝頼の死没で終わってしまっていたこれまでの「武田氏の通史」に一石を投じている。
こうして見ると、「武田氏の通史」を紹介していた他の書物と本書の違いに気付くであろう。〝これまで130年のスパンを扱った武田氏の一般書はなかった〟ということに。
これほど長いスパンでありながらも、バランス良く紹介されているので、読者も気軽に甲斐国の戦国時代を知ることができるだろう。戦国大名武田氏を基礎から知りたい人にお薦めの一冊である。
書籍情報
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.