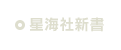星海社新書
「とるに足らないもの」たちの遠近法(レビュアー:大澤聡)

個人的なエピソードから
以前、ある論集に新左翼系総会屋雑誌に関する研究論文を寄せた。新左翼系総会屋雑誌の詳細はここでは省く。新興の言論誌が1960年代後半から70年代にかけてぽこぽこと誕生し、どれも経営主体は怪しげなのだけれどそれなりに売れていたくらいにイメージしておいてもらえればいい。サンプルとして僕が主に取りあげたのは『流動』だ。どうにも個人的に気になる雑誌で、すでに図書館や古書で全号通覧していたから執筆じたいは快調に進んだものの、途中、同誌に寄稿経験をもつ批評家にそのことを話したところ、「取るに足らないものを……」と慨嘆されてしまったので、そのエピソードごと文中に記したうえで、「取るに足らない」をキーワードに設定してまとめた。
一連の新左翼系総会屋雑誌は1970年代をとおして隆盛をきわめた。のち、1982年の商法改正で一挙壊滅にいたる(これも説明は省こう)。70年代に進行したその盛衰は、既存のヒエラルキーがことごとく解体する“80年代的”な空間を用意するプロセスそのものであったし、個別の論者なり雑誌なりの軽重と序列がこっそりとキャンセルされ、そこには渦を巻くようにして幾重ものねじれが生じてもいた。地図が塗り替えられてゆく。転形期だった。しかし、その決定的な「転形」は「取るに足らない」メディアによって担われたがゆえに、どこまでも忘却され、経緯が事後的にトレースできなくなる。現在の僕たちが直面する問題群の起点がそこにいくつも胚胎しているにもかかわらず、である。そんなかんじで立論したのだった。
じっさい、「取るに足らない」存在なのだ。それは僕も重々承知している。そのへんの遠近を見誤らない程度には当時の出版状況を擬似体験できているはずだ。しかし、そもそも世の中はどの時代でも「取るに足らない」ものたちで溢れているのだし、偶発的な条件のもとに生まれた「取るに足らない」ものたちこそが次の時代の(そう、このサイトにひっかけていえば「ジセダイ」の)下地を準備することもまた確かではある――これは僕の『批評メディア論』を支えるモチーフでもある。新左翼系総会屋雑誌はその好例だった。
とはいうものの、リアルタイムで当該雑誌を知る人にしてみれば、いまさら取りあげることじたいがやっぱり「そんなものを真剣に……」と無意味な行為に映るだろうし、拙論を読んで雑誌を知った人には「こんな雑誌が!」と、さも重大発見のように見えてしまうものらしい。両極の反応は健忘症的な僕たちのメディア構造に由来している。
ネタがベタに反転した世界で
今回、『「おたく」の精神史』に新たに追加された「序章」と「終章」のなかで大塚さんが執拗に表明している苛立ちのようなものも、きっとこのあたりと関係があるのだろう。くりかえし吐露されるのは、国内外でつむがれる「おたく/オタク」言説の素朴さや平板さに対する違和感にほかならない。1980年代に「冗談」で展開されたものごとが、時を経て「本気」で学術的考察の俎上にのってしまう。あるいは、そんな事象を「冗談」で「本気」っぽく論じてみせることに付帯する批評性がすっかり機能しなくなり、あまりにも無垢に「本気」で受け取られてしまう。そして、あれはただの「冗談」だったんだよ、と舞台裏を「本気」で自註してやらねばならない。それはやっぱり悪夢のような事態だ。
本書の元版が刊行された2000年代前半に流通した用語に翻訳するなら、「ネタ」が「ベタ」へと転倒したということになる。その転倒は、時間の偏差(=若い読者)と空間の偏差(=海外の読者)がもたらしたものである。こうして、倒錯や陰影を欠いた、僕の用語でいえば「のっぺりした世界」がずるずるずるずるとひろがってゆく。
「冗談」として(ただし、いくらかは「本気」で)遂行された80年代の事象たちを、大塚さんはこの新版の「序章」や「あとがき」のなかで、くしくもあの批評家と同じように、「とるに足らないもの」と表現している。「この程度のこと」「……に過ぎない」「くだらない事象」、とも。当時自身の手で編集していたロリコンまんが誌が後続の人間や海外の人間に再発見され、さも学術的に歴史的に重要な題材であるかのごとく特権視されてしまう、まさに「冗談」のような光景が現実にひろがる――たとえばそれは、その後のオタク文化の世界的浸透や大塚さん自身の数々の仕事から逆照射されるかたちで。評論や研究の世界に限らない。じっさい、ネットのいたる場面にその手の発言や文章を見出すことは容易い(それと同じくらいにトリビアルな批判も見つけ出せるだろう)。そんな転倒した言葉の数々は当時のリアリティをどこまでも掬いそこねてしまう。それは、おたく/オタク文化圏の内部に遡行の範囲を限定した結果でもある。
この本の位置づけ方について
さて、本書はサブタイトルにもあるとおり、1980年代論である。極私的なポジションから観測しえた80年代のひとつの光景がスケッチされる。だから、元版の刊行以来、まかりまちがってもこれを「正史」として扱うことなどないよう著者は注意を促してきた。が、それとはうらはらに、各々が脳内に措定する究極的な「正史」との差分として、叙述の偏りや特定の固有名の欠落などがしばしば指摘されもしてきた。2000年代半ばには、“80年代リバイバルブーム”の渦中で、いくつもの1980年代論が集中的に発表されることになるが、その少なからぬ部分は本書のカウンターとして提出されている。ここに逐一タイトルをあげることはしないけど、もしも新しい読者であるあなたが本書の偏りをどこか感じるのなら、それらとつなぎあわせつつ相対化してみるといい。でも、けっきょくのところ、本書の飛びぬけた面白さを理解するだけかもしれない。
その面白さのひとつは、極私的な地平から出発したはずがいつのまにか80年代の日本社会全体の論理をまるごとカバーしている、遠近の照準スイッチングの自在さにある。私的な体験の集積――それは「オタク」ではなく「おたく」と表記する方針としても表われる――であるがゆえに、結果的に本書は「大塚英志」という固有名が確立していくプロセスのドキュメントにもなっている。その過程で貴重な証言(というと、また本書の本意から逸れるのだろうけれど)がいくつも書き留められる。なかでも、「M君は自分だ」といって宮崎勤事件にコミットするにいたった経緯が回顧される「21章 あの日のこと」は個人史的にひとつのピークをなす。だからこそ、12年前の春休みに延々と続く鈍行列車の旅の途上、駅前の書店で購入したこの分厚い新書の元版をゆっくり時間をかけて読んだときには、僕は大塚さん自身が評論家として本格的に活躍しはじめる90年代との連続性のなかで各章を理解していったのだった。けれど、今回読みなおしてみてその印象はずいぶんと変わった。1970年代との連続性において「も」読まれなければならなかったのだ。
捉え方が変化したのは、今回新たに付された「序章」で80年代のおたく文化の台頭が全共闘世代のいわば「見えない文化大革命」の帰結だと見立てられ、左翼運動の文脈に位置づけなおす必要が強調されているためばかりではないだろう。むしろ、70年代との連続性はすでに随所に書き込まれてあった。それにようやく僕の目がむかったのは、端的にこちらの関心の変化の結果なのかもしれないし(新左翼系総会屋雑誌への関心もその一環だ)、いま現在の時代環境の問題かもしれない。1960年代論と1980年代論のふたつのボリュームの狭間で、1970年代だけがすっぽりと手つかずのまま放置されてある。“凪の時代”の必然として。
歴史性の回復にむけて
遅れてやって来た者たちや遠く離れた者たちに必要なのは(というか可能なのは)、たとえ「冗談」を「本気」に取りちがえていると呆れられようと、それらが「とるに足らないもの」だとわかる程度には前後左右の文脈をきっちり詰めてゆくような作業なのだろう。疑似体験と呼べる水準に達するためにはずいぶんと骨を折らないといけない。本書はその点でじつに有益だ。
海外の研究者たちに宛てたエッセイや講義が元となった「序章」では、彼ら彼女らにむけて、おたく/オタクの検証を行なう場合でも「歴史的政治史的文脈が重要であるというひどく当たり前のこと」が強調される。やりたい人間が個々勝手にその「当たり前のこと」を勉強して押さえればいいだけなのだけれど、同時に、ずたずたに切断された個別の光景をどこかで突きあわせてゆく作業も必要なんじゃないだろうかとも思う。そのときの対話に求められるのは、たがいにとってのよい聞き手ではないはずだ。先行/後発の関係性を消失させたかのように無邪気にふるまう偽善的な構えでも、もちろんない。
書籍情報
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.