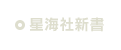星海社新書
「二階」から見える風景(レビュアー:渡邉大輔)

「80年代」との距離感覚
ぼくは、これまでにスタジオジブリをめぐる文章を二度、書いたことがある。
2年前、最初に書いたひとつは、ある文芸誌に寄せたごく短いエッセイだった。それは、ジブリをめぐってぼくのなかに長らく存在していた、ある「語りにくさ」の正体をめぐるものだった。ぼくは20代のはじめに批評を書きはじめてから、これまでほとんどジブリについて言及したことがない。当該のエッセイではその理由を、「1980年代」という自分たちの世代的な体験に求めてみた。
1982年生まれのぼくの幼少年期は、まったく誇張でなく、無数のジブリアニメとともにあったといってよい。たとえば、ぼくの生まれた年に宮崎は、雑誌『アニメージュ』に、まんが「風の谷のナウシカ」の連載を開始し、ジブリの設立はその3年後のことである。いわばぼくの世代は、80年代のジブリアニメを劇場のスクリーンや家庭用VHSで数えきれないほど観て育った「ジブリ世代」といえるだろう。ぼくの長らく感じていたジブリについて書こうとするときの、奇妙に上滑る距離感覚の計りがたさは、こうしたジブリをめぐる世代的体験がぼくたちの世代に——それこそ80年代の消費社会で生まれた無数のコンビニ商品と並んで——一種の「集合的無意識」として横たわっているからではないか……そんなことを記したのだった。
「二階」からはじまる物語
何にせよ、ジブリが発行する小冊子での連載をまとめた本書『二階の住人とその時代——転形期のサブカルチャー私史』は、姉妹編といえる『「おたく」の精神史——一九八〇年代論』とともに、そんな20代のぼくにとって、ずっと遠くも近くもあった「80年代」という時代のサブカルチャー史的な記憶を、著者ならではの融通無碍なパースペクティヴのもと、2010年代の現在にこのうえなく鮮やかに甦らせている。と同時に、本書をひもときながらぼくは、ジブリとともに、自らの足場を支え続けた80年代をようやく対象化できるようになった、30代なかばの自分も感じていた。
もとより本書の物語の舞台となり、題名に冠された「二階」とは、1970年代から日本初の本格的なアニメ総合誌『アニメージュ』などを発行し、20代はじめの著者が1980年からアルバイト編集者として出入りしていた徳間書店の二階にあった第二編集局を指す。本書では70年代末の『宇宙戦艦ヤマト』『機動戦士ガンダム』の第2次テレビアニメブームから『アニメージュ』創刊を経て、80年代なかばのジブリ前史にいたるまで、ここから今日までつうじる「おたく」文化/産業を手探りで立ちあげていった著者自身を含む無名の若者たちの青春群像の顛末がじつにいきいきと活写されている。
本書は基本的にはまんがからアニメ、特撮、フィギュア、さらに芸能誌にまでいたる、80年代サブカルチャー史であり、また出版史なのだが、やはりジブリを軸とした日本アニメ史の観点からも多くの示唆に富んでいる(まんが『ナウシカ』の第1回原稿のスクリーントーンを鈴木敏夫に頼まれた著者が貼っていたなんて、現在いったい何人が知っていただろうか?)。また、著者の仕事のなかではこれまで相対的に多く言及されてきた角川書店ではなく、ほぼはじめて本格的に徳間書店の事業にスポットをあてたという点でも貴重な証言だろう。
おたくとシネフィルの80年代
ともあれ、(著者と同様に?)さまざまな偶然が重なっていつの間にかいまや映像文化の研究者や批評家になっているぼくの眼から、80年代を論じた本書でことのほか興味深かったのは、ここで著者が自身の私的な体験に基づいて記すおたく文化の形成プロセスが、同時期の日本における「シネフィル文化」のそれとみごとに相似形を描いているように見えることだろう。
たとえば本書では、当時の著者と同じ「二階」にかかわった「おたく第一世代」の若手編集者やアニメファンたちが、こぞって貴重なアニメ映画の上映会の企画やアニメ番組の詳細なリスト作成、あるいはアニメ雑誌に掲載する作品スチール写真のレイアウトや編集作業の試行錯誤をつうじて、しだいに膨大なアニメ作品の匿名的な断片や細部から固有の「作家性」を見いだしてゆく歴史的経緯がじつにスリリングにたどられる(第1、9、11章)。宮崎駿も金田伊功も、そのようにして「発見」された。また、その「作家の発見」は同時にかれらに、それまでにはないアニメの新たな批評言語の模索も強いることになる(第20章)。
これらの一連の経緯は、やはりおもに80年代に日本の映画文化に起こった構造的な変化と明らかに一致している。実際、著者自身が第1章で蓮實重彦の「表層批評」を例に挙げることでその重なりを示しているように、当時は映画の分野でもまた、都市部のミニシアターブームや家庭用ビデオの普及などによって、それまで観られなかった膨大な過去の古典に容易かつ繰りかえしアクセスできるようになり、蓮實らの強い影響を受けた「シネフィル」と呼ばれる教養主義的な映画マニアが若い世代に急増したのだった。そして、かれらもまた知られるように、蓮實が85年に創刊した映画批評誌『リュミエール』などをとおして新たな映画批評言語をインストールしつつ、その「作家主義的」な批評に倣って、リチャード・フライシャーから鈴木則文にいたるまで、匿名的なプログラム・ピクチャーのなかから固有の「作家名」を見つけだしていったのである。
本書で明かされる創刊時の『アニメージュ』が『キネマ旬報』や『ロードショー』といった映画雑誌の編集方針をモデルとしていたという逸話も興味深いが(第16章)、いずれにしろ、いずれも表層的な記号とイメージの戯れにまどろんでいた80年代の申し子といえるおたくとシネフィルがその文化的感性においてはるかに通底していた状況——そして、現在のオタク第4世代やヤングシネフィルたちと前者とのへだたり——も、本書では図らずも鮮明になるだろう。本書がいっけんして著者の私的な体験からの叙述に支えられながら、同時にまぎれもない普遍性も帯びているのはこうした側面からもはっきりと窺い知れる。
歴史の窪地としての「二階」
さて最後に、ようやくぼく自身が適度な距離で清算できるようになったジブリの話題でこの書評を締めくくることとしよう。
大澤聡氏も『「おたく」の精神史』の書評で触れていたことだが、近年の著者の仕事では戦後のおたく文化と左翼運動史とのかかわりがしばしば強調されてきた。それはたとえば、『映画式まんが家入門』や『ミッキーの書式』などで検討される、戦前の「アメリカニズムとロシア・アヴァンギャルドの野合から生まれた戦後まんが」という有名な仮説にまで発展させられるだろう。
実際、本書でも強調される論点のひとつは、のちにジブリを率いる鈴木敏夫をはじめ、「二階の住人」たちの多くに共通する新左翼運動経験や、徳間書店の芸能誌『アサヒ芸能』に村山知義が構成主義的なグラビアをレイアウトしたといった同様の左翼運動史をめぐる記述である(第2章)。たしかに著者のいうとおり、戦後のおたく文化の成立には、「徳間康快が関わった真善美社のような戦時下・戦後へとリンクするアヴァンギャルド芸術の系譜」と「六〇年代安保と全共闘運動の一つの政治の季節を過ごした人々の存在」(89ページ)が欠かせないのかもしれない。
ところで、ぼくが昨年、とある論文集に寄稿した2度目のジブリをめぐる文章となった、少し長めの論文では、まさに著者の主張とも関係するような、ジブリをめぐる左翼運動史とのかかわりを主題としていたのだった。とはいえ、宮崎や高畑の左翼思想や組合運動の経歴についてはよく知られているだろう。その論考では、かれらのそうした経歴の背景となった、「左翼映画人のアジール」としての東映/東映動画の成立を、戦中期の満州を経由した日本映画界の左翼運動史や教育映画運動史から説き起こしてみた。
すなわち、徳間の「二階」とは、こうしたまんがから日本映画、アニメにいたるさまざまなジャンルの戦前・戦後にいたる歴史が相互流入する窪みのような場所だったのではないか。そして、その「二階」に著者が住みつきはじめた80年代に生まれたぼくは、いまやその世代的記憶の象徴であるジブリと、ようやく折り合いをつけることができてきたように思う。そして、これこそが著者が描く「歴史」ということなのかもしれない。
この「二階」という名の歴史の陥没地帯で見える風景から、ぼくたちの現在はたしかな遠近感をえられるだろう。
書籍情報
Copyright © Star Seas Company All Rights Reserved.