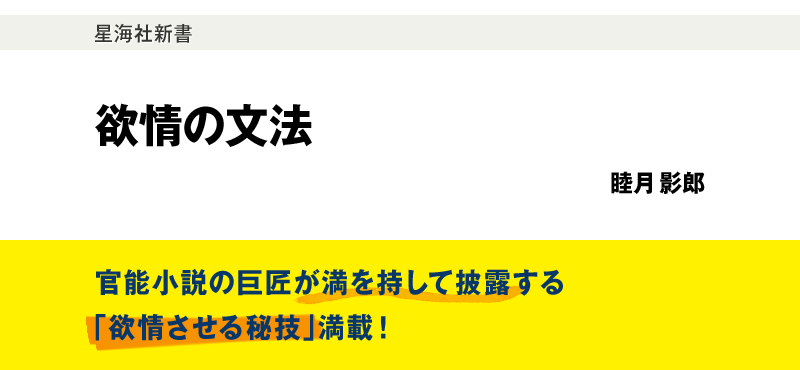
欲情の文法
睦月影郎
官能小説の巨匠が満を持して披露する「欲情させる秘技」満載!——文章だけで人を欲情させ、興奮させるエンターテイメント。それが官能小説である。ただのエロ小説だと思ってもらっては困る。あの文章の中にはあらゆる人の感情を操るノウハウが詰まっているのだ。本書では400点以上の作品を生み出してきた官能小説界の巨匠がそのノウハウと哲学を一挙公開する。「主人公が18歳童貞である理由」(44ページ)「話の順序を変えるだけで興奮度は増す」(130ページ)「男は与えられたい生き物・女は与えたい生き物」(180ページ)「キリの良い所で仕事を終えない」(219ページ)など気になる話題が満載。『欲情の文法』は、「ナマの人間」が見えにくい現代において必要な「武器としての教養」だ!
目次
はじめに官能小説から見える人間の欲と心理 3
- 官能作家は儲からないし尊敬されない稼業3
- 官能小説には「ナマの人間」が描かれている4
- 400点以上の官能作品を書き続けて見えてきたもの6
- 世界は感情や心理で動いている8
第一章 文章だけで興奮させる魅惑のエンターテインメント 17
- 欲情エンターテインメント「ポルノ」から「官能」へ18
- 官能小説は「手段」である19
- 『ネルフの女』と『おもひでぬるぬる』20
- 私が「時代物」を好きな理由21
- 妖怪だといろいろなセックスができる24
- ファンタジーとリアルの間26
- 「避妊具」「生理」「痛がる処女」は出てこない29
- 理想の展開は男と女で違う31
- あくまでメインは濡れ場である33
- 官能作家は、夢を売る商売だ35
- 活字だからこそ妄想が膨らむ37
- 楽しみ方が限定されていないから面白い41
第二章 興奮させる鍵はキャラ設定にあり 43
- 主人公が18歳で童貞の理由44
- 辛かった童貞喪失体験45
- 読者には素晴らしい童貞喪失体験を47
- 最初の女性は、甘えられる年上49
- バカボンのママに手ほどきを受けたい男たち51
- あらゆる年齢の読者に対応するために53
- ヒロインの人物設定における意外性54
- 「タレントの誰々に似ている」はご法度55
- 距離感と背徳感が欲情を生む56
- 女性崇拝の気持ちを忘れてはいけない58
- 「身分」「立場」が人を興奮させる62
- 文化系のほうが変態になりやすい64
- ギャップがある関係は官能的67
- のび太のような主人公の復讐70
- ダメ男には共感しやすい73
- 渇望の青春時代74
- とにかくオナニーがしたかった76
- やはり密室でのセックスがベスト77
- 畳の上では背中が痛い80
- 読者との距離があり過ぎてはいけない81
- 舞台に特徴はいらない83
第三章 ストーリー展開は予定調和の成長物語 85
- 定番は「教わる」☞「教える」☞「3P」86
- 予定調和がウケる87
- テーマにユニークさを入れる88
- 読者の心をつかむタイトル91
- 感情を動かすコピーとは95
- 制約を設けるとスピードが早くなる96
- 書き出しを会話か心情にすると引きつけられる101
- 主人公の説明で共感を呼ぶ104
- 童貞ならではの描写がある109
- 初体験での感動を細かく描写する112
- いざ挿入へ115
- 第一章の大テーマは、生身の女性の素晴らしさ117
- 各章ごとに三種類の年代の女性が登場する120
- いつどんな女性と何をさせるか121
- ストーリーは凝りすぎない123
- 死人はほとんど出ない126
- 作品の締めくくりは、快楽の無限ループ128
- 話の順序を変えるだけで興奮度は一変する130
- 5分で終わることを30分に広げて書く技術133
第四章 人を悦ばせる言葉と表現 137
- 官能小説では、医学的な言葉が多い138
- 分かりやすい言葉や比喩が万人ウケする139
- 時代物特有の言葉と表現142
- 自己満足な表現、マニアックな表現には要注意147
- 五感をフルに刺激する描写149
- 「真っ暗闇」は出てこない151
- 女性の匂いは五種類の組み合わせでできている152
- 会話やつぶやきを効果的に使う156
- 「……」を利用して、ためらいや戸惑いを演出する158
- 喘ぎ声のバリエーションの工夫161
- エロのスイッチが入る瞬間を描写する163
- 恥ずかしいことを書いてなんぼの世界165
第五章 男と女の性とフェティシズム 169
- 性的な悦びがなければフェチではない170
- フェチとは、変態ではなく少数派である173
- 一人でやると変態。みんなでやれば青春174
- 使用済みのコンドームを舐められるか175
- フェチは男性にしかない177
- 男女の友情は成り立つか178
- 男は与えられる生き物、女は与える生き物180
- 日本はもともと女尊男卑だった182
- 男女の違いは、遺伝子の違い183
- なぜ、男は浮気をするのか185
- 軽々しく「愛」を使うな186
- 男と女の性的な違い187
- 女性がオルガスムスを得るには長い時間が必要189
- 江戸時代はフェチの宝庫190
- フェチ描写を巡る知られざる格闘193
- 作家によって、こだわりが違う196
- すぐ脱ぐから服装は関係ない197
第六章 官能小説を400冊書き続けた私の方法 201
- 官能作家には自惚れが強い人が向いている202
- 好きでやっていたことが仕事になった204
- 人生がいい方向に転がるための心持ち207
- 締め切りは絶対に守る210
- 日中に仕事をして、夜は極力仕事をしない213
- 最後まで書き続けるコツ215
- 資料は読み過ぎない。ネットも見ない216
- 「しなくてもいい理由」を考えない217
- 書く力を鍛える練習法218
- モチベーションを持続させる方法219
- 書きながら抜くことはあるか221
- 人の数だけアイデアはある222
- ストーリーづくりに必要な三つの力224
- 妄想力を鍛える訓練226
- エロビデオは押し付けがましくてダメ227
- 夏目・川端・三島は必須229
おわりにあえて言おう、リアルの恋愛をせよ 233
- 草食系男子にこそ官能小説を読んでほしい233
第二章 興奮させる鍵はキャラ設定にあり
主人公が18歳で童貞の理由
小説で最も重要なのは、人物設定である。
それは、官能小説だけでなく、あらゆる小説で言えることだろう。ただ、官能小説特有の設定がある。私が描く官能小説の世界での人物設定のコツみたいなものを本章では紹介していきたい。それはすなわち、より興奮度が増す設定ということでもある。人物設定は、読者をより興奮させる最大要素だからだ。
私が描く主人公(男)は、常に18歳である。
なぜかと言うと、童貞喪失を描きたいからだ。何もかも知っている大人を主人公にしてもつまらないし、私自身、あまり乗り気がしない。
女性という生身の喜びを知らないけれど、人一倍女性に興味と憧れがある時期。そういう無垢な少年が、女性の体を知り、大人に成長する姿を描きたいのだ。
私が童貞喪失に重きを置いているのは、自分が幸せな童貞喪失をできなかったという過去のトラウマがあるからでもある。
辛かった童貞喪失体験
私が童貞を喪失したのは、19歳のとき。親友と一緒に行った横須賀のトルコ風呂(現在のソープランド)が初体験だった。どう見ても、自分の母親よりも年上の女性が初めての相手だった。
その初体験は、非常に辛いものだった。長年憧れていたセックスと、実際のセックスが全く別物だったからである。妄想とはものすごく違ったのだ。
本当は、挿入よりも、もっといろいろなことがしたかった。ディープキスやクンニリングといったことをしたかった。女性のナマの匂いを嗅ぎ、ムレムレに汗ばんだ股間に顔を埋めて舐め回したい。それができるならば、挿入などしなくても良かった。
ところが、初体験では、ただ義務的に挿入するだけで終わり。キスすらすることができなかった。期待していたフェラチオも、コンドームを被せるだけの簡単なものだった。一番肝心のところを除いて、いきなりラストに持っていかれたかのような初体験だった。
風俗だから、そういうものだということは分かっている。でも、自分が憧れているセックスと現実のセックスとのギャップに、正直がっかりした。快感の大きさで言えば、オナニーの十分の一くらいだったのだ。
ただ、女性器を見られたことには、とても感動した。「あぁ、女性の秘部は、こうなっていたんだ」と。
今の時代であれば、裏本や裏ビデオもあるし、インターネットで検索すれば、女性器を見ることは簡単だろう。しかし、私たちの時代では、そう簡単に見られるものではなかった。保健体育の教科書に載っているような図解でしか知らなかったわけで、全く未知なる世界だったのだ。
だから、女性に幻滅したということはない。セックスが嫌いになったというわけでもない。半分は幻滅したけれど、エロへの渇望はますます増していったのである。
女性の秘部を実際に見ることができ、「じゃ、好きな女の子のあそこも、ああなっているのだろうか」と、妄想はさらに広がったのだ。
つまり、一を知ったことで、妄想は倍加していったわけである。ゼロはいつになってもゼロでしかないけれど、一でも知れば、それは十にも百にも膨らませることができる。他の人にあてはめることができるのだ。
読者には素晴らしい童貞喪失体験を
このような初体験のトラウマを抱えているからこそ、物語の中では、素晴らしい童貞喪失を主人公にさせてあげたい。叶わなかった素晴らしい初体験を主人公にさせることで、私自身も追体験しているような気分を味わいたいのだ。
おそらく、多くの読者も同じではないだろうか。
自分が思い描くような理想的な童貞喪失を経験できた人は、少ないように思う。官能小説は、読者の夢を叶える場所でもある。読者も物語の主人公に理想を重ね合わせ、「自分の初体験がこんなふうだったら良かったのに」「こんな童貞喪失をしたかった」と、楽しんでもらえているのだと思う。
そのような理由で、主人公は必ず高校を卒業して間もない18歳の童貞。しかも、なるべく早生まれで、山羊座か魚座を主人公に設定することが多い。それも私が1月生まれの山羊座だからであるが、私の経験上、山羊座や魚座の人の方がフェチといった変態になりやすいように思う。
今の時代、18歳で童貞という設定は非現実的と思われるかもしれない。昔は15歳や16歳の主人公を書いていたけれど、今は規制が厳しくなってしまったので、仕方なくではあるけれど、未成年の18歳が童貞のギリギリのラインだろう。
さらに、主人公は一人っ子の場合が多い。姉がいたり、妹がいると、普段の生活で女性に接しているので、主人公の無垢な感じが削がれてしまうからである。男兄弟がいてもいいのだが、そこは正直に言って、面倒だからあくまでも一人っ子。男の登場は、あくまでも最小限ということだ。
毎回、童貞の主人公を書くということは、毎回新鮮な気持ちで物語に入り込める。そのためにも、毎回童貞に戻って、その度に新たな初体験をするつもりで書いている。
50歳を過ぎても毎日童貞に戻っている。慣れてはいけないということである。童貞の頃の気持ちや性に対する渇望を忘れないようにしなければ、読者の共感が得られないだろうし、私自身面白くないのだ。
新鮮な気持ちで、感謝と感激を持っていなければ、童貞喪失を描けないということである。だから、私は毎朝童貞に戻るのだ。
最初の女性は、甘えられる年上
一冊の中で登場する女性は、4〜5人といったところだろう。その中の一人がヒロインになる。
最初に主人公の相手をするのは、セックスについて何も知らない女性ではなく、手ほどきをしてくれる年上の女性だ。その女性がヒロインになることもあるし、サブヒロインの筆頭になることもある。それは、作品によって、設定が異なる。
最初の相手が年上というのも、私の憧れである。「こんな人に教わりたかった」という憧れの初体験を、物語で何度も何度も繰り返し体験しているのだ。
例えば、女教師だったり、女医や看護師だったり、あるいは親戚の叔母さんだったりする。そういった熟女、人妻、あるいは「母乳系」の年上が、主人公の最初の相手になる。
私が書いていて一番楽しいのは、手ほどきを受けるシーンに他ならない。自分がしたかったことを全て入れられるのだから楽しくないわけがない。本当は、それだけで一冊書きたいくらいだ。
知りたいことを全部教えてくれる女神のようなヒロイン(もしくはサブヒロイン)がいる。しかも、主人公の欲求を何でも聞いてくれる。そして、実際に欲求を叶えてくれる。無垢な主人公に何でも教えてくれる女神に憧れているのだ。
簡単に言ってしまえば、「私は女性に甘えたい」ということなのだろう。
50歳になったとき、毎日童貞に戻ることと、もうひとつ決意したことがある。
それは、「年下の女性でもお姉さんだと思おう」ということだ。
50歳を過ぎると、徐々に年上の範囲が狭まってくる。甘えられる女性が少なくなるからである。「たとえ年下の女性でも、お姉さんとして甘えてしまおう」と誓ったのだ。
バカボンのママに手ほどきを受けたい男たち
前にトークショーをしたとき、オタクで童貞の三十代が大勢来てくれた。彼らに質問してみると、みな「年上に手ほどきを受けたい」と言う。
「じゃ、誰に手ほどきを受けたいのか?」と聞いてみると、見事に意見が真っ二つに分かれた。
ひとつの派は、『ルパン三世』の峰不二子。これは、定番である。少年が最初に出会うグラマーな悪女だからだ。
そして、もうひとつの派は、なんと『天才バカボン』のバカボンのママだったのである。バカボンのママは、バカボンと一ちゃんの二人の子どもを産んでいるから、少なくとも二回は中出しされたことになる。
あの何かあったらすぐに飛んで行ってしまうようなバカボンのパパが、最低二回は中出しをした。ということは、バカボンのママはリードが上手な女性だろうと、オタクの童貞たちは思ったのだろう。
つまり、そういう女性に教わりたい。自分をリードしてくれる女性に、童貞を捧げたい。そういう思いは、多くの男性にあるということだ。
奇しくも、両方とも同じ声優さん(増山江威子さん)であるところが、また面白い。増山さんの声には、何かしらの色気があるのだろう。
私も、やはり受身の方が好きだ。心の中では主導権はこちらが握っているわけだけれど、形としては受身の方が好きなのだ。強引にするのではなく、向こうから積極的にしてもらう。控え目な子に、積極的になるように差し向ける。
私の小説では、よく顔面騎乗が出てくる。男が仰向けになって、「ちょっと顔に跨ってみてください」と言って、「そんなことはできない」と恥ずかしがるヒロインに、顔面騎乗をさせる。それを、「いいよ」と言って、すぐにしてしまうような女性は、最初から出てこない。
顔面騎乗という行為自体よりも、要求する男の興奮と、それに従ってしまう女性の恥じらい、ためらい、戸惑いを見たくて書くわけである。行為に至るまでの内面を見たい。それは、おそらく読者も同じ思いなのではないだろうか。
あらゆる年齢の読者に対応するために
女性の年齢は、様々である。年齢規制があるので、下は18歳。上は40歳前後。熟女と言っても、やはり50歳くらいの女性を登場させるわけにはいかない。実際は、五十代でも美しい女性はたくさんいらっしゃるけれど、それは読者の共感を生みにくいので、やはり上限は40歳前後ということになってしまう。
例えば、ヒロインを同級生の18歳で処女と設定した場合を考えてみよう。主人公の最初の相手は、二十代の女性。何でも教えてくれる存在だ。
さらに、中盤ではヒロインのお母さんが登場する。ヒロインである娘を産んだのが18歳のときだったとすると、37歳くらいに設定しても辻褄が合う。
このように、なるべく女性の登場人物の年齢には幅を持たせるようにしている。十代、二十代、そして40歳前後。他の登場人物も、そのどれかに属する。
このような設定にするのは、読者の好みを限定しないためでもある。少女が好きな人もいれば、熟女が好きな人もいる。もちろん、両方とも好きな人もいる。私は少女から熟女まで、女性であればみな大好きだから、一冊の本で女性のフルコースを楽しむことができるというわけだ。
ヒロインの人物設定における意外性
ヒロインの年齢と職業を決めるとき、その二つは意外性のある組み合わせの方がいい。昔から定番なのは、「年下の義母」という設定だろう。他には、同じ叔母にしても、女教師の叔母、女医の叔母という設定も面白い。
意外性は二つまでにする。三つ以上になると、ごちゃごちゃになってしまう。また、贅沢になればリアリティが薄れてしまうからである。
そして、重要なことは、外見のイメージを明確に書き過ぎないことである。巨乳か着瘦せするタイプかといった体型、ロングかセミロング、ショートカットといった髪型くらいの描写はする(私はショートカットが好きではないので、実際はあまり出てこない)。
ただ、あまりに外見のイメージを明確にすると、読者の想像を妨げることになるため、あまり書き過ぎない方がいい。
リアルに盲腸の跡があったとか、帝王切開の跡があったということも、絶対に書かない。時代物では、刀傷があったというのは出てくるけれど、それほど特徴的なことは書かないようにしている。
「タレントの誰々に似ている」はご法度
書いている側の私は、好きな女優さんをリアルにイメージして書く。安達祐実をイメージしたり、安めぐみをイメージしたりする。その時期の好みの女性をイメージして書くわけであるが、文字で安達祐実に似ていると書くのは、一番簡単な方法ではあるけれど、ご法度である。
あくまでも、読者には自分が好きな人、好みのタイプを想像してもらう方がいい。これは、文字だからこそできること。エロ本やAVではできないことだ。
おそらく、読者はこれまでに好きになった女性(アイドルや女優も含む)を思い描いて読んでいることだろう。同じヒロインを描くにしても、百人の読者がいれば、百人のヒロインがいるというわけだ。
だから、あんまり細かに顔の造作も描写しない。眉が濃いとか、まつ毛が長いとか、瓜実顔(瓜の種に似た面長な美人顔)といった特徴は多少なりとも書くけれど、タレントの誰々に似ているというというのは、絶対に書かない。
また、時代が変わってしまうので、特定のタレントの名前を出すと、古くなってしまう。作品が5年、10年残ったときのことも考えれば、タレントの名前は出さない方がいいのは、容易に理解してもらえるだろう。
距離感と背徳感が欲情を生む
極論で言えば、女性は二種類しかない。
セックスを「させてくれる女性」と「させてくれない女性」である。
官能小説で登場するヒロイン(サブヒロインも含む)は、一見、させてくれない女性の方だ。させてくれなそうな女性も、結局はさせてくれるのであるが、すぐにさせてくれそうな女性を描いてもつまらない。俗に言うアバズレ女とセックスをしても、そこに官能は存在しないのである。
させてくれなそうな女性が、させてくれるからこそ、官能の話になるのだ。
そういう意味では、恋人同士や夫婦のセックスは出てこない。セックスをするのが当然の話は面白くない。どちらかと言えば、してはいけない人とのセックスの話を書くのである。
一緒に暮らしていると、どうしても性欲がなくなってしまう。愛着は湧くけれども、それは肉親への愛着であって、性欲には結び付かない。距離が近過ぎる関係というのも、官能的ではないのだ。
だから、どうしても定番になってしまうが、人妻だとか無垢な少女が登場してくる。禁断のセックスといった「背徳感」が常に漂っていないといけないわけだ。
ただ、夫婦の濡れ場を全く書かないというわけでもない。例えば、叔母さんと叔父さんのセックスを覗いている第三者の目で書く場合は、夫婦の濡れ場もありだろう。そこに「背徳感」が存在するからである。
大切なのは、お互いの距離感。夫婦になると、肉親になってしまうから、面白くないし、そそられない。私が未だに独身なのも、夫婦になってしまったら、つまらないと思っているからでもある。
恋人同士というのは、肉親ではないけれど、どうしても肉親的な要素が大きくなってしまう。そこには、背徳感がないため、官能的な描写を描きにくいわけだ。
女性崇拝の気持ちを忘れてはいけない
私には女性の好みはない。全ての女性が好きだし、全ての女性には美しいところが必ず存在する。
だからと言って、セックスをすれば誰でも同じという意味ではない。みな、それぞれに良いところがあるということだ。
その根底になるのは、女性崇拝の気持ち。全ての女性は女神だと思っている。
「男を選ぶとき、働かない男、借金をする男、賭け事をする男、暴力を振るう男、この四つに当てはまる男だけは選んではいけない」と、女性には常に言っている。
例えば、街を歩いていても、女性に車道側を歩かせていたり、レストランで奥に自分が座っている男を見ると、「あいつは何をやってるんだろう」と思ってしまう。
「いきなり車が突っ込んできたら、いきなり暴漢に襲われたら、どうやって助けるんだろう」と思う。
常に女性を安全な方に持っていかないとダメ。それを無意識にできるようにならなければいけない。そういう女性崇拝の気持ちが根底にあるから、私の小説にはそういう男は出てこない。
昔は、編集者の注文でやむを得ず書いたことがあるけれど、今ではSM物やレイプ物は一切書いていない。
稀に監禁物を書くことはある。思いが高じて彼女を誘拐し、山小屋に監禁して、弄ぶのだけど、たいてい男が謝って、結局はお願いしてさせてもらうという展開になる。言葉遣いも丁寧に、「ちょっと脱がさせてもらいます」「こんなことしてもいいでしょうか?」と言うわけだ。
愛される可能性はないと分かっているけれど、主人公は強引にはできない。なぜか、監禁された女性は主人公を好きになってしまうというとんでもない展開になってしまうわけだが、そうなるのも女性崇拝の精神があるから、僅かにリアリティを残しているのである。
力づくで女性を自分のものにしたいというのは、男の本能ではあるけれど、それなら動物と同じ。動物的な本能を超えたフェチやロマンといったものを描きたい。それこそが、官能の世界であり、性の文化であると思う。
私の小説に登場する主人公は、最初は童貞だが、徐々に経験を積むようになる。何人もの女性を満足させるような手練にもなる。
しかし、決して女性崇拝の気持ちを忘れさせないようにしている。モテるようになっていくうちに、図々しくなり、横柄になっていくのが嫌いなのだ。
例えば、女性に命令をしたり、快楽のための道具のように扱ったりすることはない。どんなわがままな女性でも、主人公は優しく受け入れる。決して女性に怒ることはない。
女性崇拝の気持ちがあるから、女性に対して汚い言葉は使わない。「臭い」だとか「悪臭がする」ということは、絶対に書かない。
そもそも、美女から出るものに、何ひとつ汚いものはない。たとえゲロであっても、美女から出るゲロは「美ゲロ」なのだ。
そして、全ての女性は、美女だと私は思っている。
私の小説には、美少女や美女、美熟女といった女性しか出てこない。そんなに美女は多くないだろうと思うかもしれない。ファンタジーだから許されるということもあるけれど、私からしたら全ての女性が美女なのだから、本当のことでもある。私にとって、そこはリアルなのだ。
小説の中で登場する女性であっても、実際にお会いする女性であっても、この女性崇拝の気持ちだけは、忘れないように心がけている。
「身分」「立場」が人を興奮させる
時代物の人物設定にも少し触れておこう。
現代と江戸時代の大きな違いと言えば、やはり身分制度だろう。身分にギャップがあればあるほど、興奮度が高まる。禁断の恋、背徳感が、より強くなるからである。
例えば、殿様が身分の低い町人の娘の足を舐めたりしたら、それこそ藩が潰れてしまうかもしれないくらい重大なことである。背負っているものが、現代とは比較にならないほど大きいのだ。
現代の社長さん(それがたとえ大企業の社長であっても)が一般の女性の足を舐めても、「そういう変わった趣味の人なんだな」で済まされてしまう。でも、江戸時代はそれだけでは済まされない。実際にはありえない行為なのだ。
そのありえない行為を、あえてする喜び、上下の格差が大きいほど、下降する喜びがある。身分というギャップを乗り越える喜びがあり、だからこそ興奮度は高まる。
山から下りてきたばかりの山猿みたいな男が姫様を犯すというのは、やはりありえないこと。だけど、身分という高み、距離があるほど、攻略する喜びというのも大きい。
「姫様のあそこはどうなっているのだろうか」「姫様も厠に行くのだろうか」「姫様のお尻は、どんな匂いがするのだろうか」といったことを、山猿は知りたいのだ。
姫様に対する憧れがあり、幻想がある。そして、それを暴いた喜びが待っている。最終的には、人間はみな同じなのだけど、やはり同じであって同じではないのだ。
ただ、江戸時代も現在も、思春期の性欲というのは同じだと思う。女体への憧れは、当時も今も同じはず。
と言うのも、私が中学生のころは、春画で抜いていたこともあるからだ。エロ本を買うことができなかったため、カッパ・ブックスの浮世絵の本とかを買っていた。普通の本であれば、買ってもらえたわけである。家が狭かったので、エロ本を置いておくとすぐに見つかるという危険があったのも理由のひとつだ。
そういう本には、春画がいっぱい載っていたので、有難くオカズにさせてもらった。時空を超えて、江戸時代と同じもので抜いていたわけである。
だから、江戸時代であろうとも、現在であろうとも、男の渇望と性欲は基本的に同じだと自信を持って書いている。
文化系のほうが変態になりやすい
現代物の主人公は、「シャイで消極的な性格だけど性欲旺盛」という設定だが、時代物になると、さらに「剣術の弱い人」という設定が追加される。
なぜなら、剣術が強い人は、過酷な修行を経ているはずだから、それほど変態になりにくい。今で言うところの体育会系なのである。体育会系というのは、自分を抑える訓練を積んでいるので、変態になりにくい。むしろ淡白なセックスをするのではないだろうか。一概に言うことはできないが、変態になるのは、圧倒的に文化系の方が多いだろう。
強くなりたいという憧れはあるけれど、努力ができない内向的な若侍というのが、私の小説の主人公にふさわしい。
昔は、庶民の方が早く大人にならなければいけなかった。早く大人にならないと稼げないからである。その点、旗本の次男、三男になると、することもないので、変態になりやすい。いろいろな妄想をする時間的、金銭的余裕があるからだ。だから、どうしても武家が主人公になることが多い。
一方、町人は忙しいので、妄想する余裕が少ない。変態が生まれにくい状況なのだ。その代わり、町人ならではの楽しみもあったはず。いろいろな春画を読んだりしていただろう。
そうは言っても、町人を主人公にすることもある。それが大店の息子だったら、小遣いがあるから、岡場所(格式の高い吉原に対して、気軽に安く行ける庶民の遊郭)に行っているはずだろう。
でも、私の主人公は岡場所には行ったことがない。行けないような貧乏町人の場合もあるし、大店の息子であっても、いろいろな言い訳をして、行ったことがないことにしている。
岡場所というのは、セックスをするのが当たり前の場所だ。そういう当たり前のことを書いても面白くないのは、先に述べたとおり。官能にはなりえない。それ以前に、主人公は必ず無垢の童貞にしたいという理由が大きいだろう。
主人公は弱いため、基本的にチャンバラは出てこない。悪者に絡まれたりすることもあっても、必ず他の人に助けられる。もちろん、助けてもらうのは女性だ。
だから、強い女性が必ず登場する。それは、くノ一であったり、女武芸者であったりするわけだが、主人公の代わりに悪者をやっつけてくれる。
颯爽と美女が悪者を退治する。そのときの汗ばんだ美女に興奮するわけだ。
私は凜とした女性が好きだ。だから、女武芸者や武家娘をよく書く。そういう凜とした女性が、恥じらったり、好奇心や快感を求めたりするところを描きたい。凜とした強い女性が、女らしく喘いでしまうところを描きたいのだ。
ただ、昔は18歳で生娘というのは、少し無理がある。もう嫁に行っている年齢だからだ。だから、時代物に限っては、17歳までは許してもらっている。数え年だから、実際は15歳か16歳だけれど、17歳と表記している。
そうしないと、処女はいなくなってしまう。昔は15歳で嫁に行く時代なのである。「十五で姐やは嫁に行き……」というのは、有名な童謡「赤とんぼ」の三番の歌詞だ。
ギャップがある関係は官能的
結局、人物設定で重要なのは「ギャップ」である。凜とした女性が女らしくなるギャップ、普段キリッとしている女教師が一人の女性に戻るギャップ、貞淑に見える人妻が童貞男を求めてくるギャップ……。
そういった様々なギャップこそが、官能的なのだ。
そのためには、最初に女性を持ち上げる。女神様のように思うからこそ、ギャップというものが生まれる。
以前、女子アナのヒロインを書いたことがある。女子アナが、アナウンサーの口調で淫らなことを喋る。そのギャップがいいわけだ。
結局、どんな職業の人も、素に戻ればみな同じなのだが、最初は「こんな素晴らしい女性、あるいは、こんな堅い仕事をしている女性は、自分にとって高嶺の花だ」と思わせる。もしすぐにさせてくれそうな女性だったら、ギャップが生まれない。
私が描く主人公の男は、モテない、冴えないといったダメ男なのだが、そういう男が高嶺の花である美女を好きになる。それもひとつのギャップになる。
そのギャップをどう埋めるかというのが、官能作家である私の仕事なのだ。だから、美女はいっぱい出てくるが、モテる男は一人も出てこない。
若くて可愛い人妻と懇ろになるというのは、現実の世界ではありえない話だけど、ギリギリのラインで、さもありえそうに書くわけである。読者に、自分にも起こるかもしれないと思わせるのが、腕の見せどころでもある。
先ほども述べたように、時代物であれば、このギャップがより顕著になる。江戸時代の身分制度が大きなギャップを生んでくれるからだ。
普通であれば、武士が女性の股に顔を埋めたりすることはない。実際はしていたと思うけれど、建前としてはしないはず。でも、そこをあえてすることで、ギャップが生まれる。
武士の主人公と町人の娘という関係も、ギャップのある関係の一例だろう。その武士の主人公が、町人の娘の足裏を舐める。すると、町人の娘は腰を抜かすほど驚く。「無礼打ちで斬られるのではないか」という恐れもある。
武士の顔の上に、町人の娘が跨るということは、現代の男女以上に背徳感が生まれるのだ。こういう状況は、現代物ではできない、時代物ならではの面白さだろう。
すなわち、同じ行為であっても、その前提となっている設定にギャップがあれば、それだけ興奮度も増すということ。だから、どのような設定にするか、どれだけ設定にギャップを持たせられるかが、官能小説の肝になる。
自分とは住む世界が違う女性、すなわちしてはいけない女性だからこそ、男は欲望を抱いたり、妄想が湧いたりする。それは、現代物と時代物との違いに関係なく、人間に共通する部分なのだ。
のび太のような主人公の復讐
男は、努力で勝ち取ったものではなく、自分だけが選ばれているということに、どこかで憧れているのではないだろうか。
努力すれば勝ち取れるのであれば、みんな努力すればいいわけであって、努力できないから苦しんでいるのである。最近お亡くなりになられた立川談志師匠が「努力というのは、バカに残された最後の希望だ」と言っていたけれど、努力ができないバカもいる。
アメリカのスクールカーストでは、「ジョック」というヒーローが、ヒエラルキーで一番上に位置している。簡単に言えば、スポーツマンでマッチョで傲岸不遜な男だ。日本で言えば、昔の若大将みたいなものだろう。
一方、女性のトップは、チアリーダーで「クイーン・ビー」と言う。
その下に、「プリーザー」(ジョックの取り巻き)だとか「メッセンジャー」(使い走り)だとかいった人たちがいる。
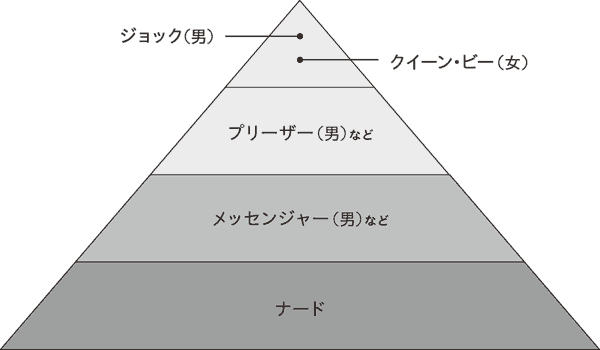
アメリカのスクールカースト
中学校や高校などで発生する「人気度のヒエラルキー」。
アメリカでは上図のような階級があると言われている。
そして、一番下に位置しているのが「ナード」と呼ばれている人たち。ナードとは、簡単に言えば、オタクのこと。ジョックという存在の対極として語られることが多い。
ところが、社会に出ると、このナードと呼ばれていた人がトップになる場合がある。ナードが映画監督になって、ホラー映画などを作ると、最初に殺されるのは、決まってジョックなのだ。
例えば、キャンプを抜け出したモテ男(ジョック)と女(クイーン・ビー)が、最初の被害者になる。これは、ナードの復讐である。モテ男に対する復讐なのだ。
私の小説も、これに近いところがある。小説の中では、モテないナード的な主人公が、美女を自分のものにするのである。
確かにスポーツマンというのは、それなりに努力をして勝ち取ったヒーローの位置だから、それはそれで大したものだけど、文化系の人間は、どこかでそういうものを毛嫌いする傾向がある。実際、私もそうだった。高校時代は、体育会系と文化系の対立があったし、水泳大会や体育祭はサボってばかりいた。
のび太は、ドラえもんの道具によって、ジャイアンやスネ夫に復讐する。復讐という言葉が適切ではないかもしれないけれど、いじめられたのび太は、ドラえもんに甘えるわけである。しかも、優しくしてくれるしずかちゃんまでいる。
努力ができないのび太は、ドラえもんという存在によって、選ばれた存在になっているのだ。この状況こそが、ナードの憧れ、文化系の憧れ、オタクの憧れ、しいてはモテない男全ての憧れなのである。
私の小説では、モテないし、冴えない童貞の少年が、美女たちと欲望の限りを尽くすわけだから、まさしくモテ男に対する復讐と言っても過言ではないだろう。
ダメ男には共感しやすい
なぜ、私はダメ男を主人公にするのか。
ひとつは、共感しやすいからだ。また、自分よりもダメな男を見ると安心するということもある。だからと言って、そのダメ男がいい思いをすると、反発するわけではない。いつの間にか、ダメ男の主人公と自分が同化してしまう。まるで自分のことのように、感情移入してしまうのだ。
その理由は、やはり「根っからのモテ男」といった共通の敵がいるからではないだろうか。程度の差こそあれ、モテない男にとって、何もせずにモテるような男は、圧倒的に敵なのである。
時代によって、読者が求めるものは変わってきたけれど、その根底にある「女性に対する渇望」は、どの時代の男にも共通するものだろう。
そして、モテない男であればあるほど、女性への渇望が強くなる。モテる男であれば、それほど努力しなくても彼女ができる。放っておいても、女性が言い寄ってくるかもしれない。
ところが、モテないダメ男にとって、女性というのは神秘の存在だ。手に触れることもできなければ、うまく喋ることすらできない男もいる。
渇望の青春時代
私の高校時代は、まさに渇望の青春時代だった。
私は神奈川県立三崎高校(当時)に入学してすぐに、横須賀から藤沢に引っ越した。転校試験に落ちてしまったため、3年間藤沢から三浦半島まで、片道2時間もかけて通うことになった。
生まれ育った横須賀の家は、昔ながらの長屋。自分の部屋などない。両親と弟がいない間、もしくは夜中の布団の中でオナニーをしていた。
藤沢の一軒家に引っ越して、何が一番嬉しかったかと言うと、自分の部屋ができたことだった。これで昼間でも夜中でも、好きなときにオナニーができると喜んだ。
当時、ようやくビニ本と呼ばれるエロ本が本屋に並ぶようになったが、少ない小遣いだったため、たまにしか購入することができなかった。
エロ本というのは、買うときが一番楽しい。ビニールで封をされているから、中身を見ることはできない。表紙と裏表紙を眺めて熟考し、恥ずかしい思いをしてレジに持っていく。一種の羞恥プレイである。そして交通事故にあわないように気をつけながら家に帰って、ビニールを破り中身を見ると、いまいちだったことも多々ある。
また、通販での失敗も数知れない。海外の裏本を通販で注文し、お金も払ったけれど、税関で没収されたこともある。そのときは、お金が勿体なかったというよりも、裏本がすぐそこまで届いているのに見られないことの方が辛かった。
高校時代のオナニーのネタは、もっぱら『週刊プレイボーイ』などの雑誌のグラビアか、想像の世界。藤圭子、新藤恵美、由紀さおりといった好きな女優さんは、定番のオカズだった。
一番のお気に入りは、アグネス・チャン。アグネスのポスターが手に入ると、目と口の部分を切り抜いて、お面のように自分の顔に被せ、鏡を見ながらオナニーをした。口からベロを出すと、まるでアグネスが淫らなことをしているようになるのだ。鏡に向かってディープキスをしたりもした。舌は私のものだけど、顔はアグネスだから、それだけで興奮できたのだ。
とにかくオナニーがしたかった
あの頃は、どんな女性と知り合いたいか、どんなセックスをするかということよりも、どんなオナニーをしたいかという方が主流だった。
腕を縛って手を痺れさせてオナニーをしたり、利き手ではない左手でオナニーをしたりした。他人の手のような感覚を味わうためである。
羽を切ったハエをペニスに止まらせると気持ちいいと聞き、4時間もかけてハエを捕まえたこともある。ところが、羽を切ったらすぐに死んでしまった。
本当に愚かな時代だった。
なぜ、そこまでするかというと、渇望していたからだ。生身の女性というのは、遠い存在だったからである。そういう時代は、誰にでも少なからずあったのではないだろうか。
その時代の熱い渇望を未だに引きずっているから、30年以上も官能作家を続けることができたのだろう。そして、多くの人の渇望を小説という形にできているからこそ、読者がついてきてくれているのだと思う。
何も取り柄はないし、女性にモテないけれど、女性に対する渇望は人一倍強いダメ男の主人公。そこに読者が共感するツボがあるのだ。
やはり密室でのセックスがベスト
ここまで、主人公やヒロイン、サブヒロインについて説明してきた。次に、場所について触れておきたいと思う。
私は、完全な密室派である。家でもホテルでもいいけれど、落ち着ける場所が好きだ。誰も来ない寝室というのが一番である。
青姦やカーセックスというのは、まず書かない。誰かが来るかもしれないというスリルも分かるけれど、好みとして落ち着けない場所ではセックスを楽しめない。また、単純に布団がないと痛いということもある。おそらく、私の読者も同じだと思う。
鍾乳洞の中や山小屋という場所も書いたことがあるけれど、あくまでも誰も来ない場所という大前提がある。それでも、屋外よりも屋内の方が圧倒的に多い。
死角になる場所も好きだ。学校が舞台であれば、保健室や理科室、体育館のカーテンの裏、屋上に続く階段の踊り場といった死角がたくさんある。そういう死角での行為は、非常に興奮する場所になる。
ただ、そういう死角では、あまり最後まですることはない。ちょっとしたことをするのにちょうどいい場所になる。
最後までするのは、あくまでも布団がある場所。落ち着いた場所でないと、私自身が落ち着いて書くことができないのだ。
そういう意味では、体育館の用具室というのはいい。マットがあるから、布団の代わりに使えるからだ。跳び箱に跨らせたりと、いろいろな道具を使えるのも魅力的だ。
学校というのは、いろいろな場所が使えたから良かったけれど、今は自主規制があるので、なかなか学校内というのは難しくなった。教育実習生の主人公と美人女教師という設定ならありうるけれど、今は女子高生が使えないため、学校内という設定も少なくなってきた。
そのため、お化け屋敷の中という怪しい場所でするという一風変わったシチュエーションを書いたこともある。
学校に比べるとバリエーションで劣るけれど、会社のオフィスや病院という場所は、昔からの定番だ。特に病院は、側にベッドがあるのがいい。
序章でも触れたが、人妻の家でセックスをする場合、いつ旦那が帰ってくるかといったドキドキ感がある。そういう演出はするけれど、決して旦那が帰ってくることはない。
あくまでも、興奮度を高めるための道具として利用するのであって、実際に帰ってきたら興ざめしてしまうだろう。
畳の上では背中が痛い
現代物であれば、部屋に入ればベッドがあるけれど、時代物になると難しくなる。わざわざ布団を敷かないといけないからだ。畳の上ですると、書いている私も読んでいる読者も、「背中が痛いのではないだろうか」といった余計なことを考えてしまう。
だからと言って、気持ちが高まっているときに、中断して布団を敷くというのは面倒だし、気持ちも萎える。不自然なく布団を敷いてある状況を作るのが、難しいところでもある。
実際は、武家屋敷には密室というものはない。隣の部屋とは襖で仕切られているだけである。いつ誰が来るかもしれないし、ノックをする習慣もなかっただろう。鍵のかかる密室がないので、すぐに開けられてしまう。
ということは、一家で留守をするような状況を作ってあげないといけないのだが、本来、武家屋敷に誰もいないということはないはずだ。その辺りは、フィクションにするしかないのである。
このように私の場合は、それほど特異な場所ということはない。いたって普通の場所と言ってもいいだろう。誰にも邪魔をされなくて、背中が痛くない場所。すると、必然的に家の寝室に落ち着いてしまうのだ。
変わった場所は、官能小説のひとつのテーマになるけれど、私の小説の特徴は場所ではない。フェチな行為や主人公とヒロインの禁断な関係をテーマにすることが多いのだ。だから、場所に意外性はないのである。
読者との距離があり過ぎてはいけない
人物の設定にしても、場所の設定にしても、読者との距離があり過ぎると、途端にウケが悪くなる。読者が主人公に感情移入できないからだ。読者は、主人公に自分を投影して読んでいるのだから、それを裏切るようなことはしてはいけない。
現実には起こらないけれど、ひょっとしたら起こるかもしれないというギリギリの設定が理想的なのだ。
よって外国人を登場させることはない。ほとんどの読者は、身近に外国人はいないから、非現実的なのだ。実は外国人を登場させたこともあるが、読者のウケはことごとく悪かった。今でもたまに出てくることがあるけれど、ヒロインではなく、あくまでもサブヒロインの一人として登場させることにしている。
ちなみに、私の小説に出てくる外国人は、全て「リンダ」という名前だ。あまり外国人の名前が分からないので、リンダで統一している。名前を考えるのが面倒という理由もある。
時代物ではハーフを書くこともある。ハーフの巨大な女武芸者で、いつも編み笠をかぶっている。赤毛を隠して、男のふりをしているのだ。その場合の名前は「蘭」。オランダ(和蘭)の蘭だ。時代物の登場人物にリンダは付けられないから、蘭にしている。
美人の外国人とのセックスは、したいけれどできないことの中に含まれるのだろうが、あまりにも現実と遠いのだろう。やはり自分とは違う世界、遠い世界だと、リアルに想像できないのかもしれない。だから、海外を舞台にしたことは一度もない。
舞台に特徴はいらない
舞台とするのは、たいていが架空の中間都市か都内かのどちらかである。作家の中には、どこの街で何丁目ということを事細かに書く人もいるけれど、私の場合は基本的に細かく設定しない。
北海道から沖縄まで、全国に読者がいるわけだから、あまり地方色を出さないように気を付けている。だから、方言が出てくることもない。あまり舞台は重要視していないのだ。究極を言えば、ひとつの家から出たことがないという作品もあるくらいだ。
特徴のない街で、特徴のない部屋でばかり行うから、官能作家は多くの作家たちの中で最も取材旅行が要らないのである。