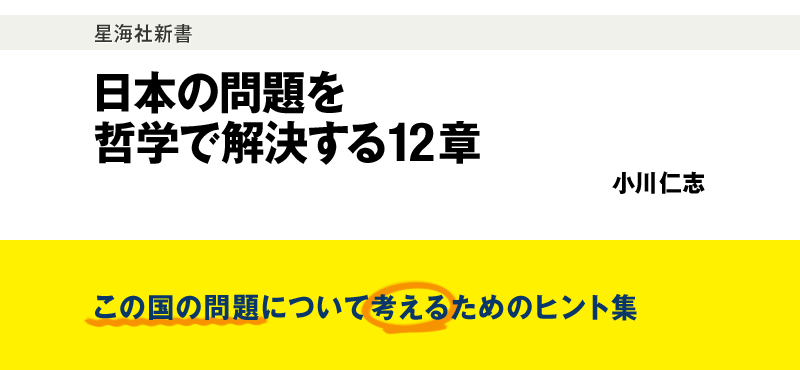
日本の問題を哲学で解決する12章
小川仁志
この国の問題について考えるためのヒント集 増税、原発、T P P……。この国には問題が山積みだ。評論家や専門家が多くの議論を重ねているが、なかなか答えは見えてこない。本書では産官学の立場を経験した哲学者が「日本の論点」をスッキリと整理。そもそもどこが争点なのか、古今東西の思想や哲学を参照しつつ、問題の本質に迫る。賛成派・反対派の考え方も踏まえた上で、ヘーゲルの弁証法を使って第三の道を探っていく。もはやこの国は待ったなしだ。ふだん国の問題について考えたことのない人ほど読む価値がある。「自分のこと」だけ考えていては幸せになれない時代だからだ。この国の問題をどこから考えればいいのか? どのように考えれば答えが見えるのか? この国の問題について考えるためのヒント集をあなたに。
はじめに 日本の問題を「そもそも」から考える
今、世の中の大問題について、現実の政治の場でも、マスメディアでも、あるいは学問の世界でも、専門家たちが必死になってどう乗り越えるべきか議論しています。
ただ、二つの意味において、それでは不十分です。
一つは、大転換期の問題であるがゆえに、政治の現場に顕著なように、「場当たり的」「表面的」な解決を模索していては、すぐに行き詰まってしまうという点です。そうではなくて、今は問題を根本にさかのぼって考える態度が求められているのです。「そもそも」という視点が必要なのです。本書が、「哲学的視点から」現代社会の問題に対峙しようとしたのは、そのためです。
もう一つは、政治やメディア、あるいは学問の世界における専門家に事を委ねていては、もはや問題は解決しないという点です。そもそも自分の国の問題は「自分ごと」のはず。それをあたかも他人ごとであるかのように、人任せにする態度に問題があります。何より、国民の知恵を総動員しないことには、この大転換期を乗り切ることなどできません。専門家だけでなく、全国民が社会問題を自分自身の問題ととらえて真摯に向き合う必要があるのです。
国全体の景気が良く、未来も明るい時代であれば、国の問題を他人ごとにしていても問題はなかったかもしれません。目の前のレールに乗っかっていれば幸せな暮らしが送れたはずです。しかし、今はこの国全体が問題を抱えています。全体が沈んでいく時代において、自分だけが幸せになる、という考え方には無理があります。そうではなくて、みんなが幸せになることによって、初めて自分も幸せになれるのです。
とはいえ、国の抱える問題に興味を持つのは、ハードルの高いことかもしれません。書店に行けば、山ほど本が積まれている。TPPの問題一つとっても、賛成派と反対派が熱い論議を繰り広げている。だからどの本を手にとっていいのかすらわからない。
本書は、そういう人のための手引きになることを目指して、いま日本で話題になっている問題のほぼすべてを網羅しました。いわば「考えるためのヒント集」というわけです。そのヒントの中には、私の専門である哲学や政治哲学の知見が多数登場します。これらは、物事を普遍的に考えるために有益な知恵であるといえるからです。
問題解決にはヘーゲルの弁証法が武器になる
自分で考えていただくための工夫として、各論点ごとに、まず賛成論と反対論の両論を示し、何が対立しているのかを明らかにしました。
そのうえで、「そもそも論」にさかのぼり、思想や哲学の知見を参照しつつ、問題の本質に迫っています。そして最後に、賛成・反対の両極を乗り越えた第三の案を提示しています。
実は、これはヘーゲルの弁証法にのっとった論理展開です。
彼の弁証法は、正(テーゼ)といわれる問題の提起に、反(アンチテーゼ)と呼ばれる反対論をぶつけて、それを止揚(アウフヘーベン)することで、つまり反対論をうまく取り込んで解決することで、合(ジンテーゼ)と呼ばれる第三の道を創造する思考方法です。ここでのポイントは、反対論を単純に切り捨てるのではなく、それをも取り込んで、より強固な発展した道を探るという部分です。
今多くの日本の論点は、原発やTPPの是非を見てもわかるように、賛否が拮抗し、行き詰まりの状況にあります。それを乗り越えるためには、弁証法的に第三の道を創造していくしかないと思うのです。その試みがうまくいっているかどうかは、本書を読んでいただいた方のご判断に委ねたいと思います。
さらに本書では、「アメリカ」の話が頻繁に登場します。これは、私たちが思っている以上に、アメリカが日本の大問題に深くかかわっているからです。民主主義を日本にもたらしたのもアメリカですし、資本主義もアメリカの専売特許と言えます。また、TPPのようなグローバル化もアメリカの要求によるものといっていいでしょう。
さらに、直接アメリカの影響によるものではなくても、ネット選挙や同性婚、死刑廃止論などは、アメリカのほうが議論が進んでいます。したがって、アメリカの議論を参考にすることは、明日の日本を考えるうえで、大きなヒントになりうるのです。偶然にも私は、昨年度約1年間、アメリカのプリンストン大学で研究する機会に恵まれました。したがって、そこで得た知見や、実際に見聞したアメリカの現実を、ふんだんに盛り込んだつもりです。
さあ、普段から国の問題を考えている方もそうでない方も、ぜひ本書を片手に「考える時間」を過ごしてみてください。そして、あなたなりの「答え」を探してみてください。一人ひとりが「考える」という、その行為自体が、国をジワジワと少しずつ幸せにし、ひいてはあなた自身を幸せにしていくものと信じています。
尚、本書に登場する人物の敬称は略させていただきましたのでご了承ください。
さて、まず第一章は、混迷を極める民主主義のお話からです。「維新の会」の橋下徹のやり方にあなたは賛成ですか? 反対ですか? そんなところから考えていきましょう。
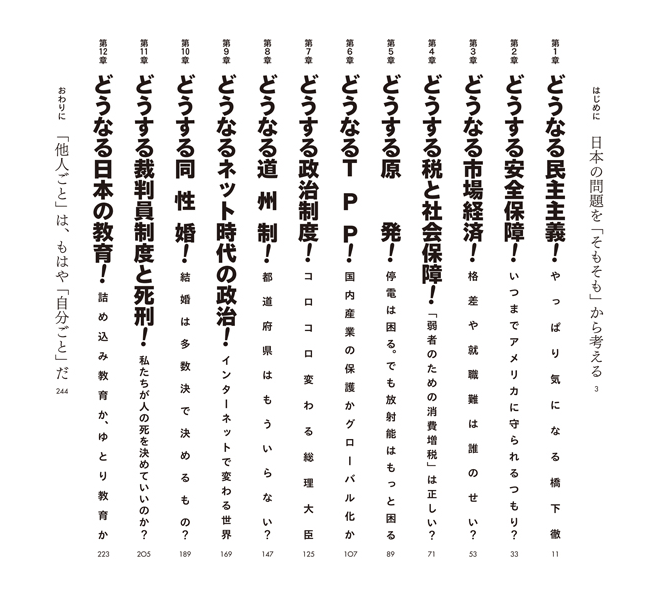
第1章 どうなる民主主義!やっぱり気になる橋下徹
今後の日本を語る上で欠かせない男 橋下徹
突然ですが、橋下徹は好きですか? 嫌いですか? どうでもいいですか? では、その理由は?
「また橋下徹の話か。もういいよ」などと言っている場合ではありません。ここで大切なのは、今彼が実際に政治権力の座に着き、ますます影響力を増しているという事実です。彼の率いる維新の会は、大阪を飛び出て国政にも進出しようとしているのですから。
橋下徹の動向は、いまや私たち全国民の生活や人生に影響を及ぼしてくる可能性があるので、どうでもいいなどとは言っていられないのです。
それにしても、いったいなぜ彼は急に台頭してきたのでしょうか。
半世紀にわたる自民党の一党独裁体制に終止符を打ち、ついに本格的な二大政党制を実現した日本。しかし、待ち受けていたのは与野党の対立によって何も決められないジレンマ地獄に過ぎませんでした。そんなこう着状態に業を煮やした国民は当然、既得権益のない第三の勢力に期待を寄せるようになります。
その期待の星が、橋下大阪市長率いる「大阪維新の会」だったのです。橋下市長の政治手法は、大阪府知事時代からそうなのですが、一点突破の独裁型。民意を背に、反対勢力をどんどん切り崩していきます。これは既得権益がないからこそなせる業といえるでしょう。
こうした強引な政治手法についた異名が「ハシズム」。独裁を彷彿させるファシズムと、橋下氏の名前を掛けたものです。
このネガティヴな表現にも表れているように、ハシズムは必ずしも肯定的評価を下されているとは限りません。
はたして独裁なのか? それともあれこそが「民主主義」なのか? アンチ橋下はいったい彼のどこが嫌なのか?
そこで、まずは賛成論と反対論の立場を明確にしたうえで、思想や哲学の視点から、つまり「そもそも論」から本質を考えることで、両見解の対立を乗り越える案を提示してみたいと思います。
実はそれは、よりよい民主主義の形を模索する営みであり、ひいては私たち自身の生活や人生をよりよいものにするための議論にほかなりません。
論点行き詰まる日本の改革を、
ハシズムとも呼ばれる橋下徹の政治に委ねてよいか?
賛成論:橋下徹の実行力とカリスマ性は素晴らしい!
ぜひ日本を改革して引っ張っていってほしい。
反対論:ファシズムにも似た強権的手法、
テレビ的人気に迎合する大衆のポピュリズムは危険だ!
そもそも民主主義とは何か?
まず、橋下徹のやり方に賛成する立場からご紹介しましょう。
たとえば、経営コンサルタントの大前研一は、「日本に残された数少ない希望の星」「橋下イズムは健全な国家ビジョンであり、まさに必要な方向性であり、手段でもある」と期待を寄せています(『Voice』2012年5月号)。
あるいは、評論家の堺屋太一は、知事時代の橋下との対談の中で、「誰かが突出しなければ改革はできません。しかし突出するには、大変な勇気と発想がいるんですね。どこから現状を打ち破ったらいいか。橋下知事が大阪都でまさにこれをやろうとしている」と持ち上げます(『体制維新――大阪都』)。
作家の佐藤優は、「橋下氏には天才的な政治的能力があり、それを日本の政治に生かすべきであると考える。橋下氏の思想をファシズムに親和的な『ハシズム』であるという批判は、間違えていると思う」と断言しています(『CIRCUS』2012年6月号)。
これに対しての反対論は以下のようなものです。
政治学者の中島岳志は「独断的で断言型の政治家」「既得権益を徹底的にバッシングすることで支持を獲得するあり方は、非常に危険」だと警鐘を鳴らします(『ハシズム!』)。あるいは最初にハシズムを有名にした本の中で、政治学者の山口二郎が、「橋下徹のやり口は、軍隊的官僚主義と能天気きわまりない単純な市場競争主義の混合物である」と痛烈に批判しています(『橋下主義(ハシズム)を許すな!』)。
また、この同じ本の中では、作家の内田樹も大阪維新の会が掲げる教育改革に異を唱え、橋下徹を批判しています。
つまり、個々の政策はもちろん賛否の対象となるのですが、それ以上に、橋下徹の問題は、その政治手法にあるといえるでしょう。換言するならば、最大の問題は「橋下徹の強引な手法がはたして民主主義といえるかどうか」という点にあります。したがって、まずは民主主義という概念について本質にさかのぼって考えてみたいと思います。
2012年3月にNHKの「ニッポンのジレンマ」という番組に出演したのですが、そのときのテーマは「民主主義の限界?」というものでした。行き詰まる日本の民主主義について、政治哲学の立場から話してほしいといわれたので、教科書的な話から順に説いていきました。
そこで、その場で話したことも踏まえながら、本書で再度教科書的な話から説き起こしてみたいと思います。
民主主義について議論するときに大切なのは、まず、①民主主義の定義をはっきりさせること、その上で、②民主主義以外の選択肢はどうしてダメなのか考える、③それでどうしても民主主義だというなら、どうすればそれが機能するのか考えることです。
さて、そもそも民主主義とは何なのでしょうか? 私たちは日ごろ当たり前のように民主主義という言葉を使っていますが、意外とその意味をよく理解していないものです。
本来、日本でいう民主主義の原語「デモクラシー」は、古代ギリシャ語で民衆を表す「デモス」と支配・権力を表す「クラティア」の合成語です。よって「民衆による自己統治」という意味になります。
ちなみに、反対の意味を持つ寡頭制は、優れた人を意味する「アリスト」と「クラティア」で「アリストクラシー」といって、「一部の人間による支配」を意味します。
注意しなければならないのは、デモクラシーは民主制という統治システムのことであると同時に、それを尊重し推進すべきという思想でもある点です。だからこそ思想を意味する「主義」をつけているのです。したがって政治学などでは、制度のことをいう時は「民主制」、政体をいう時は「民主政」と、あえて区別することもあります。
民主主義が機能不全に陥っている理由
民主主義というのは「民衆による自己統治」であることを確認しました。それでは次に、民主主義以外の他の制度ではダメなのかどうか考えてみましょう。というのも、民主主義には「時間がかかる」「コストがかかる」「多数派の支配になる」といったデメリットがあるからです。まさに今の日本がおかれた状況ですね。
他方で、民主主義以外でも、ブータンのように君主制時代でも幸福と言われている国や、中国のように社会主義でも強国になれるという例はあります。にもかかわらず、なぜ私たちは民主主義にこだわるのでしょうか?
あまりに民主主義に慣れすぎていて、疑ったこともない人も多いと思いますが、なぜ民主主義がベストだと言い切れるか、考えてみたことはありますか? ちょっと考えてみましょう。
「人権を守れるから」という答えもあるでしょう。しかし、それは司法の仕事です。多数者が支配する民主主義社会で、犠牲になった少数者を救うのが司法の役割なのです。
私が考えるに、民主主義の利点は「政治がダメになったときに、自分たちで変えることができる」という点にあるのではないでしょうか。
民主主義を疑う立場からは「数の勝負になってしまうので良くない」「多数者の専制だ」という批判もあります。ただ、それは一面的な見方であって、現状が不合理であれば、少数者が多数者になりうるという点に本質があります。マイノリティを救うためにこそ民主主義があるといっても過言ではないのです。
さて、やや駆け足かもしれませんが、どうやら民主主義は今のところベストに近い制度のように思えます。そうであるならば、きちんと機能するように方策を考えるよりほかありません。
なぜ民主主義が機能していないのか。一言でいうなら、それは本来の民主主義の定義である人民の「自己統治」が「他者統治」になってしまっている点に問題の元凶があります。つまり、私たちのあずかり知らないところで、政治が行われているということです。自分たちで統治するはずの民主主義なのに、他者が統治してしまっている。なぜ、こんなことになってしまっているのでしょうか?
これは「外的要因」と「内的要因」に分けて分析できます。
外的要因とは、経済の支配に見られるように、民主主義を取り巻く「環境の変化」のことです。アメリカの政治学者ウェンディ・ブラウンは、これを「脱‐民主化」現象と呼んでいます。経済優先で、市場の原理によって政治が動かされているため、民意が反映されなくなってしまっているのです。ですから、その状態を解消するには、政治がもっと経済をコントロールする必要があります。
これに対して、内的要因とは「土台あるいは共通善の喪失」といっていいでしょう。最後は一つになろうという気持ちがないので、決められないのです。日本でいうと、共同体の美徳とか連帯意識が共通善になるのではないでしょうか。
トクヴィルの遺言
これについては、先進国は多かれ少なかれ、同じ問題に直面しています。世界的潮流だといっていいでしょう。たとえばアメリカでも、本来は伝統的価値たる「自由主義」でまとまるはずが、99%といわれる貧しい人が増えてきて、そうもいえなくなってきたのが要因です。
なぜ日本でそうした共通善が喪失してしまっているか。私は「個人主義化」が問題だと思っています。
では、個人主義を抑えるためには、つまり共通善を育むためにはどうすればいいか。これについては、元祖アメリカ・ウォッチャーともいうべきフランスの思想家アレクシス・ド・トクヴィルが、『アメリカのデモクラシー』の中で的確な指摘をしています。
トクヴィルによると、個人主義の国アメリカがばらばらにならずにまとまっている理由は、自分の属する集団の中で身近な問題について頻繁に討議しているからだといいます。そうすることで、社会は他者との支え合いであることに気づけるというのです。
アメリカで集団討議が盛んなのは、多元社会であることや、参加を助長する文化があることが理由です。日本は事情が違いますが、なんとかして個人主義を抑える必要があるのではないでしょうか。
東日本大震災が起こった際、日本人が「瞬間的に」一つになって助け合えたのは、絶対的な危機にあって、さすがに共通善としての連帯意識を発揮せざるを得なかったからでしょう。同じ日本人として、住む場所をなくした人を見捨てるわけにはいきません。
そして今日本のおかれた政治経済的状況も、災害時に匹敵するほどの非常事態下にあるといえます。その意味で、今こそトクヴィルの遺言に耳を傾け、個人主義を乗り越えて連帯意識を発揮する必要があるのではないでしょうか。
放射能に汚染された、がれきの受け入れ拒否問題もこれに関係しています。震災からある程度時間がたって「さあ、汚染されたがれきも被災者と同様に受け入れてください」と呼びかけると、皆、掌を返したように「うちは嫌だ」といい出しました。つまりこの問題は、いかに「日本全体における土台」を意識できるかという話なのです。
さて、民主主義がなぜ機能していないのか。それは、政治が経済をコントロールできていないからであり、共通善が喪失しているからだ、というお話をしました。では、そうした要因が解消され、人民による自己統治がシステムとして整ったら、私たちは自分で決めるようになるのでしょうか?
実は、現実はそう簡単ではありません。それでも日本国民は、自分で決めようとしないでしょう。そこには二つの問題があると考えています。一つは「自分が決めるという意識がない」点、もう一つは「決める訓練が足りない」という点です。
自分で決めるという意識を持つには、「無関心の連鎖」を止めることが必要です。
「チョイス!」という映画をご存知でしょうか。ひょんなことから主人公の1票が大統領選の結果を決めることになる、という話です。主人公は、そこで初めて「本当は自分が国家のあり方を決め、動かしている」という事実に気づくわけです。私たちもその偉大さに気づくことが大事なのではないでしょうか。
その意味で、極端だと批判されることがありますが、NHK「ハーバード白熱教室」でマイケル・サンデルがやっていた、「もし自分が5人の命を握っていたら……」という思考実験をすることも有益なのではないかと思います。
あなたは、自分で決める大切さに気づきながらも「フリーライダー(ただ乗り)」になってはいないでしょうか? 政治学ではこれを「合理的無知」と呼びます。要は自分がわざわざ苦労して変えなくても、誰かがやってくれると考えるわけです。ある種のニヒリズム(虚無主義)です。
これを解消するためには、政治を行う単位をできるだけ小さくしていくことが必要でしょう。たとえば、ご近所のような狭い世界では、ただ乗りできません。ですから、ご近所で色々決めることにすれば、そこで鍛えられた意識が、国政にも反映されるようになるはずだと思うのです。
衆愚ではなく知的な市民になろう
もう一つの問題である「決める訓練」をするためには、民主主義教育の強化が必要です。その点、アメリカ人は明らかに日本人より態度表明が得意です。その理由は、教育方法にあるように思います。
私はアメリカ滞在中に小学校に頻繁に出入りし、授業までさせてもらいました。彼らは特別な科目ではなくて、幼少の頃から事あるごとにプレゼンテーションの機会を持ち、日々実践的な訓練を行っているのです。自分の意見を主張し、人と議論する。まさにそれが民主主義教育なのです。
ルールを守ることを教えるのはもちろん大事ですが、それとまったく反対で、ときには正しい方法でルールに異議申し立てする方法を教える必要もあります。これがうまくできないと、校内暴力や不登校という間違った形で事が生じてしまいます。
私は子どもたちにいつも言うのですが、本来生徒会や学生会というのは「異議を申し立ててルールを変えるためにある」わけです。だから不満があるなら、ふてくされたり、違反したりするのではなく、堂々と異議を申し立てればいいのです。教師はそんな事態を恐れますが、きちんと異議申し立てすることを教えるのも民主主義教育なのです。
日本人にはそもそも民主主義が向いていないという人もいますが、決してそんなことはありません。皆で物事を決めるというのは、もともと「和を重んじる」と言われる日本人には合っているはずなのです。
最近、デモに参加する若い人たちがいるのは希望だと思っています。デモに行くのは意味がないという人もいますが、政治へ影響を与えうることを直接体感できるというのは貴重な経験です。そういう感覚を知ることが、ニヒリズムを超克するための唯一の道であるとすら思っています。
もちろん、直接民主主義的な行動としてのデモが、それ単独で意味を持つといいたいわけではありません。デモや住民投票のような直接民主主義と、代議制のような間接民主主義は相互補完関係にあるべきだからです。あくまで、デモをきっかけとして間接民主主義に関心が出ることに意味があります。
その際ネックとなるのは、忙しくて社会を変えることにかかわっていられない社会の現実です。特に若い人は、就活や仕事、婚活などで、社会に参加する暇がない人も多いでしょう。
古代ギリシャのアテネの民主主義のように、私たちは「自由人」ではありません。彼らは年40回、民会を開き、女性・奴隷・在留外国人を除く成人男子たちが、年中討議していました。
アテネの自由人たちは、結局は「衆愚」になってしまったのですが、21世紀の私たちは決して衆愚ではないはずです。衆愚が問題なのは、空気を読んで、いや単に空気に流されて、物事を判断してしまいがちな点です。いわゆる「空気による支配」です。
古くは、誰かが戦争しないとまずいような空気をつくったことにより、それが蔓延し、戦争をしてしまった。最近なら、TPPに参加しないといけないような空気が知らず知らずのうちに蔓延してきて、参加ありきの民意が形成されていく……。空気による支配は、人々が自分の頭で考えて判断していない状態です。いくら民主主義が機能しても空気による支配が上回ってしまっては意味がありません。
しかし、私たちは今、様々なメディアを駆使して、足りない時間を補い、情報を入手して考えることができます。「空気による支配」を乗り越えることのできる「賢い群衆」(スマート・モブズ)のはずなのです。
もちろん物理的にもっと時間を確保するためには、同時に男女共同参画を推進することも必要でしょう。そこまでやると社会的にコストがかかるという人もいるかもしれませんが、アテネでも貧しい人に日当を払って政治に参加してもらっていました。私たちの裁判員制度と同じです。民主主義にはコストがつきものです。しかしそれは、独裁を避けるための必要なコストです。
ポピュリズムを警戒する人たちがいうように、私たちはややもすると独裁を招きがちです。社会学者のマックス・ウェーバーによると、私たちが支配に服する根拠は三つに分けられるといいます。
一つ目は、官僚制のように、制定された秩序の合法性と、その秩序に基づく命令に従うという「合法的支配」です。
二つ目は、明治時代の日本の天皇制のように、伝統の神聖性とそれに起因する権威に従うとする「伝統的支配」です。
そして三つ目は、北朝鮮の独裁者のように、英雄的力や模範性に対する非日常的な帰依に基づく「カリスマ的支配」です。
橋下徹に対する反対論者の危惧は「カリスマ的支配」にあるといえます。大事なことは、人々が支配の根拠に自覚的になることです。
さて、このへんで最初の問いに戻りたいと思います。はたして橋下徹の政治手法は民主主義なのかどうか、という話です。
ハシズムは「民主主義の健全さと危うさの象徴」
ハシズムの本質について再度検討してみましょう。
橋下徹が台頭してきた過程を振り返ってみますと、当選こそタレント弁護士としての人気によるものといえますが、府知事や市長への就任後は、明らかに既得権益と闘う姿勢、そして実行力への評価によるものといえます。
しかも彼の場合は、説明責任をしっかりと果たすことで、有権者をきちんと納得させています。その意味で、表面的には独裁に見えるかもしれませんが、声なき声を率先して代弁し、それが民意であることを政敵だけでなく、民衆自身に納得させるプロセスを踏んでいるのです。いかにも弱者の代弁者である弁護士的手法といえます。
この手法は、政党の綱領ともいえる「維新八策」の策定過程にも明確に表れています。橋下氏はこれを発表するに当たって、数度の段階を踏みました。一気に最終案を発表するのではなく、世論の反応を見ながら修正していったのです。
これを「したたか」と評する人もいます。もちろんそういう見方もできるわけですが、民主主義のプロセスという視点からするならば、民意を反映して綱領を作り上げるというお手本のようなやり方です。今の時点では別にパブリック・コメントのようなものを広く募ったわけではありませんが、橋下氏はツイッターなどのSNSにも敏感に反応しています。形骸化したパブコメより、よほど民意を反映しているともいえるわけです。
維新八策に掲げられた道州制の導入や首相公選制という制度は、民意反映のためのわかりやすい政策だといえます。道州制が導入されれば、市町村といった規模の小さい自治体の役割がますます重要になります。とりもなおさず、それは民意を反映した政治を重視するところに帰結するのです。首相公選制も、より直接的に民意を受けたリーダーが国を統治するための制度です。
したがって、これまで論じてきたことを前提にするならば、ハシズムが民主主義となるのも本物のファシズムと化してしまうのも、私たち国民次第なのではないでしょうか。現段階ではハシズムは「民主主義の健全さと危うさの象徴」であることは間違いありません。
つまり、既存の勢力がダメだから、既得権益のない実行力のある新勢力に取り換えるという点では民主主義の健全さが表れているわけですが、他方でカリスマを強く求めるというポピュリズム的な側面は危ういわけです。したがって、市民の政治参加によって、この危うさをどれだけ克服できるかがカギになってくると思います。ハシズムは、そのためのチャネルをきちんと開いているといえます。
言い換えるなら、今政治には民主主義を機能させるための「志」が、求められているといってもいいのではないでしょうか。
結論
国民の政治参加の度合いが、ハシズムを民主主義の希望にもすれば本物のファシズムにもしてしまう。だから彼らの動きに注視し、ツイッターでも何でもいいから、どんどん提言していくことが重要。
第2章 どうする安全保障!いつまでアメリカに守られるつもり?
日本は独立国か? 植民地か?
ある日突然、北朝鮮が攻めてきたとしましょう。「大丈夫だ。こっちにはアメリカがついているんだ」。そう思うでしょうか? でもアメリカは、中国の顔色を気にして積極的に助けようとしてくれないかもしれません。「おい、話が違うじゃないか」といいたいところですが、いくら叫んでも後の祭りです。
外交とは冷たいものです。その時々の国益を天秤にかけて、なんだかんだ理屈をつけられてしまえばもうおしまいです。
2012年5月1日、日本政府は民主党政権となって以来、初の首相の公式訪米を実現しました。そして、オバマ大統領とともに共同声明を発表したのです。
その内容は、大きく分けると二つ。一つは、日米の安全保障を強化するというもの。もう一つは、経済面での連携を強化するというものでした。具体的には、後者はTPPへの日本の参加を求めるものであり、これについては章を改めて考えたいと思います。まず本章では、安全保障を中心に見ていきましょう。
日本は外交が下手だといわれます。それが如実に表れているのが、安全保障における日本の現状です。よく指摘されるように、戦後半世紀以上がたつにもかかわらず、外国の軍隊に占領されているような国はほかに例を見ません。これではまるでアメリカの植民地です。
普通であれば、外交交渉によって兵を引き揚げてもらうことになるはずです。それができていないのですから、外交が下手だといわれても仕方ないでしょう。もちろん、憲法9条があるため、米軍が引き揚げた後の軍事的対応を自前でまかなうことができないという裏事情もあります。しかし、それもまた独立国家としては大問題なわけです。
自前で防衛できないので、他国の占領を認めざるを得ない。それによって苦しみを甘受する。なんともみじめです。
また自らの国益を最優先する他国に防衛を委ねるのは、不安でもあります。さらに、「思いやり予算」のように基地の面倒を見ていると、経済的にも損失を被ります。
今回の共同声明では、たしかに日本も安全保障に責任と役割を果たすことが確認されました。しかしそれは、国内の財政事情から、東アジアでの軍備を縮小せざるを得ないアメリカの要求によるものです。決して日本がイニシアチブをとって、沖縄からの兵の撤退を促進したわけではないのです。
結果的には、沖縄の部隊はグアム島に移転することになりました。そして、日本はその分、抑止力として海域の警戒態勢を強化することになったのです。
とはいえ、米軍の保護下にある状況には変わりがありません。アメリカの台所事情が火の車なので、一部役割を押し付けられただけの話です。保護者としてのアメリカと、被保護者としての日本という関係は、本質的には同じままなのです。
奇しくも今年は沖縄の本土復帰40年に当たります。もうこれ以上、沖縄の苦しみを放置するわけにはいかないはずです。オスプレイのように得体の知れない軍用機に怯え続けるわけにはいかないのです。
さて、私たちはいったいどうすればいいのか? このままアメリカに頼りきっていていいものかどうか?
賛成論は、これまで通り対米従属を主張します。野田内閣で、民間人から初の防衛大臣に抜擢された森本敏は、ばりばりの親米保守、つまり日米同盟を最優先する対米従属支持者です。そのほかにも、テレビによく出ている人でいうと、評論家の寺島実郎や慶応大学教授の竹中平蔵あたりが親米保守です。
これに対して、反対論は自主防衛、つまり自前で防衛を行い、自立すべきと主張します。反米保守と呼ばれる人たちです。身近なところでは、漫画家の小林よしのりや評論家の西部邁、最近ではTPP亡国論の中野剛志などを思い浮かべてもらえばいいでしょう。
論点安全保障はアメリカに頼り切っていていいのか?
賛成論:アメリカに頼るのがいちばんだ。
アメリカはきっと日本を守ってくれる。
反対論:アメリカが最後まで守ってくれるとは限らない。
自分の国は自分で守るべきだ。
そもそも「自主防衛」とはどういうことか
賛成論のいう対米従属は、現在の日本の状況ですから、先ほど述べたように沖縄の基地の負担をはじめ、半世紀以上にわたる外国軍の占領状態が問題です。また常にアメリカの顔色をうかがわなければならないという問題もあります。
ただ、だからといって反対論のいう自主防衛を掲げればそれでいいかというと、それもまた問題があるのです。
まずは、そもそも自主防衛策を取るということはどういうことなのか、よく考えてみる必要があります。その際参考にすべきなのは、やはり自前の防衛力で世界を牛耳るアメリカのシステムだといえます。そのメリット・デメリットを含め、彼らの安全保障に対する思想にまでさかのぼって考えてみたいと思います。
2011年夏、アメリカ社会は歓喜に沸きました。アメリカの特殊部隊によって、ビンラディンが殺害されたのです。9・11のあの同時多発テロの首謀者とされていた人物です。さらに秋には、リビアの狂犬といわれたカダフィ大佐もアメリカの軍事介入もあって殺害されました。こうしてアメリカは、次々とテロリストや独裁者を追い詰めていく印象を世界に植え付けることに成功したのです。
本当にビビっているかどうかは別として、残る世界の独裁者たちはこれで震えているはずだというようなメディアの論調が、全世界を駆け巡りました。しかし、このアメリカの執拗なまでの狂気は、独裁者よりも世界中の普通の人たちを改めてビビらせる結果になったのではないでしょうか。
たしかにアメリカは、国防費削減のため2011年末にはイラクから完全撤退しましたし、2013年にはアフガンでの戦闘任務を終了することを発表しています。
しかし他方で、新たにイランとの戦争を画策したり、歴史を見てもこの国が戦争にかかわらなかった時期はほとんどありません。
アメリカの新聞を見ていると、毎日必ず戦争の記事があり、街を歩けば軍服を着た人に出くわします。そして人々は彼らに「サンキュー・フォー・ユア・サービス(お勤めごくろうさまです)」と声をかけるのです。この国では戦争は日常の一光景なのです。はたしてこの光景はいつまで続くのでしょうか……。
これからオバマ政権はどういう姿勢で外交に臨み、戦争をしていこうと考えているのか。外交のトップであるヒラリー・クリントン国務長官の発言から探ってみたいと思います。次のやりとりは、タイム誌(2011年11月7日号)におけるインタビューの抜粋です。
「スマートパワー」というのは、オバマ政権がとる対外政策の名称です。軍事力や経済力の圧力のみに頼るハードパワーに加え、文化や技術による国際協力を総合した新しい対外政策のことを指しています。
滑稽なことに、ヒラリーはいつも大事な場面でiPhoneを見ている写真が提供されます。スマートパワーのイメージ戦略なのでしょうか。
たしかにやり方はいかにもスマートで知的なイメージはしますが、やっていることは同じです。リビアの反体制派をうまく取り込み、自分好みの政権をつくろうとしているのです。民主的で、貿易のしやすい政権を。
アメリカはこの成功例がモデルとなることを望んでいます。そしていずれは最大のライバルである中国でさえも、ターゲットになりかねないことを示唆しているのです。
「民主主義による暴力」という皮肉
そんなアメリカの外交政策をずばり政治思想としていい当てているのが、「21世紀のウィルソン主義」。これはウッドロー・ウィルソンスクールを擁するプリンストン大学のアン・マリー・スローターらが唱える概念です。
ウッドロー・ウィルソンというのは、ご存じアメリカの大統領で、国際連盟の提唱者でもあります。そのウィルソンがもともとはプリンストン大学の教授で、総長まで務めたことは日本ではあまり知られていません。そうしたこともあって、プリンストン大学には公共政策専門の大学院であるウッドロー・ウィルソンスクールがあるのです。
では、21世紀のウィルソン主義とは何なのでしょうか。
まずそもそもウィルソン主義とは何だったかというところから説明する必要があります。これは孤立主義を意味するモンロー主義に対抗する考え方で、民主主義を広めるために積極的に諸外国に対して働きかけていく方針のことです。
スローターもこのウィルソン主義を継承しているわけですが、21世紀においては異なる文脈でとらえる必要があると主張します。
一言でいうなら、「ウッドロー・ウィルソンは個人の権利ではなく、国家の権利の時代を生きていた」という違いです。
つまり、21世紀の今も20世紀同様、民主主義のために安全が求められるわけですが、その理由が異なるのです。
ウィルソンは「帝国主義者の侵略を止めるため」に、そして「各国に自分たちで運命を決めさせるため」に集団的かかわりを求めたのに対して、21世紀のアメリカは「よりよい経済と社会の状態を創出するため」に集団的かかわりを求めているといいます。個人の権利を守るために政府の責任強化を促すとの発想からです。
実はスローターはオバマ政権のブレーンであり、ヒラリー・クリントン国務長官のもとで、政策企画本部長も務めてきた人物です。したがって、彼女の政策がオバマ政権の唱えるスマートパワーに反映されているのは明らかなのです。
たしかにアメリカは政権が変われば、ガラッと政策が変わるものです。何しろワシントンの住人がごっそり入れ換わるほどの大転換があるのですから。
ところが、不思議なことに外交に関する基本的な考え方だけは、政党が違ったり、時代が違ったりしても、まるでアメリカを貫く太い幹のように揺らぐことはありません。
たとえば共和党のブッシュ政権で国務長官を務めたコンドリーザ・ライスや、かつてニクソン政権で国務長官を務めたヘンリー・キッシンジャーらも、同じような発想をしています。
つまり、アメリカの民主主義は、この点では満場一致なのです。
もちろん個別の戦争に反対であったり、早期撤退を求めることはあります。しかし、民主主義のための闘いそのものに反対する国民はいません。これはもうDNAといっても過言ではないでしょう。
そもそもこの国には、先住民と戦いながら、荒野を開拓することで形成されてきたという歴史があります。その際、平和を守るために闘う保安官という存在が不可欠でした。だから保安官の存在意義と不可欠性が、身体の隅から隅に至るまでしみついているわけです。
地球が一つになった今、中東の国であろうとアジアの国であろうと、非民主主義的な国家は皆、彼らの平和を脅かす「敵」です。だから保安官が必要なのです。
また、もともと民主主義という原理は、話し合いによって味方の数を増やすことを本質としているわけですが、外交の現実においては、戦争という名の暴力によって味方の数を増やす結果になってしまっています。
しかもその戦争は、アメリカの民主主義によってもたらされた結果だというのですから、まったく皮肉な話です。
日本は「アジアの駐在さん」になるのか
日本は今のところ、少なくとも表向きは憲法第9条の平和主義を堅持し、専守防衛に徹しています。イラク戦争での後方支援のような、グレーな活動もあるわけですが。
しかし、国民投票法が成立し、憲法改正が可能となった今、いつ軍隊を持つことになってもおかしくないわけです。
ましてアメリカと同盟を結び、事実、その属国として基地を提供しているような有様です。朝鮮有事に巻き込まれ、ひとたび剣を抜くようなことがあれば、もう二度と後には引けなくなってしまうのは目に見えています。
一番の理由はアメリカを見てもわかるように、ひとたび軍需産業が誕生すると、そこに既得権益が生じ、それが政治と太いパイプをもった時点で永久機関と化してしまうことです。資本主義が民主主義を圧倒する、いつものアメリカ病のパターンです。
アメリカでは戦争は有望な産業です。支持率回復のためだけでなく、景気高揚のために戦争が利用されることもあります。人殺しが政治や経済に利用されるような、そんな非人間的なメカニズムに組み込まれてしまってはいけません。
外交はあくまで平和的手段をもってなされる必要があります。どうしても武力が必要な時は、国連を通じて国際社会の総意としてなされるべきです。間違ってもアジアの保安官、いや駐在さんになってしまってはいけません。
時代が閉塞し、嫌韓流に見られるように社会が右傾化する今だからこそ、私たちはアメリカを反面教師にしなければならないのです。親米保守はただの思考停止、反米保守は啓蒙不足による短絡的な発想で、どっちも話になりません。
だいたい親米保守も反米保守も、平和を諦めている時点で、思想としては二流といわざるを得ません。一流の思想とは、平和という人間にしかなしえない理想を追求することにほかなりません。
だからといって、ガンジーのように非暴力不服従を貫けとまではいいません。そうではなくて、かつてあのイマヌエル・カントが『永遠平和のために』で提唱したように、国家の常備軍を廃止し、国際的な枠組みで平和を樹立する方向を模索すべきだと思うのです。
親米保守でも反米保守でもダメ……ではどうするか?
すでに見てきたように、賛成論のいう対米従属では、いつまでたっても基地の負担問題を解決することができません。かといって、反対論のいう自主防衛には相当のリスクが伴うことがわかりました。
そこでカントにならって私が提言したいのは「国連主導の安全保障体制に参加する」という道です。
これについては、現在でも日本は国連加盟国であり、経済的には世界第二位の貢献をしているという見方があります。そして、国連の軍隊が活動する際には、当然日本もそれに貢献していると考えるわけです。
しかし実際には、本来予定されている国連軍が組織されたことはなく、あくまで有志による多国籍軍が自発的に世界の紛争に首を突っ込んでいるにすぎません。日本もアメリカに頼まれ、いつも無理やり賛同しているのです。時には後方支援も行っています。
これは私のいう国連主導の安全保障体制とは程遠いものです。私が求めるのは、全加盟国によって組織される本来の国連軍を「常設する」ことであり、そこへの日本国の参加なのです。
本来の国連軍設置については、国連憲章の中で直接明記されているわけではありませんが、安全保障理事会の権限を定めた憲章の第42条から帰結するものです。つまり、42条において、安全保障理事会は、「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる」と定めています。
これに基づき、加盟国との特別協定によって各国が安全保障理事会に提供した軍隊から編成される国際的な軍隊をいうわけです。これまでも国連軍という名の軍隊が組織されたことはありますが、それは正規のものではなく、通称として多国籍軍がそのように呼ばれているだけです。
日本がこうした軍隊に参加することは、憲法9条に反するという反論もあるかもしれません。ただ、日本国として戦争に参加しようという話ではないのです。国連軍は、あくまで国連の指揮のもとに組織されます。したがって、何ら問題ないといえます。ある意味、現在日本が行っている多国籍軍への参加と同じなのです。
私の主張は、それを一歩進めて、本来の国連軍を常設しようというものです。
常にそういう軍隊が編成されていれば、国際的な紛争やテロに対して、即座にかつ安定的に対応することができるからです。安全保障理事会に任せていると、常任理事国が国益を楯に拒否権を発動し、対応が遅れることもしばしばです。
大事なことは、他人ごとのように国連に任せるのではないという点です。日本は国連の常設軍を組織するべく、イニシアチブをとって貢献すべきです。
アメリカの植民地であるみじめな状況から脱し、かつアメリカのように泥沼状態にならぬよう憲法9条の理想を堅持し、それでもなお安全保障上の心配を払拭するためには、この方法しかありません。
それこそ針の穴を通すような困難な外交交渉を迫られるわけですが、これはどんな苦労をしてでもやり遂げる価値のある交渉です。
私たちも、単に牧歌的に平和主義の理想をうたうだけではいけません。反対に、思考停止してやけくそになって右傾化するのでもいけません。そうではなくて、知恵とエネルギーを総動員し、国連軍常設のための外交交渉に尽力すべきです。
そのために、私たちでもできることがあります。
それは、国際世論を喚起することです。
幸い今は、ツイッターやフェイスブックというツールがあります。これは世界中の人たちが手にすることができる、平和のための武器だといってもいいでしょう。この武器を使って蜂起するのです。
国連軍の常設は、日本だけが動いても始まりません。日本発で、世界中の平和を愛する人たちが声を上げるよう働きかけるのです。
環境分野で実際に起こり始めているように、今はこうした地球市民の声を無視して外交を進めることは不可能になっています。環境問題の国際会議では、むしろNPOが会議を主導し、政府がその意向に追随しているほどです。
今後、安全保障でもそうした動きが加速していくに違いありません。日本を独立国家にするのは、いや、世界平和をもたらすのは、政治家でも外交官でもなく、私たち自身なのです。
結論
親米保守の思考停止と反米保守の短絡的な発想を超えて、日本のイニシアチブによって常設の国連軍を創り、国連が主導する新しい安全保障体制に参加するべき。