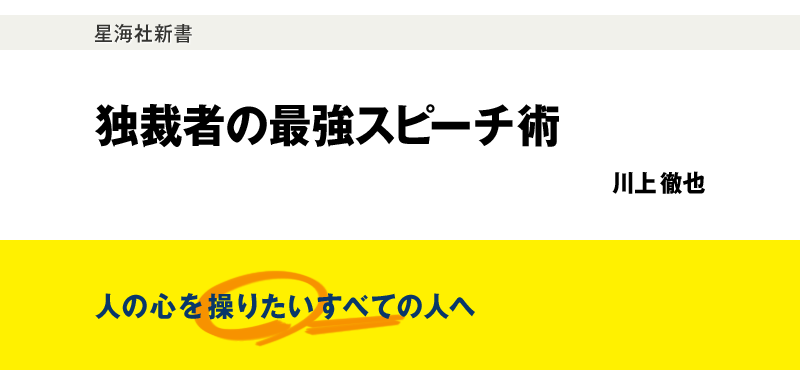
独裁者の最強スピーチ術
川上徹也
人の心を操りたいすべての人へ 本書は独裁者に学ぶスピーチ術の本である。ただ、スピーチのみならず、人の心を動かしたい人にとっては非常に有効な人心掌握術の本でもある。独裁者は、なぜ「言葉だけ」で世界を動かすことができるのか? 悪名高い独裁者であるヒトラー。そして現代日本で「独裁者」と呼ばれている橋下徹。この二人の演説を中心に、ストーリーブランディングの第一人者である著者が徹底分析。多くの人を行動に導く秘技をあぶり出す。優れた演説に共通する「人を動かすストーリーの黄金律」とは何か。「人を動かすための武器」をここに授けよう。
本書ノ悪用ヲ禁ズ
但 書
- 一、本書は、とりあげる政治家の具体的な政策や思想信条の是非を問うものではない。あくまで目的は、彼らの演説やスピーチにおけるストーリーテリングのテクニックを分析し、そのエッセンスを読者に伝えることにある。
- 二、本書では、英語のspeechの訳語が「演説」であることから、両者を同じものとして記述することも多いが、演説=広く国民や民衆に対してするもの、スピーチ=閉じられた空間で特定の集団に対してするもの、と分けて記述する場合もある。
- 三、取り上げる演説やスピーチは、断片でなく、できるだけ始まりから終わりまでを通して取り上げた。ページ数や現存している資料などの関係で略しているものもあるが、それでもできるだけ文脈をそこなわない取り上げ方をしている。そうしないと、ストーリーテリングのテクニックを理解してもらえないからだ。ぜひ演説部分を飛ばさずに読み進めていただきたい。
- 四、演説部分ではポイントとなる部分を強調してある。
これは演説者の声の大小などを表すものではない。 - 五、本書で取り上げる政治家の方々の敬称は略させていただいた。
はじめに 独裁者は演説を武器にする
「独裁者」と聞いて、あなたは誰を思い浮かべるだろうか。
おそらく多くの人が真っ先に思い浮かべるのがアドルフ・ヒトラー、その人であろう。何万人もの大衆の前で、激しい口調と身振り手振りを使って演説する姿を、テレビなどで一度は見たことがあるのではないだろうか。
そして今日、良くも悪くも「独裁者」として有名になった政治家がいる。大阪維新の会の橋下徹である。
橋下は「言葉の力」を駆使して、2012年4月現在、日本で一番注目される政治家となったといえるだろう。演説、スピーチ、記者会見での言葉の使い方、どれをとっても、今、日本の政治家で群をぬくうまさだ(唯一対抗できる可能性を感じるのは、自民党の衆議院議員、小泉進次郎だけだ)。
「橋下は独裁者」というイメージが強まったのは、2011年6月29日、自らの後援会のパーティで、当時大阪府知事だった氏が放ったこの言葉だ。
「今の日本の政治に必要なのは独裁ですよ」
前後の文脈があってのフレーズだったが、「独裁」を支持するとも取れるこの発言はマスコミや反橋下陣営からは格好の餌食にされた。橋下に「独裁者」というレッテルを貼りバッシングを浴びせた。ファシズムをもじった「ハシズム」などという言葉まで生まれた。
悪人のイメージを植え付けるこの「失言」は当時、致命的だと思われた。しかし、橋下は、そのようなバッシングを言葉の力ではねかえすことになる。
大阪府と大阪市の二重行政を批判していた橋下は、任期途中で大阪府知事を辞職。同年11月に実施される大阪市長選挙に立候補。既存政党のほとんどは反橋下で結束し、現職の平松市長は「大阪市を一人の独裁者の自由にさせてはならない」と声を張り上げた。
しかし結果は、ご存知の通り、橋下の完全勝利。同時におこなわれた大阪府知事選挙でも、それまでほぼ無名であった大阪維新の会幹事長の松井一郎氏が圧勝した。
ではこの結果は、大阪市民が橋下の政策を選んだからなのか?
そうではない、と筆者は考える。
大阪市民が選んだのは、橋下の「言葉」であり「情熱」であり「ストーリー」だ。
橋下は巧みな演説やスピーチで、聴衆の心をつかんだのだ。
「独裁」という悪人のイメージをも覆してしまうほど橋下の描いたストーリーの力は強かったと言えるだろう。
橋下徹が好んで使う「ストーリーの黄金律」
橋下の演説やスピーチを分析してみるとある事実が浮かび上がってくる。それは、橋下が感動のツボを押す法則を巧妙に使っているということだ。
その法則を本書では「ストーリーの黄金律」と呼ぶことにする。
この「ストーリーの黄金律」は私がコピーライターやストーリーブランディングを手がける中で発見したもので、演説に限らず多くの「人を動かす」コンテンツに使われている。
人間はストーリーが大好きな動物だ。文字が発明される以前から、ストーリーを語り続けてきた。世界中のどの民族にも、語り継がれてきた神話や民話がある。それはストーリーという形式が、人間の記憶に残りやすく、心を動かすことを知っていたからだ。
人間は他の動物と違い、コミュニケーションを取りながら、他の人々と協力し合いながら生きている。よって物事を効率良く、記憶に残るように伝達していかなければならない。その際にストーリーという道具は大いに力を発揮してきたのである。
そうしたストーリーの中でも、より人を惹きつけ、行動に導く、ストーリーの「型」がある。それが「ストーリーの黄金律」である。
この黄金律とはどういうものなのかは、第二章で詳しく述べることにする。
あらゆるカリスマも黄金律を知っていた!?
この「ストーリーの黄金律」をうまく使っているのは橋下だけではない。
カリスマと呼ばれるような政治的リーダーは、必ずと言っていいほど、この黄金律を演説に取り入れて民衆の心をつかんでいる。
F・ルーズベルト、J・F・ケネディ、ジョージ・W・ブッシュ、バラク・オバマ、田中角栄、小泉純一郎……。
彼らはみんな、この黄金律を使って大衆の心を大きく動かした。
黄金律こそが、人の感情を揺さぶる一番有効な方法だと知っているからだ。
ルーズベルトは黄金律を使った就任演説で、大恐慌で絶望していた国民に希望を与えた。
僅差で大統領選挙に勝利したケネディも、黄金律を使った就任演説で国民からの圧倒的な支持を得た。
ブッシュは最低支持率の大統領から、黄金律を使った演説で90%の支持率を得た。
オバマは黄金律を使った演説で無名の上院議員候補から大統領まで上り詰めた。
田中角栄は黄金律を使って、2度のロッキード選挙で信じられないほど大量に得票した。
小泉純一郎は完璧ともいえるような黄金律を使った演説で、自民党を歴史的大勝利へと導いた。
最近では、野田佳彦が2011年の民主党代表選挙の最終演説(いわゆる「どじょう演説」)で、この黄金律を使って逆転勝利し、総理大臣の座を射止めた。
タブー視されていた「あの独裁者」の演説を分析する
筆者は以前、『あの演説はなぜ人を動かしたのか』(PHP新書)という著書の中で、歴史を動かした政治家たちの有名な演説が、いかに黄金律に沿って構成されているかを分析・解説した。
ただその本では、本来であれば取り上げるべきなのに、ある理由で取り上げることができなかった有名な政治家がひとりいた。
その男は、演説で、世界の歴史を大きく変えた。
彼の名はアドルフ・ヒトラー。
悪名高いあの独裁者ヒトラーだ。
彼こそが、人類の歴史上、最大の黄金律の使い手だ、と言っても過言ではない。
しかしヒトラーの演説を取り上げると、たとえそういう意図がなくても、礼賛しているようにとらえられてしまうのでは、という当時の編集者の危惧もあり、結局取り上げないことにした。
そこで本書では、本物の独裁者であるアドルフ・ヒトラーと、アンチも含め今日本で一
番国民の心をつかんでいる政治家、橋下徹の2人を中心に、演説やスピーチを取り上げ分
析していくことにする。
ヒトラーと橋下のスピーチ術を比べる意味
ヒトラーの最大の武器は「言葉」であり「演説」だった。
「演説」の力で独裁者になったといっても過言ではない。
同じように「言葉」と「演説」を武器にして注目を集めるのが橋下徹だ。
四章で取り上げる橋下の演説を読んでいただければわかるが、彼の演説のうまさは日本の政治家では群を抜いている。
橋下がヒトラーのような独裁者となる心配は、現実的に必要なものなのか、まったくの杞憂なのか、いったいどちらが正しいのだろう。
それを判断するためには、まず本物の独裁者ヒトラーがどのような過程で権力を掌握したのか、また最大の武器となった演説はどのようなものであったかを具体的に知った上で、橋下と比較する必要がある。
橋下自身も、2012年3月18日付のツイッターで
「(独裁の懸念に対して)ヒトラー独裁のときの統治機構・メディアの情況と今のそれを比較して独裁云々を論じなければならない。今の統治機構において権力は完全な任期制。そして公正な選挙で権力は作られる。これだけでいわゆる独裁は無理。さらに何と言ってもメディアの存在。日本においてメディアの力で権力は倒される」
とツイートしている。
しかしなんとなく映像では見たことはあっても、具体的にヒトラーの演説の内容がどんなものだったかを知る人は少ないだろう。
そこで本書では以下のような構成で、ヒトラーと橋下の演説やスピーチ術を比較検討していこうと思う。
一章〜三章では、ヒトラーがどのような経緯で合法的に独裁者になることができたのか。また彼が得意とした演説やスピーチの内容やテクニックとはどのようなものであったかを紹介していく。
四章五章では、橋下の演説やスピーチの内容やテクニックを取り上げる。
そうやって二人を比べることによって、共通点と相違点が、明らかになってくるはずだ。
その上で、現在の社会情勢などを勘案し、橋下が本当の独裁者になる恐れがあるのか、現実的に心配すべきことなのか、まったくの杞憂なのかは、読者に判断してもらいたい。
劇薬である「黄金律」は毒にも薬にもなる
ヒトラーと橋下徹、この二人に共通しているのは、どちらも見事なまでに黄金律にそった演説・スピーチで、民衆の心をグッとつかんでいるという点だ。並べて取り上げるのは、橋下がヒトラーのような独裁者になると言いたいわけではない。
黄金律の「薬」の部分と「毒」の部分をわかってもらうためだ。
ヒトラーは結果として「毒」になった。
橋下はまだ現段階では判断できない。
できれば「薬」の部分だけをうまく使ってほしい。この黄金律には、「薬」の部分と「毒」の部分がある。人の心をグッとつかみ動かす特効薬でもあると同時に、猛毒になる危険性もある両刃の剣なのだ。
よきリーダーが使えば、応援をうけながらいい政策が実行できる。悪しきリーダーが使えば、取り返しのつかない道に突き進んでしまうかもしれない。
天使の使い方もできるし、悪魔の使い方もできる。白魔術にもなるし、黒魔術にもなる。使い方や使う人によって結果は大きく違ってくるのだ。
薬の部分は、色々な場面に応用できる。
もちろん、ビジネスにおいても大きな武器になる。人の心をうまくつかみ動かすことができるからだ。会社や社会でリーダーシップを発揮したり、みんなから応援してもらうようになるためには、とても有効なテクニックになるだろう。
あなたには黄金律の「薬」の部分をぜひご自分のビジネスに応用してもらいたい。
もちろん毒の部分だって使おうと思えば使える。しかし絶対に悪用しないでいただきたい。逆に、誰かが、その「毒」の部分を使おうとしている時に気づいてほしいのだ。
黄金律の内容を知っていれば、簡単には騙されたり煽られたりしないはずだ。
「独裁者」と「カリスマ」は紙一重。カリスマ性があり決断力のあるリーダーが、ある程度、独裁者の側面を持つのは、政治の世界だけでない。むしろ実業界においての方がわかりやすいかもしれない。
2011年に亡くなったスティーブ・ジョブズは、カリスマ性はあったが、一方独裁者としても有名であった。
本書で紹介する演説・スピーチのテクニックを、各自咀嚼して、ビジネスや生活における「正しい武器」にして使ってもらえればうれしい。
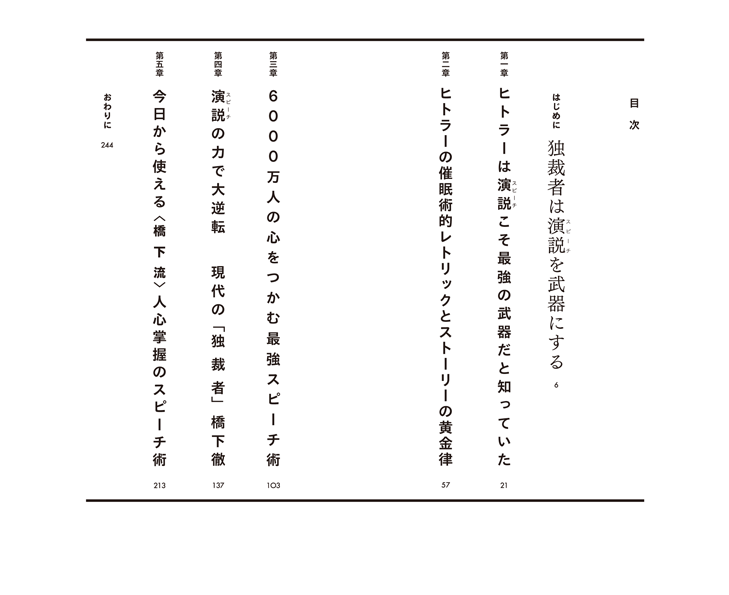
第一章 ヒトラーは演説こそ最強の武器だと知っていた
今日、文筆にたずさわる騎士やうぬぼれ屋はみんな、
次のことをよく覚えておくがいい。
すなわちこの世界における最も偉大な革命は、決してガチョウの羽ペンで導かれたものでないのだ!ということを。
そうだ。ペンにはつねに革命を理論的に基礎づけることだけが残されている。
だが、宗教的、政治的方法での偉大な歴史的なだれを起した力は、永遠の昔から語られることばの魔力だけだった。
おおぜいの民衆はなによりもまず、つねに演説の力のみが土台となっている。
そして偉大な運動はすべて大衆運動であり、人間的情熱と精神的感受性の火山の爆発であり、困窮の残忍な女神によって扇動されたか、大衆のもとに投げこまれたことばの放火用たいまつによってかきたてられたからであり、美を論ずる文士やサロンの英雄のレモン水のような心情吐露によってではないのである。
『わが闘争』(アドルフ・ヒトラー 平野一郎・将積茂訳)より
他の独裁者とヒトラーはどこが違うのか?
歴史上「独裁者」と呼ばれた人物は多い。
思いつくままあげてみると、スターリン、ムッソリーニ、毛沢東、金日成、ポル・ポト、カストロ、フセイン、カダフィなどだ。
独裁者はカリスマでもある。
何らかのカリスマ性がないと独裁者にはなれない(世襲で独裁者になるような例外もあるが)。先にあげた独裁者たちにもいずれも何らかのカリスマ性もあった。
そんな中でも際立ったカリスマ性を持っていた独裁者といえば、アドルフ・ヒトラーだ。
ヒトラーは、権力を掌握した方法が他の独裁者とは決定的に違う。
他の独裁者たちは民主主義のルールの下に選ばれたのではない。革命・クーデター・他国の傀儡、成り立ちは違うが、共通しているのは何らかの軍事力を背景に政権を掌握したということだ。
一方、ヒトラーは少なくとも表面的には「合法的」に政権を獲得し、独裁を手に入れた。
民主的に生まれた独裁者、ヒトラー
ヒトラーやナチスといえば、親衛隊、ホロコーストによるユダヤ人大虐殺、ヨーロッパ各国への軍事侵攻など暴力的なイメージを思い浮かべる。それゆえ政権奪取にも武力を使用した、暴力的なクーデターだったのではないかと誤解している人も多いのではないだろうか。
実際はそうではない。ナチスは、当時最も理想的な憲法を持っていた民主国家ワイマール共和国で、「民主的」「合法的」に政権を奪取したのだ(ナチスには政権を取る前にも突撃隊と呼ばれる武力組織があり、その威嚇行為などはあったにせよ)。
また政権奪取は数年で達成できたことではない。
ヒトラーがナチスこと国家社会主義ドイツ労働者党の党首になったのが1921年。そして首相になったのが1933年。政権獲得までには12年以上かかっている。徐々に議会での勢力を伸ばしていったのだ。
10年以上かかったとはいえ、ものすごい勢力の伸ばし方であることは間違いない。特に世界恐慌が始まった1929年からのナチスの台頭はめざましいものがあった。第一次世界大戦の敗戦国であり、ベルサイユ条約で過酷な賠償条件をのまされたドイツは、特に大恐慌の影響が大きかった。街には失業者があふれ、先の見えない圧倒的な閉塞感の中、ヒトラーが語る新しいドイツに希望を見いだす国民が増えていったのだ。
それでも国民の大多数がヒトラーを支持していたわけではない。政権獲得直前の選挙でさえ、ナチスへの投票率は30パーセントあまりしかなかった。
むしろヒトラーやナチスを危険視する声の方が高かったのだ。
そんな状況にもかかわらず、ヒトラーは政権の座につくことに成功し、そこからあっという間に独裁国家をつくりあげていった(形式上は合法的に)。
ヒトラーやナチスは政権奪取後、自らの国家を第三帝国と称した。962年にはじまる神聖ローマ帝国、1871年にビスマルクにより成立したドイツ帝国に次ぐ、ドイツ民族による三度目の帝国という意味である。
ヒトラーが首相に就任した1933年から、第二次世界大戦が終わる1945年まで12年間、第三帝国の独裁政権は続いた。
では、画家志望のさえない青年だったヒトラーが、なぜ絶対的な権力を手に入れ、希有の独裁者になり得たのか、簡単に振り返ってみよう。
演説を武器にして支持者を広めていった
アドルフ・ヒトラーは1889年オーストリア生まれ。
画家になりたくてウィーンの美術アカデミーを受けるも2年連続して不合格。
オーストリア=ハンガリー帝国の兵役を逃れるためにミュンヘンに移住する。翌年、オーストリア当局に逮捕され本国に強制送還されるも、検査で不適格の判定がでたために兵役を免除される。
その後、「大ドイツ主義」という思想にふれ、第一次世界大戦では一転して、オーストリア国籍のままドイツ帝国軍に志願する。伝令兵として活躍し、終戦時の階級は伍長補(正確には上等兵とも)だった。
戦後もミュンヘンで軍に留まって調査活動などに従事していたが、たまたま調査で訪れたドイツ労働者党に入党することになる。
ヒトラーが入党した当時、ドイツ労働者党は、ミュンヘンのビアホールで集会を開いてくだをまくだけの、党員が数十人のほんの小さな政治結社だった(ヒトラー自身は後の演説などで7番目の党員で創立メンバーのひとりだったと主張している)。
党での活動を続ける中、ヒトラーは自身の演説の才能に気づく。
ヒトラー自身の言葉を借りればこうだ。
「私は三十分の演説をした。そして、以前から根拠なくただ内心だけで感じていたことが、現実のこととして証明された。私には演説する力があったのだ」
ヒトラーの繰り出す熱い言葉は、聴衆の心を確実にとらえた。彼の演説めあてに大勢の人が聴きにくるようになった。演説が終わったあと、党への寄付も集まるようになった。30歳にしてヒトラーは自分の天職をみつけたのだ。
やがて党名は国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)に改名され、集会ではほとんどヒトラーが演説するようになった。
演説はドイツ各地でおこなわれるようになり、観衆の数もどんどん増えていった。聴衆はヒトラー主演の舞台を観にいくような感覚だった。
演説の内容はほとんど同じ。ベルサイユ条約とワイマール共和国への不満、敗戦の失望感や屈辱、経済的な困窮、知識人層やユダヤ人への憎悪などを怒りをもって表現し口汚く罵るのだ。
当時のドイツは、第一次世界大戦の敗戦の影響が色濃く残っていた。戦勝国(特にフランス)の「ドイツいじめ」は露骨だった。屈辱的なベルサイユ条約を結ばされ莫大な賠償金を支払うことになり、軍隊も厳しく制限されていた。国内は大不況の嵐がおしよせ、国民の生活は苦しく、失業者が街にあふれだした。
そんな中、戦争に負けたのは、共産主義者とユダヤ人の裏切りがあったからだという噂が広まっていた。富裕層にユダヤ人が多いことも、一般大衆にとってはやり場のない憤りの原因だった。
一般大衆にとっては、ヒトラーの怒りを帯びた演説が心に響いた。自分が心の奥底で思っていたことを、自分の代わりに言葉にして吐き出してくれるからだ。
ヒトラーほど、当時の一般大衆の不満や怒りや希望をいち早く見つけ、それを熱い言葉にして肯定してくれる政治家はいなかった。またヒトラーには、複雑な問題をわかりやすいスローガンにしてひと言で表現する才能もあった。
ヒトラーの演説は2時間以上になることも多く、その言葉は下品で乱暴であったが、なぜか人をひきつける魅力があったのだ。
こうしてヒトラーは、演説と言葉の力で、一躍党内外から注目される政治家になり、ナチスの党首となった。党員の数も飛躍的に増えていった。
絶体絶命のピンチを救った渾身のスピーチ
ヒトラーが34歳の時、彼の人生における大きな挫折であり、その政治家人生の一大転機となる事件が起こる。
ミュンヘン一揆だ。ヒトラーは考え方を同じくする同志たちと、ワイマール共和国転覆を目指してクーデターを企てたのだ。
この事件は死者14名を出したが未遂におわり、ヒトラーは反逆罪で逮捕され、ナチスの活動も禁止されることになった。
ヒトラーの政治生命も絶たれたと思われた。実際、新聞にはそのような報道が躍った。だが、ここでも彼の言葉の力が自身を助けたのだ。
国民法廷の被告席での最終弁論で、ヒトラーは渾身のスピーチをする。その内容は以下のようなものだった。
「責任はわたしひとりで負う。だがわたしは犯罪者ではない。(中略)
わたしが反逆罪を犯すわけがない。一九一八年の売国に抵抗する行為に、反逆など存在しない。(中略)
何千回でも有罪判決をくだすがいい。歴史という永遠の法廷をつかさどる女神が、起訴状と判決とを笑って破り捨ててくださるだろう。
女神はわれらを無罪だとおっしゃっているのだから」
『アドルフ・ヒトラー 五つの肖像』(グイノ・クノップ 高木玲訳)より
このスピーチでヒトラーは、傍聴人から大喝采をうけ、一躍英雄となった。裁判官からも強い共感を得て、反逆罪としては非常に軽い禁錮5年の判決が下った。刑務所内でも英雄扱いの特別待遇だった。
ヒトラーはこの期間に著書『わが闘争(Mein Kampf)』を口述筆記する。『わが闘争』は彼の目指す国家社会主義の思想を集大成したものだった。ユダヤ人問題、共産主義、人種論など、彼が後の人生で犯す愚行の数々の芽は、すべてこの本の中に書かれてある。
結局ヒトラーは恩赦をうけ、わずか9カ月で釈放される。それとともにナチスの活動も再開が認められたのだった。
民主的に民主政治を破壊しようとした
ミュンヘン一揆で大きな挫折を味わったヒトラーは、出獄以降、憲法にのっとった民主的な手続きを経て合法的に政権を奪取することにした。
ただそれは政権奪取したのちも民主的政治を続けるという意味ではない。
現にヒトラーは自らの演説で「私の究極の目標はドイツ30政党を排除することだ」と述べている。
いわば民主的に、民主政治を破壊しようと試みたのだ。
そのために、ヒトラーは、彼自身が持っていた希有の才能である「スピーチ力」を最大限に生かそうと努力を重ねた。
全身が映る鏡の前で身振りなどを何度も研究し、取り巻き連中に効果的かどうかを尋ねることもよくあった。ヒトラーの演説では、彼自身が興奮のあまりおこなっているように見えるポーズも、ちゃんと計算されたものだったのだ。
また演説が終わった後にも反省会が開かれることもよくあったという。
ナチスに資金援助を続けていたハンフシュテングル家の長男で当時11歳だったエゴンは、ヒトラーが数万人の聴衆を熱狂させた演説をした直後に、部下たちとの反省会の現場にいあわせた時の記憶をこう述べている。
「ヒトラーは鉛筆で(終わったばかりの演説の原稿に)書きこみをしながら独り言を言っていた。『ここはよかった……ここは効果満点だった……ここは削るべきだな……』
彼は生涯で最も感動的な演説をおえてからまだ一時間とたっていなかった。
彼は説教し、懇願し、怒号し、絶叫した。それなのに、そこにいるのはわたしが見たこともないほど冷静で理性的な一人の男だった」
『アドルフ・ヒトラー』(ジョン・トーランド 永井淳訳)より
こうしてさらに磨かれていったヒトラーの「スピーチ力」によって、ナチスは党勢を急速に伸ばしていった。
たった一度のスピーチで選挙資金を獲得
1928年、はじめての国政選挙に挑戦し12人の当選を果たしたナチスは、翌年の世界恐慌により急速に党勢を拡大。30年の総選挙では得票率約18パーセントで107議席を獲得。最小政党から一躍国会第二党へと大躍進をとげる。また地方選挙でも勝利を続け、ナチスはもはや国政で無視できない大勢力となっていた。
同じ頃、急速に台頭してきたのが共産党などの左派勢力だ(30年の総選挙では得票率約13パーセントで第三党)。
1932年はヒトラーにとって、非常に浮き沈みが激しい一年となった。
この年は結局4回の国政選挙がおこなわれることになる。まずは春に予定されていた7年ぶりの大統領選挙。相手は第一次世界大戦の国民的英雄で人気の高い現職のヒンデンブルク。彼はすでに84歳の高齢であった。
ヒトラーは大統領選挙に出馬するのを非常にためらったが、腹心の部下たちは賭けに出るよう強く推した。彼らの最大の問題は選挙資金であった。
この問題も、ヒトラーはたった一度のスピーチで克服する。
このスピーチは、ドイツ鉄鋼業の中心地デュッセルドルフでおこなわれた。相手はドイツ工業クラブの資本家たち300名。最初は冷ややかに聴いていた聴衆たちは途中から完全にヒトラーに惹きつけられた。
ヒトラーはこの演説で「ボルシェヴィズム(ロシア共産主義)を今ここで何とか阻止しなければ、かつてのキリスト教のように世界を覆い尽くし、レーニンはその教祖として崇拝されることになるだろう」と資本家たちを脅した。
そして「ナチスこそが共産党勢力をくい止める唯一の政党だ」と語り、労働組合の廃止や、経営者たちの利益になる政策を準備していることもほのめかした。強いドイツを蘇らせるためには民主主義では不十分であり、独裁者による強いリーダーシップが必要であることも主張した。
この脅しと利益を取り交ぜた巧妙なスピーチは、資本家たちの感情と理性の両面を強く刺激した。結果として莫大な寄付が集まり、最大の懸念であった選挙資金の問題は当面解決した。
飛行機による大々的な遊説
ヒトラーはオーストリア国籍からドイツ国籍を得て、大統領選に出馬した。
「ヒンデンブルクには名誉を。ヒトラーには票を」というスローガンで戦った結果、約30パーセントの票を得て、現職のヒンデンブルク大統領についで二位になる。ただし、一位だったヒンデンブルクも過半数にわずかに及ばす、憲法の規定により上位三名による再選挙となった。
選挙に敗れ消沈している幹部たちとは対照的に、ヒトラーはすぐに選挙演説をはじめた。
「国民社会主義諸君! 党同志諸君! 第一回の選挙戦は終わった。
他のあらゆる政党が一致して総動員をしたにもかかわらず、われわれのプロパガンダに対して当局が激しい抑圧をしたのにもかかわらず、国民社会主義ドイツ労働党はわずか一年半の間に選挙民をほとんど倍加させた。
……われわれは今日異論の余地なくドイツで最強の党にのし上がった。今日から再選挙が開始された。……私がリードしていこう」
『ヒトラー全記録 20645日の軌跡』(阿部良男)より
この決選投票でヒトラーは37パーセント近くまで票を伸ばし存在感をみせつけた。
さらに同年7月におこなわれた総選挙では、ナチスは得票率約37パーセントで608議席中230議席を得て大躍進をとげ第一党になった。
これらの選挙戦で、ヒトラーは資本家たちから集めた豊富な選挙資金をバックに、飛行機による大々的な全国遊説を実行した。他の政党の党首が鉄道でまわっているのに対して、ヒトラーは一瞬にしてどこにでも現れるというカリスマ的なイメージを国民にうえつけた。各地でおびただしい数のビラがまかれポスターが貼られ、遊説先の都市は、ハーケンクロイツ(鉤十字)旗に覆われた。ヒトラーによる大演説会では、数万人規模の聴衆が押し寄せた。
しかし、政権獲得前のナチス、ヒトラーの勢いはこの時点が最高潮だった。
同年11月、パーペン内閣に不信任案が提出され、圧倒的多数で可決されふたたび選挙になった。この選挙で右肩上がりだったナチスの勢いは失速。得票率もダウンし、196議席と第一党は維持したが議席を大幅に減らしたのだ。
この選挙結果は、ナチスの危険性に多くの民衆が気づいたからだと思われた。
「おとぎ話」のような政権獲得劇
1933年は、ヒトラーが政権獲得に成功し、一気に独裁国家の基礎をつくりあげることになる重要な年だ。
しかしその年頭、ナチズムは衰退に向かうだろうというのが一般的な見方だった。
前年11月の総選挙で勢いに陰りがみえ、選挙資金も底をつきかけていた。初の敗北に党員たちの気勢も上がらず、党内にも亀裂がおこりはじめていた。「ヒトラー総統は賞味期限が切れた」「ヒトラー王国の崩壊」などと揶揄する新聞記事も多くみられた。
この時点ではまだ、ドイツ国民の過半数は、ヒトラーやナチスに嫌悪感を抱いていたし、その存在を過小評価していたのだ。
ナチスの幹部たちも、今年は厳しい一年になるだろうと予測していた。
しかしヒトラーだけは、強気を崩さなかった。元日、部下たちとワグナーのオペラを鑑賞したヒトラーは「今年は我々のものになる」と断言したという。
実際、彼の予言通り、その1カ月後ヒトラーは政権を奪取し、数カ月後には独裁体制を合法的に樹立することになる。
当時の首相は、パーペンの後を継いで前年12月3日にその内閣が発足したシュライヒャーだったが、1カ月もたたないうちに早くも政権運営が行き詰まっていた。
ヒンデンブルグ大統領は、誰が首相になっても議会で過半数が取れず機能しない状態にうんざりしていた。
大統領自身は兵卒からの成り上がり者のヒトラーのことを嫌っていたが、安定した政権をつくるためには、議会第一党のヒトラーを連立政権に引き入れざるを得ない状況だったのだ。
ヒンデンブルクをはじめ、保守系の政党は、何とかヒトラーを副首相など閣僚の一員として迎え連立政権を組もうとして画策した。しかしヒトラーは、首相に就任すべきは自分だと主張して譲らなかった。
そんな中、どの政党も注目していなかったリッペ州という地方の議会選挙に、ナチスは総力をあげて取り組み一大キャンペーンをおこなう。
ヒトラーは何度も現地入りし、精力的に演説を実施した。結果は圧勝。
普通の見方をすれば、単なる地方議会での勝利だったが、象徴的な意味合いは大きかった。衰退に向かうとみられていたナチスが勢いを取り戻した瞬間だった。
1月後半、大統領をまじえた保守勢力とヒトラーとの交渉はぎりぎりまで続いた。あくまで強気のヒトラーの態度に交渉は難航した。
そのような状況で、パーペンは政権返り咲きを狙って、ヒンデンブルクにヒトラー首相任命を提言した。大統領もヒトラーを首相に任命せざるを得ないという決断を下す。ヒトラーは、首相の座以外は他党に大幅に譲歩した。ナチスから内閣に入閣したのはフリックとゲーリングのみ。主要ポストは他党に譲った。
こうして、1933年1月30日、ヒトラーはワイマール共和国の首相に任命されたのだ。43歳の時であった。
ヒトラー自身も側近でさえも、直前まで本当に首相に任命されるという確信をもてない中での就任だった。
現に、ヒトラーに忠実な部下で、後に国民啓蒙宣伝大臣になるヨーゼフ・ゲッベルスは「ヒトラーが首相、夢のようだ。まるでおとぎ話だ」と日記に記している。
過小評価されていたヒトラー
こうしてヒトラーは「合法的」に首相になった。
就任式でヒトラーは「私はドイツ国民の幸福を願い、もてる力のすべてを結集し、憲法と法律を遵守し、私に課せられた義務をその良心に従って実行し、いかなる人に対しても公平かつ公正に職務を遂行していく所存です」と大統領の前で誓いの言葉を復唱した。
ナチス政権が誕生したことに危惧を抱いていた勢力も、ヒトラーの穏健な態度にひとまず安心した。
その夜、ベルリンでは、ナチス支持者による大々的なたいまつ行進が実施され、深夜遅くまでお祭り騒ぎのような状態になった。これはゲッベルスのアイデアで、彼はその行進をラジオで実況中継し、さらに盛り上げた。
ゲッベルスはこの夜の興奮を以下のように日記に記している。
「まるで夢のようだ。ヴィレヘルム街(官庁街)は我々のものだ。
総統はすでに首相官邸で仕事をしている。われわれは階上の窓際に立つ。
幾十万の群衆が炎々と燃え盛るかがり火の中に、白髪の共和国大統領と若い首相の前を通り、二人に彼らの感謝と歓喜の声を浴びせる。
国民の出発だ!
ドイツは目覚めたのだ!
自発的爆発となって、国民はドイツの革命を承認したのだ。
我々の胸中に去来するものは筆舌につくせない。泣き笑いしたいくらいだ。
ラジオが初めてドイツ国民の示威を放送する。我々は初めて全てのドイツの放送局を通じて話しかける。僕に言えたのは、ただ、我々はいま非常に幸福であること、我々はさらに働きつづけたいということであった」
『勝利の日記』(ゲッベルス 佐々木能理男訳)より
ただこのような熱狂はナチス支持者のあいだだけでおこったものだ。
ナチスの台頭を危惧する国民の多くはまだまだ事態を楽観していた。
大臣のほとんどは他党員でしめられているし、ナチスが議会で過半数をにぎっているわけでもない。大統領もいる。ヒトラー自身も、ああやって就任式で、共和国の憲法と法律を守ると誓ったではないか。
副首相に収まった元首相のパーペンはヒトラーを取り込んで、自らの政権を強化したぐらいのつもりでいた。2カ月後にはヒトラーを追いやって、自分が実権を握るつもりでいたのだ。共産党などの反対勢力も、ヒトラー政権はどんなに長くても1年2年で消えると予想していた。
ナチス支持者以外の国民の多くは、首相がコロコロと替わる政治体制が日常茶飯事になっていたため、ヒトラー首相就任の意味を重大に考えていなかった。政治への無関心が蔓延していたのだ。
彼らは数カ月後、自分たちの考えが甘かったことを知る。
いずれもヒトラーを過小評価していたのだ。
独裁体制に向けて牙を剝き始める
ヒトラーの行動は早かった。
まずは宿敵、共産党から手をつけた。警察組織を押さえ、共産党を徹底的に弾圧した。政権獲得の日の夜にはドイツ共産党の新聞を発禁処分にし、ナチスと小競り合いになった共産党員をベルリンだけで60名逮捕した。
2月1日、大統領に提案してまたも議会を解散させた。
同日、ヒトラーは、首相就任後はじめてラジオで全国民にむけて施政方針を演説した。そこでは強硬派のイメージを一変させ、猫撫ぜ声ともいえるような柔らかな口調で、穏健的な政策を語った。また大統領に対しては最大級の賛辞を送り、へりくだることも忘れなかった。国民はそんなヒトラーの肉声を直接聞き、安心した。
2月3日、ヒトラーは軍の主要司令官の前で演説する。直接会うまで軍の幹部たちは、ヒトラーのことを軽んじ懐疑的でいた。何しろ相手は元伍長補の成り上がり者だ。また、膨張を続けるナチスの突撃隊が軍を脅かす存在になるのではないかという危惧もあった。
しかしヒトラーの演説を聴くと、軍の司令官たちは態度を一変させた。まさに自分が聴きたい内容が言葉にされていたからだ。それは「軍備増強」であり「軍部の地位向上」であった。また突撃隊についても、軍部を安心させ持ち上げることを忘れなかった。
2月4日、「ドイツ民族保護のための大統領令」が公布される。これによって、デモ・集会・政党機関紙などが規制されることになる。
さらに選挙戦の真っ最中の2月27日、ナチスを独裁に向かわせる決定的な事件がおこる。国会議事堂が何ものかによって放火され炎上したのだ。
ナチスはこの放火事件を共産党の仕業と断定(当時からナチス自身の自作自演説も根強くあったが真相は不明)。共産党が武力蜂起するという噂から非常事態を宣言し、翌朝からブラックリストに載っていた共産党員の一斉逮捕に踏み切った。また実行犯としてオランダ共産党員ファン・ルッペを逮捕して処刑した。
またヒトラーは、翌2月28日に「国民と国家の防衛のために」と名付けられた緊急令を大統領に提出した。
これはワイマール憲法が定める基本的人権や言論の自由等を停止し、政府が国民を自由に逮捕し好きなだけ勾留することを可能にするものだった。いわばワイマール憲法を骨抜きにし、今後12年に及ぶヒトラーの独裁に法的根拠を与えるものであった。
しかしその時点では、共産党の脅威の方に目がいき、多くの人間は独裁体制の始まりに気づかなかった。ヒンデンブルク大統領もこれにあっさり署名した。
この緊急令を根拠に、ナチスは残りの選挙戦で他党を弾圧した。集会の自由を禁じて、機関紙なども発行禁止にした。
一方、財界からは巨額の選挙資金を拠出させ、大がかりな選挙運動を展開した。すべてのラジオ局はナチスの選挙活動だけを専ら放送した。
3月5日の投票日には、ナチスの突撃隊や親衛隊が街をパトロールし選挙民を威嚇した。まるで内戦さながらの選挙戦となった。またナチスは自動車隊を組織し、高齢者など歩行困難な人々を投票所へ動員した。
選挙結果は全647議席中、ナチスは288議席(得票率約44パーセント)と過半数に届かなかった。独占的な選挙運動にもかかわらず、まだ過半数の国民はナチス、ヒトラーを選ばなかったのだ。また猛烈な弾圧にもかかわらず共産党も81議席を獲得した。ちなみにこの選挙は、ヒトラー政権において最初で最後の民主的な選挙となる。
「独裁者・ヒトラー」を決定づけた演説
3月9日、選挙結果に不満をもったヒトラーは、81の共産党の議席を剝奪。議席総数が566になり、ナチスは単独過半数を得ることになった。
しかしそれで満足するヒトラーではなかった。今度は「人民と国家の苦難を除去するための法案」を作成する。その内容は、タイトルとは大きくかけ離れていた。国家予算を含む立法権、外国との条約承認権、憲法修正の発議権などすべての立法府の権利を政府に4年間引き渡すという内容だった。つまり「全権委任法案」だ。
この法案の可決にはワイマール憲法を改正する必要があるために、議員の3分の2の賛成が必要だった。
そこからナチスの他党への猛烈な工作が始まった。謀略や脅しや噓の約束を駆使して、小政党から次々と賛成をとりつけた。
3月23日、ベルリンのクロル・オペラ劇場を仮議事堂として国会が開かれた。ヒトラーは今後の4カ年計画を発表するとともに、「全権委任法案」を提出した。
その時のヒトラーの演説は、びっくりするくらいの低姿勢だった。
「これは絶対に必要な万が一の時のための法律で、簡単に行使するものではないし、議会の権利も、大統領の地位も決して脅かすようなものではない」と、何度も強調した。また「フランス、イギリス、ソ連との平和的な関係を促進する」ことも約束した。
しかし演説の最後になると、ヒトラーは一転して強い口調でこう脅かした。
「もしも議会がこの友好的な協力の機会を拒否するのであれば、我々は断固として議会と戦う決意がある。戦争を選ぶのか? 平和を選ぶのか? それを決めるのは、議員先生諸君、あなた達だ」
ナチスの突撃隊や親衛隊がものものしく武装して圧力を加える中、投票がおこなわれた。結果、賛成441票、反対94票で可決。参議院では全会一致で可決。こうしてヒトラーに対する全権委任が「合法的」に確定し、ドイツは独裁国家への道を進むことになる。
もちろん、ヒトラーが議会でした約束が守られることはなかった。
4年の時限立法のはずがどんどん延長されていった。
翌年、ヒンデンブルク大統領が亡くなるとすべてのタガが外れた。ヒトラーは大統領と首相を兼ねる国家元首=総統の地位につく。これ以降の歴史的悲劇については、本書の趣旨とは違うのであえて触れない。
1月30日に天から降ってきたようなチャンスをヒトラーとナチスは見逃さず、たった2カ月で独裁体制を確立したのだ。
『わが闘争』の演説論
さえない20代を過ごしたヒトラーが独裁者にまで上りつめたのは、今までみてきたように、何よりも「演説の才能」があったことが大きな要因であった。
彼の演説に対する考え方は、獄中で口述筆記された『わが闘争』の中に詳しく記されている(以下いずれも角川文庫版より引用)。
ヒトラーは、書き言葉ではなく、演説こそが、世の中を動かすものだと考えていた。
「すべての力強い世界的革新のでき事は、書かれたものによってではなく、語られたことばによって招来されるものだ」
(下巻 第六章 初期の闘争―演説の重要性)
なぜなら、書き言葉では民衆の反応をダイレクトに読み取り修正することができないが、演説ではそれが可能だからだと言うのだ。
「演説家は聴衆の表情によって、かれらが第一に自分がいったことを理解したかどうか、第二にかれらが全体についてくることができるかどうか、そして第三にどの程度まで提議したものの正しさについて確信したか、ということを読みとることができるのである」
(下巻 第六章 初期の闘争―演説の重要性)
また、学者などの理論家では指導者になれず、演説によって大衆の心をつかめる者だけが指導者になりうるのだということを強調する。
「偉大な理論家が、偉大な指導者であることはもっとまれである。むしろ扇動者のほうが指導者にむいているだろう。(中略)
ある理念を大衆に伝達する能力を示す扇動者は、しかもかれが単なるデマゴーグ(大衆扇動家)にすぎないとしても、つねに心理研究家であらねばならない。そうすればかれは、人間にうとい、世間から遠ざかっている理論家よりも、つねに指導者にもっとよく適するであろう。というのは、指導者であるということは大衆を動かしうるということだからである」
(下巻 第十一章 宣伝と組織)
大衆は愚鈍だから同じ言葉を繰り返す
ヒトラーは、学者に代表されるようなインテリや知識層をとことん嫌い、見下した。
「こういう考え方に対してブルジョア的インテリゲンツィアが抗議するのは、かれら自身が語られたことばによって大衆に影響を与える力と技術をあきらかに欠いていたがために、つねに純粋の文筆活動だけに没頭し、演説によって実際に扇動的に活動することをあきらめているからである」
(下巻 第六章 初期の闘争―演説の重要性)
特に演説などの宣伝活動は、学識あるインテリ相手ではなく、教養の低い大衆に対して行うべきであることを何度も強調する。
「宣伝は永久にただ大衆にのみ向けるべきである!」
(上巻第六章 戦時宣伝)
「民衆に対する政治家の演説というものを、わたしは大学教授に与える印象によって計るのでなく、民衆に及ぼす効果によって計るからである」
(下巻 第六章 初期の闘争―演説の重要性)
かといって、ヒトラーは、民衆や大衆のことを決してリスペクトしていたわけではない。彼らのことも以下のように見下していた。
「大衆の受容能力は非常に限られており、理解力は小さいが、そのかわりに忘却力は大きい。」この事実からすべて効果的な宣伝は、重点をうんと制限して、そしてこれをスローガンのように利用し、そのことばによって、目的としたものが最後の一人にまで思いうかべることができるように継続的に行なわれなければならない。
人々がこの原則を犠牲にして、あれもこれもとりいれようとするとすぐさま効果は散漫になる。というのは、大衆は提供された素材を消化することも、記憶しておくこともできないからである」
(上巻 第六章 戦時宣伝)
ヒトラーは大衆を愚鈍だと考え、だからこそ同じフレーズを何回も何回も繰り返し語る必要があると考えていたのだ。
「宣伝は、鈍感な人々に間断なく興味ある変化を供給してやることではなく、確信させるため、しかも大衆に確信させるためのものである。
しかしこれは、大衆の鈍重さのために、一つのことについて知識をもとうという気になるまでに、いつも一定の時間を要する。最も簡単な概念を何千回もくりかえすことだけが、けっきょく覚えさせることができるのである」
(上巻 第六章 戦時宣伝)
2005年の「郵政民営化」。2009年の「政権交代」。日本の選挙においても重点をうんと絞ってひとつのスローガンにし、何千回も繰り返した陣営は大勝利をおさめた。橋下徹の「大阪都構想」も同じと言えるだろう。
またヒトラーは、民衆の大多数が、政策などを冷静に見比べるのではなく、感情で動くことを以下のような言葉で表現した。
「民衆の圧倒的多数は、冷静な熟慮よりもむしろ感情的な感じで考え方や行動を決めるという女性的素質を持ち、女性的な態度をとる」
(上巻 第六章 戦時宣伝)
演説の時間や場所にも気を配る
ヒトラーは、演説する場所や時間にも気をくばった。
特に夕方にこだわった。なぜなら夕方が一般的に人間の心理的バリアが一番弱まる時間帯だからだ。
場所についても同様だ。人の心が動きやすい場所とそうでない場所がある。
一般的に人はまわりに人が大勢いて、その熱気を感じると、自分の心も動きやすくなる。
たとえば、格闘技の試合を観に行ったとする。いくらすごい試合をしていたとしても、観客がまばらだったらどうだろう? 同じ内容でも、満員の観衆が熱狂する中で観るのとはテンションがまったく違ってくるだろう。
ヒトラーは演説をする場面において、このような人間の感情的な要素を非常に重要視した。
「感情的な先入見、気分、感覚などをくつがえして、他のものでおきかえることがどんなに困難であるか、またその成果がどれほど多くの計り知れない影響や条件にかかっているかということは、敏感な演説家ならば、講演が行なわれる時間すらもその効果に対して決定的な影響がありうるということを推測しうるのだ。同じ講演、同じ演説者、同じ演題でも午前十時と午後三時と晩とでは、その効果はまったく異なっている」
(下巻 第六章 初期の闘争―演説の重要性)
ヒトラーは、演説の演出や喋り方も場所によって変えた。
狭い限定された場所では短く歯切れのいい演説をしたが、野外などの大規模な集会では演説の内容よりも会場全体の雰囲気を盛り上げる演出に力を入れた。大きな会場では、演説の内容をきちんと聴き取れないことも多い。しかし多くの聴衆が熱狂するような仕掛けをつくると、演説を聴き取れなかった人も満足するからである。
同じアーティストのコンサートでも、小規模なライブハウスでやるのと、スタジアムでやるのでは、演出は大きく変わってくるのと同じだ。
さて、本章では独裁者・ヒトラーが、どのようにして権力を手に入れたか。そして、その際に演説がどれほどの効果を発揮してきたかを述べてきた。またヒトラーが演説の際にどのような点を重視していたかについても述べてきた。
次章では、実際のヒトラーの演説を取り上げながら、より詳細にヒトラー演説のカラクリを見ていきたいと思う。そして、私が提唱する「ストーリーの黄金律」とはどういうものか。そしてヒトラーがどのようにその黄金律を活用(悪用)したかについても述べていきたい。