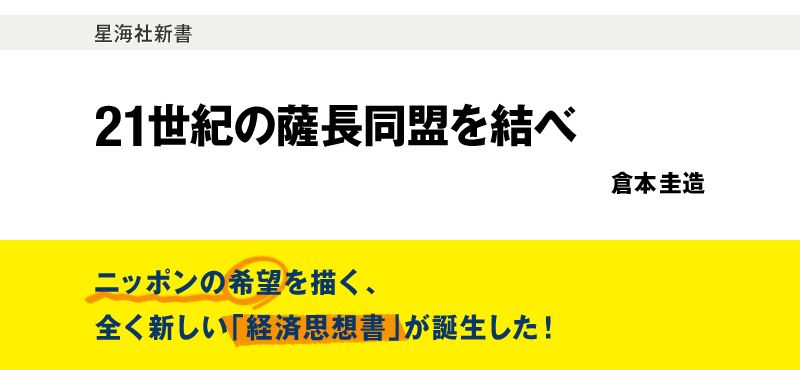
21世紀の薩長同盟を結べ
倉本圭造
ニッポンの希望を描く、全く新しい「経済思想書」が誕生した!——京都大学→マッキンゼー→ホ……ホストク ラブ??? 「グローバリズム的思考法」や「リクルート社&外資コンサル型人材」ばかりがもてはやされる風潮に違和感を覚え、日本社会の「本当の現場」を 生身で見て歩くことで、今の日本に必要な〝新しい経済思想〞を追い求めた、33歳・在野の思想家による衝撃の処女作が誕生。幕末に〝集団主義者〞の薩摩と 〝個人主義者〞の長州が手を組んだのと同様の「ありえない、けれど時代を変えるために絶対に必要な連携」を、現代の「国内派日本人」と「国際派日本人(グ ローバリスト) 」との間に生み出せれば、そこから大変革が始まる!! ——10年間の探求の末に著者が辿りついた「次世代の希望」とは?
はじめに ニッポンの「次世代の希望」はこの本にある!
「本当の自然の豊かさ」は、私たちの想像を超えたところにある
一昨年の夏、私は京都府の美山というところにある、京大農学部演習林に指定されている「芦生の森」という山地へ行く機会がありました。そこの奥地には人間の手が加わっていない、いわゆる「原生林」が残されているのですが、そこの土を踏んだ瞬間、あまりの柔らかさに「うわっ!」と驚きの悲鳴をあげてしまいました。
山奥にある「原生林部分」にたどりつくまでには林業のために整備された道があり、人の手で植林もされているので、「へー、これが噂に聞く芦生の森かー」というブランドネームに騙された感慨はあるものの、それほど「ものすごいなあ!」という感じもせず、「まあ、この程度だろう。うんうん、自然っていいよねー」的感覚で通って行ける場所でした。
しかし、その林道の行き止まりまで行き、道なき道を魚屋さんみたいなゴム長靴で踏み分けて行く地帯に入ると、地面の感覚がぜんぜん違うんですね。
アスファルトに比べて舗装されていない土は柔らかくて足腰に優しいよねという話はよく聞きますが、その「舗装されていない田舎道」がマンションのカーペットの床程度の固さだとすると、原生林の地面は厚さ15センチのスポンジの上を歩いているような、そしてヌカルミに足を踏み入れてしまうと膝までズボッと入ってしまうような、それほどの、「こんな地面は踏んだことがなかった」というぐらいの柔らかさなんですよ!
つまり、「本当にぜんぜん違う」んですね。
私は子供のころ、父親につれられて結構あちこちの山に登りましたが、それでも「こんな土は踏んだことがなかった」というぐらい「本当にぜんぜん違った」のです。
都会に住む人に比べて田舎に住んでいる人は自然を知っているようなイメージがありますが、しかし田畑という「人類最初の工場施設」に日々触れていらっしゃる農家の方々でも(むしろ、〝だからこそ〟という部分があるかもしれませんが)、この「本当にぜんぜん違う自然の土」に出合う機会は非常に少ないのではないかと思われます。
最近、テレビや雑誌で話題なのでご存じの方も多いかもしれませんが、青森県の弘前市に、世界でも珍しい「無農薬・無肥料のリンゴ」を栽培する木村秋則さんという方がいらっしゃいます。
無農薬とまではいかずとも、有機栽培をうたう食品はあちこちで目にする昨今、「まあ、リンゴで無農薬栽培をする人もいるんだね」と軽く流してしまいそうになるところですが、しかしリンゴの無農薬栽培というのは、とてつもなく難しいらしいのですね。
リンゴだって最初はどこかの野生植物だったわけですから、農薬なしで育たないはずがないように思えますが、今のリンゴは人類の歴史とともに品種改良がくり返され、元の種とは比べ物にならないほど大きく、そして甘い実をつけるようになっているため、結果として病気や害虫に弱く、野菜やコメが無農薬で作れようとも、リンゴだけは不可能だろうと長い間言われていたそうです。
何年も壊滅的な病気と害虫被害を受け続け、極貧のなかで試行錯誤をくり返しながらやっと成功したお話や、そうしてできたリンゴは長く置いておいても腐らないだとか、彼のリンゴの木は通常の何倍も長く根を密に張っているので、地域のリンゴが壊滅的な被害を受けた台風のときもほとんど無事だったとか、単純にとにかくムチャクチャ美味しいらしいといった話まで、この「奇跡のリンゴ」をテーマにした書籍は何冊も刊行されているので、ご興味をお持ちの方はぜひお読みください。
ともあれ、その「奇跡のリンゴ」にたどりつくまでの木村さんの奮闘記のなかに、もう何をやっても病害虫被害を食い止めることができず、ぼろぼろになっていくリンゴの木と極貧生活を味わわせている家族への申し訳ない気持ちで絶望し、自殺しようと首つり用のロープを持って岩木山へ深夜に登って行くシーンがあります。
しかし、そこで出合ったドングリの木が、山中で人間が肥料や農薬をやるでもないのにちゃんと実を付けているのを見て、「何が違うんだろう?」と疑問に思った結果、「土がぜんぜん違う」ということに気づいたことが、大きな転機になったというんですね。
そのドングリが自生していた山奥の土はフカフカで柔らかく、そして温度が高く、微生物の活動が活発なのか、独特の刺激臭がするんだとか。一方で、リンゴ畑の土を見るとカチカチで固くて、温度も低く、匂いもない。
山奥の土にあるような、ある種の「豊かさ」を畑に再現することができれば、リンゴの木は本来の生命力を取り戻し、無農薬でも力強く実を付けてくれるんじゃないか? その直感が転機となり、そこからの試行錯誤の結果、今や見違えるような生命力を持つリンゴ畑ができあがりました、メデタシメデタシというお話なわけです。
そういうお話を聞くと、都会育ちの若者としては、農家の皆さんの苦労など知らずに「へー、すごいなあ」と思ってしまうわけですが、「土がぜんぜん違う」と言われてもどう違うのか、具体的なイメージが湧いてくるわけではありません。
読者のあなたも、耳学問として「やっぱ、自然の土は偉大だよねー」という知識があったとしても、「どう違うのか」がイメージできる方は少ないのではないかと思います。
NHKの番組で木村さんが紹介されたときには、木村さんに憧れるリンゴ農家のおじちゃんが自分も無農薬栽培をしようとしていましたが、「土を固めないように機械を畑に入れてはいけない」という教えがそれほど大事なものだと想像できず、ついつい機械で農薬代わりの酢を散布してしまい、結果大失敗に終わるという話が放送されていました。
それくらい、「土がぜんぜん違う」と言われても、すでに人間の手が深く入った「人工的な自然」のなかでしか暮らしたことのない我々には、なかなか想像がつかないところがあります。
しかし、美山の原生林のスポンジより柔らかい土壌には、そこにいる微生物たちや、コケ類やシダ類といった植物たち、それを食べる小さい虫たちや、クマやシカやサルといった動物たちなど、人間の手で単純化した環境にはいない「多種多様な生き物たち」が暮らしているんだなあ、ということが「理屈でなく実感」できるような柔らかさがありました。
そして、ちょっとロマンティックすぎる連想だと思われるかもしれませんが、「こういう世の中になればいいなあ」と、強く思いました。
ホンモノの「自然の生存競争」と「豊かな土壌」は両立している
人間には、巨木タイプの人間もいれば昆虫タイプの人間もいます。熊タイプも鹿タイプも、日の当たらないところで着々と本分をこなす微生物タイプの人間もいることでしょう。読者のあなたご自身は、何タイプの人間だと思われますでしょうか。
そして、巨木だけが偉いとか微生物はダメだとか、そういう差別は自然界には一切なく、それぞれが生態系全体のなかでかけがえのない役割を果たして共に生きているというのが「社会の理想状態」であるという考え方は、多くの読者のみなさんにも納得していただけるビジョンなのではないでしょうか。
社会全体が短視眼的に単純すぎる部分に特化すると、言ってみれば「生態系が単純化」してしまい、「イキイキと生きられる人間の種類」が非常に限定されるようになり、その人間の本来の性質からすると無理に無理を重ねて生きねばならなくなるような人が増え、社会に怨念が渦巻いて、良からぬ状況が現出してしまいます。
今の日本は、言ってみればそういう状況だと考えられます。
もちろん、経済の問題があります。理想だけではメシは食えません。弱肉強食は世の常です。冷戦時代の共産主義の大失敗を例に挙げるまでもなく、経済がちゃんと元気でないと、どんな理想も結局誰のためにもならない苦労のなかに朽ち果てるでしょう。
しかし考えてみてください。今の時代「経済市場の競争原理」と「弱肉強食の自然の生存競争」とを対比する比喩はよく使われますが、その芦生の原生林にだって「冷酷非道の完全無慈悲な生存競争」は存在しているわけです。
森のなかの植物たちはすべて、光を求めてシノギを削っています。大きな巨木が倒れた場所には、いっせいに成長の早い陽樹たちが芽吹き、背を伸ばし、「俺こそがこの位置で光をいちばん浴びてやるぜ」とギラギラした欲望を燃やして頑張っています。
大きな巨木に絡まりながらツルを伸ばすことで、なんとか光にたどりつこうとする植物もいます。あるいは逆に、光の量が少ない暗がりでもちゃんと生きていけるような命のあり方を選択する植物もいます。
「あんたの場所を奪っちゃったらかわいそうだから、俺あんまり伸びないでおくよ」といったナアナアの譲り合いなど一切ないように見えます。
にもかかわらず。にもかかわらず、です。芦生の原生林には豊かな生態系があるように見える。そこで生きている生き物の種類は、人工的に単純化した森とは比べ物にならないほど豊かなものです。しかし、そこで起きていることは決して「自然の厳しい生存競争」から無縁のものではないわけですよね。
つまり、「本当の自然の厳しい生存競争」は「多種多様な生命の豊かさ」を内包したものである、と言えます。
やればやるほど土壌がやせ細っていく「資本主義社会の生存競争」
一方で、今の世の中で行われている「適者生存の経営競争」とやらは、「それが自然の摂理なんだぜ」とタフぶって見せる精神によって行われているにもかかわらず、「本当の自然が持っている豊かな多様性」を持ったものになっているでしょうか?
なっている……かもしれない。なっていない……かもしれない。どう思われますか?
規制緩和や情報技術の発達によって、昔に比べて圧倒的に多様なビジネスの形態が生まれているわけですから、ある意味では「多様性は増している」と思われる方もいるでしょう。
一方で、やはり「儲けやすい性質」ばかりに光が当たる流れが加速することで、自分本来の力や性質がまったく役立たずだと判定され、日々抑圧されて生きているような気分を持っている方、あるいはそういう人が多くいる現状に心を痛めておられる方は、「多様性は破壊されている」と感じていることと思います。
あなたがどちらの立場でいようと、今の時代の経済競争に適合しないタイプの人間だということで居場所を失い、貧困に苦しんだり、ましてや怨念を溜め込んで犯罪に走ったりする層が確実にいて、治安的問題としても、彼らのサポートのための公的予算の問題としても、もっと根源的にそういう存在がいていいのかという良心レベルの問題としても、それが社会全体にとって何らかの解決を必要とする問題であることには、同意いただけるのではないかと思います。
いわゆるマルクス的と言いますか、労使問題として、あるいは福祉の問題として彼らの問題を扱うやり方もあるでしょうし、現状においてはそれが必要とされてもいるでしょう。
しかし同時に、「彼らの本来的な活かし方」を「そもそも論」のレベルで我々が理解していさえすれば、もっと根本的な解決が図れるのではないか? という発想も、我々は真剣に考えるべきではないでしょうか。
やはり、自分の長所を社会のなかで活かすことができず、不自由な状況に押し込められて、ある種のほどこしのようなものを受けて暮らすよりも、自分らしくイキイキと社会に参加することでお互いに益し合う人生になった方が、幸せなのではないでしょうか。
彼らを救うための公的支出が増え続けることによる国や自治体の財政難も深刻なものですし、無理やり鋳型にはめ込むような勤労主義が(その倫理的是非はともかくとして)受け入れられるご時世でもない今、「彼らの本来の良さを、どうしたら経済付加価値に転換できるのか」ということは真剣に考えるべき課題だと思います。
そしてそれは自然の摂理に反することではなくて、本来、自然の摂理はそうなっているはずだとさえ、私は原生林の奥地でガイドさんと話しながら考えていました。
よく経済学者が「公的な規制によって市場環境が歪められ、適切な自然の淘汰メカニズムが働いていないのが問題だ」という趣旨の発言をします。「神の見えざる手」に任せていればすべてうまくいくはずなのに、そうなっていないのは人為的に「歪めて」いるからだという発想です。
規制緩和問題と関連した部分でのこの発想の可否はとりあえずおいておきますが、しかし我々は、「本当の原生林」「本当の自然淘汰」はむしろ「生物多様性を促進する」ものであるということを知っています。つまりそれは「どこかで人為的に歪められて伝わっている」のではないでしょうか。
今の市場経済は「どこが」歪んでいるから、「抑圧されて怨念の塊になる人たち」が生まれているんでしょうか? どうすれば、「本当の自然淘汰メカニズム」を働かせて、芦生の森のような豊かな生態系を、現実の経済のなかに出現させることができるのでしょうか?
それを考えてみるのが本書のテーマです。
グローバリズムとは、「ダメ人間の怨念」がどこまでも蓄積される社会のこと
多少の一進一退はありますが、世界は刻一刻と緊密に結びついていくグローバリズムの時代です。そうすると、自分の生まれ育った土地から半径5キロ以内だけで完結していたような時代に比べれば、時代の流れは速くなり、チャンスを摑んで豊かになる人も、旧来のやり方が通用しなくなって没落する人も出てきます。
ある意味、グローバリズムの時代というのは、「時代に乗り遅れたダメ人間(扱いされる人たち)の怨念」がどこまでも蓄積されていく社会というようにまとめても良いでしょう。これは全世界共通の現象です。
活況に沸く中国でも、アフリカの貧しい国でも、もちろん日本国内でも、豊かになる人はどこまでも豊かになりますが、「ダメ人間扱い」された人たちの怨念はどこまでも蓄積されていきます。そして、その蓄積された怨念はどこかで暴発し、テロを生んだり、不幸な通り魔事件や家族内殺人事件を生んだりもするでしょう。
しかし、もしその「ダメ人間扱いされやすいタイプの本性」をうまく経済に活用できる方策が生まれればどうでしょうか? そうすれば、20世紀に人類を二つに分断した果てしのない罵り合いを越えて、新しい経済活動パターンを生み出すことができるでしょう。
日本経済はもう20年来ずっと不調と言ってよく、危機感を持つ有志の人々は、口々に「このままではダメだ」と焦燥感を持っておられることでしょう。しかし、「このままではダメだ。もっと頑張らなくては」という「危機感を持つ有志の熱意」が燃えれば燃えるほど、一方で「もうええやん、経済発展とかそういうの。ウザイんだよね……小さく小さくマイペースに生きていければそれでええんよ」という人々の願いも大きくなります。
「ちゃんと経済発展しないと、吞気なこと言ってるアンタのスローライフを支える普通の社会福祉とかだってできなくなるんだぜ!」という「危機感を持つ有志の人々」のご意見はまったくそのとおりです。はっきり言って100%正しい。
しかしそれでもなお、そういうあなたの熱意が燃え盛るほどに、それを嫌がる人たちの願いも大きくなります。これでは鏡のなかの自分とケンカをしているようなものです。
「北風と太陽」の「北風さんの苦悩」みたいなものです。
そこで、「もっと頑張れ」ではなくて、「現在ダメ人間扱いされてしまっている人々の本来的な価値」を、どうやったら「経済付加価値に転換できるか」を真剣に考えれば、今はフテ腐れてしまっている人たちにも生きる希望が生まれますし、「〝ダメ人間を切り捨てている国の経済〟よりももっと根本的に新しい価値を生み出せる〝タフな経済〟」が実現するでしょう。
「北風と太陽」の「太陽作戦」です。
「自分はこうやって成功したんだからお前もこうやれ」を越えて
私は以前、マッキンゼー・アンド・カンパニーという外資系経営戦略コンサルティング会社で、日本企業に「外資っぽい戦略」を授ける仕事をしていました。
しかし、そのプロセスのなかでは、「これでいいはずなんだけど、なんか〝日本人の本能〟とうまく嚙み合わないんだよなあ」と思うことが多く、それ自体は必要なことが多いものの、〝これだけ〟を続けていけば「いずれ日本中に怨念が渦巻いて、前向きな意見がぜんぜん出なくなったりするだろうな」と感じていました。
そこにいずれ「アメリカンなロジック(論理)」と「日本人のリアル」を発展的にシナジーする(相乗効果的に協力し合う)新しい考え方が必要になるだろう。それには、何かアメリカ直輸入的なものでなく、欧米直輸入的なものでなく、かといって昭和の日本にあったようなものへの単純な懐古主義でもなく、「いま目の前にある日本人のリアル」を深く多面的に見たうえで、まったくゼロから作り直すような「視点」が必要になるだろう――そう思いました。
というより、日々の仕事のなかで、身を切られるようにヒシヒシと「痛感」していました。
そこで私はマッキンゼーを退職し、まず、若くて転職余力があるうちに、恵まれた環境にいたのではわからない日本社会の暗部を見なくてはならないと思い、訪問販売やネットワークビジネスといった、良識派な読者の方からすると評判のよろしくない業界に参加してみたり、ときにはホストクラブや新興宗教団体にまで潜入して、「そこで生きている日本人のリアル」をこの目で見ていくことから始めました。
思春期にオウム事件などを経験した私としては、そういう今の社会の〝平均的良識〟の〝外側〟にいる人たちが、どういう生い立ちで、どういうことを考えて、どういう望みを持って生きているのかを、ルポルタージュやインタビューではなく、「自分もその立場に一員として参加する」ことで知っておくことが必要だという強い感覚があったからです。
そしてその後、マッキンゼー(誰もが知っている超大企業や各国政府、欧米の多国籍企業などがクライアント)とは対照的な、〝純和風〟コンサルティングを標榜する船井総合研究所に入り、今度は商店街のおっちゃんの店から、大きくても年商100億程度の中小企業のコンサルティングにも従事しました。
そして最終的に「本当の転換は企業単位でなく個人単位からでなくては起こせない」という結論に達し、今は個人相手の「人生戦略コンサルティング」のようなものを起業して暮らしています。そのクライアントには、20代の営業ウーマンさんから50代の大企業エンジニアのオジサンまで、ときにプロボクサーさんまでいます。
そのプロセスのなかで見えてきたことは、日本人それぞれの「今」というのは立場によってまったく違う状況にあり、「自分はこうやって成功したんだからお前もこうやれ」というだけでは解決できない断絶がそこにはあるということです。しかし、その「断絶」を越えて、「新しい連携」を生み出せれば、「今の延長でとにかく頑張る」よりももっと楽に、スムーズに、幸せに、新しい経済付加価値を生み出せる可能性があります。
本書は、「俺(アタシ)がこんなに頑張っているのに、頑張れば頑張るほど〝日本のみんな〟に憎まれたり遠ざけられたりするのはどうしてだろう?」と不満に思っている「グローバリズムの論理のなかで頑張っているあなた」には、「あなたのことを嫌っているように見える」、あるいは「あなたがいくら頑張っても脚を引っ張りまくってくる(ようにあなたには見える)」、あの「日本のみんな」と「どうやって協力し合って生きていったらいいのか」という視点を与えてくれる本になっています。
また逆に、「最近の日本人はみんな自分の利益のみ追求する身勝手な人間ばっかりになってケシカラン」と嘆く「日本人としての和」を生きておられる方には、あの「我利我利で生きているケシカラン個人主義者たち」も、本当はあなたと同じ「日本を良くしたい」という赤心のもとに動いているのだということをご理解いただき、そして「どうやって彼らと協働していったらいいのか」を示唆する内容となっています。
あらゆる国難を幕末にたとえるのは良くない部分もありますが、あえてこの状況を坂本龍馬の時代にたとえるのならば、これは21世紀の日本で実現されるべき「薩長同盟」であると言えます。
幕末期の日本において薩摩藩と長州藩が手を組んだことは、ただ倒幕派の大きな二つのグループが手を結んだということだけではなくて、「理論先行で個人主義者の集まりである長州藩」と「親分の意向で集団が一つの生き物のように動く(いわゆる〝和をもって貴しとなす国=日本〟のイメージ)薩摩藩」という「非常に相容れない志向性」を持った二つのグループが手を結んだという「大きな転換」でもありました。
「個人主義者の日本人」と「集団主義者の日本人」は、日常でいつも一緒にいるとお互い嫌な思いをすることが多いわけです。しかし、「お互いの本来の長所を活かし合う」ような連携ができれば、お互いが「とても心強い味方」になり得ます。
当初はものすごく憎しみ合っていた薩長両藩が手を握ったような「新しい連携」が生まれれば、日本経済は息を吹き返すことでしょう。
つまりこの本は、「長州藩側(グローバリストの日本人)」にも、「薩摩藩側(〝和の国〟の日本人)」にも、「両方」にとって意味のある本になっているはずだということです。
ピンチのときにこそ、大変革は起こせる!
「ただもっと頑張る」を越えて、「豊かな原生林のように、生命にとって〝自然〟で、〝自然だからこそタフ〟な経済」へ……今の日本はとにかくどこにも希望がない状態になりつつありますが、どこにも希望がない状態だからこそ、「本当に大きな転換」ができるチャンスだとも言えます。
数年前なら、国内派の日本人には、たとえば当時のトヨタのような絶対的なスターがおり、彼らは自分たちのあり方の延長でどこまでも行けると思っていたでしょう。また、外資側の立場にいる人間も、アメリカという存在が確固として好景気を続けていたので、自分たちのやり方こそ正しいと信じていたでしょう。
しかし、リーマンショック以降の世界は、どこにも「絶対的な成功者」がおらず、「とりあえずアレに従っておけばよい」という基準もなくなってしまいました。
いまやトヨタ的なもの〝だけ〟でも限界があるようだし、グローバリスト派も行き詰まり、そして労働運動側の人たちだって「もっと分け前をよこせ」というだけでは限界があることを痛感せざるを得ない状況です。
しかしだからこそ、まったく新しい自分たちのやり方を、今までは敵だと思っていた人たちを巻き込んで実現していくことができる時代だとも言えるでしょう。
よく言われているように、ピンチはチャンスです。物事の良い面をとらえて、みんなで「新しい経済」に一歩ずつ向かっていきましょう。
アメリカ的なものを世界的にゴリ押しすることの限界と問題があちこちで明らかになっているなか、その先の希望に当たる〝何か〟が、日本のなかにあるんじゃないかという感覚は、海外における静かな日本文化ブームのなかに〝期待〟としては広まっていると言えるでしょう。
しかし、肝心の我々日本人自身が、今の日本のあり方に海外からの期待ほどには自信を持つことができない。常に「こんなの、本当に自分がやりたいことじゃない。こんなの、本当の自分じゃない」と思うような毎日を生きているために、外側からの期待と自分たち自身のイメージが嚙み合わない状況にあるように思われます。
新興国の経済が順調に伸びているのは、彼らはまだ「生まれて初めて車を買ったり薄型テレビを買ったりエアコンを買ったり」する人たちだからです。それらの「20世紀的成功の象徴」にはだいぶ飽き気味になってしまっている私たちは、彼らのようなガツガツとした熱意を経済に導入することは難しいかもしれません。しかし、飽きている私たちだからこそ、「その次」をゼロから新しく作り出すことができるはずです。
その方法について私は、この10年間、模索と実験を続けてきました。
震災の災禍のなかで世界が日本に注目し、国難に当たって「なんとかしなくちゃ」という意識が高まっている今、「なんとかしたいとはみんな思っているんだけど、じゃあどうすればいいのか?」という問いに答える本となっていることを願います。
日本人は、普段は世界一煮え切らないくせに、いざ本当の危機状態に陥ったときには「昨日までの自分たちってなんだったんだろうね」というような大改革を起こして立ち直ってきた民族です。今こそ、その「期間限定でなぜか出てくる底力」を発揮するべきときではありませんか?
コミュニケーション不全を越えて、「分断」を越えて、「薩長同盟的相乗効果」に持っていけば、日本から「次世代の希望」になるようなビジネスが次々と生み出せるはずです。
これを読むあなたとともに、日本に「新しい連携」と「新しい経済」を生み出せることを願っています。