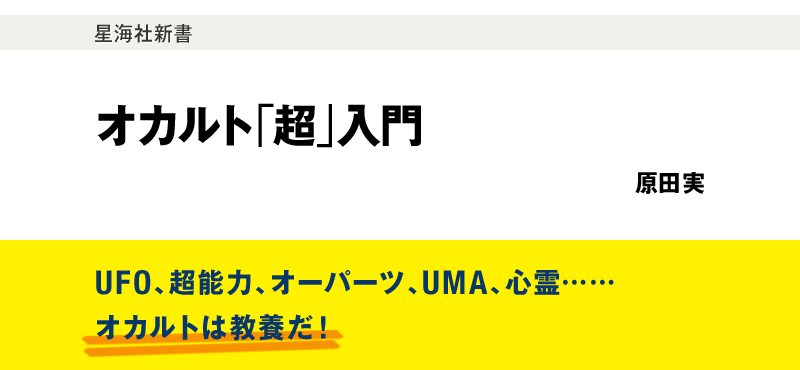
オカルト「超」入門
原田実
UFO、超能力、オーパーツ、UMA、心霊……オカルトは教養だ!本書は、オカルト史を形作った“オカルト重大事件”について、その成り立ちと背景を歴史研究家の視点から解説したものだ。オカルトは好き者の道楽や雑学だと思われがちだが、歴史家の視点で見ると全く違った顔を見せる。実はオカルト世界の事件や遺物・文献などは、その時代を反映したものばかりなのだ。例えば1950年代以降に発生したUFO目撃現象には、冷戦下での米国民の不安が色濃く影を落としている。そう、オカルトとは単純に「信じる・信じない」の不思議な現象ではなく、その時代の社会背景をも取り込んだ「時代の産物」なのだ。そして、オカルトの世界を覗き見ることで、この世界を「異なる視点」で読み解くことができるようになる。さあ、教養としてのオカルトの世界へ旅立とう。
序 文オカルトが教養になるために
私はその日、UFOを見た
1981年11月23日夜のことである。
私は、古史古伝『竹内文書』ゆかりの神社・皇祖皇太神宮の祭礼に参加するため茨城県磯原町に滞在し、同じ旅館に泊まっていた人々と夜通し語り合っていた。
そのうち、興が乗ってきた私たちは、総勢17人で深夜の散歩にとくりだした。一同が夜空を見上げていた時である。突然、満月ほどもある大きな光体が空中に現れ、ジグザグに飛び回ったあげく、いったん2つに分かれ、さらにまた1つに合わさるなどの複雑な動きを見せて、やがて姿を消した。
その数年後、私は「古史古伝と神道霊学の専門出版」を謳い文句にする出版社・八幡書店に勤務していた。
その出版社で『岩屋天狗と千年王国』という書籍を出した、1987年のことだ。
関連会社の事務所に、倉庫に入りきらない『岩屋天狗と千年王国』の在庫を積んでいた。事務所の留守番をしていた人がふと気が付くと、いつのまにか一人の老人があがりこんでその本を眺め、何やらうなずいていた。そして、ちょっと目を離したうちに姿を消していたという。
その人物が玄関を通った形跡はなく、いつ部屋に入り、いつ部屋を出て行ったかもわからなかったそうである。ためしに、著者・窪田志一の写真を見せて確かめたところ、その老人が窪田であることは間違いないという。
つまり、新刊の著者が版元の視察に来たというわけだが、あいにくとその新刊『岩屋天狗と千年王国』というのは遺稿集だった。つまり、本ができたからといって著者本人が見に来るはずはないのである。
前者はUFO事例、後者は心霊現象――つまり、どちらも本書で扱うオカルトの範疇である。
オカルトが好きだからこそ、検証する
UFO、心霊、超能力、UMA(未確認動物)、超古代文明など、世にオカルトと総称されるような事柄の存在を、私は否定するものではない。
しかし、オカルト的な事象の存在を認めることと、聞きかじったオカルト話をなんでも鵜吞みにしたり、世間に流布している解釈(たとえばUFOといえば宇宙人の乗り物とするなど)を無批判に受け入れたりするのは別問題である。
オカルトの話題について、情報の真偽を問うたり仮説の検証を行なったりする人は、しばしばオカルト嫌いとみなされてしまいがちだ。時には、無粋だと言われることもある。
しかし、人は本当に好きなもの、関心があるものに関しては、偽物や出来の悪い物をつかまされるのを拒むものである。エルメスのブランドマークらしきものが入ってさえいれば、どんな紛い物でも買うというエルメスのファンはいない。
ところが、オカルトに関しては、ファンなら内容にこだわらないはずというおかしな認識が蔓延しているわけだ。それは多くの人に、「オカルトなどうさんくさいものだ」という思い込みがあるからかもしれない。
もともとうさんくさいものなのに、検証などしてどうなるのだというわけだが、考えてみれば、それこそオカルトに対して失礼な話である。
本当に不思議なものを求めるには、不思議とされているものの中から、実は不思議ではなかったものを丁寧によりわけていく作業が必要だろう。
その結果、ほとんどの事例が、不思議でもなんでもないということになるかもしれない。しかし、不思議なものに関心がある限り、この作業をやめるわけにはいかない。
世界のどこかに、未だ隠された、本当に不思議なものが転がっているに違いない――少なくとも、その可能性を否定はできないと思うからだ。
オカルトという教養を手に入れるために
さて、「オカルト」は、ラテン語occulta(隠されたもの)を語源とする語である。したがってオカルティズムとは「隠されたものへの探求」を意味する。
つまり、世界の本質、人間の本質といったものは、通常の知識や感覚ではとらえられない「隠されたもの」であり、それを探るためには特殊な叡智が必要だというわけだ。その叡智を探求し、継承し、後に続く者へと伝授する人こそオカルティストである。
哲学や宗教学では、このような考え方を神秘主義といい、日本の密教や修験道なども神秘主義的色彩が強いとされる。神秘主義は高度に体系化されており、緻密な理論を持つ。いわば、高尚なオカルトであり、現在でも一定の敬意を払われている。
それに対して、本書で扱うUFO、心霊、超能力、UMA(未確認動物)、超古代文明などは、体系化されておらず、理論的にも未熟であることから、通俗オカルトと位置づけることができる。現在、オカルトという言葉から想像されるのは、主にこちらのほうだろう。
本書では、通俗オカルトの重大事件を扱い、そこから、「実は不思議ではなかったものを丁寧によりわけていく作業」を行っていく。それは、ロマンをはぎ取る無粋な行為では全くない。
通俗オカルトの背後に「隠されたもの」を「探求する」ことは、オカルトの原義に立ち返ることであり、それと同時に、新たな叡智を獲得しようとする営みでもある。
なぜなら、通俗オカルトに関するさまざまなテーマは、それが生まれた社会の文化や時代背景をよく反映しているからだ。
たとえば、1950〜60年代のUFO目撃事例には、アメリカとソ連の両大国が相手を危険視し、相互に監視しあっていた当時の国際情勢――いわゆる「冷戦」が反映している。また、そのUFOから降りてきたという宇宙人たちの姿には、当時流行していた映画やテレビ番組の内容が影響しているふしがあるのだ。
このようにして個々の事例を見ていくなら、オカルトを通じて、それが語られた社会の文化や時代背景を考察することも可能になるだろう。ただ単に、事実かどうかを検証する行為なのではなく、検証した上で、ウソや間違いからも多くのことを得られるというスタンスだ。
このような過程を経ることにより、信奉者以外には雑学と見なされがちな通俗オカルトは、世界を読み解いていくための特殊な叡智として蘇るだろう。
通俗オカルトは、新たな教養になり得る存在なのである。
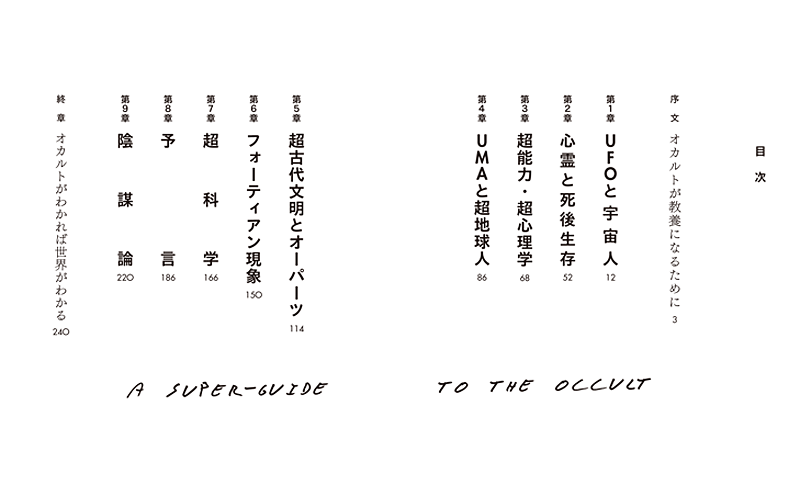
UFOは実在する
UFOの話題は、いわゆるオカルト話の中でも、もっとも息が長く多くの世代によって親しまれてきたものである。年配の方なら1970年代のTV特番でイメージを作った方もおられるだろうし、最近では、YouTubeなどの動画サイトにはUFOを撮影したという映像が次々とアップされ続けている。
本書の幕開けにふさわしいテーマと言えるだろう。
UFOは本当にあるのか、それとも存在しないのか、結論から先に言えばUFOは確かに実在する。なぜなら、UFOというのはUnidentified Flying Object(アンアイデンティファイド・フライング・オブジェクト、未確認飛行物体)、「つまり正体がわからない空飛ぶ物」という意味でしかないからだ。
しかし、UFOがあるとかないとか議論される時の「UFO」は、もっと狭い意味に使われるのがふつうだ。つまりは宇宙人の乗り物の意味である(もっとも宇宙人の乗り物などと正体を特定した時点でUFOの原義からは離れてしまうはずなのだが)。
この場合、UFOがある、という説が成り立つには、「地球以外の天体に人類のような知的生物が存在する」、そして、「その生物が地球まで乗り物で来ている」という2つの仮定が満たされる必要があるわけだ。
火星の運河と月人騒動
さて、空の天体にも住人がいるという考え方は古代の神話や伝説にまでさかのぼる。といってもその「住人」は神々や妖精だったわけで、日本でも月の人が地上で育ち、やがて月へと帰っていく『竹取物語』(9世紀)や、亀を捕えた漁師がその亀の導きで星の世界に行くという浦島子の話(『丹後国風土記』逸文、8世紀。御伽噺『浦島太郎』の原型)などがある。
知的生物としての宇宙人のイメージが定着する上で大きな影響があったのは、19世紀における火星人と月人の「発見」だった。
火星人の概念を早くから説いたのは、ドイツ出身の天文学者フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヘルシェル(1738〜1822)だった。ちなみに彼は英国に移住してから業績を上げたこともあり、日本では英国名のウィリアム・ハーシェルの方が通りがいい。ヘルシェルは火星だけでなく太陽を含むあらゆる天体に生物がいるとみなしていた。
1877年、イタリアの天文学者ジョヴァンニ・スキアパレッリ(1835〜1910)は火星の表面を望遠鏡で観測している時、その表面に縦横に走る筋を見つけた。スキアパレッリはそれが水の流れによってできた溝と考え、イタリア語でCanali(水路)と名付けた。ところがそれが運河(人工の水路)を意味する英語のCanalsと混同されたため、火星には広大な運河を作れるような高度の文明があるという話になってしまったのだ。
アメリカの天文学者でローウェル天文台を建てたことで有名なパーシヴァル・ローウェル(1855〜1916)は、1895年に〝Mars〟(『火星』)という著書を出した。ローウェルは火星の「運河」に関する膨大なスケッチをまとめ、火星人と火星文明の存在を証明しようとしたのだ。
ちなみにローウェルは、1883年から93年にかけて5回も日本を訪れて滞在し、日本文化に関する論文をいくつも著した。どうやら彼は、自分たちと異質の文明というテーマに魅せられていたらしい。
さて、先述のヘルシェルの子でやはり天文学者として名をなしたジョン・ハーシェル(1792〜1871)が月人を発見したというニュースがアメリカを賑わせたのは、1835年のことだった。
その年の8月21日、大衆新聞『ニューヨーク・サン』は、当時南アフリカのケープタウンで天体観測中だったハーシェルによる未曾有の発見に関する予告記事を掲載した。その後、同月25日から6回にわたってハーシェルが望遠鏡の中に見たという月世界の記事を連載したのだ。
それによると月には海や森があり、野牛に似た獣や一角獣などの動物がいた。月世界にも人間がいたが、彼らは地球人と違ってコウモリのような翼を有していたという。
『ニューヨーク・サン』の記事は多くの新聞に転載され、アメリカ中の話題になった。作家エドガー・アラン・ポーはこの記事をヒントに『ハンス・プファールの無類の冒険』(1835)という月旅行譚を書き、月人を登場させている。
現在ではスキアパレッリやローウェルが報告した「運河」は何らかの錯覚の産物とされている。また、『ニューヨーク・サン』の記事はまったくの捏造で、当時のハーシェルはそんな記事が書かれていることさえ知らなかった。火星にはすでにいくつもの探査機が着陸しているが、火星人どころか明確な生物の痕跡はいまだ発見されていない。月にいたっては生物がいないことはもはや常識だ。
しかし、ローウェルらの主張や『ニューヨーク・サン』の記事などが19世紀の人々、特にアメリカ人に宇宙人のイメージを定着させたことは確かである。
そして、それは20世紀における新たな神話創世につながっていく。
ケネス・アーノルド事件
1947年6月24日午後3時頃、自家用機でワシントン州カスケード山脈のレーニア山近くを飛んでいた実業家のケネス・アーノルド(1915〜1984)は、奇妙なものを見た。レーニア山上空9500フィート(約2900メートル)あたりを並んで飛んでいる9つの物体だ。その物体には、航空機なら当然あるはずの垂直尾翼がなかった。
アーノルドは、その飛行物体が山頂から山頂に移動する時間を計ることでその速度を、近くを飛んでいたDC――4機との比較でその大きさを、それぞれ概算した。
その結果、飛行物体の速さは超音速のマッハ2、大きさは45〜50フィート(約14〜15メートル)という数値が得られたという。1947年前年まで、航空機での最速記録はアメリカ空軍のチャック・イェーガーが実験機ベルⅩ1で出した時速1078キロとされていたが、これはマッハ1(時速1225キロ)にも及んでいない。つまり、当時の航空機ではありえないほどの速さで飛んでいたことになる。
アーノルドの目撃報告はアメリカ各地の新聞に大きく報じられた。それらの記事の見出しに使われたFlying Saucerという言葉はたちまち流行語となり、日本でも「空飛ぶ円盤」の訳語で広まった。1970年代までは宇宙人の乗り物を意味する語としては「UFO」より「円盤」の方が通りがよかったくらいだ。
アーノルドは、飛行物体が投げた皿(Saucer)が水面をはねるように軽々と飛んでいたと言っただけで、飛行物体の形状については現代のステルス機のように全体が翼となった左右に長い構造のものとみなしていた。
しかし、Flying Saucerという言葉が一人歩きした結果、その飛行物体は皿のように丸い円盤だったということになり、それ以降、円盤状の飛行物体の目撃報告が相次ぐことになる。
UFOファンの間では、6月24日はUFO記念日と呼ばれており、アメリカでは1954年以来、この日にUFO研究者によるさまざまな催しが行われている。最近ではUFO記念日は、大きなカレンダーや歳時記にも載せてもらえるようになった。それもアーノルドのこの目撃報告がきっかけになっている。
アーノルドの目撃は世界初の正式に記録されたUFO遭遇事件となった。空軍も彼が目撃した飛行物体に関心を持ち、アーノルドから正式な報告書を受け取っている。
アーノルドの報告がマスコミや軍に注目されたのは、それが未知の秘密兵器ではないかと思われたからである。
第二次世界大戦の最中、アメリカの政府広報はドイツや日本の脅威を国民に訴え続けていた。その戦争が終わってまだ2年しかたっていないこの時期、同盟国の残党がひそかに逆襲の時をうかがっているのではないかという不安もあった。
また、ソ連は戦時中、アメリカにとって連合国の同志だったわけだが、それは日独という共通の敵あればこそであり、ソ連の共産主義はアメリカの国是と一致するものではなかった(アメリカでは長らく共産主義政党は非合法であり、現在も監視対象である)。そのため、戦後はソ連がアメリカの新たな仮想敵国として台頭してきたのである(米ソ冷戦の始まり)。アーノルドが見た物がそうした敵対勢力の兵器だったとすれば、それがアメリカ国内に持ち込まれていることになるわけで、大変な事態というわけだ。
ちなみにアメリカ合衆国という国は自由を求め、圧政から逃れるという名目で宗主国・イギリスに戦争を挑んで独立した元植民地である。そのため、「自由の敵」への恐怖は国民に共有されるものとなっているし、国民の結束のためにあえて「自由の敵」を見出そうとする傾向もある。
第二次大戦中のアメリカ国民はその「自由の敵」をナチスドイツや大日本帝国に見出したし、冷戦時代にはソ連(そしてその指図で動くと信じられた共産主義者)こそ「自由の敵」の筆頭になっていたわけだ。アーノルド事件への軍やマスコミの反応は、その「自由の敵」襲来への不安感を天空に投影したものとみなすこともできる。
しかし、アーノルドの報告した飛行物体を兵器と見るなら、そのスペックは(当時の)地球上のものとしてはあまりに高すぎる。そのため、それが地球外の産物だという説が現れ、そして広まるのはあっという間だった。アーノルド自身もその可能性を否定しなかった。
なお、アーノルドが目撃した飛行物体の速度や大きさについては、アーノルドが自家用機から飛行物体までの距離を見誤って過大な数値を出した可能性があることが早くから指摘されていた。
つまり、もっと小さくて遅い飛行物体の集まり(たとえば鳥の群れ)を見誤ったことも考えられるわけだ。しかし、いったん生まれたUFO神話の成長はとどまることがなかった。
フー・ファイター
イギリスの作家ハーバート・ジョージ・ウェルズが「火星の運河発見」に触発され、火星人が地球に攻めてくる小説『宇宙戦争』を発表したのは1898年のことだ。
1938年10月30日、アメリカのCBSネットワークがこの小説をドラマ化した際、ドラマ内の臨時ニュースを事実と思い込んだ人々が全米各地でパニックに陥った事件もある。
もっとも、1938年はヨーロッパ和平をめぐってドイツと英米の緊張が高まっていた時期でもあり(第二次世界大戦勃発はその翌年)、この(ドラマ内の)ニュースをドイツ軍の奇襲と思っていた人も多かったようだ。
第二次世界大戦中、空の脅威と言えば、それは同盟国の空襲に対する不安だった。アーノルド事件は別の空の脅威、すなわち宇宙人の侵略の可能性をアメリカ国民に印象づけるきっかけとなった。
実は第二次世界大戦当時、アメリカ軍はしばしば不可解な飛行物体に悩まされていた。
1942年2月25日午前2時頃、カリフォルニア州ロサンゼルスでレーダーが「国籍不明の航空機」を捕捉、軍は市内に空襲警報を発令、灯火管制を敷いた後、午前3時過ぎに空中への砲撃を開始した。この時、超高速でジグザグに飛ぶ複数の光る物体の編隊を空中に見たという目撃者もいた。
しかし約1時間に及ぶ砲撃にもかかわらず一機の敵も撃ち落されることはなく、後に残ったのは砲弾による建物への被害と心臓麻痺による死者3名のみだった。
また、アメリカ軍は空に現れる明るい火の玉に悩まされていた。戦時中に目撃された火の玉の最古の報告は1941年9月、英国籍の兵員輸送船プラスキ号の船員が見た、満月の半分ほどの大きさの発光体とされる。
1943年頃からは多くのパイロットがその火の玉を目撃、搭乗機が火の玉に追いかけられたという報告もなされるようになった。
アメリカ軍はこの火の玉を同盟国側の新兵器かと疑ったが、捕虜になったドイツ人や日本人のパイロットを尋問するうちにその考えは否定された。彼らもまた空中の火の玉にしばしば悩まされていたのだ。
この火の玉はフー・ファイターと呼ばれた。その由来は、当時のマンガ『スモーキー・ストーヴァー』の主人公の口癖〝Where there’s foo, there’s fire(フーあるところ火あり)〟をもじったものと言われる。
アーノルド事件を契機に、アメリカ軍は戦時中に現れたこれらの飛行物体について新たな見直しを迫られることになった。また、アーノルド事件報道の影響で全米各地から寄せられるようになった一般市民からの目撃報告にも対応する必要に迫られた。
マンテル事件
そんな中で起きたのが1948年1月7日のマンテル事件だ。その日、空軍にケンタッキー州、テネシー州、オハイオ州の各地から奇妙な飛行物体を目撃したという報告が相次いだ。
午後2時45分頃、ケンタッキー州フォート・ノックス近くのゴッドマン空軍基地付近を飛行していた同州空軍州兵のF51ムスタング戦闘機の編隊は、ゴッドマン空軍基地からの連絡を受け、飛行物体の追跡にむかった。
3機の編隊のうち、もっとも飛行物体に接近したトーマス・F・マンテル・ジュニア大尉は、他の2機が離脱した後も追跡を続けた。彼は基地管制塔に、飛行物体が巨大なこと、戦闘機の半分ほどの速度で移動していることを連絡し、午後3時15分頃消息をたった。その日の夕方、捜索に向かった部隊が発見したのは散乱するマンテル機の残骸だった。
やがてこの遭難事故についての話題は、マンテル機は飛行物体が放った光線で撃墜された(目撃者はいない)、マンテル大尉の遺体がなかった(実際には操縦席についたままで発見)、機体残骸が放射能汚染されていた(その事実はない)などの尾鰭がついた形で流布することになった。
空軍軍人の中から、ついにUFOとの遭遇による「戦死者」が出た……軍人たちからしてみれば、UFOは同じ釜の飯を食った友の敵だ。本部も本腰を入れて調査にとりかからなければならない。
UFO研究機関としてのアメリカ空軍
アメリカ空軍には1947年12月からプロジェクト・サインというUFO調査機関がおかれていたが、それはプロジェクト・グラッジと改名され、さらに1952年3月にプロジェクト・ブルー・ブックと名付けられた。
プロジェクト・ブルー・ブックは1969年に廃止されるまでの間、計1万2618件もの目撃報告を調査し、その約95パーセントまでを既知の現象や飛行物体、つまりは飛行機、天体、鳥、雲などの誤認とみなした。あのマンテル事件についても、マンテル大尉が追いかけたのは金星だったとした。
空軍では、プロジェクト・ブルー・ブックの他に外部にもUFO調査を委託した。それは当時上院議員だったジェラルド・フォード(1913〜2006、後に第38代大統領)の提案でコロラド大学学長エドワード・ユーラー・コンドン博士(1902〜1974)が設立したコンドン委員会だ。
コンドン委員会は69年1月に約1000ページものいわゆるコンドン・レポートを発表して解散した。コンドン・レポートは「UFO研究は科学的知識の発展にはほとんど何も貢献しない」と結論づけており、プロジェクト・ブルー・ブック廃止の原因ともなった。
しかし、プロジェクト・ブルー・ブックやコンドン・レポートの発表に納得しない人は多かった。プロジェクト・ブルー・ブックの初代指揮官だったエドワード・J・ルッペルト大尉(1923〜1960)は退役後の1956年、空軍上層部はUFOの真実を隠蔽していると主張した(ただし彼は晩年、UFO目撃はすべて誤認だという説に傾いていた)。
海軍退役軍人ドナルド・エドワード・キーホー元少佐(1897〜1988)は1949年からUFOの調査を開始し、1956年に民間UFO研究機関NICAP(全米空中現象研究委員会)を設立した。
彼は軍内部の人脈にも情報源を持っていたが、それだけ軍の秘密主義的体質に疑念を抱き、1964年にはアメリカ議会両院に空軍のUFO資料公開と公聴会の開催を陳情している。キーホーによると、かつて彼の盟友であったルッペルトの晩年の「変節」は軍上層部の圧力によるもので、そのストレスがルッペルトの寿命を縮めたのだという。
プロジェクト・ブルー・ブックの顧問には、天文学者で、後にノースウェスタン大学教授となるジョゼフ・アレン・ハイネック博士(1910〜1986)がいた。
彼は軍のプロジェクト終了と同時に民間機関CUS(UFO研究センター)を立ち上げ、後半生をUFO研究に捧げた。ハイネックはUFO目撃の実例を検討するうちに公式発表とは別の見解を持つようになり、空軍は目撃報告の誤認率を高く見積もりすぎていると批判した。
プロジェクト・ブルー・ブックは、いわば身内ともいうべき人々からも批判されてしまったわけだ。キーホーやハイネックは長らくアメリカの、そして世界のUFO研究を指導する立場となる。彼らの軍や政府への不信感は多くの研究家に共有されるものとなった。
なお、マンテル機墜落の直接の原因は、戦闘機の高度が上がりすぎたための気圧低下で大尉が気を失い、操縦不能に陥ったためと思われる。
また、マンテル機が追跡した飛行物体の正体は宇宙人の乗り物でも金星でもなく、気球だった可能性が高い。ルッペルトも後の調査で、海軍の調査用気球がゴッドマン基地近くで打ち上げられていたことを確かめたという(この気球については後述)。
ところで、冷戦時代のアメリカ軍にはUFOが宇宙人侵略の先兵ではなかったとしてもその研究を続ける必要、そしてその成果を秘密にする必要があった。
仮想敵国からの軍用機やミサイルに備えて、空軍はレーダーや偵察飛行によって空の守りを固めている。それらによって感知された飛行物体の正体がすべて判明するわけではないが、だからと言って敵の攻撃と即断してしまうと全面核戦争も起こりかねない。
だから、正体が確認できなくとも少なくとも敵の攻撃ではないという判断を下すためにUFO全般の研究をしなければならないし、その資料の出所はそのままアメリカの防衛網とつながっているため、秘密にしなければならないのだ。
結果としてプロジェクト・ブルー・ブック廃止後も、米空軍は全米、そしておそらくは全世界最大のUFO研究機関であり続けている。
ヒル夫妻とアブダクション
1950年代に入ると、空飛ぶ円盤と宇宙人はSF映画やコミックなどの題材としてすっかりおなじみのものになった。
もちろん、それらはまじめなドキュメントではないが、ここで重要なのはアメリカ国民にとってそれらがイメージを共有できるような身近な存在になったということである。
1961年9月19日深夜、バーニーとベティーのヒル夫妻はカナダでの休暇を終え、パンアメリカンハイウェイ3号線を一路、ニューハンプシャー州ポーツマスの自宅へと車を走らせていた。
ランカスターの南に差し掛かった時、ベティーは星のように輝く動く飛行物体を目撃した。その飛行物体は彼らの車を追うかのように動き、やがて空中で方向をかえて車から数十メートルのところまで迫った。
バーニーは車を止め、車外に出て双眼鏡で飛行物体を眺めていたが、やがてわめきだすとあわてて車に戻ってきた。2人は家に帰り着いたが、普通なら5時間で辿りつける道のりになぜか7時間もかかっていた。
翌1962年の暮れ、2人はボストンの精神科医ベンジャミン・サイモン博士の催眠治療を受けはじめた。
その結果、2人は空白の2時間に起きたことをようやく思い出した。彼らはUFOの中に拉致され、宇宙人から身体検査を受けていたのである。ベティーは髪の毛のサンプルを採取され、さらに臍から長い針をさしこまれて妊娠識別テストまでされたという。
ベティーは、UFOの中で宇宙人から見せられた星図を書いてみせた。アマチュア天文家のマージョリー・フィッシュはその星図を分析し、彼らが地球から23光年先のゼータ・レチクルという星から来たことをつきとめた。こうしてUFO神話に、宇宙人による拉致(アブダクション)という新しい要素が加わった。
なお、ヒル夫妻は幾度も逆行催眠によって拉致体験を思い出したが、だんだんその矛盾は大きくなっていった。ベティーは当初、宇宙人の顔立ちを黒髪で大きな鼻といっていたが、後の証言では禿頭でのっぺりした顔立ちとなっている(そしてその顔は偶然にもその証言を行う直前に放送されたTVドラマ『アウター・リミッツ』に登場した宇宙人にそっくりだった)。
バーニーもまた宇宙人に拉致されたことを証言したが、ベティーの証言の詳細さに比べて、その内容はシンプルだった。そして、バーニーはベティーからよく彼女が見る奇妙な夢のことを聞かされていた。
彼らは、バーニーがアフリカ系、ベティーがヨーロッパ系と当時では珍しい異人種間夫婦であり、周囲の好奇の目によるストレスも大きかっただろう。
しかし、UFO目撃証言で有名人になってから、彼らはかえって人目を避ける必要はなくなった。晩年のベティーはことさらに研究者たちの目を引くような言動をとるようになり、新たなUFO目撃証言をくりかえした。ヒル夫妻、特にベティーにとってUFO目撃証言は自己実現の場となっていた。
ヒル夫妻事件以降、宇宙人に拉致(アブダクション)されたという証言はアメリカを中心に次々と発表されるようになった。
特に、1978年を境にその件数は急激に増大した。また、拉致したという宇宙人の姿も灰色(グレイ)の肌に小柄、禿頭、大きな目とのっぺりした顔といういわゆるグレイ・タイプでほぼ一致している。
ちなみに前年の1977年には、拉致を含む宇宙人との接触体験を描いたスティーブン・スピルバーグ監督の映画『未知との遭遇』が大ヒットしており、その映画に出てくる宇宙人もグレイ・タイプだった。
宇宙人の目撃事例を調べていると、その姿に当時流行っていた映画やテレビ番組などの影響が明確に表れていることがある。ヒル夫妻事件はその典型である。
その本当の正体が何者であれ、連中はその時代の人にとって比較的イメージしやすい「宇宙人」の姿でUFOから降り立つ傾向があるらしい。
アダムスキーとコンタクティーたち
宇宙人に拉致されたという人々がいる一方で、宇宙人から紳士的な対応を受けたという人々もいた。
パロマ天文台関連で勤務していた教授ジョージ・アダムスキー(1891〜1965)は1952年11月20日午後12時半、カリフォルニアの砂漠で空飛ぶ円盤から降りてきた金髪の宇宙人と会った。
テレパシーで会話したところによるとその宇宙人はオーソンという金星人で、美女とみまごう容姿だったが男性だという。アダムスキーはその後、何度も宇宙人と会見し、宇宙文字が撮影された写真のネガや宇宙人の足跡といった証拠品も与えられた(それが本当に証拠になるかどうかはさておき)。
彼はさらに、火星人や土星人の招待を受けて自ら円盤に乗り、さまざまな星を訪れたという(ちなみに、アダムスキーによると現代の天文学は誤っており、火星や金星といった他の惑星はもちろん月や太陽も地球と似た環境で人が住んでいるという)。
アダムスキーはその体験(?)と宇宙人から与えられたという知見に基づく宇宙哲学を提唱、多くの著作と精力的な講演活動でそれを広めた。また、アダムスキーが円盤の写真を公開した後には同じようなUFOを目撃したという証言が多く発表されるようになり、その形状はUFO定番形式の一つとなった(いわゆるアダムスキー型)。
アダムスキーの著作からうかがえる宇宙人たちは、物理学の初歩的知識も怪しかったが、魂の輪廻や意識の向上といった実証できない問題にはくわしい方々ばかりだ。
また、アダムスキーの円盤写真にしても真空掃除機の部品を組み合わせることで同じ形ができることは早くから指摘されていた。
しかし、一方で多くの人がそれと同じ形状のものを空中に見た(と思った)こともまた確かなのだ。
ちなみにアダムスキーの「教授」はあくまで自称である。また彼がパロマ天文台関連で勤務していたというのは天文台近くのハンバーガーショップのことだった。
何にしてもアダムスキーが多くの支持者を得たのは確かで、それ以降、多くの人が宇宙人と会って教えを受けた、あるいは宇宙人からテレパシーでメッセージを受けたと主張するようになった。
そうした人々をコンタクティー(コンタクト=接触する者)という。たとえばプレアデス星人セムジャーゼとコンタクトしているというビリー・マイヤー(1937〜)や、複数の宇宙人とテレパシーで交信しているというアイリーン・レークス女史(1958〜、青森県出身の日本人)といった方々だ。
コンタクティーの中には世界的規模の教団を作って教祖におさまった人もいる。また、最近では日本の高名な新興宗教教祖が宇宙人との交信記録を書籍として刊行している。
1913年のイギリス映画『火星からの使者』には、悪人を更生させる使命を帯びて地球に来る善意の火星人ラミエルが登場する。キリスト教における守護天使のイメージを火星人に置き換えたわけだが、オーソンやセムジャーゼはこのラミエルの同類と言えそうだ。
フラットウッズ事件
さて、UFOから現れたという宇宙人の中には、グレイ・タイプや人間そっくりの者以外にもさまざまなバリエーションがあった。
人間離れした宇宙人たちの中で特に有名なのはフラットウッズモンスターである。
1952年9月12日午後7時15分頃、アメリカのウェストヴァージニア州フラットウッズの小学校で遊んでいた数人の子供たちが、光る物体が町の上空に現れ、郊外の丘に落ちていくのを目撃した。
彼らから話を聞いたキャサリン・メイ夫人は息子のエディ・メイ、フレッド・メイを含む子供たちと当時17歳のユージン・レモンを伴い、その落ちた物体を捜しに行くことにした。
丘に到着した彼らは、高さ6フィート(1・8メートル)ほどの円盤状の火の玉が光を点滅させているのを見た。周囲には鼻を突くような異臭が漂っていた。
そして、レモンが懐中電灯で照らしだした先には、フードのようなものをつけた身長10〜12フィート(3〜3・6メートル)ほどの怪物が両の目を光らせつつ、空中に浮かんでいるのが見えたのである。
彼らは恐怖にかられて丘を駆け下りた。メイ夫人からの連絡を受けた警察が出動し、彼らの証言をとった。この事件は地元の新聞に大きく取り上げられ、さらにメイ夫人とレモンがニューヨークのニュース番組に出演して目撃談を語ることで全米、さらに全世界の話題となった。
この時、メイ夫人らが見た怪物「フラットウッズモンスター」は、日本では「3メートルの宇宙人」の通称でも知られている。目撃者の当時の証言に基づくイラストは、日本でも多くの雑誌やオカルト本に転載された。
2002年9月、フラットウッズでは、12〜14日の3日間をかけてフラットウッズモンスター記念フェスティバルが開催された。その際、存命中の目撃者の証言に基づき新たなイラストが描かれたが、こちらはいかにもメカニックになっている。
UFOが着陸するのが目撃されたという事件は、しばしば怪物の目撃とセットになっている。そして、その怪物はUFOの搭乗員と解釈されることが多い。
たとえば、1954年11月28日にベネズエラのペタレで起きた目撃事件では身長1メートル足らずの小柄で毛むくじゃらな猿のような生物が出たとされるし、同年9月10日にフランスのカルブールではやはり身長1メートルほどの潜水服のヘルメットに足が生えたようなロボットが円盤とともに目撃されている(目撃者の名から、デワイルド事件と呼ばれる)。
1958年12月20日、スウェーデンのドメスデンでのUFO目撃事件では、その周囲にゼリー状の宙に浮かぶ生物が4体も出たという。フラットウッズ事件はそれらの中でも初期の事例である。
1950〜70年代にかけて、UFOとともに現れた怪物にはさまざまな姿があったが、実はその当時のB級映画にもロボット型、獣型、アメーバ型とさまざまな宇宙人や宇宙怪獣が登場していた。UFO搭乗者たちの多くは当時流行した架空の怪物たちと似通っていた(1980年代以降、UFO搭乗者がグレイ・タイプ主流になるのは先述の通り)。
なお、オカルト事件の真相究明で有名なジョー・ニッケル氏は、フラットウッズの現地調査を行い、光が点滅する円盤は飛行場の着陸塔、怪物は高い木の枝にとまったフクロウの見間違いで、異臭は現地の植物が発したものとのレポートを2000年に発表している。
しかし、いったんできあがった怪物のイメージはそうした分析など物ともしないほど強固なようである。
ロズウェル事件の再発見
UFO目撃事件のバリエーションが豊かになるにつれて、研究者により、忘れられた事例の発掘・再評価も進められた。
その最大の成果ともいうべきものがロズウェル事件だ。
1947年7月8日、アメリカのニューメキシコ州ロズウェル陸軍航空基地からマスコミにプレスリリースがなされた。その内容は「墜落した空飛ぶ円盤の回収に成功した」というものである。ケネス・アーノルドの目撃証言からわずか2週間ほどしかたっていないこの時期の発表は、まさにホットニュースだった。
ところがその直後に行われた記者会見では、円盤回収というのは誤りで、実際に見つかったのは気象観測気球の残骸にすぎないというものだった。こうして騒動はいったん終息する。
しかし1980年、ウィリアム・ムーア(1943?〜)とチャールズ・バーリッツ(1913〜2003)の共著でロズウェル事件に関する書籍が出されて以来、この事件は世界でもっとも有名なUFO墜落事件になってしまった(ちなみにバーリッツは英語学校で有名なベルリッツ家の一員)。
ムーアとバーリッツによれば、軍は実際にロズウェル郊外で墜落したUFOの機体と宇宙人の遺体を回収したが、それを秘密にするため、記者会見では虚偽の発表を行ったという。
ロズウェルとその近郊では、墜落した円盤や宇宙人の死体を見たという人々もいた(1980年以降に名乗り出た人もいる)。しかし、彼らの証言には矛盾が多く、墜落現場さえ特定できないという有様になっている。
さらに1995年には、ロズウェルで回収した宇宙人の遺体を解剖した記録フィルムなるものが現れ、日本でも1996年2月2日に『宇宙人は本当に解剖されていた!!』(フジテレビ系)という特番でとりあげられた。
しかし、このフィルムはあまりにも稚拙な偽造だったため、UFO研究者からも早々に相手にされなくなってしまった。ちなみにこのフィルムに映っている「宇宙人」は70年代末以降おなじみになったグレイ・タイプだ。
1994年、ニューメキシコ州選出の下院議員スティーヴン・H・シフは、アメリカ会計監査院に命じてロズウェル事件の再調査を行わせた。アメリカ空軍でも独自の調査を開始した。
翌年、会計監査院と空軍はそれぞれの報告を提出した。会計監査院は円盤が墜落した証拠も、軍が隠蔽工作を行ったという証拠も得ることはできなかった。
空軍の報告書は、1947年時点では軍事機密だったプロジェクト・モーガルの存在に触れていた。当時、米軍はソ連の核兵器開発の状況を確かめるためにロシアから気流にのってくる放射性物質を上空でとらえようと試みていた。それがプロジェクト・モーガルである。そのための気球の存在は軍内部でも担当部署以外には機密扱いだったため、ロズウェル基地がそれを回収した時に情報が錯綜してしまったのである。
1997年にはウィリアム・ムーアさえ、ロズウェルに墜落したものが宇宙人の円盤だったという説を撤回してしまった。しかし、いったん生まれた伝説はそう簡単に消え去ることはない。
1994年にはカイル・マクラクランが隠蔽工作に翻弄される軍人を演じた実録風テレビドラマ『ロズウェル』が放送された。また、1999年から2002年に放送された連続ドラマ『ロズウェル 星の恋人たち』も人気を博した。その他、映画やドラマ、ゲームなどでネタとしてロズウェル事件をとりこんだ作品は枚挙にいとまがない。
現在、ロズウェルには国際UFO博物館が建てられ、町の貴重な観光資源になっている。
ミステリーサークルとキャトル・ミューティレーション
草原で草が倒れて輪などの模様を描く現象は、ヨーロッパ各地で古くからよく知られていた。
伝説では、それらは妖精が踊った跡だとか悪魔が草を刈った跡として説明される。また、UFO研究がさかんになってからは、宇宙人の乗り物の着陸跡(ソーサーネスト、円盤の巣)とみなす説も出てきた。
1980年8月、イギリスの『ウィルトシャー・ジャーナル』は、ウェストベリーにある有名な地上絵・ホワイトホースの近くに、直径18メートルもの円形の草が倒れた跡が三つ現れたことを報じた。これがいわゆるミステリーサークル(イギリスではクロップ・サークルと呼ばれる)騒動の発端だった。
やがてイギリス南部の各地の麦畑などに複雑な幾何学図形を含む様々なミステリーサークルが現れ、さらにはヨーロッパ各国やアメリカ、カナダ、日本でも出現するようになった。
ミステリーサークルに含まれる複雑な図形は、自然現象の結果とは到底思えない。ソーサーネストからの連想もあり、ミステリーサークルが宇宙人からのメッセージとして作られたものだという説が現れるのは自然な流れだった。1996年には小型の空飛ぶ円盤が麦畑の上を飛び回るにつれミステリーサークルが形成されていく現場を撮影したフィルムまで公表された。
一方、やはり宇宙人のしわざと思われた現象にキャトル・ミューティレーション(家畜切断)がある。これは1970年代、アメリカの各地で報告された現象で、農場の牛や馬の行方が分からなくなり、見つかった時には血を抜かれ、眼球や性器などをえぐりとられた無残な死体になっているというものだ。
この現象については、宇宙人が地球生物の組織サンプルをとるためにレーザーで牛や馬を切断したという解釈がまことしやかに説かれるようになり、死体の発見現場にUFOが飛んでいた、UFOが牛をつりあげていくのを見たなどという証言者まで現れるようになった。
日本では1990年代、早稲田大学教授(当時)の大槻義彦氏がUFOそのものも含め、これらを総合的に説明する仮説を提示した。
それはすべて球電(空中放電で空気がプラズマ化したもの)のしわざとする通称プラズマ説である。つまりUFOは球電の見間違い、ミステリーサークルは球電の爆発で草が倒れた結果、キャトル・ミューティレーションは球電にあたったために動物の水分が多い組織が焼けた結果というわけだ(なおミステリーサークルと球電を結びつける説についてはイギリスに先行研究がある)。
しかし、実は大槻氏が乗り出す頃には、この2つの現象についてはほぼ解決がなされていた。
アメリカでは1980年に元FBI捜査官ケネス・M・ロメロ・ジュニアがキャトル・ミューティレーションの正体を実験で確かめていた。
牛の死体を牧草地に放置すると数日のうちに鳥や昆虫、肉食獣によって柔らかい組織が喰われ、血も流れ出してしまう。つまりは宇宙人もプラズマも関与することなく、〝キャトル・ミューティレーションされた〟死体ができあがるのだ。
ロメロは入念な聞き込みで、発見された家畜の死体と宇宙人を結びつける根拠となるような噂がウソや誤りばかりであることを調べ上げた。彼のレポートが発表されるや、アメリカ人のキャトル・ミューティレーション熱はいっぺんに冷めてしまった。
イギリスでは1991年9月、『トウディ』誌でダグ・バウワーとデビッド・チョーリーという2人組の老人が1970年代末以来、イギリス南部のミステリーサークルのほとんどを作っていたことを告白した。
麦畑に多く発生したのは、麦の茎は強く倒しても根元から抜けることがなかったからだった。ダグとデビッドは、ロープと木片を組み合わせた簡単な道具を使って効率よくサークル作りを進めることができた。他の地域のサークルはイギリスからのニュースに刺激された者たちの模倣だった。1996年のビデオもまたちょっと気がつけばトリックとわかるようになっていた(円盤が飛来する前から場面センターがサークルの中心になっている)。
ミステリーサークルは、今も世界各地に現れ続けている。ダグとデビッドが始めた遊びは、今も世界中のいたずら者たちを魅了し続けているわけである。
なお、彼らが作り始める以前のサークルについては何らかの自然現象が含まれている可能性がある。たとえば、生物学で「妖精の輪」といえば、地表にキノコの菌糸が広がって円形に草が枯れた場所ができることである。
MJ-12とエリア51
UFO目撃証言が度重なり、誘拐被害者やコンタクティーも名乗り出ているというのに、政府や軍は積極的に動こうとしない。
あるいは、政府や軍は正確な情報を握っているにもかかわらず、国民から隠しているのではないか。特に目撃証言が多いアメリカでこのような疑問を抱く人が出るのは自然だった。
1953年、コネチカット州ブリッジポートを本拠に会員を1500人以上を擁する団体IFSB(国際空飛ぶ円盤局)が「空飛ぶ円盤はもはや謎ではないが、その情報は上層部の命令で押さえられている」と宣言、解散した。
その主宰者が、3人の黒ずくめの男にUFO研究から手を引くよう脅されたと証言して以来、黒衣の男たち(MIB=メン・イン・ブラック)がUFO目撃者や研究家につきまとうという噂が次第に広まっていった。噂を広めた人々はその謎めいた男たちを政府のエージェントとみなした。
1987年、テレビ・プロデューサーのジェイム・H・シャンデラとウィリアム・ムーア(先述)、そして物理学者のスタントン・T・フリードマンはある文書を公開した。
それは、1952年11月18日にロスコー・H・ヒレンケッター海軍大将がドワイト・D・アイゼンハワー次期大統領(当時)へと宛てた機密文書で、UFO問題への国家的対応は大統領直属の極秘機関マジェスティック12(MJ-12)が行っていること、その機関は1947年におけるロズウェルでの墜落円盤回収に伴って設立されたことを示すものだった。
その文書はもともと、フィルムに撮影された状態で1984年12月11日、シャンデラの家に無記名の小包として配達されたものだという。
シャンデラらは、国立公文書館の中にこのMJ-12文書が本物であることを証明する文書を見つけたとも主張した。
しかし、すぐにMJ-12文書に使用されたタイプライターが62年に発売された型式であることや、文書の書式が50年代の公文書としてはありえないことが指摘された。国立公文書館の証拠文書なるものも(発見時から見て)つい最近に紛れ込まされたものであることも判明し、MJ-12文書は多くの研究者から相手にされなくなってしまった。
MJ-12と同様、UFO情報隠匿のための政府・軍機関としてよく話題になるのはエリア51だ。これはラスベガスの北北西にある実在の軍事基地で、そこでは米軍が回収した墜落円盤や宇宙人の遺体が保管されており、宇宙人のテクノロジーを応用した新兵器の開発が行われているという。
もっとも、この話をマスコミにリークしたロバート・スコット・ラザーは経歴詐称がはなはだしく(たとえば彼はマサチューセッツ工科大学とカリフォルニア工科大学を卒業したと主張しているが、どちらの大学にも彼に関する記録はない)、その証言はあまり信用がおけない。また、エリア51は今ではあまりに有名で、中に入れないまでも近くまで行って写真をとる観光客は絶えず、もはや極秘の研究などできそうにない。
UFOがらみで政府から流出した極秘情報と言われるものには、他にアメリカ政府が宇宙人と交渉して人間や家畜を用いた実験を黙認しており、そのための機関であるダルシー研究所では1979年に特殊部隊員66名が死亡する内紛があったなどというジョン・リアの証言、シャンデラらのMJ-12文書はダミーで実際の対UFO政府機関の名はマジョリティ12といい、かつてクリルという名の宇宙人がアメリカ国内に滞在していたというミルトン・ウィリアム・クーパーらの証言などがある。
彼ら証言者はごく近い人脈で結びついており、傍目からはホラ吹きクラブのように見えなくもない。
介良事件の小型円盤
1972年8月、夏休みも終わりに近づいたある日のこと、高知県高知市介良というところで数人の中学生が、田んぼの上をふわふわと飛んでいるハンドボールくらいの光る物体を見た。
その光る物体は、それからしばらくその界隈に出没していたが、9月の中旬、ついにその物体に布をかけて捕まえることに成功した。
それは大きめの灰皿を逆さにしたような形で、底部には小さい穴がたくさん開いていた。中学生たちが物体をさかさにしてその穴から水を注ぎこんだところ、やかんに2杯もの水が中に納まり、虫の声のような音が聞こえた。彼らはナップザックに入れて物体を持ち運ぼうとしたが、後でナップザックを開けてみるとその物体は姿を消していたという。
後には何の物的証拠も残らなかったが、中学生たちの証言は当時、テレビで取り上げられて話題になり、彼らの話を聞きに小説家の遠藤周作までが介良を訪れたほどだった。
UFO目撃事件については、その目撃されたものを宇宙人の乗り物と信じる人と、でっち上げや見間違いで片づける人の意見が平行線をたどることが多い。
しかし、そのどちらの立場からも解釈に困るようなどうにも座りの悪い事例はハイストレンジネスと呼ばれる。
1961年4月18日にアメリカ・ウィスコンシン州のイーグル・リバーで、老人が自宅庭でUFOから降りてきた人物と遭遇したという事件では、その人物は老人にクッキーのようなものをくれた。そのクッキーの成分は小麦粉、砂糖、油脂と地球のものと変わらなかったが、なぜか塩だけは使われていなかった。
1979年にイギリスのブルーストンウォークのジーン・ヒングリー夫人が出会ったUFOからは、身長1メートルほどで背中に水玉模様の翼が生え、透明のヘルメットをかぶった小人が3人降りてきた。小人たちはヒングリー夫人に光線銃を撃って痛がらせたあげく、夫人が煙草を一服しようと火をつけたとたんたちまち逃げ出したという。
これらのように、とても本当の話とは思えないが、わざわざでっちあげるのはあまりに間が抜けた展開の事例、それがハイストレンジネスだ。介良事件は日本で起きた典型的なハイストレンジネスである。
あるいは、こうしたハイストレンジネスにこそ、UFO目撃や宇宙人遭遇事件の本質が現れているのかもしれない。
ハイストレンジネス事例におけるUFOや宇宙人の振る舞いは、民間伝承における妖精や妖怪、神々などを連想させるものがある。
介良事件の捕えられた円盤にしても、人を化かす河童なり狐なりを捕らえたが逃げられてしまったという内容の民話は日本各地に伝わっている。イーグル・リバーで宇宙人がもたらしたというクッキーには塩が含まれていなかったが、西洋の民話では妖精は塩を嫌うとされている。ヒングリー事件の翼が生えた小人と言えば絵本の妖精画そのものの姿だ。
さらに言えば、こうした類似はハイストレンジネスに限ったことではない。
西洋には妖精が人をさらうという話もある(すなわちアブダクション)。また、貢物として家畜の臓物や肉を求める神は多くの神話に登場する(すなわちキャトル・ミューティレーション)。
そして、その中には、西洋で教養の基本とされるギリシャ神話や、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教の信仰の基礎とされる旧約聖書も含まれているのである。
つまり、かつては妖精を見たとか、妖怪に化かされた、神に出会ったなどと伝えられたのと同じ現象が現代ではUFOや宇宙人との接近遭遇という形で現れているという考え方がなりたつのである。
もちろん、その現象が実際には何なのか、さまざまな解釈の余地はあるだろうが、その現象は古代から形を変えつつ、現代のUFOまで綿々と続いているわけだ。
ところで、本書序文で私自身が目撃したUFO事例について記したが、今にして思えば、あれは2つのサーチライトが雲に映って生じた光の輪だった可能性が大である。
しかし、あの時の私たちにとって、天空に浮かぶ光はその正体がわからないという意味でまさに「未確認飛行物体」だったのである。
