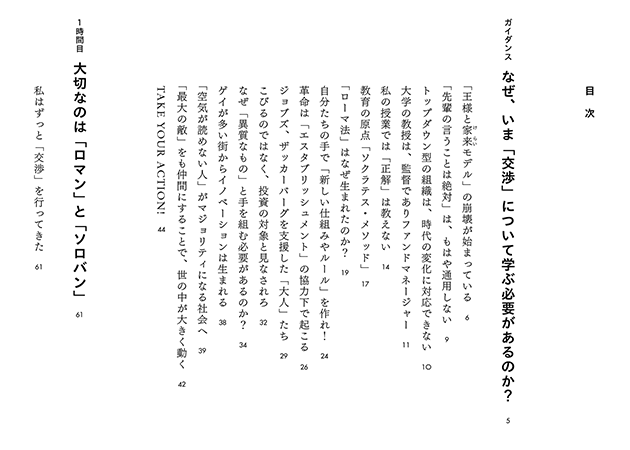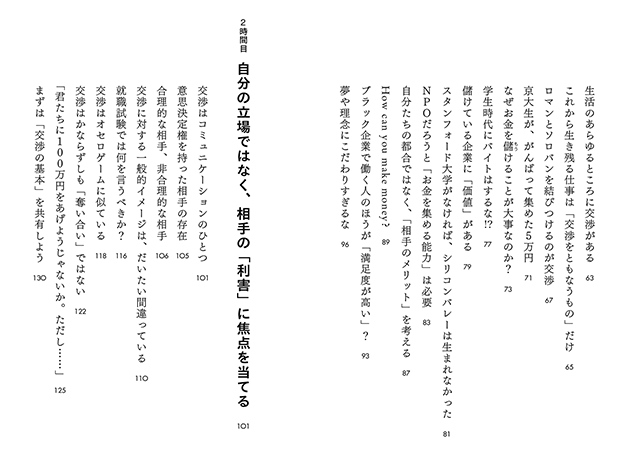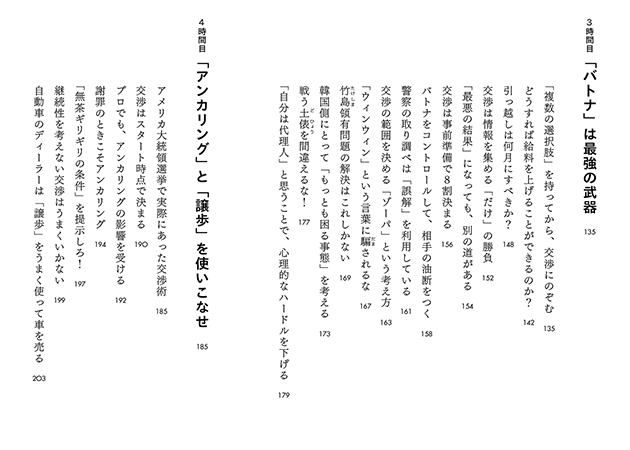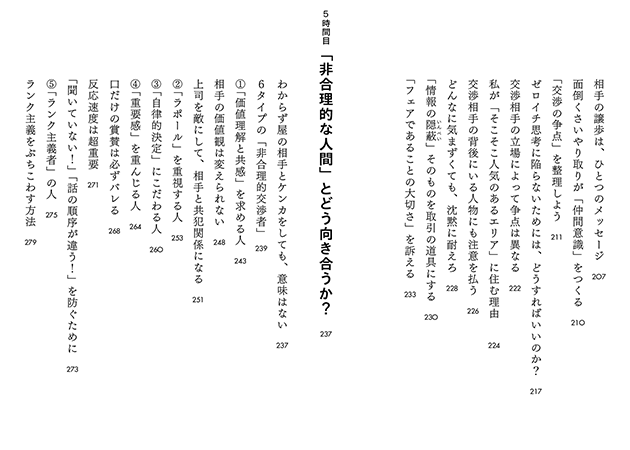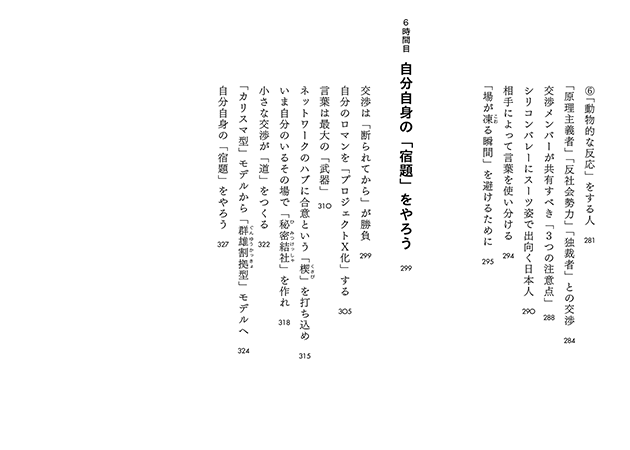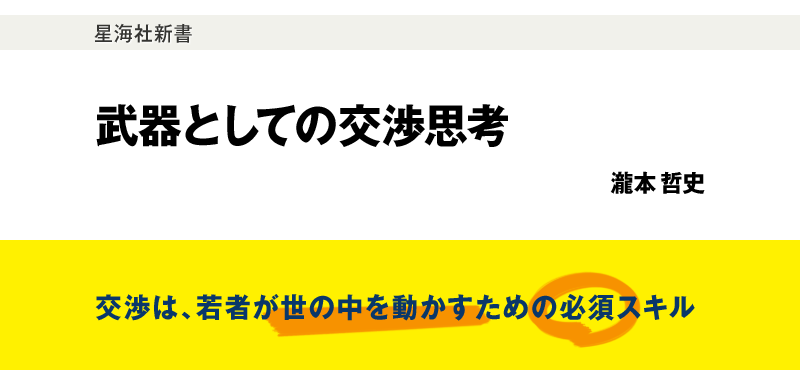
武器としての交渉思考
瀧本哲史
世の中を動かすためには、自分ひとりの力ではとても足りない。ともに戦う「仲間」を探さねばならない。そして、彼らを味方にし、ときには敵対する相手や、自分たちよりもはるかに巨大な力を持つ「大人」とも、「交渉」によって合意を結ぶ。そうやって初めて、世の中を動かしていくことができる。そう、交渉思考こそが今の君たちに必要な〝武器〟なのだ。
世の中を動かすためには、自分ひとりの力じゃとても足りない。
ともに戦う「仲間」を探し出さなければならない。
そして、彼らを味方にし、ときには敵対する相手や、自分たちよりもはるかに巨大な力を持つ「大人」とも、「交渉」によって合意を結ぶ。
そうやって初めて、世の中を動かしていくことができる――。
そう、交渉こそが、
いまの君たちに必要な
〝武器〟なのだ。
ガイダンス なぜ、いま「交渉」について学ぶ必要があるのか?
こんにちは、瀧本哲史です。
本書は、私がいま、京都大学で二十歳前後の学生に教えている「交渉の授業」を一冊に凝縮したものです。
「交渉」というと、みなさんはどういったものをイメージしますか?
おそらく、企業間のビジネス交渉であったり、犯人を言葉で説得する「交渉人」なんかを思い浮かべるのではないでしょうか。
では、どうして私は、ビジネススキルや説得手法のひとつに数えられることが多い「交渉」を、わざわざ学生に向けて教えているのか?
少し長い前置きになりますが、まずはそのあたりのことからお話ししたいと思います。
キーワードは「時代の変化」と「仲間」、そして「同盟」「革命」です。
同盟、革命などと聞くと、少々ぶっそうな感じがするかもしれませんが、いまの若い人には確実に必要な視点になります。
では、さっそくガイダンスを始めましょう。
「王様と家来モデル」の崩壊が始まっている
私が現在、メインで教えているのは、京都大学のいわゆる教養課程ですが、それ以外にも複数の組織・団体から呼ばれて、年に何度かお話しさせていただく機会があります。
依頼されるテーマで多いのが、私が専門とする「ディベート」です。
ディベートとは、あるテーマを設定し(たとえば「選挙の棄権に罰則を設けるべきか、否か」など)、賛成と反対の立場の双方に分かれて意見を戦わせ、第三者の審判にどちらが正しいか判定をゆだねる、という議論の方法のひとつです。
論理的で正しい議論の仕方を学ぶのに効果的なため、「言葉のスポーツ」とも呼ばれています。
最近では、高校の総合学習の時間などにも取り入れられるようになり、私もいろいろなところで正しいディベートの方法について講義するようになりました。
これまで意外なところでは、海上自衛隊からディベートについて教えてほしいという依頼があり、何度か研修を行ってきました。また、Jリーグのユースチームからも頼まれて、若いサッカー選手たちにディベートについて話したことがあります。
この2つのプロフェッショナルな組織が、わざわざ一般の民間人である私のところにディベートの講義を依頼してきたことに、私はひとつの大きな時代の変化を感じました。
その変化とは、ひと言でいえば、あらゆる組織における「王様と家来モデル」の崩壊です。
最近ではそんなことはありませんが、自衛隊といえば、ひと昔前のイメージでは「上官の言うことは絶対」というのがあたりまえ。ときには鉄拳制裁も辞さない、まさに文字通り「鉄の規律」が支配する軍隊型の組織と思われていました。
実際、かつての旧日本軍はそのような組織でした。
戦場では兵士の敵前逃亡は許されません。たとえ死ぬことがほとんど確実な作戦でも、上官の命令には絶対に従わなければならない。だから、「王様」である上官の下に何層もの「家来」である部下がいる、強固なピラミッド型の組織を作っておく必要がありました。判断するのは、ピラミッドの上層部だけでよかったわけです。
しかし、いまの自衛隊は、旧日本軍とはかなり違う、非常に洗練された合理的な組織です。いくら上官といえども、ワケのわからない命令を下したり、無意味に部下を命の危険にさらすようなことは厳しく禁じられています。
また、自衛隊の隊員の多くは、平和な日本で生まれ育った若者です。上司からのあまりに無茶な指令や、一方的な暴力をともなうような指示がくり返し行われていたら、「こんな組織にはいられない」と判断して、辞めてしまって当然です。
せっかく苦労してリクルートしてきた若者を、何年もかけて一人前の自衛官に育てたのに、辞められてしまっては元も子もありません。
だから自衛隊でも、きちんと上司が部下に対してロジカルに意図を説明し、良好なコミュニケーションがとれる関係を築いておく必要があります。上官と部下に強固な信頼関係があってこそ、厳しい訓練や困難な災害救助活動にも立ち向かうことができるのです。
そこで自衛隊では、主に幹部候補を対象に、いろんな組織マネジメントやコミュニケーションの手法を勉強させるようになった。
その研修の一環でディベートを学ばせたいと考えて、私にお声がかかったというわけです。
「先輩の言うことは絶対」は、もはや通用しない
Jリーグのユース選手にディベートを教えるのも、同様に大きな時代の趨勢によります。
大学の運動部に代表される日本の体育会も、ひと昔前は「先輩の言うことは絶対」の年功序列型組織がほとんどでした。
しかし、いまの時代、そんなチームが勝ち続けることはできません。
とくにレベルが上になればなるほど、「なぜチームでこの練習をすべきなのか?」「自分たちの弱点はどこで、どうやって克服すればいいのか?」といったロジカルな思考が、ひとりひとりの選手に求められます。
そして、考えたことをきちんと相手に伝えて、相手にも同意してもらう必要がある。
Jリーグでも、海外で活躍する選手が増えるにつれて、日本人選手には、サッカーのスキルだけではなく、チーム内外でのコミュニケーションスキルが問われるようになっています。
チームのなかでどうして自分がそのようなプレイをしたのか、自分が考えるサッカーとはどんなものなのか――そういうことをきちんとチーム内で主張し、意見を戦わせ、共通の目標に向かって合意することが、優秀な選手になるためには必須となってきている。
そこで、選手たちがディベートの技術を学ぶことになったのです。
トップダウン型の組織は、時代の変化に対応できない
私がみなさんに自衛隊とJリーグチームの話をしたのは、「上の偉い人が言うことに従っていればいい」という「王様と家来モデル」が、ピラミッド型組織の代表と思われているようなこの2つの組織においても、とっくの昔に終わってしまっている、ということをお伝えしたかったからです。
「王様と家来モデル」というのはつまり、上の立場の人間が下の立場の人間に「このようにふるまえ」と秩序を強要し、下の立場の人間はそれに対して基本的に反論の権利を持たない状態のことを指します。
かつての日本では、社会を構成するもっとも基本的な単位であった「家庭」も、家父長という王様の下に家族がいるモデルで運営されていました。そして、会社をはじめとする社会を構成する組織も、それに倣って構築されていました。
しかし最近になって、この「王様と家来モデル」型の秩序は、あらゆる組織で通用しなくなってきています。
「王様と家来モデル」では、家来がいち早く状況の変化に気づいても、その情報が意思決定権を持つ王様のところに上がっていくまでに、長い時間がかかります。
そして、ようやく王様が方針を決定しても、その指令が現場に降りるまでにはさらに時間を要し、実行するときにはとっくの昔に状況が変わっている、といったことがよく起こります。
また、家来の人間には、基本的に判断する権利が与えられていないので、王様の判断が間違っていても指令を実行するしかなく、その結果、さらに状況を悪くしていきます。
つまり、「王様と家来モデル」のように指揮系統がトップダウンの組織は、必然的に状況の変化に機敏に対応できなくなり、誤った方向に向かったとしても引き返せなくなるのです。
大学の教授は、監督でありファンドマネージャー
太平洋戦争に敗北した旧日本軍が、まさにこのタイプの組織でした。
昨今の経済のグローバル化で苦境に陥っている多くの日本の大企業も、組織のシステム自体に問題があるために、環境の変化に対応できなくなっているように見えます。
私が身を置くアカデミズムの世界も、かつては「王様と家来モデル」が普通でした。ドラマ『白い巨塔』で描かれたように、絶対的な力を持つ教授の下に、家来のような助手たちが従っているという図式です。
いまでも一部で残っているようですが、そのような研究室から驚くような研究成果が生まれることはほとんどありません。
イノベーティブな発見が生まれるのは、若いスタッフが自由に研究を行っているところばかりです。そういう研究室では、大学や企業から研究資金を集めてきて、若手のスタッフがどんどん新しいことにチャレンジできる環境を整えるのが、教授のもっとも重要な仕事になっています。
たとえば、新しい成果をつぎつぎと生み出している京都大学工学部のある半導体系の研究室では、「あなたの研究テーマなら、企業と合同で研究を行ってみるといい」「君は大学で研究者として、じっくりアカデミックに研究を続けてみたらどうか」「修士論文は少しチャレンジかもしれないが、研究者として生きていくために、こういったテーマでやってみては?」などと、教授が研究者それぞれの適性や願望に合ったテーマを選んだり、アドバイスする仕組みができあがっています。
そして実際、その研究ができるように、大学や企業と交渉して資金を集めたり、合同研究のアウトラインを決めたりするのも、教授の仕事となっています。
研究者にとっては、その研究室に行くことは自分自身を「投資する」ことと同じです。教授は、彼らの才能や努力をうまく「運用する」ことによって、研究室全体の利益を最大化しながら、同時に在籍するメンバーたちのキャリアも向上できるよう、舵を取っているのです。
とくにその教授が注意しているのが、企業のニーズと学生・研究者のニーズと研究室のニーズの3つをうまくマッチングさせて、バランスをとることだと言います。
これは、「オレがこの研究をするから、おまえらはただ手伝え!」といった、従来の「王様と家来モデル」ではありません。教授は、チーム全体の監督であり、ファンド運用者なのです。
私から見れば、その教授の研究室は、もはやベンチャー企業に近い。
こういった新しい組織から、時代を変えるイノベーションは起こってくるのです。
私の授業では「正解」は教えない
大学の授業も、変わりつつあります。
これまで、一般的な大学の授業のプロセスは、先生が大教室でたくさんの学生に向かって講義をし、学生はそこで教わった情報や知識を暗記して、テストでそれらを再確認する、というのがふつうでした。
そこでは先生が「王様」、学生が「家来」という立場だったわけです。
しかし、最近、NHKの番組がきっかけで大きな話題となった、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の授業は、かなり様子が違っていました。
授業で扱うのは「正義とは何か」といった捉えどころのないテーマ。先生と学生同士が「5人の命を救うために、1人を見殺しにするのは正しい行いか?」といった問題に対して意見を述べ合い、とことん議論を突き詰めて考えていきます。
しかし、最終的に「これが正しい」という正解は提示しません。
京都大学で私が行っている授業も、このサンデル教授の授業と同様に、いつも「答えがないもの」をテーマに扱っています。
たとえば、「起業」です。
どんな会社を作ればいまの時代、継続的に収益を上げて、世の中に求められる製品やサービスを送り出すことができるのか? 過去の成功、あるいは失敗したケースを取り上げて、学生たちと討論しながら、何が命運を分けたのかを探っていきます。
しかし、いくら過去の事例を取り上げたところで、会社を取り巻く社会状況は時代とともに刻々と変化していきますので、起業に関して「絶対にこうすれば成功できる」という正解は存在しません。
だから私の授業では、教壇に立つ私の意見を一方的に教えるのではなく、インタラクション(相互の交流)をとても重視しています。
教師である私や、自分以外の学生が何かの情報を発信したら、ひとりひとりがそれについて自分の頭で考えて、カウンターとなる意見を出すように求めます。
先生が常に正しいことを言っているというわけではない、という前提がクラス全員に共有されているので、私の考えが、ひょっとすると学生に論破されるかもしれません。
この形式の授業には「王様」も「家来」も存在しません。教員と学生には、ある種の対等性があるわけです。
私がよく知る東京大学の若手教員は、授業中に学生がツイッターをやることを全面的に認めています。
「ケータイ禁止!」「パソコンは鞄にしまっておけ!」といった先生が多いなか、その授業では、学生たちにツイッターで感想や反論、わからない点を投稿させ、学生同士のやりとりを活性化させたり、そのツイッターの投稿に教壇に立つ先生自身が反応したりすることで、授業を一方通行のものにはしまいとしているのです。
もちろん、ツイッターに熱中しすぎて授業内容への理解がおろそかになってしまっては本末転倒ですが、教わった内容をただ暗記するだけの「死んだ授業」を変えていこうとする流れがいま、私やこの先生にかぎらず、各大学の若い先生を中心に起きています。
知識や情報の確認テストでいくら良い点数をとっても、いまの時代にはほとんど無意味でしょう。漢字の読み書きが典型ですが、いまやネットで検索すれば漢字検定一級の問題であっても、誰でも10秒で答えが出せます。
「誰でもできること」に価値はありません。そして、「誰でもできること」しかできない人材は、いまの時代、確実に買い叩かれる運命にあります。
だから、思考力や洞察力、想像力を育むかたちに大学教育も変えていかなければなりません。若手教員のあいだで双方向の授業への流れが生まれているのは、時代の変化を反映させてのことなのです。
教育の原点「ソクラテス・メソッド」
じつは、いまの日本の大学で一般的に行われているような、一斉方式・一方通行の授業スタイルは、中世にイタリア・ボローニャ大学で発明されたものです。
本来的な知のあり方、勉強の仕方とは、サンデル教授がハーバード大学でやっているように、学問の場に集う人々がひとつのテーマについてとことん話し合い、議論を戦わせて、ゴールを探すというスタイルでした。
この対話形式の授業を、別名「ソクラテス・メソッド」と呼びます。
哲学者のソクラテスが弟子との問答を通して「真理」の追究にあたった故事に由来する方法であり、いまから2400年前の古代ギリシャの時代から近代まで、それは王道の教育スタイルだったわけです。
そもそも、教育(education)という言葉は、ラテン語で「引き出す」という意味のエデュカーレ(educere)が語源だと言われています。
つまり、上の立場の人間の考えを「押しつける」ことでも、正解を「詰め込む」ことでもなく、相手から思考力や洞察力、想像力を「引き出す」ことこそが、教育本来の姿なのです。
ソクラテス・メソッドは、まさに正統な教育のあり方だと言えるでしょう。
ちなみに、現在でもソクラテス・メソッドで授業を行っている代表的な教育機関として、ロースクールとビジネススクールがあります。
その2つの学校に通う学生たちが目指すところは、法律家と経営者です。
裁判にも経営にも「絶対の正解」はありません。だから、どちらの職業にとっても必要なのは、「議論を通じて最善解を探し、自分の意見の賛同者を増やしていく」という姿勢となります。
この2つの教育機関が伝統的にソクラテス・メソッドを採用しているのは、必然的であると言えるでしょう。
日本では明治時代以降、ひたすら上から与えられた「正解」を「暗記する」ことが、正しい勉強であると思われてきました。
そのため、大学の授業も(もっと言えば、小中高校の授業も)「王様と家来モデル」で運営されてきましたが、それに変化の兆しが出てきているのは、議論を通じて「いまの最善解」を探す必要性が、時代の要請として高まってきているからかもしれません。
「ローマ法」はなぜ生まれたのか?
自衛隊やJリーグの変化とアカデミズムの世界の変化、双方に共通するのが、「上から与えられる〝正解〟ではなく、自分たちで〝答え〟を導き出す」という姿勢への転換です。
それは言葉を換えると、「自分たちで考え、自分たちで〝秩序〟を作り出す」行為とも言えるでしょう。
しかし、そういった考え方自体は、けっして新しいものではありません。
人類史をひもとくと、人々が集まって、話し合い、合意して秩序を作り出すという社会のあり方には、2000年以上の歴史があることがわかります。
その最初の具体的な姿が「ローマ法」です。
古代ローマで暮らしていた「自由人」と呼ばれる人々は、「奴隷」とはちがって、自分たちの意思で自由に物事を決めて、行動することができました。
しかし、自由人同士が各々の意見を戦わせているうちに、ときには言い争いが起こります。対立が発展して、武力をともなう戦いに結びつくこともありました。
そこで彼らは、「自律的に物事を考えることができ、それぞれ武力を持っている複数の自由人が、暴力的な手段をとることなく、お互いが合意することによって秩序を作っていこう」と考えました。
そうして生まれたのが「契約」に基づく最初の法律、「ローマ法」なのです。
ローマ法ができる以前の古代文明の社会秩序というのは、「全能の神」によって上から与えられるものでした。
王様は、天上の神が定めた秩序を代行する権利を持っているとされたわけです。
そして、社会での「契約」、つまり「誓い」や「約束」も、神に対してするもので、人間に対してするものではありませんでした。
いまでもその名残が見られるのが、西洋式の結婚式です。
キリスト教の結婚では、新郎新婦は永遠の愛をお互いに誓うのではなく、神に対して誓います。
その結果、ふたりは終生変わらぬ愛情を持ち続けるようにと「拘束」されるわけです。
「神に対する契約」ではなく「人間同士の契約」が効力を持つようになったのは、ローマ法の成立からになります。そのときから人間社会では、ふたりの人間がお互いに合意すれば、契約が成り立つことになりました。
ローマ人たちは、この考え方を「パクタ・スント・セルヴァンダ」(合意は拘束する)と呼びました(厳密に言うと、合意が拘束力を持つには、ローマでは合意したうえで一定の要式を満たす必要がありましたが、少し脇道にそれるのでここで詳しくは述べません)。
ちなみに、私が法学部の学生だった頃は、この言葉が冗談としてよく使われ、たとえば「12時にどこどこで会おう」と友人と決めると、「パクタ・スント・セルヴァンダ」と最後に言うのがお約束になっていました。
この「契約が人間を拘束する」という考え方は、現在の法秩序の根本となっています。
スイス生まれの哲学者で、フランス革命にも多大な思想的影響を与えたジャン=ジャック・ルソーは、この考え方を「社会契約論」と名づけました。
私たちがいま生きる社会の基本となる国家や政府というものの仕組みも、「みんなが契約して合意のもとに作られた」と考えられているのです。
束縛があって初めて自由が得られる
みんなが「契約を守ろう」と約束することで社会が健全に回っていく――これが民主主義にもとづく近代国家の基本理念です。
契約は、守らなければ何らかのペナルティが科されます。そういう意味で、契約とは必ず個人にとって「自由を束縛するもの」になります。
しかし、なぜわざわざ、お互いに自由を束縛する必要があるのでしょうか?
それは、全員が完全に自由になると、他者の自由と衝突するために、かえって不自由になってしまうからです。
たとえば、みんなでひとつのシェアハウスを借りて、各自が勝手気ままに生活したらどうなるでしょうか?
共有スペースや台所はゴミだらけとなり、悪臭を放つようになるかもしれません。好き勝手に友達を連れ込んで連日のように騒ぐ人がいたら、他の住人は不愉快で仕方ないでしょう。
共同生活を円滑に運営するためには、面倒であってもゴミ出しや掃除の当番を決めて、互いに迷惑をかけないように最低限のルールを作ることが必要となってくるわけです。
しかし、そこで大切なことがあります。
それは、「自分を束縛するルールは、他の人との合意に基づいて決めなければならない」ということです。
もし誰かが「門限は9時ぴったり。それまでに帰って来ない人は、絶対に中に入れません!」などと一方的なルールを強制してきたら、それは他の人の自由の侵害に当たりますし、そんな不自由な思いをするくらいなら、わざわざシェアハウスに住む必要はありません(ちなみに、そのシステムで運営されているのが「寮母」のいる学生寮などです)。
だから、住人同士が話し合って、「冷蔵庫のなかのものは勝手に食べない」「光熱費は頭数で割って毎月何日までに払うこと」といった最低限のルールに関しての「合意」を結ぶことで、できるだけ自由度を高めながら、快適に生活できることを目指すわけです。
これは社会でも一緒です。
みんなが自由に生きるためには、必要最低限のルールを合意に基づいて決めて、各自が守っていく。そうすることで「自由を最大化」することができるというわけです。
ルールというのは、社会でいうところの「法」になります。
つまり、「自由主義」と「法治主義」というのは、じつは表裏一体の関係なのです。
自由になった人は、つぎに「どういう場合ならば、自分は拘束されてもいいのか」「どんな場合は、相手を拘束していいのか」という問題を他の人と話し合って、意思を一致させておく必要があるわけです。
自分たちの手で「新しい仕組みやルール」を作れ!
社会のなかで真に自由であるためには、自分で自分を拘束しなければならない。
だから、何に拘束されるのはオーケーで、何に拘束されてはいけないのか、あくまで自分で決めなければいけません。
話し合いの相手が自分よりも強い立場にいることもあるでしょう。しかし、その強い相手に対しても、自分が合意した結果として拘束されるのであって、強制的に約束を守らされてはいけないのです。
その合意を作り出す手段こそが、この本のテーマである「交渉」になります。
交渉とはけっして、単なるビジネススキルではないのです。
人間が何千年もかけて作り出してきた民主主義の社会は、人々が交渉した結果である「合意に基づいた契約」を行うことで、秩序を生み出していくのが基本となります。
ところが、時代や国によっては、そうではないことも多々ありました。
私たちが住む日本も、かつては個人が職業を選ぶこともできなければ、住む場所も勝手には決められませんでした。
誰か偉い人が「こうやって生きろ」と命令したことに、従わざるをえなかったわけです。
太平洋戦争の終結によって、民主主義国家として生まれ変わったあとでも、日本社会は真の自由人同士が作る社会ではない側面が強く残っていました。
地縁や、血縁や、社縁といったしがらみがあったことや、世間の「空気」を重んじる価値観などが理由かもしれませんが、「お上の言うことには逆らうな」という雰囲気が長い間あったことは確かです。
それは、いまでも色濃く存在しています。
しかし、さきほども述べたように、もはやその「王様と家来モデル」で生きていくことは、誰にとっても困難な時代となってきています。
2011年に起きた東日本大震災と福島の原発事故は、盤石と思われてきた日本の社会システムがいかにもろいものであったかを、白日の下に晒しました。
国の財政は破綻が懸念され、年金などの社会保障が今後もきちんと続くかどうか、誰にもわかりません。
日本の高度経済成長を支えてきた大企業のいくつかは、いつ倒産してもおかしくない状況となっています。今後は、中国やインドの企業に買収されるようなことが、日常的に起きてくることでしょう。
これまで日本を支えてきた「頭の良い偉い人が作った仕組みやルール」が、もはや通用しなくなってきているのです。崩壊はしてないまでも、明らかに機能不全を起こしている。そういったことが、誰の目にも明らかとなりました。
だからこそいま、若い世代の人間は、自分たちの頭で考え、自分たち自身の手で、合意に基づく「新しい仕組みやルール」を作っていかなければならない。
そのために、交渉の仕方を学ぶ必要があるのです。
革命は「エスタブリッシュメント」の協力下で起こる
前置きが長くなりますが、さらに大きな視点で、いまこそ若い人が交渉を学ぶべき理由について、説明していきたいと思います。
どの国のどの時代であろうと、社会が大きく変わるとき、その運動の中心を担うのは、20代、30代の人間です。
日本の明治維新も、その中心となったのは20代後半から30代前半の若者でした。
明治維新のきっかけとなった薩長同盟が締結されたとき、薩摩藩側の代表をつとめた大久保利通は35歳。長州藩の木戸孝允は32歳でした。
戊辰戦争で最後まで新政府に抵抗したのちに、明治政府の重臣となった榎本武揚は、31歳で海軍のトップに就任しています。
日本の初代総理大臣、伊藤博文は、大久保利通が死んで36歳で内務卿となり、その時点で事実上の国政のトップに立っています。
これは、いまの政治家と比べれば一目瞭然ですが、驚くべき若さです。
しかも、彼らの多くが地方出身者であり、若いときには暴勇で知られて、武士とはいえ「郷士」と呼ばれる下層階級の出身、そんな人ばかりでした。
しかし、変革期の国家で若い人が社会の中枢に躍り出るのは日本だけではありません。アメリカの独立も、フランス革命も、近年、アフリカ北部や中東の国々で連鎖して起きた、ジャスミン革命を発端にした「アラブの春」も、その前線で戦ったのは常に若者です。
さまざまな国でこれまでに起こされてきた革命は、ほとんどすべてが若者たちの手によって成し遂げられてきたのです。
しかし、ここで見落としてはならない重要なことがあります。
それは、革命の裏には必ず、若者たちをバックアップするエスタブリッシュメント層(社会的な権威・権力を持つ人々)がいたということです。
日本の明治維新を担ったのは、坂本龍馬や高杉晋作などの志士と呼ばれた若者たちでしたが、彼らの多くは自分の生まれた藩から「脱藩」しています。
当時の藩の決まりでは、脱藩に対する刑罰は死刑であるのがふつうです。
ところが、志士のひとり、江藤新平は、生まれ故郷の佐賀藩を脱藩したあとに帰郷しますが、前藩主であった鍋島直正は、彼の才能を高く買っていたために無期謹慎に罪を軽減し、江藤の命を救ったのです。
それにより江藤は政治活動を継続することができ、のちに明治新政府に加わることになりました。
また、長州藩出身の桂小五郎(のちの木戸孝允)も、10代のときから藩主・毛利敬親に特別に目をかけられ、藩の若き俊才として優遇的な立場を与えられていたことが、のちの活躍につながる大きなきっかけとなったのです。
他にも、たとえば中国で共産革命を主導した毛沢東には、14歳年上の中国共産党初代トップ、陳独秀がいました。「新青年」という言論誌を創刊し、魯迅らの言論活動を支援していた超名門の家の出である陳は、北京大学の図書館職員として働いていた20代の毛沢東に活躍の場を提供。毛が世に出るきっかけをつくっています。
このように、革命というものは、若者たちだけの力で成し遂げられるものではありません。革命を成す若者たちは、その時代、その国で権力を握る、エスタブリッシュメント層の人々から支援を受け、ときに彼ら「大人たち」に変化を促すことで、世の中を動かしてきたということが言えます。
つまり、本当に世の中を動かそうと思うのであれば、いまの社会で権力や財力を握っている人たちを味方につけて、彼らの協力を取りつけることが絶対に必要となってくるわけです。
ジョブズ、ザッカーバーグを支援した「大人」たち
「革命」には、協力する大人がいることが必須となる。
そのことは、政治だけでなく、ビジネスの世界においても同じです。
世界最大のIT企業に成長したアップルの例でいえば、誰もが知る創業者のスティーブ・ジョブズと、「ウォズの魔法使い」と呼ばれた天才プログラマー、スティーブ・ウォズニアックのふたりが知り合って創業したことは有名です。
ふたりが出会ったのは1971年、ヒューレット・パッカードの夏季インターンシップの場であり、スティーブが16歳、ウォズが21歳という若さでした。
その5年後にアップルは第1号のパーソナルコンピュータを発売し、大ヒットとなりますが、その創業時に実はもうひとり、インテルでマーケティングの仕事をしていたマイク・マークラという人物がいて、若いふたりをサポートしたことは、それほど知られていません。
アップルは、創業時に30代半ばだったマークラが、手持ちの資金9万2000ドルを投資し、またバンク・オブ・アメリカから貸付枠を得るなど、実務的な面を取り仕切ったからこそ、初期から成功することができたのです。
世界初のブラウザを発明し、初期のインターネットを爆発的に普及させることに貢献したネットスケープは、マーク・アンドリーセンという人が22歳のときに作った会社です。
彼の後ろ盾にも、コンピュータグラフィックスという分野を築き上げた大企業、シリコングラフィックスの創業者、ジム・クラークがいました。
彼が、マーク・アンドリーセンの開発したウェブブラウザ「モザイク」を見て惚れ込み、メールを送ったことが創業のきっかけとなったのです。その後、ふたりは共同でモザイク・コミュニケーションズ社(のちのネットスケープ・コミュニケーションズ社)を設立しました。
また、利用者がついに9億人を超えたフェイスブックは、19歳で同サービスをスタートさせた創業者のマーク・ザッカーバーグが有名ですが、彼のうしろにもペイパルを大成功させた投資家、ピーター・シールがいました。
20歳近く年上のシールから50万ドルの出資を受け、さらに会社の成長のために邪魔だった人物の除外を手助けしてもらうことで、フェイスブック社は急成長を遂げることができたのです。
このように、アメリカのシリコンバレーで生まれたベンチャーで、のちに世の中を驚かせるようなサービスや製品を開発して、巨大な企業に成長した会社の背後には、若い起業家たちを支援する「大人の人々」がいることがじつに多いのです。
こびるのではなく、投資の対象と見なされろ
これは、日本の会社でも同じことです。
近年、爆発的に成長して話題となっているグリー株式会社は、社長の田中良和氏が27歳のときに創業し、携帯ソーシャルゲームを事業の中心とすることで大きく飛躍しました。
その成長のきっかけは、通信業界の大企業であるKDDIと提携を結んだことです。
また、グリーと携帯ゲームの覇権を争っているDeNAも、プロ野球球団を買収するまでに急拡大しましたが、彼らもまたリクルートやソニーコミュニケーションネットワーク(ソネット)などの大企業の出資によって、最初の事業の基盤を作っています。
「エスタブリッシュメントの支援を得る」ということは、ビジネスの世界で成功するためには、ほとんど必須といっていい条件となっています。
そのことは、ライブドアの社長だった堀江貴文氏と、楽天の三木谷浩史氏のたどった軌跡を比較すると、よくわかります。
どちらもたった10年ほどの期間で、何千人もの従業員を抱えるまでに大きく成長したIT企業の若い創業社長です。ふたりともにプロ野球球団や放送局の買収に乗り出し、メディアを賑わせました。
しかし、ふたりの現在の状況は、大きく明暗を分けています。
「金で買えないものはない」などの挑発的な発言で、エスタブリッシュメント層の怒りを買ってしまった堀江氏は、最終的に粉飾決算の罪で服役することとなり、彼の創業したライブドアも上場廃止となってしまいました。
2012年には韓国資本のNHNというネット企業に吸収され、社名も消失することとなったのです。
それに対して、年配者に好かれることで知られる三木谷氏の楽天は、経団連にも加入し(のちに自ら脱退しますが)、望みどおりプロ野球の球団買収にも成功します。
いまや楽天は、時価総額で日本有数の企業に成長しました。
私たちの知らないところで、いまなお日本経済はエスタブリッシュメント層にがっちりと牛耳られており、彼らの意思に正面から反抗することがいかに大きな反発を招くかを、堀江氏は身をもって教えてくれたと言えるかもしれません。
とはいえ私は、「自分が成功するために、老人たちにうまく取り入れ」と言っているわけではまったくありません。
若者が「世の中を変えよう!」と立ち上がるだけでは、けっして社会は動かせない。革命を起こすには、大きな権力を握る大人と対等に交渉して、合意を結び、具体的なアクションにつなげていかねばならない。
つまり、彼らにこびるのではなく、「将来見込みがある若者」として、彼らから「投資の対象」と見なされる必要があるわけです。
この本のキーメッセージのひとつが、まさにここにあります。
世の中を動かすためには、自分ひとりの力ではとても足りない。ともに戦う自分たちの「仲間」を探さねばなりません。
そして、彼らを味方にし、ときには敵対する相手や、自分よりもはるかに巨大な力を持つ「大人」とも、交渉によって合意を結ぶ。
そうやって初めて、世の中を動かしていくことができるわけです。
なぜ「異質なもの」と手を組む必要があるのか?
交渉では、自分とはまったく考え方も立場も異なる「異質な人」と話し合い、合意を結ぶことが求められます。
この「異質な人」とのコミュニケーションも、若い人にとってはたいへん重要だと私は考えています。
最近、就職活動に取り組む若者の間では、会社を選ぶ際に、仕事の中身やそこでどれだけ給料がもらえるかよりも、そこで働く人たちの価値観が自分と共通しているかどうかが重視されるようになっているようです。
「仲間」という言葉は、時代のキーワードにもなっています。
国民的なマンガ『ワンピース』を題材に、仲間の持つ力やその作り方を分析した本が売れていたり、都心に暮らす20代の若者同士がひとつの大きなマンションや一軒家を借りて、そこで擬似家族的に暮らすのも流行しています。
また、ツイッターやフェイスブックなどSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)と呼ばれるインターネットサービスが爆発的に会員を増やしており、友達とつながるための交流ツールは、10年前では考えられないほどに発展しました。
こうした流れを見るに、いまの若者の間では「仲間探し」がトレンドとなっているようです。
私も若い人が「仲間」を探すことはたいへん重要なことだと思っていますし、本書で述べる交渉も、それに大いに役立ってくれるはずだと信じています。
しかし、仲間探しには注意すべき点もあります。
ひとつは、SNSのようにごく狭い関心領域でつながった友人のなかにいると、どんどん自分の世界が「タコツボ化」(異文化との接触が断たれた状況になること。似た言葉に「ガラパゴス化」がある)していくことです。
よく政治的な世論調査の結果に関して「ネットではまったく逆の意見ばかりなのにおかしい。情報操作されているのではないか」などと憤っている人がいますが、それはその人が見ているネットの意見が偏っているだけの話です。
ネットのなかで、仕事や趣味や価値観が似通った人の意見だけを見続けるうちに、それが世の中で「普通」の感覚だと勘違いして、知らぬ間に一般社会からどんどん乖離していきかねません。
自分では、多種多様な仕事やプロフィール、世代や価値観の人々と有機的につながっているつもりでも、「ツイッターやフェイスブックをやっている」という括りでは、きわめて同質的なつながりなのです。
ツイッターのユーザーのなかには、社会でやっていくのは苦労するだろうなと思われる若者の姿を見ることも珍しくありません。
先日も、大学生活に適応できない学生同士がシェアハウスを借りて共同生活し、「俺たちは自由に生きているんだ」ということをツイッター上で確認し合っている様子を目撃しましたが、その姿に感動した地方の高校生が家出をして、東京のそのシェアハウスに合流してしまったようです。
その集団は一見、自由でオープンであるかのように見えて、その実、もっとも視野が狭い閉鎖的な集団であるとも言えるでしょう。「シェアハウス」などという流行り言葉に騙されてはいけません。
タコツボのなかにいるのは居心地がいいことですが、それはときとして、非常に危険な結果を生むこともあります。
かつて、社会変革を訴えた日本赤軍やオウム真理教などの組織も、どんどんタコツボ化して自滅していきましたが、それは彼らが、自分たちの外部の異質なものとの対話の通路を閉じていたからではないかと私は思います。
ゲイが多い街からイノベーションは生まれる
居心地の良い仲間同士で過ごすことには、別の危険もあります。
それは「自分と似た人間、同質な人間ばかりと出会っていても、大きな〝非連続的変化〟は生み出されない」ということです。
非連続的変化とは、たとえば馬車が自動車になったり、インターネットの発明によって情報の流通量がそれまでの何百万倍にも高まるような、それまでの常識では考えられないような飛躍的な変化のことを言います。
社会を大きく変えるような発明や新商品を生み出すためには、この非連続的変化をいかに起こすかが大切となります。
アメリカのシリコンバレーや、数々のベンチャー企業を輩出するスタンフォード大学などは、まさに都市や大学が非連続的変化を生み出し続ける母体となっていると言えるでしょう。
なぜ、それらの都市や大学では、非連続的変化を起こす人が定期的に生まれるのか?
それについて、トロント大学の都市経済学の専門家、リチャード・フロリダ教授が興味深い研究を行いました。
アメリカのハイテク産業で大きく伸びている都市の国勢調査を分析したところ、「同性愛者」(ゲイ)と「俳優や芸術家、デザイナーなどのクリエイティブな仕事に従事する人」(ボヘミアン)が多いことがわかったのです。
フロリダ教授はこれを「ゲイ指数」「ボヘミアン指数」と名づけ、どれくらい都市がクリエイティブであるかの指標とすることを提唱しました。
教授によれば、ゲイやクリエイター層の人々は、一般的に美的センスに優れており、他者への寛容の気持ちや文化的開放性をより強く持っているために、多くの才能や人的資本を惹きつけると言います。
また、非常に強く社会で差別されているゲイのような人々を受け入れる都市は、それだけ異質なものへの許容度が高く、多様性を持っているために、新たなビジネスやイノベーションが生まれやすいというのです。
「空気が読めない人」がマジョリティになる社会へ
私は、いまの日本社会も、これまでのような小さな仲間内で回る社会から、異質なものと出会って大きく変化していく社会へと、ゆるやかに移り変わろうとしているように感じています。
ちょっと前の流行語で「KY」という言葉が話題になりました。
これは、「空気が/読めない」の頭文字からとった言葉ですが、世の中の暗黙の了解やいわゆる「お約束」(=空気)を知らず知らずに無視してしまう人のことを揶揄する文脈で、一時たくさん使われました。
しかし、なぜこの時代に「KY」という言葉が流行したのか考えると、違った文脈でこの言葉を捉えることができます。
誰もが世の中の「暗黙の了解」を自然に感じ取って、その通りにふるまっていれば、こんな言葉が流行る理由はありません。つまり、「空気が読めない人」が以前に比べてずっと日本社会で増え続けて、むしろマジョリティになりつつあるからこそ、この言葉が流行ったのではないか。
私はそう考えているのです。
以前の日本社会では、所属する会社や業界ごとに、それぞれの企業文化や価値観が確固としてありました。銀行には銀行の、公務員には公務員の、ゼネコンにはゼネコンの世界のルールがあり、そこで長年働く人々は、自然とその価値観に染まっていくのがふつうでした。
つまり、以前の日本でも、「空気」は統一されていたわけではなく、それぞれの人々が生きる社会組織ごとの「空気」があったわけです。そのなかで生きていくかぎり、他の空気を持つ組織とは、積極的に混じり合う必要はありませんでした。
しかし、バブル崩壊後のこの15年で、状況は大きく変わりました。
急激なグローバル化とIT化により、経済環境はすさまじい速さで変貌するようになり、あるとき大儲けした会社が、数年後には倒産するということも珍しくなくなりました。
企業は生き残るためにつぎつぎに新しい分野、成長産業に乗り出すことを余儀なくされ、業界横断的なプロジェクトがあたりまえとなり、そこで働く人々も、自分たちの業種に閉じこもっているわけにはいかなくなりました。
自分たちの世界の空気とはまったく異なる空気のなかで生きている他者と、一緒になって生きていかざるをえなくなった。
だから、「空気」が読めなくなったのです。
いまの日本は、地縁や血縁や会社の社縁でつながった古いタイプの組織が瓦解して、新しい組織や新しいルールを自分たちで作っていく社会に変化していく、ちょうど入り口の段階にあるように見えます。
異質なもの、自分とは前提とする考え方や文化的な背景すらもぜんぜん違う相手と交渉して組んでいくことがないと、自分たちの仲間内だけの狭い世界でごちゃごちゃ縮こまって過ごしているだけになってしまう。
そんな場所からは、他の国や他の社会で生きる人を惹きつけるような魅力はけっして生まれません。
だから私は、若い人にできるだけ自分と「異質な人」と交流すること、そして仲間になることを勧めます。
そのときにも、「交渉の力」が必須となるのです。
「最大の敵」をも仲間にすることで、世の中が大きく動く
交渉のパワーには、どれほどのものがあるのか?
自分の考えとぜんぜん合わない人や、自分よりはるかに強い力を持っている人とも、交渉して合意を結ぶことで、目的を達成することができます。
交渉が世の中を動かした例は数限りなくありますが、日本近代史のなかでもっとも大きな成果を上げた交渉といえば、徳川幕府が300年続けてきたシステムをひっくり返す直接的なきっかけとなった「薩長同盟」が、まさにその代表です。
さきほども「エスタブリッシュメントの支援を得る」話のところで名前を挙げましたね。
江戸時代、それぞれの藩は、現在の「国」にあたる存在でした。各藩は一応幕府のことを奉ってはいましたが、本音のところでは、自分の藩の勢力を強くすることだけに関心がありました。
なかでも薩摩藩と長州藩は、ともに藩政改革に成功し、幕末において地方の有力外様大名として威勢を誇っていました。
幕末に政府の力が弱まると、長州藩は尊王攘夷論を掲げ、京都で政局をリードする存在となり、ついには江戸幕府に対して公然と反旗を翻すようになります。
それに対して幕府は、薩摩藩の武士を中心とする征伐隊を編制し、送り込みます。
両者は文字通り殺し合いをするほどの敵対関係となり、「禁門の変」と呼ばれる武力衝突事件では何十人もの死者が出ました。幕末の時点で、薩摩と長州は真っ向から対立するライバルであり、敵であり、利害関係が完全に相反するグループだったわけです。
ところが、坂本龍馬らの仲介により、2つの藩がよくよく話し合ってみたところ、「倒幕」という切り口で意見をまとめることができてしまった。
そして、薩摩と長州という2つの強い藩が手を結んだ結果、300年間続いた徳川幕府を倒すことに成功し、新しい日本国家をつくることができたのです。
武力をもって殺し合うほど仲が悪かった薩摩藩と長州藩が、互いの利害を分析した結果、協力して幕府を倒したほうがいいという合意にいたり、同盟を結ぶことになった。
一見すると利害関係が完全に対立する二者でも、よくよくその利害を分析することで、普通であれば考えられないような組み方ができます。
そして、その二者がそれぞれに大きな力を持っていればいるほど、その合意が生み出すパワーは大きくなります。
これがまさに、交渉の持つ最大の力なのです。
TAKE YOUR ACTION!
薩長同盟がなされた幕末の時代と、現在の日本の状況は、ある意味でとてもよく似ています。
黒船の襲来から始まった日本の開国は、現在の激しくグローバル化を迫られる日本経済の姿と重なって見えます。
それまで300年間続いた徳川政権が弱体化し、天保の飢饉が起きて農村の一揆が頻発するようになっていった状況も、いまの民主党政権に代表される政治への失望と、3月11日に起きた東日本大震災と原発事故という未曾有の災害の姿とよく似ています。
この閉塞した日本の現状を変えようと、志ある人々が、NPOや私塾のようなものを作る動きがかなり活性化しています。
しかし、それらはまだ個々に、バラバラに動いている状況であり、連携してひとつの大きなムーブメントになるにはいたっていません。
ジョージ・ソロスという世界最大の投資家は、1980年代の終わりに、東欧革命の渦中にあった社会主義国家、ハンガリーの民主主義運動を支援していました。
彼自身がハンガリー生まれのユダヤ人であったことから、どうにか
して母国の民主化を達成させたいと考え、さまざまな支援活動を行っていたのですが、そのなかでもっとも効果があったと言われているのが、「コピー機を配ったこと」でした。
社会主義国家で情報が統制下にあったハンガリーでは、コピー機も政府の管理下にあり、民主化運動のグループが自分たちの意見をチラシやビラで配ることがむずかしかったのです。
そこでソロスは大量のコピー機を私財で購入し、ハンガリーの国中にばらまくことで、情報の流通性を高め、のちに起こる革命を支援しました。
それとまったく同じような気持ちで私は、自分が「軍事顧問」をつとめるこの星海社新書シリーズを通じて、日本社会にたくさんの「ゲリラ」が生まれることを支援したいと思っています。
前著の『武器としての決断思考』(星海社新書)では、ディベートの考え方を使って、個人が「いまの最善解」を見つけ出していくための思考法をお伝えしました。
その本によって、自分の頭で考え、決断できる若者が大量に生まれたはずだと、私は思っています。
つぎの段階は、この世の中に生まれた数十万人のゲリラ同士が、共通の目的のために手を結び、具体的なアクションを起こしていくことです。
日本中のいろいろな場所でゲリラが組織化され、大人たちや、自分たちと異質な人々とも手を組んでいく。
いまの日本に必要なのは、まさに「21世紀の薩長同盟」的な、昔では考えられなかったような二者が結びつき、大きなパワーを生み出すことなのです。
本書を読んで「交渉という名の武器」を手に入れたみなさんが、仲間と一緒にこれからの日本を変える〝チーム〟を作っていくことを強く期待しています。
それではこのへんでガイダンスを終えて、いよいよ「交渉の授業」を始めていきましょう。
ガイダンスで手に入れた「武器」
- 人は自由でいるために、拘束される。
- 合意を作り出す手段が「交渉」。
- 本気で世の中を動かすつもりなら、
「エスタブリッシュメント」の支援を得よ。 - 「異質なもの」と結びつくことで、
大きな変化が起こせる。 - バラバラに動くな。
組織化して、アクションを起こせ!