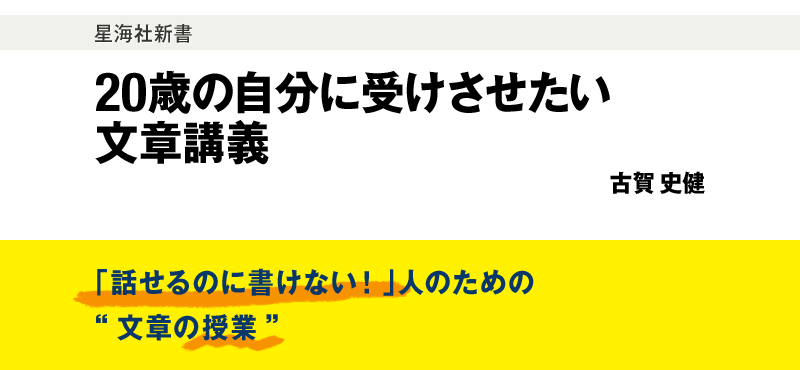
20歳の自分に受けさせたい文章講義
古賀史健
「話せるのに書けない!」人のための“文章の授業”——どうすれば自分の気持ちや考えを「文章だけ」で伝えることができるのか? この授業のスタート地点はそこにある。そう、僕らは「話せるのに書けない!」のだ。人に口で伝えることはできても、それを頭の中で文章に変換しようとすると、とたんに固まってしまう。メールの一通すら、うまく書けない。「話すこと」と「書くこと」はまったく別の行為なのだ。決して「同じ日本語じゃないか」などと思ってはいけない。この授業では、現役のライターである僕が、現場で15年かけて蓄積した「話し言葉から書き言葉へ」のノウハウと哲学を、余すところなく伝えていく。学校では誰も教えてくれなかった“書く技術”の授業をいま、始めよう!
はじめに 「話せるのに書けない!」のはなぜか?
文章がうまくなる必要なんてない
まず最初に、本書の目標を明らかにしておこう。
ぼくは〝書くこと〟を職業とする、現役のフリーランスライターだ。そしてタイトルからもわかるように、本書は〝文章の書き方〟について語られた一冊である。ということはつまり、本書の目標は「文章がうまくなること」なのだろうか?
残念ながら、少し違う。
文章が「うまく」なる必要などない。
本書が第一の目標とするのは、「話せるのに書けない!」を解消することだ。より正確にいうなら〝話し言葉〟と〝書き言葉〟の違いを知り、その距離を縮めることである。
どういうことか、説明しよう。
文章の得意な人は、平気な顔をして「文章なんて、話すように書けばいいんだよ。話すのも書くのも、同じ日本語じゃないか」と言う。
しかし、このアドバイスはまったく役に立たない。話すように書けるのなら、誰も苦労しないだろう。文章の苦手な人が悩んでいるのは「話せるのに書けない!」というもどかしさなのだ。
誰だって、話すことはできる。感情にまかせて口喧嘩することも、気のおけない仲間たちと夜通し語り合うことだってできる。日本語を使って意思や感情を表現することに、これといって不自由を感じない。時間が許すのなら、いつまでもしゃべっていたいとさえ思っている。
にもかかわらず、メールの一通すら「書けない!」のだ。
ここではっきりとさせておこう。「話すこと」と「書くこと」は、まったく別の行為だ。決して「同じ日本語じゃないか」などと同じ土俵で語ってはいけない。
こう考えてほしい。
言葉を話すとき、あなたは〝テレビ〟である。
満面の笑みを見せることもできるし、怒鳴り声を上げることもできる。自分の気持ちを、言葉、表情、声、身振りなど、さまざまな道具を使って伝えることができる。実際そうやって話しているし、相手も素直に理解してくれるだろう。
一方、文章を書くときのあなたは〝新聞〟である。
喜怒哀楽を表情で伝えることもできないし、怒りに震える声を聞かせることもできない。テレビどころか〝ラジオ〟ですらないのだ。使える道具は、言葉(文字)だけ。声や表情などの使い慣れた武器をすべて奪われ、ただ言葉という棒きれ一本で勝負しろと迫られる。自分の気持ちを正確に伝えるのはかなり困難で、「言葉だけ」で読まされる読者からしても、理解するのは難しいはずだ。
テレビディレクターから新聞記者に転身すること。「話すこと」と「書くこと」の違いは、それくらい大きいのである。
「話し言葉」を「書き言葉」に変換するノウハウ
じゃあ、どうすれば自分の気持ちを「言葉だけ」で伝えることができるのか?
日常会話では表情や声に乗せていた〝感情〟を、どうやって言葉に落とし込むのか?
大学や大手予備校の先生方ではなく、ぼくが本書を書くべき理由は、たぶんこの一点に絞られる。
なぜなら、ぼくはライターなのだ。
各方面で活躍されている方々にインタビューをして、取材現場で語られる生き生きとした「話し言葉」を、原稿という「書き言葉」に変換する。しかも、できるだけわかりやすい書き言葉に変換する。それがぼくの仕事だ。
当然、インタビューとして語られた言葉を書き起こすだけでなく、取材相手の表情、声、あるいは沈黙なども読み取って、そこに込められた「言葉として語られなかったこと」までも原稿にしていかなければならない。
ライターの仕事を始めて15年、書籍づくりに携わるようになって10年近くが経つが、ぼくが一貫して続けてきたのは、まさに「話し言葉」を「書き言葉」に変換することであり、「言葉として語られなかったこと」を言葉に変換することだった。
今回、ぼくは本書のなかで〝文章の授業〟に挑戦したいと思う。これまで自分がライターとして蓄積してきた「話し言葉から書き言葉へ」のノウハウを、余すところなく伝える現場からの授業だ。
簡単に自己紹介しておこう。
15年前、ぼくは小さな出版社に就職し、その翌年にはフリーライターとして独立した。これといったコネもなく、業界経験も1年未満での独立だ。まともな仕事などあるわけがない。フリーになって最初に請け負った仕事は、旅行会社のチラシに掲載される日帰りバスツアーの案内文だった。
しかしその後、少しずつ一般誌やビジネス誌での仕事が入るようになり、この10年ほどは、毎年平均10冊以上、合計で80冊以上の書籍づくりにライターとして携わってきた。
年間10冊といえば、少なく見積もっても毎年原稿用紙3000枚以上の文章を書いてきた計算になる。われながら気が遠くなる数字だ。
なかには10万部、20万部を超えるベストセラーとなった本も多数あり、インタビュー集である『16歳の教科書』シリーズ(講談社)は、累計70万部を超えるベストセラーに育てていただいた。
本書で述べる「話し言葉から書き言葉へ」を請け負うプロとしては、それなりの自信があるし、経験もノウハウも持っているつもりだ。ライターである自分にしか語れないことは山のようにあると思っている。
学校の作文はすべて忘れよう
続いて、なぜ〝文章の授業〟なのかについて語ろう。
そもそもあなたは〝文章の授業〟を受けたことがあるだろうか?
義務教育から高校、大学と、記憶を丹念にたどってほしい。作文や読書感想文は山ほど書かされた。しかし、〝書く〟という行為の意味や意義、そして具体的な技法にまで踏み込んだ授業を、受けたことがあるだろうか?
おそらく「ない」はずだ。
国語の授業では、その大半が〝名作の品評会〟に費やされる。名作を読まされ、感想を言わされ、教師の退屈かつ道徳的な見解を聞かされ、なんだかよくわからないまま時間が過ぎていく。それが一般的な国語の授業だ。
学生時代、ぼくは不思議でならなかった。
たとえば、いっさい絵筆を持たせることなく、延々と〝名作の品評会〟に明け暮れる美術学校なんて、考えられない。数式を品評するだけで終わる数学の授業なんて、ありえない。陸上競技のビデオ鑑賞で終わる体育なんて、あるはずがない。
なのに、どうして誰も〝文章の授業〟をしてくれないのか?
読解力が大切なのは、よくわかる。でも、それと同じかそれ以上に〝書く力〟も大切なのではないか?
反論はあるだろう。
「文章の授業といえば、作文があったじゃないか。いろんなテーマで書かされ、赤字で添削される作文は〝書く〟ことのトレーニングだったはずだ」
たしかに作文はあった。赤字で添削されたり、寸評を添えられたりした。句読点のルールや原稿用紙の使い方なども教わった。しかし問題は、文章の書き方・組み立て方を体系的に教わってきたか、ということだ。
自分の小中学校時代を振り返ってみても、〝書く技術〟らしきものを教わった記憶は皆無に等しい。作文の時間にはいつも「思ったとおりに書きなさい」「感じたままに書きなさい」と指導されてきた。
じゃあ、なにも教わらない子どもたちは、どうやって文章を書いていくのか?
子どもたちが頼りにする基準はただひとつ、「先生の目」である。
つまり、「なにを書けば先生からほめられるか?」と、教師との人間関係を基準に考えるようになるのだ。
模範的な作文がつまらない最大の理由は、ここにある。
いつも教師の顔色を窺い、「自然を汚すのはよくないと思いました」とか「これからは弟にやさしくしようと思います」など、いかにもお行儀のよい意見を書く。教師もそれを「とてもいいことに気づきましたね」とほめる。作文技術など、いっさい関係ない。「いいこと」を書いていれば、それで評価されるのである。
……この話、どこかおかしいと思わないだろうか?
文章の書き方を指導するはずの作文が、いつの間にか〝心の指導〟にすり替わっている。道徳的な価値観を押しつけるものになっている。
そう、作文も読書感想文も〝書き方指導〟ではなく、形を変えた〝生活指導〟になっていたのである。
こんな教え方では、書くことが苦痛になるのも当たり前だ。
文章を書くとき、「いいこと」を書かなきゃ、と考える人は意外なほど多い。
ぼく自身、小学校時代には心にもないウソで塗り固めた作文をたくさん書いてきた。文章を書くのは好きだったが、学校の作文は大嫌いだった。
もちろん本講義で、道徳など語るつもりはない。ぜひ過去の作文は忘れて、講義に臨んでいただきたい。
書くこととは、考えることである
本書は、講義形式で構成されている。それぞれどのようなテーマを採り上げていくのか、あらかじめ紹介しておくことにしよう。
- ガイダンス…… そもそも文章とはなんなのか?
- 第1講 リズム …… 読みやすい文章に不可欠なリズムとは?
- 第2講 構成 …… 文章はどう構成すればいいのか?
- 第3講 読者 …… 読者を引きつける条件とは?
- 第4講 編集 …… 編集するとはどういうことか?
すんなり意味のわかるものと、一瞬「?」と首を傾げるものとがあるだろう。
ガイダンスを除けば、たったの4講である。その代わり、各講義の内容はかなり濃い。ページ数も、当初の予定より大幅に増えていった。もちろんそこはライターとして、最大限の読みやすさを心掛けたつもりである。
ここでガイダンスに入る前に、本書の最終的な目標はどこにあるのかを述べておこう。
個人的にぼくは、できれば高校を卒業するまでの間に、遅くとも20歳までの間に、しっかりとした〝書く技術〟を教える環境が必要だと思っている。道徳でも生活指導でもない、自分の思いを「言葉だけ」で伝える技術だ。
なぜ、若いうちに〝書く技術〟を身につけるべきなのか?
答えはひとつ、「書くこととは、考えること」だからである。
〝書く技術〟を身につけることは、そのまま〝考える技術〟を身につけることにつながるからである。
仕事や人生で困難にぶつかったとき、どんなに頭を抱えて考え込んでも、堂々巡りをするばかりでまともな答えは出てこない。
ところが、悩みを文章に書き起こしていくと、意外な答えが見つかる。
詳しくは講義に譲るが、〝書く〟という行為のなかには、論理性の確立や思考の整理など、さまざまな要素が潜んでいる。〝書く〟というアウトプットの作業は、思考のメソッドでもあるのだ。
日帰りバスツアーの案内文から出発し、第一線のライターとして身を立てるに至ったぼくが保証する。
〝書く技術〟が身につけば、ものの見方が変わる。物事の考え方が変わる。そしてきっと、世界を見る目も変わってくる。
大風呂敷を広げた責任は、ちゃんと取るつもりだ。
それではさっそく講義をはじめよう。
目次
はじめに「話せるのに書けない!」のはなぜか? 7
- 文章がうまくなる必要なんてない 7
- 「話し言葉」を「書き言葉」に変換するノウハウ 9
- 学校の作文はすべて忘れよう 12
- 書くこととは、考えることである 15
ガイダンス その気持ちを「翻訳」しよう 27
- うまく言葉にできない、頭の中の「ぐるぐる」 28
- なぜ〝翻訳〟が必要なのか? 31
- 「頭の中が見せられるなら見せるんだ」 35
- 「あー、面白かった」しか言えない人 38
- 聞いた話を〝自分の言葉〟で誰かに話す 42
- 「地図・絵・写真」を言葉にしてみる 47
- 「書く時代」が訪れる前に 50
第1講 文章は「リズム」で決まる 55
- 文体とは「リズム」である 56
- 「リズムの悪い文章」はなぜ読みにくいのか? 59
- 「バカバカバカ」と笑う女子高生 64
- リズムのカギは接続詞にある 68
- 美文よりも「正文」を目指す理由 73
- ローリング・ストーンズに学ぶ文章術 77
- 文章の「視覚的リズム」とは? 81
- 句読点は「1行にひとつ」 83
- 改行のタイミングは早くていい 86
- 漢字とひらがなのバランスを考える 89
- 音読してなにをチェックするのか 93
- 断定はハイリスク・ハイリターン 99
第2講 構成は「眼」で考える 105
- 文章の面白さは「構成」から生まれる 106
- 起承転結は悪なのか? 109
- 文章のカメラワークを考える 113
- 導入は「映画の予告編」のつもりで 120
- 予告編の基本3パターン 123
- 論理展開のマトリョーシカ人形 129
- すべての文章には〝主張〟が必要だ 132
- 〝理由〟と〝事実〟はどこにあるか 136
- 〝面倒くさい細部〟を描く 140
- 構成の〝絵コンテ〟をつくる 145
- 文字量を〝眼〟で数える 148
第3講 読者の「椅子」に座る 155
- あなたにも〝読者〟がいる 156
- 「10年前の自分」に語りかける 159
- たったひとりの〝あの人〟に向けて書く 164
- 「わかるヤツにわかればいい」のウソ 170
- 「生理的に嫌いな文章」に注目する 174
- 読者は「どんな姿勢で」読んでいるか 180
- 〝説得〟せずに〝納得〟させる 183
- 人は「他人事」では動かない 187
- 〝仮説&検証〟で読者をプレーヤーにする 189
- 読者を巻き込む「起〝転〟承結」 191
- 冒頭に「真逆の一般論」をもってくる 195
- 読者と一緒に「寄り道」をしよう 198
- 自分の文章に自分でツッコミを入れる 202
- 「大きなウソ」は許されるが、「小さなウソ」は許されない 206
- 「わかったこと」だけを書く 209
- 目からウロコを何枚落とすか? 214
- なぜ「あなたにも〝読者〟がいる」のか? 220
第4講 原稿に「ハサミ」を入れる 227
- 右手にペンを、左手にはハサミを 228
- 「なにを書くか?」ではなく「なにを書かないか?」 230
- 伝わる文章は〝オレンジジュース〟 233
- まずは頭の中の〝ぐるぐる〟を紙に書き出す 238
- 下手な文章術より映画に学べ 244
- 「もったいない」のサンクコスト 248
- なぜ文章を切り刻むのか? 251
- 図に描き起こすことができるか? 映像は思い浮かぶか? 256
- 行き詰まったらフォントを変えてみる 259
- 1回ではダメ。2回は読み返す 262
- 「いい文章」とはなにか 266
おわりに 273
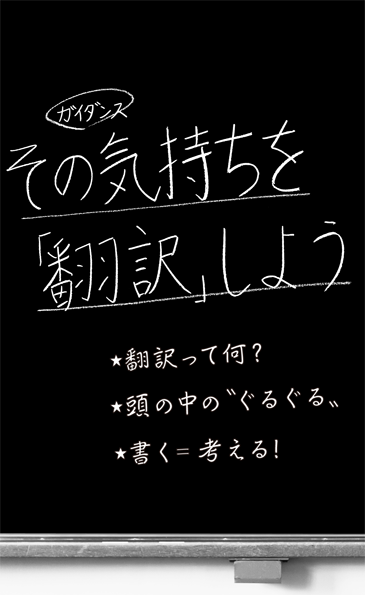 写真提供 ©R.CREATION/orion/amanaimages
写真提供 ©R.CREATION/orion/amanaimages
うまく言葉にできない、頭の中の「ぐるぐる」
これから文章講義がスタートするわけだが、この時間はガイダンスとして、本講義全体の土台となる話をしていきたい。
まず質問だ。
あなたは書くことについて、どんな悩みを抱えているだろうか?
悩みの種類は人それぞれである。初歩的なところでつまずいている人もいれば、もっといい文章が書きたい、もっと面白い文章が書きたい、とさらなる上達を願っている人もいるだろう。
しかし、われわれが文章を書く上でぶつかる諸問題は、ほとんどが次の2点に集約されるのではなかろうか?
- ①文章を書こうとすると、固まってしまう
- ②自分の気持ちをうまく文章にすることができない
つまり、文章のスタート段階における「書けない!」と、なんとか書きはじめた後にぶつかる「(うまく)書けない!」である。
書きたいことは山のようにある。頭のなかにはたくさんの〝思い〟が駆けめぐっている。けれど、書けない。なにをどう書けばいいのかわからない。
あるいは、〝自分の思い〟と〝書き上げた文章〟との間に、途方もないギャップを感じる。書くには書いたけど、とても自分の言いたかったことを言い表せたとは思えない。
日記、ブログ、メール、企画書、レポート。どんな種類の文章であれ、そしてどんなレベルの書き手であれ、文章を書く際の悩みはこの2点に集約される。
それでは、考えよう。
どうしてわれわれは書けないのか?
なぜ「話せるのに書けない!」のか?
答えは簡単だ。書こうとするから、書けないのだ。
文章を「書こう」としてはいけない。「自分の気持ちを書く」という意識は、今日この日をもって捨て去ってしまおう。
これは、文章の定義に関わる問題である。
われわれの頭のなかには、たくさんの〝思い〟が駆けめぐっている。
もちろん〝思い〟は目に見えない。言葉であるとも限らない。不鮮明な映像であったり、色だったり、あるいは漠とした気配や予感のようなものかもしれない。〝思い〟というと言語化されたもののようだが、頭をぐるぐると駆けめぐっているのは言葉ではない。言葉以前の、茫漠たる〝感じ〟である。
このぼんやりとした〝感じ〟や〝思い〟のこと、そしてそれが駆けめぐるさまのことを、ぼくは「ぐるぐる」と呼んでいる。
われわれが文章を書くときに引っかかってしまうのは、まさにこの点だ。
作文の授業で「思ったとおりに書きなさい」と言われても、頭を駆けめぐっているのは言葉以前の「ぐるぐる」である。自分がなにを思い、どう思っているのか、自分でもよくわからない。言葉にできないのだ。
話すのであれば、「ぐるぐる」の〝感じ〟を喜怒哀楽の声や表情で伝えることもできる。しかし文章では声が出せず、表情も見せることができない。
じゃあ、どうすれば文章が書けるのか?
どうすれば自分の〝感じ〟や〝思い〟を、文章として正しくアウトプットできるのか?
ぼくの結論はシンプルだ。書くことをやめて〝翻訳〟するのである。
文章とは、つらつらと書くものではない。
頭のなかの「ぐるぐる」を、伝わる言葉に〝翻訳〟したものが文章なのである。
「なんじゃそりゃ?」でかまわない。まずはここから、ガイダンスをスタートしよう。
なぜ〝翻訳〟が必要なのか?
文章とは、頭のなかの「ぐるぐる」を、伝わる言葉に〝翻訳〟したものである。
これは本講義における「文章とはなにか?」の定義だ。もちろん、いきなり〝翻訳〟だと言われてもピンとくるはずがないし、違和感だらけだろう。
そこで最初に、ぼくが〝翻訳〟という言葉に行き着いた経緯について話したい。
きっかけは、ある数学者への取材だった。
学生時代に数学が大の苦手だったぼくは、その先生に取材するのがちょっと怖かった。取材の準備として「いますぐわかる数学」みたいな本を何冊か読んでみても、うまく理解できない。もしかしたら、ちんぷんかんぷんな話をされて、原稿にならないんじゃないか。そんな不安が拭えなかった。
ところが幸運なことに、取材ではすべてが「わかった」。
もし高等数学の話なんかをされたら完全にアウトだっただろう。けれど、その先生は身振り手振りを交えて、数学という学問の面白さをわかりやすく、熱っぽく語ってくれた。「数学って、そういう学問だったのか!」「こんな先生に数学を教わっていたら人生変わったのに!」と感激した。
この取材原稿を書く際、頭に思い浮かんだ言葉が〝翻訳〟である。
いま自分は「数学ができる人」の話を、「数学が苦手な一般読者」に伝えようとしている。注意すべきは、ここでひとつでも「数学の言葉」を使ってしまったら、読者にはなにも伝わらないということである。
というのも、ぼく自身がそうなのだが、数学が苦手な人にとっての「数学の言葉」とは、ほとんど外国語も同然なのだ。聞いた瞬間に拒絶反応を示し、思考停止に陥ってしまう。
つまり、その原稿でぼくは「外国語みたいな数学の言葉」を「ぼくでも理解できる言葉」に〝翻訳〟しなければならなかったのである。
そうと気づいてからは、原稿を書くのが楽しくてたまらなかった。
数学が苦手な人は、数学のどこでつまずいているのか、数学にどんな先入観を持っているのか、数学のなにを教えてほしいのか。自分が苦手だったからこそ、その気持ちが痛いほどわかるし、彼らに伝わる言葉で説明することができる。自信を持って「数学って、こういう学問なんだよ!」と伝えられる。
思い返してみると、「得意分野を見つけること」が推奨されるライターの世界において、ぼくは専門らしい専門をなにひとつとして持ってこなかった。
グルメに詳しいわけでもないし、旅行情報に詳しくもなければ、映画ライターや音楽ライターというわけでもない。ITや経済知識も中途半端で、すべてに対して素人である。
しかし、素人だからこそぼくは、取材先で得た情報を「その分野の素人にも通じる言葉」へと〝翻訳〟することができる。へんな話だが、何物にも染らない素人であることは、ぼくにとって最大の強みなのだ。
さて、ぼくはこの〝翻訳〟という発想は、あらゆる種類の文章に通じるはずだと思っている。先に見た2パターンの悩みを思い出そう。
- ①文章を書こうとすると、固まってしまう
- ②自分の気持ちをうまく文章にすることができない
①で悩んでいる人は、まだ頭のなかの「ぐるぐる」を整理できていない状態だ。文章とは頭のなかの「ぐるぐる」を〝翻訳〟したものだ、という発想が欠如している。まず必要なのは〝翻訳〟の意識づけだろう。
②で悩んでいる人は、「ぐるぐる」を〝誤訳〟してしまっているわけだ。こちらはもっと具体的な〝翻訳〟の技術が必要だろう。
なんとなく、〝翻訳〟のイメージが摑めてきただろうか?
われわれは、自分という人間の〝翻訳者〟になってこそ、そして言いたいことの〝翻訳者〟になってこそ、ようやく万人に伝わる文章を書くことができる。
書けない人に足りないのは、〝翻訳〟の意識であり、技術なのだ。
「頭の中が見せられるなら見せるんだ」
文章を書こうとすると、固まってしまう。
なにをどう書けばいいかわからず、手が止まってしまう。
こうした「書けないこと」のもどかしさについて、文章とはまったく違う視点からスポットを当てた、ぼくの大好きな歌がある。
「伝えたい事が そりゃ僕にだってあるんだ」
という一節ではじまる奥田民生さんのバラード、『CUSTOM』だ。
若干フレーズの順番は前後するが、歌詞の内容を簡単に紹介しよう。
歌詞中の〝僕〟は、「伝えたい事が そりゃ僕にだってあるんだ」と打ち明ける一方で、「伝えたい事は 言葉にしたくはないんだ」と矛盾した思いも抱えている。
おかげで「そしたらどうしたらいいのさ」と悩み、「頭の中が 見せられるなら見せるんだ」と、半ば投げやりに考えたりもする。
結局、〝僕〟はどうするのか? その答えがカッコイイ。
「そこで目を閉じて 黙って 閃いて 気持ち込めて 適当なタイトルで ギターを弾いてみました」
「だから目を閉じて 気取って 間違えて 汗をかいて あやふやなハミングで 歌を歌ってみました 叫びました」
と続け、大音量のギターとともに直接的な〝思い〟をがなり立てる、圧巻のクライマックスへと突入していくのである。
文章を書こうとしても、なかなか書けない。伝えたいこと、書きたいことは山ほどあるはずなのに、なぜか手が止まってしまう。いっそ頭のなかを見せられればいいのに、それもできない。
これは『CUSTOM』の〝僕〟が抱えているのとほとんど同じ、コミュニケーション不全をめぐる悩みである。
では、『CUSTOM』の〝僕〟はどうしたか?
ギターを弾き、歌を歌った。
頭のなかに駆けめぐる有形無形の思いを、歌という形に〝翻訳〟してみせた。そう、これは〝翻訳〟の歌なのである。
そうやって考えると、冒頭の「伝えたい事が そりゃ僕にだってあるんだ」という一節に込められた意味が、より深く理解できるようになる。
われわれはどうして〝翻訳〟をするのか?
伝えるためだ。
伝えたい相手がいるからだ。
他者でも読者でも、言葉はなんでもいい。誰かになにかを伝えたい、つながりたいと思うからこそ、〝翻訳〟をするのだし、しなければならないのだ。
逆に言えば、読者を無視した〝翻訳〟には意味がない。〝翻訳〟は、それを受け止めてくれる相手の存在があってこそ、成立する。たとえ自分が「うまく言葉にできた」と思っても、それが相手に伝わらなければ〝翻訳〟は失敗なのである。
このガイダンスの終了後、ぼくは文章を書く上での〝技術〟に踏み込んでいく。
「文章に技術はいらない」
「思いつくまま好きに書くのが、いちばん素直な文章だ」
「技術がなくても真心があれば伝わる」
ぼくは、これらの意見に同意することなど到底できない。歌に置き換えて考えてほしい。リズムもメロディもめちゃくちゃな歌を、誰が聴いてくれるというのだろうか?
文章には、一定の知識や技術、ルールが求められる。音楽でいうところのリズムやメロディ、コード進行などに該当する部分である。
本講義では、小手先のテクニックではなく、精神論やお説教でもない、本当に役立つ根幹部分の技術を考えたいのである。
「あー、面白かった」しか言えない人
「はじめに」でぼくは「書くこととは、考えること」だと述べた。
〝書く技術〟を身につけることは、そのまま〝考える技術〟を身につけることにつながるのだ、と。
この真意について、読書感想文を例に考えてみよう。
普段本を読むとき、われわれは「あー、面白かった」と思っていればそれでいい。それ以上の気持ちを誰かに説明する必要なんてどこにもないし、主人公の名前を忘れてしまってもかまわない。
ところが、読書感想文となれば、そうはいかない。
「夏目漱石の『坊っちゃん』を読みました。とっても面白かったです」
これでは、なにも伝わらないのだ。
そうではなく、『坊っちゃん』を読んだことのない人にもわかるように、どこがどう面白かったのか言葉を尽くして説明しなければならない。『坊っちゃん』の面白さを、自分の言葉に〝翻訳〟していく必要があるのだ。
たとえば、『坊っちゃん』はどんなストーリーだったのか。
そこにはどんな登場人物がいて、それぞれどう絡んでいったのか。
主人公はあのとき、なぜあんなことをしたのか。
作者の夏目漱石はなぜ、彼(主人公)にそんなことをさせたのか。
そして読者たる自分は、物語のどこに「面白さ」を感じたのか。また、それはなぜなのか。
感想文を書こうと思うなら、こうして物語の内容、魅力、ポイント、欠点など、あらゆることを自分の頭で整理・再構築し、アウトプットしていかなければならない。
これは非常に面倒で、骨の折れる作業だ。
しかし、いったんこのステップを通過すると、『坊っちゃん』に対する理解度はまったく違ったものになる。
だってそうだろう。なにも書かなければ「あー、面白かった」だけで終わるはずだった。「なんかよくわかんないけど面白い」で片づけることができた。
ところが、感想文を書くためには、その「なんかよくわかんない」部分に、言葉を与えなければならない。あいまいな記憶、漠とした感情に、論理の串を突き刺さねばならない。書き上げたあと、より深い理解が得られるのは、当然のことである。
実際に過去の経験を振り返ってみても、ただ読んだだけの本と、しっかり感想文まで書いた本とでは、記憶の有り方まで違っているはずだ。
書くことの醍醐味、自分の言葉に〝翻訳〟することの醍醐味は、ここにある。
われわれは、理解したから書くのではない。
理解できる頭を持った人だけが書けるのではない。
むしろ反対で、われわれは「書く」という再構築とアウトプットの作業を通じて、ようやく自分なりの「解」を摑んでいくのだ。
順番を間違えないようにしよう。人は解を得るために書くのだし、解がわからないから書くのだ。おそらくこれは、世界的な文豪たちでも同じはずである。
わからないことがあったら、書こう。自分の言葉に〝翻訳〟しよう。そうすればきっと、自分なりの解が見つかるはずだ。長年ライターとして生きてきたぼくが、断言する。
文章の世界では、しばしば「考えてから書きなさい」というアドバイスが語られる。考えもなしに書きはじめても、いい文章にはならないと。
たしかにそれはその通りなのだが、もしも目の前に20歳の自分がいたら、ぼくはもっと根本的なアドバイスをおくるだろう。
つまり「考えるために書きなさい」と。
書くこととは考えることであり、「書く力」を身につけることは「考える力」を身につけることなのだ。〝書く〟というアウトプットの作業は、思考のメソッドなのである。
メールや企画書がうまく書けるようになるとか、卒論やレポートの評価が上がるとか、そんなものは枝葉末節にすぎない議論だ。
聞いた話を〝自分の言葉〟で誰かに話す
あまり観念的な話ばかりをくり返しても意味がない。
このあたりで、具体的にどうすれば〝翻訳〟できるのか考えていこう。
以前、若いライターの方から取材原稿の書き方についてアドバイスを求められ、ぼくはこんなことを言った。
「取材が終わって会社や家に帰ったら、誰でもいいから捕まえて少しだけ時間をもらおう。そして5分でもいい、今日は誰にどんなテーマで取材をしたのか、その人はどんなことを話していて自分はどう思ったのか、思いつくまましゃべってみよう。そうすると、原稿に向かったときスムーズに書けるようになるよ」
聞いた話を、誰かに話す。これは〝翻訳〟の第一歩だ。
実際、ぼくも取材が終わると、誰かを捕まえて取材した内容を(その日のうちに)話すように習慣づけている。複数回や長時間におよぶロングインタビューは別だが、60〜90分程度の取材なら、必ず誰かに話す。この効果は絶大だ。
取材に限らず、たとえば友達としゃべったことを誰かに話すのでもいい。〝翻訳〟の基礎を身につけるために、ぜひ意識的にチャレンジしていただきたい。
話すことによってなにが得られるか?
ぼくは〝3つの再〟と呼んでいる。
- ①再構築……言葉にするプロセスで話の内容を再構築する
- ②再発見……語り手の真意を「こういうことだったのか!」と再発見する
- ③再認識……自分がどこに反応し、なにを面白いと思ったのか再認識する
まず①の「再構築」については、ここまで述べたとおりだ。
特に取材の場合、いくら事前に質問事項を用意していても、話が思わぬ方向に展開していくことが多い。Aの話をしていたかと思えばDの話になり、Dかと思えばTになり、再びAに戻ってNに飛び、というように話題はピンボールのように跳ね回る。友達との会話でもそうだろう。
そこで、誰かに「自分の言葉で」話すことによって、バラバラに散らばった内容を再構築し、理解を深めていくのである。
よくないのは次のような話し方だ。
「それであいつが『ゴールデンウィークは彼女と海外に行きたい』と言ってね。『どこに行くの』って聞いたら、『ハワイに行く』って言うから、『それなら台湾にでも行って飲茶の食べ歩きをしたら? そっちのほうが安いよ』って言ったんだ」
これは交わした台詞を再現しただけで、いっさいの「再構築」がない。頭も使わないし、なんのトレーニングにもならないだろう。最低でも、次の文くらいは〝翻訳〟したいところだ。
「今度のゴールデンウィーク、あいつは彼女とハワイに行きたいらしいんだ。でも、せっかく旅行するなら食べ物がおいしいところがいいからね。台湾に行って飲茶の食べ歩きでもしたらどうか、って提案したんだよ。去年オレも行ったけど、ハワイよりずっと安上がりだし」
大切なのは、語られた内容とその場の状況、そこに至るまでのいきさつなどを、自分なりにまとめること、そして筋道の通ったひとつのストーリーとして語ることである。
続く②の「再発見」は、非常に大切な要素だ。
取材にしても普段の会話にしても、相手の話を聞きながらその内容を100パーセント理解することは基本的に不可能だ。知らない言葉が出てくることもあるだろうし、話が前後して頭が混乱することもある。あるいは相手の話し方が支離滅裂で、何度聞いてもよくわからないことだってあるだろう。
ところが、聞いているときにはわからなかったことが、自分の言葉に〝翻訳〟する過程で「ああ、なるほど。あの人の言ってることはこういうことだったんだ!」と突然理解できる瞬間がある。ちょうど、ジグソーパズルのピースを組み合わせているうちに「ああ、このジグソーパズルはモナリザの肖像画だったのか!」と気がつくような感覚だ。
たとえば、先の「彼女とハワイに行く」という話でも、自分の言葉に〝翻訳〟していくうちに「ああ、もしかしてあいつ、ハワイで彼女にプロポーズするつもりなのか! そういえば指輪の話もしてたし、やたら人生を語ってたな」と再発見するかもしれない。「だから飲茶の食べ歩きにまったく興味を示さなかったんだ!」と。
そして③の「再認識」だが、これも大きな気づきである。
誰かから聞いた話を、別の誰かに伝えるとき、そこには必ず「私」というフィルターが入る。テープレコーダーのように「聞いたまま」を伝えるのでは意味がないし、そもそも不可能だ。そして「私」というフィルターを通過するとき、どうでもよい情報はノイズとして取り除かれる。フィルター経由で出てくるのは、「私」が面白いと思った情報、重要だと思った情報だけである。
フィルターやノイズといった表現がわかりにいなら、カメラのピントだと思ってもらってもいい。われわれは〝翻訳〟するとき、自分が対象のどこにピントを合わせているのか知ることになる。同じ野球選手の話を聞いても、バッティングの話にピントを合わせる人もいれば、守備の話にピントを合わせる人もいるだろう。あるいはユニフォームの話にピントを合わせる人だっているかもしれない。
どこにピントを合わせるかは、その人の自由であり個性だ。
そして自分の言葉に〝翻訳〟してみると、自分が話のどこにピントを合わせていたのか、あらためて思い知らされる。
先の話にしても、話しているうちに自分が指輪や人生ではなく「彼女とハワイに行く」という話題にばかりピントを合わせていたことがわかる。自分にとってはそこがいちばん面白く、「伝えるべき情報」と判断していたわけだ。
そもそも、「聞いた話を、誰かに話す」くらいは、誰もが毎日意識せずとも行っていることである。そこで今後は〝再構築〟〝再発見〟〝再認識〟の3つを頭に入れながら、聞いた話を人に話すようにしてみよう。
ひと文字も書かずとも、文章の練習はできるのだ。
「地図・絵・写真」を言葉にしてみる
もうひとつ、紙もペンもパソコンも使わない〝翻訳〟を紹介しよう。
先ほどの〝翻訳〟は「言葉として語られたものを、自分の言葉に置き換える」という作業だった。
そこで今度は「言葉でないもの」を、自分の言葉に置き換えてみるのだ。
いちばん手っ取り早いのは、地図だろう。
たとえば最寄り駅から自宅までの道のりを、まったく土地勘がない人にもわかるように言葉で説明してみる。説明のための文章を、頭のなかで考える。
「改札を出て左手に、西口の出口があります。出口までの距離は20メートルほど。そして西口を出ると正面にバスターミナルとタクシー乗り場があるはずです。右手には三井住友銀行と、その隣にマクドナルド。左手には自転車置き場が見えるでしょう。そのままバスターミナルを迂回するように右に進んで……」
と、事細かに描写していくのだ。
もちろん、「駅を出てコンビニを曲がると大きなビルがあるから、そっちに進んで信号を曲がったところ」と伝えても、相手は迷うだけである。
駅を出るとは、西口なのか東口なのか、それとも2番出口のように数字の振られた出口なのか。コンビニとはセブンイレブンなのかローソンなのか、ファミリーマートなのか。曲がるとは右折なのか左折なのか。この説明からは、なにひとつ伝わってこない。
きっと、かなり面倒な作業に感じられるだろう。
しかし、ネットもカーナビなかった時代、ほんの20年ほど前までは、誰もがこうやって道を教え合っていたのだ。決して無理な話ではないはずである。
また、以前取材させていただいた日本語学者の金田一秀穂先生は、これに加えて「絵や写真を言葉で説明する」というゲームも提案されていた。
たとえば、1枚の写真を見ながら、
「テーブルの上に、小さなグラスが置いてある。逆光に照らされ、白く輝いて見える。大きさはちょうど手のひらに収まる程度。容量にして180cc。使い古され、やや曇っている。曇りをよくみると、それは小さなキズの集まりである」
というように、言葉で説明・描写していくのである。
そして金田一先生は、このゲームのルールとして「自分の意見をいっさい入れないこと」を挙げていた。
自分の意見とは、つまり主観や感情のことだ。逆光に照らされたグラスを描写するときに「初夏の朝を思わせる柔らかな光に照らされ」と思い入れたっぷりに語っても、それが正しく伝わるとは限らない。
初夏の朝についてのイメージは人それぞれだし、初夏の朝の光が「柔らかい」と感じる人がどれくらいいるのかもわからない。鋭い陽差しを思い浮かべ、セミの鳴き声がけたたましく響き渡る、不快な情景をイメージする人もいるだろう。
より詳しく説明しようと安易なレトリック(美辞麗句のようなもの)に走るほど、正確な描写から離れていってしまうのだ。
この「地図を言葉で説明する」と「絵や写真を言葉で説明する」は、〝翻訳〟のトレーニングとしてなかなか面白いのではないだろうか。ゲーム感覚でかまわないので、ぜひ一度試していただきたい。
「書く時代」が訪れる前に
このガイダンスにおける最大の目的は、「書こうとするな、翻訳せよ」の原則を頭に叩き込んでもらうことである。
文章とは「頭のなかの『ぐるぐる』を、伝わる言葉に〝翻訳〟したもの」である、という定義。そして文章を書きあぐねている人、うまく書けずにいる人は〝翻訳〟の意識や技術が足りていないのだ、という認識。
さらには、われわれは「書くために考える」のではなく、「考えるために書く」のだということ。「書く」というアウトプットのプロセスを通じて、われわれは自分なりの解を得ていくのだということ。
このあたりの認識を共有していただければ、もうガイダンスとして説明すべきことはほとんど残されていないように思われる。
そこで簡単な雑感とメッセージを述べて、このガイダンスを締めくくりたい。
ぼくが小さな出版社に就職した15年前、会社の名刺にはメールアドレスがなかった。
中小企業のほとんどは自社のホームページを持たず、1人1台のパソコンも支給されていなかった。取引先と交わす手紙といえば、年賀状や暑中見舞い、招待状に詫び状くらいのものだった。
誤解しないでほしい。別に戦前の話をしているのではない。高度成長期の思い出話でもない。たった15年前、1990年代後半の話である。
当時のことを思えば、毎日何十通、あるいは100通以上ものメールをやりとりする現在は、明らかに異常である。書きすぎだし、書かされすぎである。
しかしぼくは、この時代の変化を前向きに捉えたいと思っている。
きっとこれからますます「書く時代」「書かされる時代」になるだろう。メール、企画書、プレゼン資料、謝罪文、就活のエントリーシート、ブログ、SNS、そして今後生まれるだろう新しいコミュニケーションサービス。われわれが文章を書く機会は、この先増えることはあっても減ることはない。くり返すが、15年前の社会人はメールすらも使っていなかった。5年前、つまり2007年の社会人は、ツイッターもフェイスブックも使っていなかった。
今後どんな変化が起こって、どれだけ書く機会が増えるかなんて、とても想像することはできない。
かつてITを使いこなす力が「仕事力」の明暗を分けた時代があった。
しかし、iPhoneやiPadの例を見るまでもなく、ITツールの操作性は日を追うごとに平易なものとなり、いまや幼稚園の子どもでも直感的に使えるようになった。そして将来的には、日常的な英会話でさえも、優秀な翻訳ソフトの登場によって「みんなのもの」になる可能性が高いと言われている。
では、文章にも同じことが起こるだろうか?
「書くこと」のすべてを機械にまかせる時代は来るだろうか?
それはありえない話だ。「書くことは考えること」であり、そこだけは機械まかせにはできない。むしろ予測変換などの文章入力支援ツールが一般化していくほど、ホンモノの文章力との差が明らかになっていくだろう。
ぼくは、この講義を本気で「20歳の自分に受けさせたい」と考えている。
のちの自分がライターになるからではない。どこでどんな仕事に就こうと、文系であろうと理系であろうと、業種や職種に関係なく生涯にわたって身を助けてくれる武器、それが文章力なのだ。
これを読んでいるあなたが何歳なのか、それはわからない。しかし、あなたが何歳であれ、ここで文章力という武器を手に入れておくことは、将来に対する最大級の投資になる。
ぜひ「書こうとするな、翻訳せよ」の原則を胸に、ホンモノの文章力を手に入れていただきたい。思考のメソッドを手に入れていただきたい。
そうすれば10年・20年後、あなたはいまの自分に感謝するはずである。